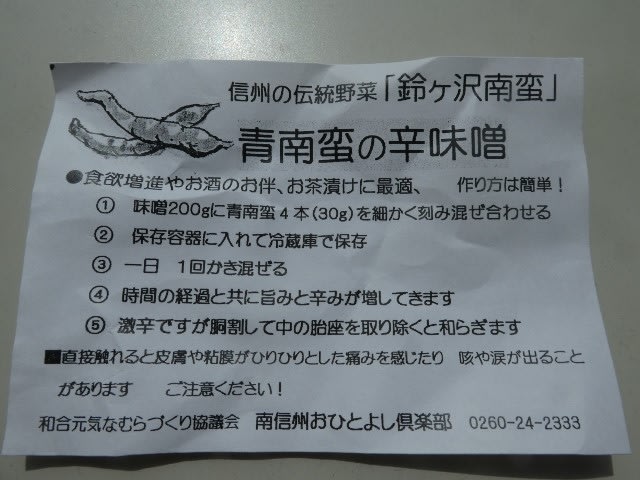名古屋の大和屋守口漬総本家の守口漬をいただきました。


守口漬に使われている守口大根は、ギネスにも認定された世界一長~い守口大根。
【画像、お借りしました】

直径は2cm程度ですが、長さは1.2mにもなります。
愛知県扶桑町と岐阜県木曽川流域で栽培されており、あいちの伝統野菜にも認定されています。
が、この守口大根の来歴はちょっと複雑です。
江戸時代、大阪の守口地区では宮前大根と呼ばれる細根大根が栽培されており、
守口漬に利用されたことから守口大根と呼ばれていました。
一方、美濃国の長良川沿いでも、古くから「美濃干大根」と呼ばれる細長い大根が作られていました。
ところが、大阪の宮前大根の生産者が減少し、収量も減ってくると、
守口漬用に岐阜の「美濃干大根」を代用するようになりました。
こうして、美濃干大根も守口大根と呼ばれるようになりました。
そして、戦後、岐阜県から愛知県に導入されました。
わかりやすくするために、「守口大根」を青と赤で色分けして書いてみましたが、
このふたつは別の品種。
なにわの伝統野菜に認定されている守口大根と
あいちの伝統野菜に認定されている守口大根は別の品種です。
さて、今回いただいた守口漬は木曽川河畔で栽培された守口大根が使われています。

職人が一本一本、指先で確認し、塩漬を二度、酒粕で二度、さらに仕上漬をします。
その期間、足かけ三年・・・。
袋から出してみましょう。

約40cmの守口大根が出てきました。
まわりの粕を丁寧にふき取ってカットしてみました。

職人さんの手間暇を惜しまない心が、このきれいなべっこう色を守り、
伝統の味を今に伝えてくれます。
ただ、このべっこう色は危険。
お酒を飲んだ気分になるので、運転する予定のない時にいただく方が良いかも・・・。(^_-)-☆
ごちそうさまでした。