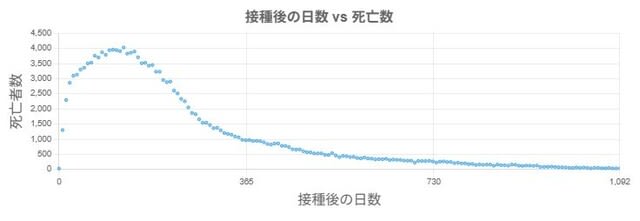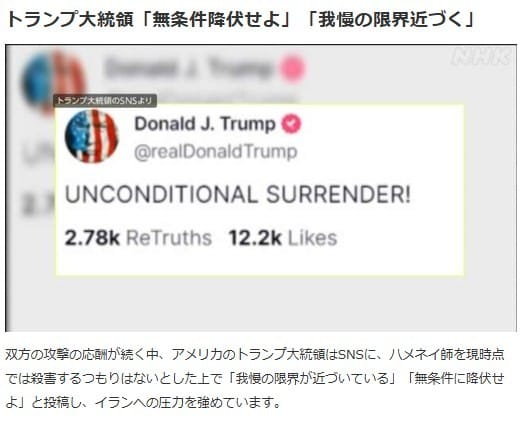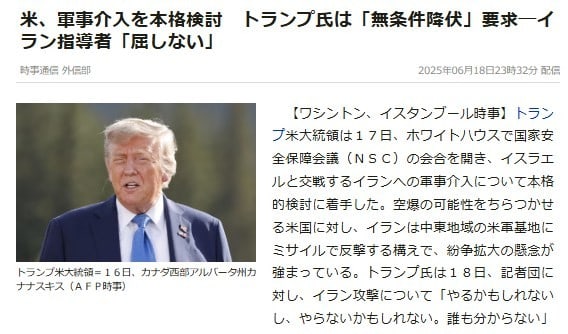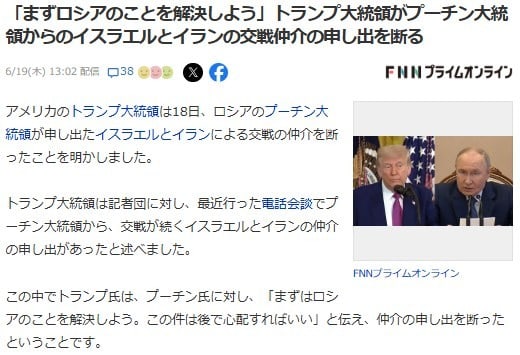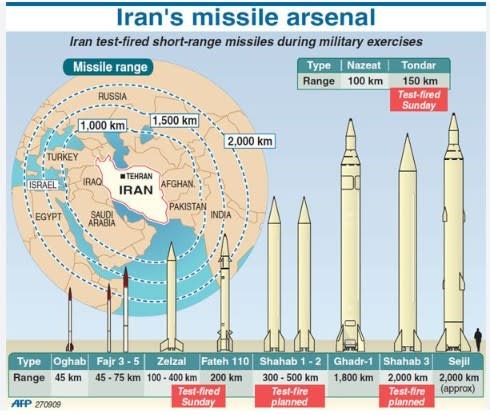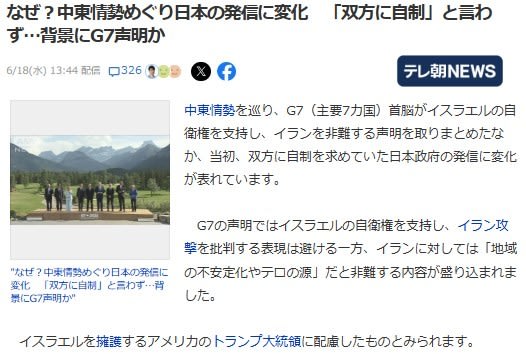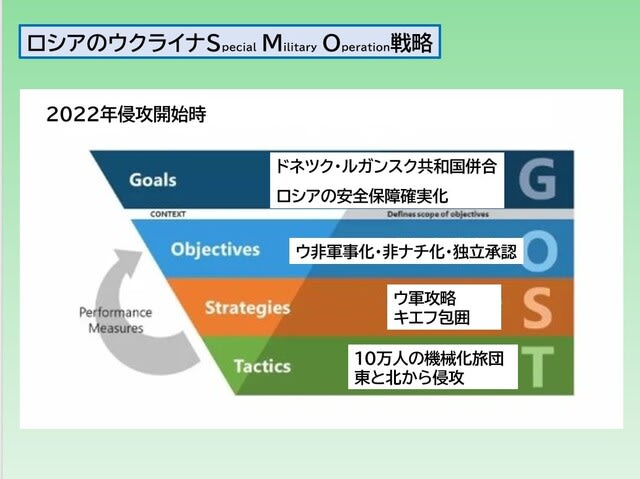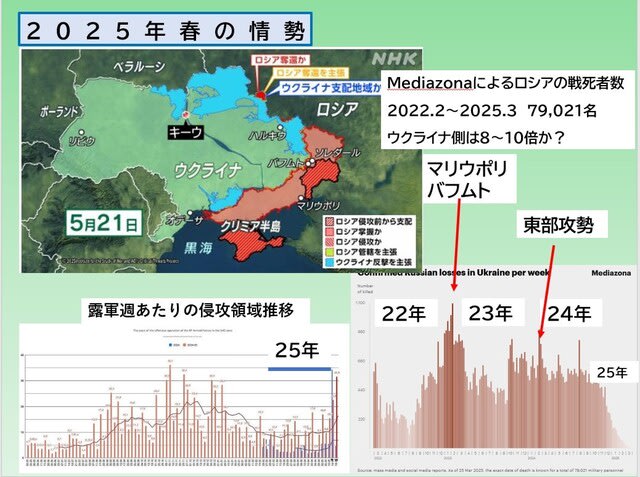2025年6月28から29日、大阪で開催された日本透析医学会総会に参加しました。28日金曜から開催されていましたが、透析施設は日曜以外全曜日営業日なので、実際には土日は交代で、主に日曜参加という人が多いのが実際でしょう。内容も同様のテーマで重なった物も多く、繰り返し発表になる演者もある所が他の学会と異なります。参加者も医師、看護師、臨床工学士、栄養士など透析医療に関わる人全てなので1万人規模の大きな学会になります。私も30年以上この学会に参加していますが、透析医療の発達と透析患者の変遷で他の医学会同様内容や特集となるテーマはかなり変化してきました。その中で備忘録を兼ねて特徴的だったテーマをまとめておきます。

各種ダイアライザーの進化や、透析液を血液と混ぜてから透析するOn-line HDFが普及している事は以前と変わらないのですが、学会として専門医・指導医維持のための研修を学会期間中に行うと、参加者が研修に集中してそれ以外の催しがガラガラになってしまうという弊害を避けるために、今回は、研修は全て学会終了後にオンライン配信することにしたのは良い試みと言えるでしょう。他の学会も次第にその方向に移りつつあります。コロナ禍によるオンライン化発達の良い面とも言えます。以下特徴的なテーマは
- IT活用による省力化や新しい医療の試み
- 患者の高齢化に伴う合併症の管理と予防、フレイル、動脈狭窄、心不全や弁膜症治療。
- 栄養管理、自由な食事の重要性
- 透析を止める時
〇 特別講演 アバターと未来医療 大阪大学 石黒 浩氏

テレビなどでも紹介されて、大阪万博でも人間そっくりのロボットが会場で人気を呼んでいる。ヒトの動きを再現するメカトロニクスはほぼ完成している。後は認知機能をいかに再現するか。ロボット工学では理系と文系の境がなくなり、社会(上下関係)・意識(相手が集中しているか)・意図や欲求・知能・身体性(熱い寒い湿気のうっとおしいとか)・知性を構成的にアプローチして瞬時に生成AIに反応させることが課題になっている。
医療に関して、より初歩的なアバター化として、精神的問題を抱える人がアバターを介して社会参加が進む実践も万博会場で行われている。
〇 CKD-MBDに関する指標の変化(低回転骨を恐れない)
二次性副甲状腺機能亢進の治療において、VitD製剤でなく、カルシミメティクス製剤による適正化は、低回転骨領域までPTHが下降しても海外、国内の統計ともに骨折のリスクが下がる(多分骨からのカルシウム溶出を抑えるから)。これは繰り返し統計が示された点である意味目からうろこのパラダイムシフトと思いました。実臨床では、PTHの下がりはVitD製剤の方が早く、コントロールするには使いやすいのですが、カルシミメティクス併用でカルシウム値を見ながらゆっくり調整すると良さそうと思いました。
〇 骨密度をどうみるか
YAM(若年成人平均骨密度との比較)70%以下は骨粗しょう症として治療の対象になる点は一緒ですが、圧迫骨折や大腿骨頸部骨折などの脆弱骨折があったら骨密度と関係なく治療の対象。一方で骨脆弱性は骨密度70%+骨質30%の影響を受けるので、骨密度の価に一喜一憂することは無意味。FRAXなどのツールで骨折リスクの予測もできる。デノスマブはやめるとリバウンドが大きいので注意が必要。ビスフォスフォネート製剤でつなげば良い。

フレイルとの関連を含めると、運動によるミオカイン(筋肉から出るサイトカイン)が、筋増殖と骨の強化を促すので運動は特に重要。筋量が減るサルコペニアよりも筋力が減るダイナぺニアの方が重篤。
〇 鉄と貧血
フェリチン100以下、トランスフェリン飽和度20%以下は鉄補充が必要。フェリチン300以上は不要。ただしフェリチンは炎症で増加するので注意必要だが、フェリチン50以下は貯蔵鉄も減っている状態なので早急に対応を。鉄が足りないと心血管イベントも増加する。実臨床ではスクロオキシ水酸化鉄(ピートル)はこの目的で多用している。特にHIF-PH阻害剤を造血に使うときは鉄剤が必須と思う。
〇 PPIの汎用化(透析患者の50%が連用)
エリスロポエチン製剤の低反応性につながる。肺炎や骨密度の低下、鉄吸収阻害、リン下降剤の効果低下(特にホスレノールやカルタン)。胃PH2.5以上で腸内細菌の変化、VitB12吸収阻害につながる。ピートルは影響を受けにくいが、透析患者のポリファーマシーを避ける目的で、新しい薬剤のテナパノル(フォゼベル)はPPIとも関係なくリンも下がるので良い薬だと思う(キリンの宣伝になっている)。
PPIは実臨床でもいつも私は問題化して注意しています。
〇 透析患者の食事
カリウム2000mg以下で行ければ、果物や野菜は食べても良い。アシドーシスの予防になる。PLADO(Plant-dominant low-protein diet)は地中海食などでも推奨され、酸化ストレスの予防にもなるが、日本食はもともとPLADOなので和食中心の食事ならば塩分を気を付ければそれで良い。nPCRタンパク異化の指標は、腸内細菌の尿素産生など多くの要素が入って正確ではないので気にしなくて良い。統計ではよく透析すれば余り食べなくても健康が保たれる事が証明された(高齢者)。
最近トウモロコシが旨いので食べ過ぎて高カリウム(6.7mEq/Lとか)になっている透析患者さんが多い。8超えると心臓が止まる。レンジゆででは、1/3切れで300mgなのでこれくらいなら良いですが、一本(100円位で売ってる)食べてしまうと一日のカリウム量の半分に達するので要注意。