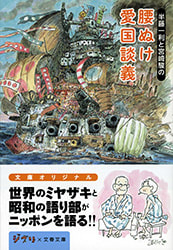

スタジオジブリの「風立ちぬ」封切り前の6月末にNHKの「仕事ハッケン伝」という番組を偶然に見た。漫才コンビ「オリエンタルラジオ」の中田敦彦がジブリに1週間入社して鈴木敏夫プロデューサーのもとで「風立ちぬ」の新聞広告のキャッチコピーづくりにチャレンジするものだった。番組の内容自体にもひきつけられたが、最後に採用された「人間・宮崎駿、72歳の覚悟」というコピーにハッとさせられた。そうか、もうそんなお年なんだ!と。

「風立ちぬ」を観て、宮崎駿の渾身の作品だと痛切に感じ、思い出しながら反芻していたところ、ベネチア国際映画祭のコンペティション部門出品の公式会見で星野社長から宮崎監督の引退発表があった。予感的中・・・・・・。

9/6の宮崎駿ご本人による引退会見は13ヵ国から600人を超す報道陣が集まったという。私もこの日の会見は大注目していた。
「何度もやめるといって騒ぎを起こしてきた人間なので、またって思われているんですが、今回は本気です」と言っての笑顔に、人生にひと区切りをつけた清々しさが伝わってきた。
各国の記者からの質問にどんどん答えていかれたが、心に残ったのは以下のようなことだった。ネット検索の一問一答情報等から、かなり引用(それにしても一問一答といってアップされている文章が情報元によってけっこう違うことがわかった)。
宮崎駿監督、引退会見の一問一答まとめ
東京新聞:宮崎駿監督引退会見 「生きるに値する」伝えた

「『風立ちぬ』は『ポニョ』から5年かかった。その間、シナリオを書いたり漫画を書いたり、いろんなことをやっていましたが、やはり5年かかる。今、次の作品を考え始めると、5年じゃすまないでしょう。この年齢ですから。次は6、7年かかるかもしれない。僕はあと3カ月で73歳。(作品完成までに)80を過ぎてしまう。この前、83歳の半藤一利さんとお話をして、本当にいい先輩がいると思った。僕も83歳になってこうなれたらいいなと。だから(創作を)続けられたらいいと思いますが、今までの仕事の延長線上にはない。僕の長編アニメーションの時代ははっきり終わった。今後、やろうと思っても、それは年寄りの世迷言だと」
僕は児童文学の多くの作品に影響を受けてこの世界に入った人間ですので、基本的に子どもたちに「この世は生きるに値するんだ」ということを伝えるのが自分たちの仕事の根幹になければならないと思ってきました。それは今も変わっていません。
→ここで、どっと目頭が熱くなってしまった。「生きることへの肯定感」がもてない今の時代に、だから宮崎作品は貴重だったのだと痛感する。

アニメ監督にもいろいろな方がいるが、アニメーター出身の僕は自分で描かないと表現できない。どんなに体調を整えて節制しても、集中できる時間が年々減っていく。「ポニョ」に比べると、机から離れるのが30分早くなった。加齢によって発生する問題は仕方がない。僕は僕のやり方を貫くしかない。長編アニメーションは無理だという判断をした。
東映の労働組合で(←ここがカットされてしまう)高畑勲と出会って、いろんな話をしました。それで『ハイジ』をやったとき、まったく打ち合わせの必要がなかったんです。考えていることが分かる。監督はスケジュールが遅れると怒られる。高畑勲は始末書をいくらでも書いていましたけれども、そういうのを見るにつけ、監督はやりたくないと思っていました。しかし、ある時期がきて、監督をやれといわれたときは途方に暮れたんです。僕は、監督や演出をやろうという人間じゃなかった。僕は監督をやっている間も、アニメーターとしてやってきた。それについてはずいぶんプロデューサーが補佐してくれました。そういうチーム、腐れ縁があったおかげでやれてこられたんです。
ジブリをつくったころ(1985年)は、日本が浮かれ騒いでいる時代だったと思います。経済的にもジャパン・アズ・ナンバーワンなんてやっていた。そういうことに、僕は頭にきていました。経済はいいけれど心はどうなんだ。頭にきていないとナウシカなんかつくりません。その後、バブルは崩壊。ソ連も崩壊してもう二度と戦争は起きないと思っていたのにユーゴスラビアでは内戦が起きてしまうというようなことになってしまった。今までの作品の延長上に作れなくなって、僕や高畑監督は豚や狸を主人公にして切り抜けた。そこから長い下降期に入った。バブル崩壊とジブリのイメージは重なっているんです。
「僕は文化人になりたくないんです。僕は町工場のおやじ。それを貫きたいと思っています。」
ジブリの冊子『熱風』で「憲法を変えるのはもってのほか」と発信したことも、「自分の思っていることを率直に話した。ただ、それを発信し続けるかというと、僕は文化人じゃない。その範囲でとどめたい」とのこと。
→なるほど、町工場のおやじさんなんだ、勝手に文化人扱いしてはいけないんだと納得。

半藤一利さんと話をされたことへの言及で書店で対談本が出ていたことを思い出した。手に取ってみたのだが、その時はあまりぴんとこなかった。さっそく紀伊国屋書店に立ち寄って買ってきて読み始めたが、実に面白い。冒頭はその表紙の写真。
半藤一利と宮崎駿の 腰ぬけ愛国談義 (文春ジブリ文庫)

お二人とも漱石ファンだということでたちまち意気投合し、半藤さんの軍艦野郎ぶり、宮崎さんの飛行機野郎ぶりなど、70~80歳代の当時は普通に小国民だった男の子の感覚などもわかっての昭和史をたどる談義に引き込まれた。「持たざる国・日本の行く末を思料する7時間余にわたる対談」をこれから読んでいくことになる。
歴史を学んでこれからのことは考えていかなければならない。また、実践だ。














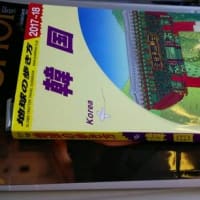
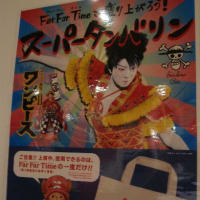

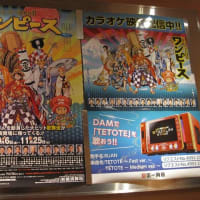
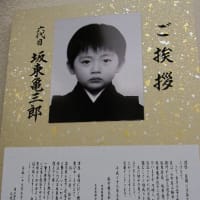
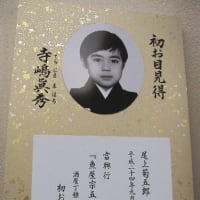

労働組合カットですか!
冷戦は終わったのに、もっと悪くなっていくようで。
東京オリンピックとは、来たくない人たちもいるでしょう。
先日読み終わりましたが、実に面白くて友人に回しました。
労働組合活動の中で高畑勲と出会って意気投合したから「ジブリ」が生まれたのですが、そういうことくだりは省略されていました。労組の組織率が2割を切っていますし、それも御用労働組合を入れての数値ですから、きちんと物申す労働組合の活動は国民の多数派が知りませんよね。運動の側にきちんとした組み立て直しが必要です。雰囲気だけリベラルな人が一定数いても、権力を最大行使した右傾化をとめることはできないと思ってます。
けれども『腰ぬけ愛国談義』の中で、宮崎さんがいいこと言ってました。「多くの人が不安だ、不安だという時には不安がるな。みんなが楽観的になっている時には不安がれ。多数派に押し流されるな」というようなことでした。
不安を煽るだけでなく、元気を出していけるように工夫していくことが必要なんだとは思っています。