
*大阪、九州・佐賀経由で奈良へ
懸案事項だった紀伊半島を一周する旅に出た。その前に、高校および中学校の同窓会に出席するために、九州・佐賀に行くことにした。
「東京→大阪→武雄→佐賀・大町→大阪→奈良→串本(潮岬)→伊勢(三重)→名古屋→東京」という大まかなコースである。
2024(令和6)年9月20日、東京を出発、大阪下車。兵庫・宝塚泊。
9月21日、新神戸発、博多を経て佐賀着。佐賀泊。
9月22日、佐賀・武雄市で高校同窓会出席。武雄泊。
9月23日、佐賀・大町町で中学校同窓会出席。佐賀泊。
9月24日の朝、佐賀を出発し、まずは紀伊半島の真ん中部の「奈良」に向かった。
奈良は何度か行っているのだが、行くところは桜の吉野、石舞台や高松塚のある明日香、里山から離れた室生寺あたりで、教科書に載っている奈良の代表的な東大寺、法隆寺という有名な寺には行っていなかった。
奈良に行って、法隆寺はともかくもなぜ東大寺に行かなかったのだろう。鎌倉の大仏は何度も見ているのに、奈良の大仏を一度も見ていないのは、何だか胸を張れないような気持になってきていた。
日本の大仏といえば、まずは東大寺の大仏をあげざるを得ないだろう。ともかく、東大寺の大仏は見ておかねばと思ったのだ。
「佐賀」駅8時48分発の列車に乗り、「博多」駅10時23分発の新幹線「さくら」で12時59分「新大阪」駅に着いた。大阪から奈良への列車を探した。
奈良に着いたら、すぐに東大寺に行きたかったので、駅に近いところのホテルにしようと、列車のなかでスマホでホテルを探し、JR奈良駅のすぐ近くのホテルを予約した。
スマホが普及して便利になったものだ。電波が届くところはどこででも、列車のなかでも電話連絡ができる。
スマホがない時代は、私のように行き当たりばったりの旅人は、目的地に着いてから駅周辺の観光案内所に出向いて当地の案内書や地図をもらい、宿泊施設を紹介してもらったり調べたりした。小さな町で案内所がない場合や案内所がすでに閉まっているときは、自分で探すしかなかった。
それはそれで何とかなるものだし、苦労や失敗もあるが、それも旅の一部だと思っている。そして、苦い経験や辛い体験ほど長く印象に残っていて、人生に彩りを与えているものだ。
「新大阪」駅13時11分発、「おおさか東線」にて「久宝寺」駅13時43分着。久宝寺駅13時51時51分発、「関西本線」にて「奈良」駅14時18分着。
*奈良・東大寺の大仏
ホテルに荷物を預け、すぐに駅前のバスで東大寺に向かった。
バスの中から鹿が見え隠れした。
東大寺の参道近くでバスを降りると、観光客に交じって鹿がいる。いる、いる。参道を歩くと、もうあちこちに鹿がいる。人を恐れないどころか、観光客には寄ってきて愛嬌を振っている。最初は可愛いと思っていたのが、エサをせびりに寄ってくるたびに、だんだん煩わしくなってくる。
それよりも、歩くのに注意が必要なのだ。というのも、道路にはあちこちに焦げ茶の塊りや丸い粒が落ちている。すでに踏みつぶされてか固まっているのもある。鹿の糞である。これを踏まないように足元を注意しながら歩かなければならないのだ。
ニューデリーの道では、あちこち牛の糞が落ちていたのを思い出した。
鹿を払いのけ足元に注意しながら参道を歩いていくと、大きな門に着く。
「南大門」である。門の左右には、運慶、快慶等作とされる阿吽の金剛力士立像が見る者を睥睨している。
南大門をくぐり、さらに進んで右手の鏡池を過ぎると中門がある。中門の先に、大仏が収められている「大仏殿」が現れる。長らく「世界最大の木造建築」といわれてきた、見るからに大きな伝統的建築物だ。
さてと、ふと足首を返してスニーカーの裏底を見てみた。すると、注意しながら歩いてきたはずなのに底に黒いものが……。
何とかしようと思って左右を見まわすと、中門から大仏殿に向かう道の右側に細い水路が延びている。浅く、水がゆっくりと流れているようである。スニーカーを浸すと底がちょうど浸かるぐらいなので、洗ってみたがきれいにとれない。
その先、大仏殿の手前の右手に手水舎があった。そこで、手を洗う(清める)とともに、スニーカーの底を洗う、もとい、浄(きよ)める。
いよいよ殿の中に入って、大仏を見た。いや、大きいので仰ぎ見たといった方が正しい。
大仏は本尊一体だけではなかった。左右に、従わせるかのように金色に輝く菩薩像が置かれていた。(写真)
中央の本尊である大仏は、全体に黒く、薄目で正面を見ている表情は優しいのか厳しいのかわからない。左手は開いて膝の上にのせ、右手は前に曲げた掌を正面を向けている。
正面に向けた右手は、人々の恐れを取り除き安らぎをもたらす印らしいが、これ以上近づくなといっているように見える。
しばらくじっと見ていたが、人を寄せつけないような威厳がある。
「東大寺」は華厳宗の大本山で、奈良時代(8世紀)に聖武天皇が建立した寺である。本尊の大仏は、正式には盧舎那仏(るしゃなぶつ)といい、大地震や戦火に2度あって、現在の像は江戸時代に修復されたものである。像の高さは約14.7m。鎌倉の大仏の像高は約11.4mであるので、こちらの大仏が幾分大きい。
個人的感想でいえば、鎌倉の大仏の方に親しみが持てる。
鎌倉の大仏は厳かな建物のなかに鎮座しているのではなく路上にあるので、後ろから見ると少し侘びしげもに見える(奈良の大仏は後ろ姿は見られない)。
手は、両手で膝の上で組んだまま(状態)である。相手に説教するのでもなく、自我に没頭しようとしているように見える。
鎌倉の大仏を見ると何だかほっとするが、奈良の大仏にはそれはない。威圧感の方が大きい。
威厳のある大仏殿をあとにして、広い境内の東奥にある「二月堂」に向かった。
二月堂の横には三月堂が、前には四月堂があった。
階段を上がった二月堂からは、奈良市街が一望できるのびやかな風景が広がっていた。
東大寺をあとに、近くにあるこれも有名な「興福寺」に向かうことにした。
懸案事項だった紀伊半島を一周する旅に出た。その前に、高校および中学校の同窓会に出席するために、九州・佐賀に行くことにした。
「東京→大阪→武雄→佐賀・大町→大阪→奈良→串本(潮岬)→伊勢(三重)→名古屋→東京」という大まかなコースである。
2024(令和6)年9月20日、東京を出発、大阪下車。兵庫・宝塚泊。
9月21日、新神戸発、博多を経て佐賀着。佐賀泊。
9月22日、佐賀・武雄市で高校同窓会出席。武雄泊。
9月23日、佐賀・大町町で中学校同窓会出席。佐賀泊。
9月24日の朝、佐賀を出発し、まずは紀伊半島の真ん中部の「奈良」に向かった。
奈良は何度か行っているのだが、行くところは桜の吉野、石舞台や高松塚のある明日香、里山から離れた室生寺あたりで、教科書に載っている奈良の代表的な東大寺、法隆寺という有名な寺には行っていなかった。
奈良に行って、法隆寺はともかくもなぜ東大寺に行かなかったのだろう。鎌倉の大仏は何度も見ているのに、奈良の大仏を一度も見ていないのは、何だか胸を張れないような気持になってきていた。
日本の大仏といえば、まずは東大寺の大仏をあげざるを得ないだろう。ともかく、東大寺の大仏は見ておかねばと思ったのだ。
「佐賀」駅8時48分発の列車に乗り、「博多」駅10時23分発の新幹線「さくら」で12時59分「新大阪」駅に着いた。大阪から奈良への列車を探した。
奈良に着いたら、すぐに東大寺に行きたかったので、駅に近いところのホテルにしようと、列車のなかでスマホでホテルを探し、JR奈良駅のすぐ近くのホテルを予約した。
スマホが普及して便利になったものだ。電波が届くところはどこででも、列車のなかでも電話連絡ができる。
スマホがない時代は、私のように行き当たりばったりの旅人は、目的地に着いてから駅周辺の観光案内所に出向いて当地の案内書や地図をもらい、宿泊施設を紹介してもらったり調べたりした。小さな町で案内所がない場合や案内所がすでに閉まっているときは、自分で探すしかなかった。
それはそれで何とかなるものだし、苦労や失敗もあるが、それも旅の一部だと思っている。そして、苦い経験や辛い体験ほど長く印象に残っていて、人生に彩りを与えているものだ。
「新大阪」駅13時11分発、「おおさか東線」にて「久宝寺」駅13時43分着。久宝寺駅13時51時51分発、「関西本線」にて「奈良」駅14時18分着。
*奈良・東大寺の大仏
ホテルに荷物を預け、すぐに駅前のバスで東大寺に向かった。
バスの中から鹿が見え隠れした。
東大寺の参道近くでバスを降りると、観光客に交じって鹿がいる。いる、いる。参道を歩くと、もうあちこちに鹿がいる。人を恐れないどころか、観光客には寄ってきて愛嬌を振っている。最初は可愛いと思っていたのが、エサをせびりに寄ってくるたびに、だんだん煩わしくなってくる。
それよりも、歩くのに注意が必要なのだ。というのも、道路にはあちこちに焦げ茶の塊りや丸い粒が落ちている。すでに踏みつぶされてか固まっているのもある。鹿の糞である。これを踏まないように足元を注意しながら歩かなければならないのだ。
ニューデリーの道では、あちこち牛の糞が落ちていたのを思い出した。
鹿を払いのけ足元に注意しながら参道を歩いていくと、大きな門に着く。
「南大門」である。門の左右には、運慶、快慶等作とされる阿吽の金剛力士立像が見る者を睥睨している。
南大門をくぐり、さらに進んで右手の鏡池を過ぎると中門がある。中門の先に、大仏が収められている「大仏殿」が現れる。長らく「世界最大の木造建築」といわれてきた、見るからに大きな伝統的建築物だ。
さてと、ふと足首を返してスニーカーの裏底を見てみた。すると、注意しながら歩いてきたはずなのに底に黒いものが……。
何とかしようと思って左右を見まわすと、中門から大仏殿に向かう道の右側に細い水路が延びている。浅く、水がゆっくりと流れているようである。スニーカーを浸すと底がちょうど浸かるぐらいなので、洗ってみたがきれいにとれない。
その先、大仏殿の手前の右手に手水舎があった。そこで、手を洗う(清める)とともに、スニーカーの底を洗う、もとい、浄(きよ)める。
いよいよ殿の中に入って、大仏を見た。いや、大きいので仰ぎ見たといった方が正しい。
大仏は本尊一体だけではなかった。左右に、従わせるかのように金色に輝く菩薩像が置かれていた。(写真)
中央の本尊である大仏は、全体に黒く、薄目で正面を見ている表情は優しいのか厳しいのかわからない。左手は開いて膝の上にのせ、右手は前に曲げた掌を正面を向けている。
正面に向けた右手は、人々の恐れを取り除き安らぎをもたらす印らしいが、これ以上近づくなといっているように見える。
しばらくじっと見ていたが、人を寄せつけないような威厳がある。
「東大寺」は華厳宗の大本山で、奈良時代(8世紀)に聖武天皇が建立した寺である。本尊の大仏は、正式には盧舎那仏(るしゃなぶつ)といい、大地震や戦火に2度あって、現在の像は江戸時代に修復されたものである。像の高さは約14.7m。鎌倉の大仏の像高は約11.4mであるので、こちらの大仏が幾分大きい。
個人的感想でいえば、鎌倉の大仏の方に親しみが持てる。
鎌倉の大仏は厳かな建物のなかに鎮座しているのではなく路上にあるので、後ろから見ると少し侘びしげもに見える(奈良の大仏は後ろ姿は見られない)。
手は、両手で膝の上で組んだまま(状態)である。相手に説教するのでもなく、自我に没頭しようとしているように見える。
鎌倉の大仏を見ると何だかほっとするが、奈良の大仏にはそれはない。威圧感の方が大きい。
威厳のある大仏殿をあとにして、広い境内の東奥にある「二月堂」に向かった。
二月堂の横には三月堂が、前には四月堂があった。
階段を上がった二月堂からは、奈良市街が一望できるのびやかな風景が広がっていた。
東大寺をあとに、近くにあるこれも有名な「興福寺」に向かうことにした。











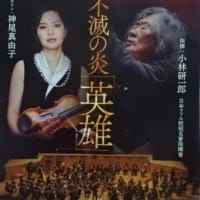

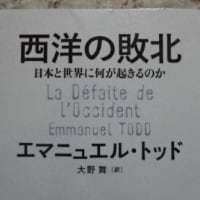











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます