
*列車の旅の魅惑
私は基本的に国内の旅では、飛行機は使わず列車である。飛行機による“点の旅”でなく、列車およびバスによる“線の旅”を旨としている。
佐賀に帰省(帰郷)する際も、学生時代から年に2~3回帰っていたので、計150回くらい東京~九州を往復したことになるが、飛行機を利用したのは僅か3回である。もうずいぶん昔のことだが、東京(羽田)—福岡空港2回、東京—佐賀空港(開港時に)1回のみ。
あと、船(東京港―徳島港―新門司港)で1回、夜行バス(東京—福岡)で1回がある。
東京から九州・佐賀に行くのに、新幹線開通後は主に東京~博多間は新幹線を利用するのが多いが、ときに気紛れに山陰本線を各駅列車で乗り継いで関門海峡を渡ったり、寝台特急列車で四国へ行って、八幡浜あるいは宿毛から九州(大分県)へ船で渡り、そこから佐賀へ帰ったりもした。
要は、鉄道オタクではないが列車が好きなのである。
列車で、今までの景色を置き去りにして、新しい風景に分け入っていく感覚がいい。それに加えて、窓の外の景色を見ているという一つの状態で(例えば本を読んだり、食事(駅弁)をしたりお茶を飲んだり、他に何かをやったりしている状態でも)、目的地もしくはどこかに向かって移動しているという二重感覚が心地よい。
旅するときは、軽い文庫か新書本を1冊バッグに入れていくのだが、ほとんど読んだことがない。本を読むのは家でもできると考えたら、そのときの通り過ぎ去る一瞬一瞬の風景、そこにいる状態が大切だと思えるのだ。
前にも見た同じ場所・景色でも、季節やそのときの空が違うように、あるいは以前とそのときの自分の気持ちも違っているように、それは同じ景色ではない。通り過ぎる風景は、人生の時間のようだ。
だから、列車は速ければいいというものでもない。
*北の宗谷岬から下北半島、津軽半島の突端、終着駅
人はなぜか突端、先端に好奇心を抱くものだ。そして、最果てという響きに心魅かれ、そこへ行ってみたいと思う。
南極や北極を目指すのも、エベレストやマッターホルンに登るのも、その現れだろう。
そんな地球規模、世界規模でなくとも、日本の国内でも地図を眺めていると、気になる突端、先端、最果て、行き場のない終着駅はあるものだ。
列車が好きだといっても突端、先端を意識して周ったことはないのだが、思えば、何となくそこへたどり着いた、誘われるように行ってしまったということはある。
地図を見ていると、突端、先端、それに終着駅は気になる存在ではある。
終着駅の最たるところは、北の突端にある「稚内」駅であろう。北海道に行ったら、一度は行かねばと思わせる駅である。
日本最北端の駅、北海道の「稚内」(宗谷本線)には2度行き、そこから利尻・礼文島にも渡ったが、今思えば近くの最北端の地、宗谷岬に行かなかったのが悔やまれる。
本州の最北端といえば、北海道と向かい合う斧のような形の青森県の「下北半島」である。下北半島は、本州の最北端ということだけでなく、その形からして何だろう、何かあるなと思わせる。
この半島は恐山に惹かれ2度行ったが、野辺地から大湊(おおみなと)線で終着駅の「大湊駅」で降りることになる。
現在(2024年)は、その一つ手前の「下北駅」が緯度としては本州最北端の駅であるが、当時はそのことを知らなかったので下北駅は通り過ぎただけである。そのことは全く意識していなかったのだ。住んでいる近くの下北沢駅は何度も行ったというのに!
恐山をあとにして、陸奥湾側から仏ヶ浦をなぞり突端の大間崎を周り下風呂温泉あたりにたどり着くという航路で、2回とも船で半島を周回した。
下北半島は、何やら掴みづらい半島ではある。
下北半島と向かい合っているのが「津軽半島」である。この半島と北海道の間に津軽海峡がまたがっている。
かつて、この海峡を津軽連絡船が通っていた。津軽からこの船が離れるときに、船に乗っている人と陸地で別れを惜しむ人たちがテープを繋いで、手を振る姿が映し出されるたびに郷愁を抱いた。
現在は青函トンネルが開通し、本州と北海道は列車で繋がっているが、トンネルが開通する前の1974年と1983年、津軽連絡船に乗って北海道へ渡った。
1988(昭和63)年に開通した青函トンネルは世界最長の海底トンネルであり、2016(平成28)年にスイスのアルプス縦貫「ゴッタルドベーストンネル」が開通するまでは、世界最長のトンネルであった。
1997(平成9)年のこと。札幌へ行く途中、青森から津軽線の終着駅で降りたった。竜飛(たっぴ)崎を遠く見ながら、凧あげをしていたのを眺めるなどしばらく時間を費やしたあと、青函トンネルで函館へ渡る「海峡線」に乗った。
海底を通る海峡線に乗った私は、トンネルの途中の駅「竜飛海底駅」で降りた。トンネル内に「竜飛海底駅」(青森県側)と「吉岡海底駅」(北海道側)という2つの海底駅があったのだ。
降りたといっても、そこに街があり住人がいるわけではない。世界的にも珍しい海底トンネルの見学のための駅である。
竜飛海底駅は本州最北端の駅だった。そして、吉岡海底駅は北海道最南端の駅だったし、海面下149.5mの世界一低い位置にある鉄道駅であった。
過去形で書いたのは、2014(平成26)年、北海道新幹線開業に伴い駅は廃止され、今は緊急時の避難施設となり、両駅はなくなったのだ。
今にして思えば、世にも貴重で稀有な海底のトンネル駅だった。
*九州最南端、最西端の駅
2016(平成28)年、霧島へ行ったとき、鹿児島から九州の最南端を走る大隅半島の終着駅「枕崎駅」、その先の「坊津」(ぼうのつ)に行くため、指宿枕崎線に乗った。そのとき途中の駅「西大山駅」が日本最南端の駅(普通鉄道)と知った。開聞岳が目の前に見える素朴な駅だった。
※2003(平成15)年、沖縄都市モノレールが開通し、モノレールも含めると「赤嶺駅」が日本最南端の駅になる。
長崎の平戸島に行くとき降りたのが松浦鉄道西九州線「たびら平戸口駅」である。ここが日本最西端の駅(普通鉄道)である。
この近くにある煉瓦造りの田平天主堂には、なんとフランスにある「ルルドの泉」が造られている。
*紀伊半島の突端「潮岬」への想い
地図で四国を見ると、カニを上から見たような形をしている。そして、下(太平洋)の方の両サイドに尖った先端(岬)が脚のように出ている。
四国へ行ったときである。
高松から徳島、牟岐線を経て、高知の太平洋・土佐湾の右(東)サイドの尖った先端である「室戸岬」へ行って、予土線で宇和島へ行き、八幡浜から船で九州(別府)へ帰ってきたとき、もう一つの左(西)の先端「足摺岬」が気になった。
それで、次に四国に行ったとき、室戸岬を通って、土佐くろしお鉄道で「足摺岬」へ行った。そして、宿毛から船で九州(佐伯)へ渡った。
そのとき、漠然と「潮岬」の存在が浮かんできた。
紀伊半島の先端である潮岬に行かねばならない、と思った(義務ではないのに)。和歌山市や新宮・那智には行ってはいるのだが、紀伊半島の突端には行っていないのだ。
そう思っているうちに何年かが過ぎていった。人生とは、そうやって老いていくものだなぁと、少し寂しくもなった。振り返れば、やり残したものがいっぱいあるのだ。
この秋、紀伊半島に行こうと決意した。
*紀伊半島とは
日本列島の地図を見ると、南の太平洋側には、いくつかの半島が突き出ているというより垂れ下がっているようにある。房総半島(千葉)も、伊豆半島(静岡)も、紀伊半島も、似たような形をしている。
そのなかでも、日本列島のほぼ中央にある紀伊半島の大きさは目につく。この半島こそ、日本の最大の半島なのである。
それでは、紀伊半島はどこからどこを言うのだろう。
半島のくびれから見ると、西は大阪(大阪府)あたりで、東は津(三重県)あたりだろうか。
半島の内陸部にはでんと奈良県があり、奈良の西、大阪から南は和歌山県が太平洋岸まで延びている。奈良の東、和歌山の北に三重県があり、名古屋(愛知県)へ続く。
半島の中央部には、千メートル以上、2千メートル近い山が連なる紀伊山地が横断している。紀伊は木の国からきているといわれているように、内陸部は山でおおわれている。それを包むように海が広がり、その先端が太平洋を望む「潮岬」なのである。
(写真は、この度行った潮岬と本州最南端の潮岬灯台)
この秋に紀伊半島に行こうと思っていた矢先に、9月に九州の佐賀の出身高校、武雄で同窓会を行うという知らせが来た。東京から帰ってくる者がいるからと、その隣町の出身中学校、大町町で相乗りの形で、次の日に中学校の同窓会を開くことになった。
ということで、九州に行った帰りに、紀伊半島を周ることにした。
「東京→大阪→武雄→佐賀・大町→大阪→奈良→串本(潮岬)→伊勢(三重)→名古屋→東京」という大まかなコースを想い描いた。
とりあえず、宿泊ホテルも決めずに地図を頼りに出発した。
私は基本的に国内の旅では、飛行機は使わず列車である。飛行機による“点の旅”でなく、列車およびバスによる“線の旅”を旨としている。
佐賀に帰省(帰郷)する際も、学生時代から年に2~3回帰っていたので、計150回くらい東京~九州を往復したことになるが、飛行機を利用したのは僅か3回である。もうずいぶん昔のことだが、東京(羽田)—福岡空港2回、東京—佐賀空港(開港時に)1回のみ。
あと、船(東京港―徳島港―新門司港)で1回、夜行バス(東京—福岡)で1回がある。
東京から九州・佐賀に行くのに、新幹線開通後は主に東京~博多間は新幹線を利用するのが多いが、ときに気紛れに山陰本線を各駅列車で乗り継いで関門海峡を渡ったり、寝台特急列車で四国へ行って、八幡浜あるいは宿毛から九州(大分県)へ船で渡り、そこから佐賀へ帰ったりもした。
要は、鉄道オタクではないが列車が好きなのである。
列車で、今までの景色を置き去りにして、新しい風景に分け入っていく感覚がいい。それに加えて、窓の外の景色を見ているという一つの状態で(例えば本を読んだり、食事(駅弁)をしたりお茶を飲んだり、他に何かをやったりしている状態でも)、目的地もしくはどこかに向かって移動しているという二重感覚が心地よい。
旅するときは、軽い文庫か新書本を1冊バッグに入れていくのだが、ほとんど読んだことがない。本を読むのは家でもできると考えたら、そのときの通り過ぎ去る一瞬一瞬の風景、そこにいる状態が大切だと思えるのだ。
前にも見た同じ場所・景色でも、季節やそのときの空が違うように、あるいは以前とそのときの自分の気持ちも違っているように、それは同じ景色ではない。通り過ぎる風景は、人生の時間のようだ。
だから、列車は速ければいいというものでもない。
*北の宗谷岬から下北半島、津軽半島の突端、終着駅
人はなぜか突端、先端に好奇心を抱くものだ。そして、最果てという響きに心魅かれ、そこへ行ってみたいと思う。
南極や北極を目指すのも、エベレストやマッターホルンに登るのも、その現れだろう。
そんな地球規模、世界規模でなくとも、日本の国内でも地図を眺めていると、気になる突端、先端、最果て、行き場のない終着駅はあるものだ。
列車が好きだといっても突端、先端を意識して周ったことはないのだが、思えば、何となくそこへたどり着いた、誘われるように行ってしまったということはある。
地図を見ていると、突端、先端、それに終着駅は気になる存在ではある。
終着駅の最たるところは、北の突端にある「稚内」駅であろう。北海道に行ったら、一度は行かねばと思わせる駅である。
日本最北端の駅、北海道の「稚内」(宗谷本線)には2度行き、そこから利尻・礼文島にも渡ったが、今思えば近くの最北端の地、宗谷岬に行かなかったのが悔やまれる。
本州の最北端といえば、北海道と向かい合う斧のような形の青森県の「下北半島」である。下北半島は、本州の最北端ということだけでなく、その形からして何だろう、何かあるなと思わせる。
この半島は恐山に惹かれ2度行ったが、野辺地から大湊(おおみなと)線で終着駅の「大湊駅」で降りることになる。
現在(2024年)は、その一つ手前の「下北駅」が緯度としては本州最北端の駅であるが、当時はそのことを知らなかったので下北駅は通り過ぎただけである。そのことは全く意識していなかったのだ。住んでいる近くの下北沢駅は何度も行ったというのに!
恐山をあとにして、陸奥湾側から仏ヶ浦をなぞり突端の大間崎を周り下風呂温泉あたりにたどり着くという航路で、2回とも船で半島を周回した。
下北半島は、何やら掴みづらい半島ではある。
下北半島と向かい合っているのが「津軽半島」である。この半島と北海道の間に津軽海峡がまたがっている。
かつて、この海峡を津軽連絡船が通っていた。津軽からこの船が離れるときに、船に乗っている人と陸地で別れを惜しむ人たちがテープを繋いで、手を振る姿が映し出されるたびに郷愁を抱いた。
現在は青函トンネルが開通し、本州と北海道は列車で繋がっているが、トンネルが開通する前の1974年と1983年、津軽連絡船に乗って北海道へ渡った。
1988(昭和63)年に開通した青函トンネルは世界最長の海底トンネルであり、2016(平成28)年にスイスのアルプス縦貫「ゴッタルドベーストンネル」が開通するまでは、世界最長のトンネルであった。
1997(平成9)年のこと。札幌へ行く途中、青森から津軽線の終着駅で降りたった。竜飛(たっぴ)崎を遠く見ながら、凧あげをしていたのを眺めるなどしばらく時間を費やしたあと、青函トンネルで函館へ渡る「海峡線」に乗った。
海底を通る海峡線に乗った私は、トンネルの途中の駅「竜飛海底駅」で降りた。トンネル内に「竜飛海底駅」(青森県側)と「吉岡海底駅」(北海道側)という2つの海底駅があったのだ。
降りたといっても、そこに街があり住人がいるわけではない。世界的にも珍しい海底トンネルの見学のための駅である。
竜飛海底駅は本州最北端の駅だった。そして、吉岡海底駅は北海道最南端の駅だったし、海面下149.5mの世界一低い位置にある鉄道駅であった。
過去形で書いたのは、2014(平成26)年、北海道新幹線開業に伴い駅は廃止され、今は緊急時の避難施設となり、両駅はなくなったのだ。
今にして思えば、世にも貴重で稀有な海底のトンネル駅だった。
*九州最南端、最西端の駅
2016(平成28)年、霧島へ行ったとき、鹿児島から九州の最南端を走る大隅半島の終着駅「枕崎駅」、その先の「坊津」(ぼうのつ)に行くため、指宿枕崎線に乗った。そのとき途中の駅「西大山駅」が日本最南端の駅(普通鉄道)と知った。開聞岳が目の前に見える素朴な駅だった。
※2003(平成15)年、沖縄都市モノレールが開通し、モノレールも含めると「赤嶺駅」が日本最南端の駅になる。
長崎の平戸島に行くとき降りたのが松浦鉄道西九州線「たびら平戸口駅」である。ここが日本最西端の駅(普通鉄道)である。
この近くにある煉瓦造りの田平天主堂には、なんとフランスにある「ルルドの泉」が造られている。
*紀伊半島の突端「潮岬」への想い
地図で四国を見ると、カニを上から見たような形をしている。そして、下(太平洋)の方の両サイドに尖った先端(岬)が脚のように出ている。
四国へ行ったときである。
高松から徳島、牟岐線を経て、高知の太平洋・土佐湾の右(東)サイドの尖った先端である「室戸岬」へ行って、予土線で宇和島へ行き、八幡浜から船で九州(別府)へ帰ってきたとき、もう一つの左(西)の先端「足摺岬」が気になった。
それで、次に四国に行ったとき、室戸岬を通って、土佐くろしお鉄道で「足摺岬」へ行った。そして、宿毛から船で九州(佐伯)へ渡った。
そのとき、漠然と「潮岬」の存在が浮かんできた。
紀伊半島の先端である潮岬に行かねばならない、と思った(義務ではないのに)。和歌山市や新宮・那智には行ってはいるのだが、紀伊半島の突端には行っていないのだ。
そう思っているうちに何年かが過ぎていった。人生とは、そうやって老いていくものだなぁと、少し寂しくもなった。振り返れば、やり残したものがいっぱいあるのだ。
この秋、紀伊半島に行こうと決意した。
*紀伊半島とは
日本列島の地図を見ると、南の太平洋側には、いくつかの半島が突き出ているというより垂れ下がっているようにある。房総半島(千葉)も、伊豆半島(静岡)も、紀伊半島も、似たような形をしている。
そのなかでも、日本列島のほぼ中央にある紀伊半島の大きさは目につく。この半島こそ、日本の最大の半島なのである。
それでは、紀伊半島はどこからどこを言うのだろう。
半島のくびれから見ると、西は大阪(大阪府)あたりで、東は津(三重県)あたりだろうか。
半島の内陸部にはでんと奈良県があり、奈良の西、大阪から南は和歌山県が太平洋岸まで延びている。奈良の東、和歌山の北に三重県があり、名古屋(愛知県)へ続く。
半島の中央部には、千メートル以上、2千メートル近い山が連なる紀伊山地が横断している。紀伊は木の国からきているといわれているように、内陸部は山でおおわれている。それを包むように海が広がり、その先端が太平洋を望む「潮岬」なのである。
(写真は、この度行った潮岬と本州最南端の潮岬灯台)
この秋に紀伊半島に行こうと思っていた矢先に、9月に九州の佐賀の出身高校、武雄で同窓会を行うという知らせが来た。東京から帰ってくる者がいるからと、その隣町の出身中学校、大町町で相乗りの形で、次の日に中学校の同窓会を開くことになった。
ということで、九州に行った帰りに、紀伊半島を周ることにした。
「東京→大阪→武雄→佐賀・大町→大阪→奈良→串本(潮岬)→伊勢(三重)→名古屋→東京」という大まかなコースを想い描いた。
とりあえず、宿泊ホテルも決めずに地図を頼りに出発した。












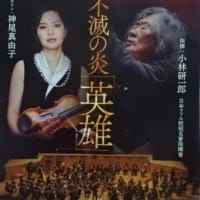

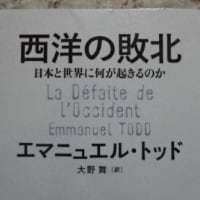










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます