
佐賀の地方町で育った僕には、隣の福岡県の大牟田市は大都会だった。父親の両親と妹、つまり僕の祖父母と叔母が住んでいた。
子供のころ、夏休みや冬休みには父や母に連れられてよく大牟田に遊びに行った。僕が少し大きくなったころには、弟と二人で行ったこともあった。
祖父母の家は平屋の市営住宅だったが、建てられて間もないと思われるきれいな造りだった。桜色の屋根で、小さいながらも庭があり、佐賀のわが家に比べればとてもしゃれていると感じた。
祖父は隠居していて、書画や木の彫り物を楽しんでいる風流人だった。
かつて大牟田は、日本有数の石炭の町として栄えていた。文字通り、町の中心に栄町があった。そこには松屋デパートがあり、そこに連れて行ってもらうのが楽しみだった。
松屋には屋上遊園地があり、その下の階の食堂で、旗のついたお子様ランチを食べるのが何よりの楽しみだった。
僕が子どもではなくなったころ、石油に代わられた石炭産業は不況になり、1960年代後半からは大牟田も徐々に寂れていった。そして、1997(平成9)年には、町を支えていた三井三池鉱も閉山となった。
僕も高校を卒業後、東京に出てきてからは、めったに祖父母の住む大牟田に行くこともなくなった。
そして今は、祖父母も叔母もなくなり、大牟田には住んでいた家屋もない。
*
人口の推移を見れば、町の盛衰がよくわかる。
1960(昭和35)年当時の福岡県の人口を見ると、以下の通りである(千人以下四捨五入)。
・福岡市 65万人
・八幡市 32万人
・小倉市 29万人
・大牟田市 21万人
・久留米市 16万人
・門司市 15万人
八幡、小倉、門司、戸畑、若松の5市は、1963年に合併して北九州市として103万都市となり、政令指定都市となった。北九州市から遅れること9年後の1972年に政令市となった福岡市が、100万人を突破したのは1975年のことである。
現在(2013年)の人口はどうなっているかといえば、その後、福岡市への一極集中が加速し、九州におけるミニ東京と化している。
・福岡市 150万人
・北九州市 97万人
・久留米市 30万人
・大牟田市 12万人
福岡市と久留米市を含むその周辺都市が人口を増やすなかで、大牟田市の人口減は著しい。大牟田市と久留米市は逆転している。
2011年、鹿児島まで延びた九州新幹線の鹿児島ルートが開通し、大牟田市にも停車するのだが、この恩恵を大牟田は得ていない。地図を見てもわかるように、新幹線の停車駅である新大牟田駅は中心街とはほど遠いところで、JRの在来線の駅とも離れたところにある。どうしてこんなところにあるのかと、誰もが疑問に思うところにあるのだ。
それに比し久留米は、新幹線はJR在来線の久留米駅と直結していて利便性は高い。
哀しいかな、これでは差がつく一方である。
*
5月の半ばのころ、関西に住む弟が少し暇がとれたと言って、珍しく佐賀に帰ってきた。それで、去る晴れた日、二人で大牟田へ行くことにした。いや、もうだいぶん日が過ぎたので、行ったと過去形だ。
子供のころ行ったように、電車とバスを乗り継いで、歩いてあの家に行くことにした。おぼろげに脳裏に残っている風景をなぞるように、歩いてみたのだ。子供のころの足跡を確認するかのように。
佐世保線の佐賀駅で降りて、バスで柳川に行った。
子どものころは、佐賀駅から列車に乗っていた。今では廃線でなくなった佐賀駅から福岡県の瀬高まで通った国鉄の佐賀線で、柳川まで行き西鉄電車に乗り換えていたと思う。佐賀線が廃線になってからは、佐賀からバスを利用していた。
佐賀線は、佐賀・諸富から福岡・大川に行く途中の、今では重要文化財となっている筑後川に架かる昇開橋を走った。
柳川から大牟田行の西鉄電車に乗る。
柳川から、徳増、塩塚、中島と田園地帯を電車は走る。中島では、有明海に広がる河口に何艘も船が停泊している。昔ながらの風景だ。
さらに、江の浦、開、渡瀬と過ぎて、倉永で降りる。
倉永の駅の近くに来ると、高いとんがり屋根の建物が見える。「緑の丘の赤い屋根」ではないけれど、歌の文句のようなしゃれた建物だと思っていた。
倉永の次は銀水だ。銀水で降りたことはなかったが、「次はギンスイ」と、その名前を聞いただけで、銀水には何があるのだろう、どんなきらびやかな街だろうと想像したものだ。
倉永の駅を降り改札口を出て、昼時なので、どこか食堂でもないかと見渡したが、店などは見当たらないそっけない駅前だ。駅前は、すぐ目の前に道路が左右に走っている。
とりあえず、進もう。
駅前の道路を渡ると、前に古い石垣の家が見える。子供のころからある家で、今ではますます古くなっている。家に掲げられている刀とか包丁といった、いわくありげな看板が、何か子ども心に恐ろしかった。
この家は、何年か前に偶然テレビで紹介されているのを見たのだが、刀を研ぐ伝統を受け継いでいるらしかった。やはり、いわくある建物だったのだ。
その家をなぞるように道を歩いていくと、踏切のある線路にぶつかる。JR線である。
線路を渡り、左に学校を見ながら少し曲がった道を歩くとT字にぶつかり、それを右に行くと左に八幡神社がある。ここで、蝉を捕ったことがある。
今は閑散とした印象だが、かつては木々が繁り、緑豊かな神社だった。
神社を通り越すと、大きな通りにぶつかり、それを道なりに歩くと右手に病院がある。木々の間に立ち並ぶ白い木造の病院で、高く覆い繁った木々の枝葉で、その前の道は昼間でも影で充たされていた。今では、風景も建物もすっかり変わっている。
病院が途切れた緩やかな曲がり道の右側に、小さな下り坂の路地があり、そこを降りていく。すると、畑にぶつかった。畑のなかの畦道を歩いていく先に、住宅が並んだ町並みがあった。
そこが、「吉野」の祖父母と叔母が住む町だった。
今は、路地の先に畑はなく、住宅地になっていた。その家の間の道の先の小さな丘の上に、やはり住宅街があった。
かつての桜色の屋根の並んだ住宅はなくなり、鉄筋の住宅に変わっていた。
住宅街を突っ切るメインの道路と、その住宅の先の商店街にある肉屋が、かつての面影をかろうじて残していた。
吉野で昼食をと思ったが、ここでも適当な食堂が見あたらなかった。
吉野の商店街から大牟田の中心街の栄町までバスで行った。
バスを降りて、繁華街の方に向かって歩いていると、線路があり、その先にアーケードが見えた。入口のモダンなアーチには、「GINZA」とある。大牟田・銀座道りである。(写真)
アーケードの商店街を歩いた。しゃれた定食屋に入って、遅い昼食をとった。そこで、松屋デパートがあったところを訊いたら、この道のすぐ先だと言う。
そのあたりに行くと、2004年に閉店した松屋の建物はすでに取り壊されていて、駐車場になっていた。かつては、この辺りは多くの人で賑わっていた。
人通りが少ない街中を歩いた。繁華街は寂れていたが、まだ飲み屋は多いように思えて、少しほっとした。昔は、元気で威勢のいい炭鉱マンが、この界隈で気炎を吐いていたであろうと想像した。
僕は、かつて松屋デパートにはメリーゴーランドがあったと記憶していて、このブログにもそう書いたことがあるが、どうもそうではないようだ。
観覧車だったようだ。観覧車に乗ったのを、いつしかメリーゴーランドに変質させたのだろうか。
記憶はあいまいで不確かである。
だから、記録していかなくてはいけない。
子供のころ、夏休みや冬休みには父や母に連れられてよく大牟田に遊びに行った。僕が少し大きくなったころには、弟と二人で行ったこともあった。
祖父母の家は平屋の市営住宅だったが、建てられて間もないと思われるきれいな造りだった。桜色の屋根で、小さいながらも庭があり、佐賀のわが家に比べればとてもしゃれていると感じた。
祖父は隠居していて、書画や木の彫り物を楽しんでいる風流人だった。
かつて大牟田は、日本有数の石炭の町として栄えていた。文字通り、町の中心に栄町があった。そこには松屋デパートがあり、そこに連れて行ってもらうのが楽しみだった。
松屋には屋上遊園地があり、その下の階の食堂で、旗のついたお子様ランチを食べるのが何よりの楽しみだった。
僕が子どもではなくなったころ、石油に代わられた石炭産業は不況になり、1960年代後半からは大牟田も徐々に寂れていった。そして、1997(平成9)年には、町を支えていた三井三池鉱も閉山となった。
僕も高校を卒業後、東京に出てきてからは、めったに祖父母の住む大牟田に行くこともなくなった。
そして今は、祖父母も叔母もなくなり、大牟田には住んでいた家屋もない。
*
人口の推移を見れば、町の盛衰がよくわかる。
1960(昭和35)年当時の福岡県の人口を見ると、以下の通りである(千人以下四捨五入)。
・福岡市 65万人
・八幡市 32万人
・小倉市 29万人
・大牟田市 21万人
・久留米市 16万人
・門司市 15万人
八幡、小倉、門司、戸畑、若松の5市は、1963年に合併して北九州市として103万都市となり、政令指定都市となった。北九州市から遅れること9年後の1972年に政令市となった福岡市が、100万人を突破したのは1975年のことである。
現在(2013年)の人口はどうなっているかといえば、その後、福岡市への一極集中が加速し、九州におけるミニ東京と化している。
・福岡市 150万人
・北九州市 97万人
・久留米市 30万人
・大牟田市 12万人
福岡市と久留米市を含むその周辺都市が人口を増やすなかで、大牟田市の人口減は著しい。大牟田市と久留米市は逆転している。
2011年、鹿児島まで延びた九州新幹線の鹿児島ルートが開通し、大牟田市にも停車するのだが、この恩恵を大牟田は得ていない。地図を見てもわかるように、新幹線の停車駅である新大牟田駅は中心街とはほど遠いところで、JRの在来線の駅とも離れたところにある。どうしてこんなところにあるのかと、誰もが疑問に思うところにあるのだ。
それに比し久留米は、新幹線はJR在来線の久留米駅と直結していて利便性は高い。
哀しいかな、これでは差がつく一方である。
*
5月の半ばのころ、関西に住む弟が少し暇がとれたと言って、珍しく佐賀に帰ってきた。それで、去る晴れた日、二人で大牟田へ行くことにした。いや、もうだいぶん日が過ぎたので、行ったと過去形だ。
子供のころ行ったように、電車とバスを乗り継いで、歩いてあの家に行くことにした。おぼろげに脳裏に残っている風景をなぞるように、歩いてみたのだ。子供のころの足跡を確認するかのように。
佐世保線の佐賀駅で降りて、バスで柳川に行った。
子どものころは、佐賀駅から列車に乗っていた。今では廃線でなくなった佐賀駅から福岡県の瀬高まで通った国鉄の佐賀線で、柳川まで行き西鉄電車に乗り換えていたと思う。佐賀線が廃線になってからは、佐賀からバスを利用していた。
佐賀線は、佐賀・諸富から福岡・大川に行く途中の、今では重要文化財となっている筑後川に架かる昇開橋を走った。
柳川から大牟田行の西鉄電車に乗る。
柳川から、徳増、塩塚、中島と田園地帯を電車は走る。中島では、有明海に広がる河口に何艘も船が停泊している。昔ながらの風景だ。
さらに、江の浦、開、渡瀬と過ぎて、倉永で降りる。
倉永の駅の近くに来ると、高いとんがり屋根の建物が見える。「緑の丘の赤い屋根」ではないけれど、歌の文句のようなしゃれた建物だと思っていた。
倉永の次は銀水だ。銀水で降りたことはなかったが、「次はギンスイ」と、その名前を聞いただけで、銀水には何があるのだろう、どんなきらびやかな街だろうと想像したものだ。
倉永の駅を降り改札口を出て、昼時なので、どこか食堂でもないかと見渡したが、店などは見当たらないそっけない駅前だ。駅前は、すぐ目の前に道路が左右に走っている。
とりあえず、進もう。
駅前の道路を渡ると、前に古い石垣の家が見える。子供のころからある家で、今ではますます古くなっている。家に掲げられている刀とか包丁といった、いわくありげな看板が、何か子ども心に恐ろしかった。
この家は、何年か前に偶然テレビで紹介されているのを見たのだが、刀を研ぐ伝統を受け継いでいるらしかった。やはり、いわくある建物だったのだ。
その家をなぞるように道を歩いていくと、踏切のある線路にぶつかる。JR線である。
線路を渡り、左に学校を見ながら少し曲がった道を歩くとT字にぶつかり、それを右に行くと左に八幡神社がある。ここで、蝉を捕ったことがある。
今は閑散とした印象だが、かつては木々が繁り、緑豊かな神社だった。
神社を通り越すと、大きな通りにぶつかり、それを道なりに歩くと右手に病院がある。木々の間に立ち並ぶ白い木造の病院で、高く覆い繁った木々の枝葉で、その前の道は昼間でも影で充たされていた。今では、風景も建物もすっかり変わっている。
病院が途切れた緩やかな曲がり道の右側に、小さな下り坂の路地があり、そこを降りていく。すると、畑にぶつかった。畑のなかの畦道を歩いていく先に、住宅が並んだ町並みがあった。
そこが、「吉野」の祖父母と叔母が住む町だった。
今は、路地の先に畑はなく、住宅地になっていた。その家の間の道の先の小さな丘の上に、やはり住宅街があった。
かつての桜色の屋根の並んだ住宅はなくなり、鉄筋の住宅に変わっていた。
住宅街を突っ切るメインの道路と、その住宅の先の商店街にある肉屋が、かつての面影をかろうじて残していた。
吉野で昼食をと思ったが、ここでも適当な食堂が見あたらなかった。
吉野の商店街から大牟田の中心街の栄町までバスで行った。
バスを降りて、繁華街の方に向かって歩いていると、線路があり、その先にアーケードが見えた。入口のモダンなアーチには、「GINZA」とある。大牟田・銀座道りである。(写真)
アーケードの商店街を歩いた。しゃれた定食屋に入って、遅い昼食をとった。そこで、松屋デパートがあったところを訊いたら、この道のすぐ先だと言う。
そのあたりに行くと、2004年に閉店した松屋の建物はすでに取り壊されていて、駐車場になっていた。かつては、この辺りは多くの人で賑わっていた。
人通りが少ない街中を歩いた。繁華街は寂れていたが、まだ飲み屋は多いように思えて、少しほっとした。昔は、元気で威勢のいい炭鉱マンが、この界隈で気炎を吐いていたであろうと想像した。
僕は、かつて松屋デパートにはメリーゴーランドがあったと記憶していて、このブログにもそう書いたことがあるが、どうもそうではないようだ。
観覧車だったようだ。観覧車に乗ったのを、いつしかメリーゴーランドに変質させたのだろうか。
記憶はあいまいで不確かである。
だから、記録していかなくてはいけない。













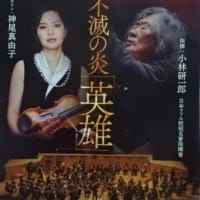

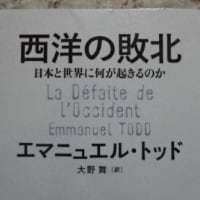









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます