
「呼子」
「よぶこ」、と口の中で言ってみる。すると、いつも不思議な感覚にとらわれる。
曖昧に、不確かに、女性、それも少女の名を呼んだような気になるのだ。
その曖昧な感覚は、すぐに、絣か木綿の浴衣のような着物を着たそのおかっぱ髪の少女が、海岸で佇んでいる風景になる。そこは、小さな船が停泊している人気(ひとけ)のない漁港だ。
鄙びた漁港、それが呼子の原風景だ。いや、想像が創った呼子の原型だ。
まだ若かった頃のことだ。
唐津に来たついでに、そこからバスで呼子に行った。名前に引かれてふらりと行ってみた、という程度だった。
呼子は、唐津の虹の松原に護られている海のように浜辺が続いているのではなく、玄界灘の海に接する岸壁がずっと延びている漁港の町だ。その頃は、朝市が有名なくらいだった。
バスを下りたら、すぐ近くの延びる海岸に行った。今ほど呼子の町が知られていなかったので、人は見あたらなかった。
海岸といっても海の向こうには島(加部島)が広がっているので、想像していた玄界灘の大海原が広がっているという風景ではない。田舎の小さな漁港の佇まいである。
岸壁には小さな船が何艘か並んで浮かんでいた。これがイカ釣り船かと思って、しばらく眺めていた。港は静かで、何も起こりそうになかった。着物姿の少女がいたのでもない。
しばらく海辺を眺めていると、イカ釣り船より大きな船が停まっているのが見えた。よく見ると、その船には「壱岐」行きと書いてある。
ここから、壱岐に行く船が出ているのを知らなかった私は、小さな驚きと同時に、壱岐の島にも行ったことがなかったので、思わずその船に跳び乗ったのだった。
初めての呼子の旅は、初めての壱岐の旅になった。
*武雄の巨木、「川古の大楠」
10月20日、武雄温泉「楼門亭」に宿泊。
翌10月21日、朝9時に、高校時代の同級生が、どこか佐賀で昼食をしようといって車で迎えに来た。
では、「呼子でイカを食おう」と提案し、唐津の呼子に向かって出発した。
武雄温泉楼門から北へ向かって走ると、伊万里に至る手前の若木町に、古木がある。
ずいぶん前に行ったことがあるが、通り道なので寄ってみた。以前より、周りは整備されている。久しぶりに見たのだが、やはり、大きい。木の根元には祠も祭ってある。
この「川古(かわご)の大楠」は、環境省自然環境局の、いわゆる「緑の国勢調査」による「巨樹・巨木林調査」にて全国で第5位にランクされる巨木で、国の天然記念物に指定されている。
若木の「川古の大楠」は、武雄神社の「武雄の大楠」と同様にかなり大きいと知ってはいたが、全国第5位とはもっと知られていい事実であろう。
ということで、気になる全国の巨木を調べてみたので、ベスト10を記しておこう。
木の大きさの判断としては幹の周りを測るということになる。といっても、その計測方法に国際的な基準はない。環境省の「巨樹・巨木林データベース」の調査方法は、ヨーロッパの多くの国が採用している、地上から130cmの高さの幹周である。
□「全国最大級の巨木」(上位10傑) 平成13年3月現在
――環境省自然環境局・自然環境保全基礎調査
1.「蒲生(かもう)の大楠」 鹿児島県蒲生町 八幡神社 クスノキ 幹周2,422 cm 天然記念物等(国)
2.静岡県熱海市 来の宮神社 クスノキ 2,390㎝ 天然記念物等(国)
3.沖縄県島尻郡東風平町 ガジュマル 2,350㎝
4.「北金ヶ沢のイチョウ」 青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢 イチョウ 2,200 cm 天然記念物等(都道府県)
5.「川古の大楠」佐賀県武雄市若木町川古 クスノキ 2,100 cm 天然記念物等(国)
5.福岡県築上郡築城町 クスノキ 2,100 cm 天然記念物等(国)
7.「武雄の大楠」 佐賀県武雄市武雄町 武雄神社 クスノキ 2,000 cm 天然記念物等(市町村)
7.「権現山の大カツラ」 山形県最上郡最上町 カツラ 2,000 cm
7.「蚊田の森」 福岡県糟屋郡宇美町 宇美八幡宮 クスノキ 2,000 cm 天然記念物等(国、都道府県)
10.沖縄県島尻郡東風平町 ガジュマル 1,990 cm
武雄市の4位の「川古の大楠」の他に、武雄神社の「武雄の大楠」が7位に入っている。先の10月19日、くんちの祭りに行った佐賀・白石町の稲佐神社の楠も、別の巨木調査でベスト50に入っている。
なにしろ佐賀県は楠が多い。佐賀県に限らず楠は九州全般に多いのだが。
という流れで言えば、佐賀県の“県の木”は楠である。他に、熊本県、鹿児島県、そして兵庫県が楠である。
ここからが問題なのであるが、佐賀県の“県の花”はなにか?というと、これがまた楠なのである。
楠も確かに花は咲くが、ほとんど目立たない。楠の花を知っている人は多くないだろう。
う~ん…。県木、県花の両方とも楠という、県としてのアピールも、工夫も面白みも無いのである。佐賀県は何を考えているのか? 何も考えていないのか?
楠以外に県に、木ではない花はないのか? ただただ、花が思いつかなかったのか?
花がなければ、う~ん…。楠の花より、“みかんの花”がまだ花のイメージが湧いてくる。それに、みかんは佐賀の特産物だし、佐賀らしさもあるではないか。
また、みかんには、「みかんの花が 咲いている 思い出の道 丘の道…」(「みかんの花咲く丘」)という誰もが親しんでいる歌もある。
ということで、大きな楠を後に呼子に向かった。
*唐津の近松門左衛門の墓、「近松寺」
武雄から伊万里をかすって唐津に入った。
唐津市内に入って、友人の誘いであまり知られていないが面白い寺があるというので、その寺に行った。
その寺は「近松寺」(きんしょうじ)といった。旧藩主・小笠原家の菩提寺で、江戸時代の有名な浄瑠璃・歌舞伎作家の近松門左衛門の墓石がある、臨済宗南禅寺派の寺である。
近松門左衛門といえば、先日10月17日、大阪の御堂筋を歩いた際、人形浄瑠璃「曽根崎心中」の舞台となった曽根崎の「お初天神」に行ってきたばかりである。
近松門左衛門は、大阪で浄瑠璃・歌舞伎などの上方人情劇の作家として活動し、大坂・天満で72歳の生涯を閉じた。
近松の墓と伝えられているものは、尼崎の広済寺、大阪の法妙寺に加え全国7か所を数えるという。それで、なぜ近松の墓が唐津にあるかである。境内の石碑に説明文があるが、実情は定かではない。
境内には、小笠原家に関する資料を展示した小笠原記念館も立つ。
しかし、この寺で見ておきたいのは枯山水の禅庭である。庭には茶室もあり、織部燈篭(キリシタン燈篭)なるものもある。
*イカは呼子にかぎる
唐津の市外から海辺の町・湊(みなと)を走って、呼子へ向かった。
時刻は、もう昼の12時近くである。武雄の楼門亭の旅館は朝食がない素泊まりだったし、それに朝から何も食べなかったので、頭の中はイカでいっぱいだ。
呼子といえばイカで、いつも行くのは老舗の「河太郎」だ。ここは、店内にある生簀の中のイカを注文を受けてから取り出して調理してくれる、“活き造り”の本家である。
ところが、海辺にある河太郎の前に着くと、店の前にはかなりの人の行列だ。昼飯時だし、それに今日は土曜日だ。残念だが、こちらは空腹で、何時(いつ)イカにありつけるかわからないのに列に並ぶつもりはない。
すぐに河太郎を後に海岸通りを進むと、通りに面したホテルの1階に食事の看板が目についた。店を選んでいる暇はないので、席が空いているのを確認して、中に入った。
席について注文をしようとすると、“イカの活き造り定食”の一択だった。それで、いいのだ。
出てきたイカは大きい。ガラス細工のような透明感。体は刺身用として切り捌かれているのに、まだ脚はくねくねと動いている。(写真)
呼子の活き造りでは、普通ケンサキイカ(ヤリイカ)が出てくるが、日によって、つまりその日の収穫によって違うイカが出ることもある。今日はどうもアオリイカのようだ。
刺身としての頭と体で、ご飯(これが大盛りなのだ)を1杯。そのあとゲソ(脚)を天ぷらにしてもらい、それでご飯をお替り。
連れの友人は太っていて大食なのでこのくらい何のことはないのだが、私も空腹もあってよく食べた(もともと痩せの大食いではあるのだが)。
佐賀に来たら、呼子のイカを食べようと思ったので、“くんち”も堪能したことだし、満足というものである。
*
最初に、「呼子」と呼べば少女を思い浮かべると書いたが、もう一つ女性を思い浮かべる町がある。
それは、「松江」である。
この島根県の町(市)は、「怪談」を書いたラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が住んだ町で、私も好きな町だ。
町(街)のイメージと関係ないが、「松江」と呼ぶと、やはり女性、呼子より少し大人の女性が浮かぶ。「抒情文芸」に投稿しているような、少女というか女性である。
*再興する佐賀
この日の夜は、佐賀市に宿泊。
佐賀の駅前には、誰でも立ち寄れるフリーのテーブルや椅子を置いた広場風空間が造ってあり、駅構内の西側サイドに飲み屋などの新しい店が並び、駅前の元スーパーがあったビルには県の観光案内所ができた。
県もやっと、何もない佐賀というイメージを払拭しようと動きだしたようだ。
私はいつものように、駅の中央通りを南の佐賀城方面へ歩いてみる。
手にした1枚のチラシを見ると、この日(10月21日)は、たまたま「佐賀さいこうフェス」という祭りの日だった。「佐賀の再興」と「最高の佐賀」をテーマにした音楽とアートの催しだという。
「再興」とは、「衰えたり、滅びたりしていたものが、ふたたび興ること。また、それを興すこと…」とあるので、やはり佐賀は一度、衰えたり滅びたりしたのか?
佐賀県人には、ひそかに、幕末・明治維新の頃は佐賀(佐賀人)は輝いていたという自覚がある。
会場となっている県立博物館・美術館前に行ってみると、広い野天のなかに屋台が出ていて椅子の並んだ客席があり、人波の奥にはステージが設けられて演奏が行われている。いつの間にできたのか、広い原っぱの会場が出現している。
正確な風景は思い出せないが、以前といってもごく最近まで、ここ県立博物館・美術館前に原っぱなどなかった。おそらく、宅地整理をしたのだろう。
もうほぼ最後となる演奏を聴いて会場を後にし、中央本町に行って愛敬町から移転した中国料理店「栄志」で夕食とした。
その帰り、久しぶりに以前より人が少なくなった佐賀の繁華街・飲み屋街を歩き、久しぶりにバーに入った。
久しぶり、という感覚は気持ちがいい。
「よぶこ」、と口の中で言ってみる。すると、いつも不思議な感覚にとらわれる。
曖昧に、不確かに、女性、それも少女の名を呼んだような気になるのだ。
その曖昧な感覚は、すぐに、絣か木綿の浴衣のような着物を着たそのおかっぱ髪の少女が、海岸で佇んでいる風景になる。そこは、小さな船が停泊している人気(ひとけ)のない漁港だ。
鄙びた漁港、それが呼子の原風景だ。いや、想像が創った呼子の原型だ。
まだ若かった頃のことだ。
唐津に来たついでに、そこからバスで呼子に行った。名前に引かれてふらりと行ってみた、という程度だった。
呼子は、唐津の虹の松原に護られている海のように浜辺が続いているのではなく、玄界灘の海に接する岸壁がずっと延びている漁港の町だ。その頃は、朝市が有名なくらいだった。
バスを下りたら、すぐ近くの延びる海岸に行った。今ほど呼子の町が知られていなかったので、人は見あたらなかった。
海岸といっても海の向こうには島(加部島)が広がっているので、想像していた玄界灘の大海原が広がっているという風景ではない。田舎の小さな漁港の佇まいである。
岸壁には小さな船が何艘か並んで浮かんでいた。これがイカ釣り船かと思って、しばらく眺めていた。港は静かで、何も起こりそうになかった。着物姿の少女がいたのでもない。
しばらく海辺を眺めていると、イカ釣り船より大きな船が停まっているのが見えた。よく見ると、その船には「壱岐」行きと書いてある。
ここから、壱岐に行く船が出ているのを知らなかった私は、小さな驚きと同時に、壱岐の島にも行ったことがなかったので、思わずその船に跳び乗ったのだった。
初めての呼子の旅は、初めての壱岐の旅になった。
*武雄の巨木、「川古の大楠」
10月20日、武雄温泉「楼門亭」に宿泊。
翌10月21日、朝9時に、高校時代の同級生が、どこか佐賀で昼食をしようといって車で迎えに来た。
では、「呼子でイカを食おう」と提案し、唐津の呼子に向かって出発した。
武雄温泉楼門から北へ向かって走ると、伊万里に至る手前の若木町に、古木がある。
ずいぶん前に行ったことがあるが、通り道なので寄ってみた。以前より、周りは整備されている。久しぶりに見たのだが、やはり、大きい。木の根元には祠も祭ってある。
この「川古(かわご)の大楠」は、環境省自然環境局の、いわゆる「緑の国勢調査」による「巨樹・巨木林調査」にて全国で第5位にランクされる巨木で、国の天然記念物に指定されている。
若木の「川古の大楠」は、武雄神社の「武雄の大楠」と同様にかなり大きいと知ってはいたが、全国第5位とはもっと知られていい事実であろう。
ということで、気になる全国の巨木を調べてみたので、ベスト10を記しておこう。
木の大きさの判断としては幹の周りを測るということになる。といっても、その計測方法に国際的な基準はない。環境省の「巨樹・巨木林データベース」の調査方法は、ヨーロッパの多くの国が採用している、地上から130cmの高さの幹周である。
□「全国最大級の巨木」(上位10傑) 平成13年3月現在
――環境省自然環境局・自然環境保全基礎調査
1.「蒲生(かもう)の大楠」 鹿児島県蒲生町 八幡神社 クスノキ 幹周2,422 cm 天然記念物等(国)
2.静岡県熱海市 来の宮神社 クスノキ 2,390㎝ 天然記念物等(国)
3.沖縄県島尻郡東風平町 ガジュマル 2,350㎝
4.「北金ヶ沢のイチョウ」 青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢 イチョウ 2,200 cm 天然記念物等(都道府県)
5.「川古の大楠」佐賀県武雄市若木町川古 クスノキ 2,100 cm 天然記念物等(国)
5.福岡県築上郡築城町 クスノキ 2,100 cm 天然記念物等(国)
7.「武雄の大楠」 佐賀県武雄市武雄町 武雄神社 クスノキ 2,000 cm 天然記念物等(市町村)
7.「権現山の大カツラ」 山形県最上郡最上町 カツラ 2,000 cm
7.「蚊田の森」 福岡県糟屋郡宇美町 宇美八幡宮 クスノキ 2,000 cm 天然記念物等(国、都道府県)
10.沖縄県島尻郡東風平町 ガジュマル 1,990 cm
武雄市の4位の「川古の大楠」の他に、武雄神社の「武雄の大楠」が7位に入っている。先の10月19日、くんちの祭りに行った佐賀・白石町の稲佐神社の楠も、別の巨木調査でベスト50に入っている。
なにしろ佐賀県は楠が多い。佐賀県に限らず楠は九州全般に多いのだが。
という流れで言えば、佐賀県の“県の木”は楠である。他に、熊本県、鹿児島県、そして兵庫県が楠である。
ここからが問題なのであるが、佐賀県の“県の花”はなにか?というと、これがまた楠なのである。
楠も確かに花は咲くが、ほとんど目立たない。楠の花を知っている人は多くないだろう。
う~ん…。県木、県花の両方とも楠という、県としてのアピールも、工夫も面白みも無いのである。佐賀県は何を考えているのか? 何も考えていないのか?
楠以外に県に、木ではない花はないのか? ただただ、花が思いつかなかったのか?
花がなければ、う~ん…。楠の花より、“みかんの花”がまだ花のイメージが湧いてくる。それに、みかんは佐賀の特産物だし、佐賀らしさもあるではないか。
また、みかんには、「みかんの花が 咲いている 思い出の道 丘の道…」(「みかんの花咲く丘」)という誰もが親しんでいる歌もある。
ということで、大きな楠を後に呼子に向かった。
*唐津の近松門左衛門の墓、「近松寺」
武雄から伊万里をかすって唐津に入った。
唐津市内に入って、友人の誘いであまり知られていないが面白い寺があるというので、その寺に行った。
その寺は「近松寺」(きんしょうじ)といった。旧藩主・小笠原家の菩提寺で、江戸時代の有名な浄瑠璃・歌舞伎作家の近松門左衛門の墓石がある、臨済宗南禅寺派の寺である。
近松門左衛門といえば、先日10月17日、大阪の御堂筋を歩いた際、人形浄瑠璃「曽根崎心中」の舞台となった曽根崎の「お初天神」に行ってきたばかりである。
近松門左衛門は、大阪で浄瑠璃・歌舞伎などの上方人情劇の作家として活動し、大坂・天満で72歳の生涯を閉じた。
近松の墓と伝えられているものは、尼崎の広済寺、大阪の法妙寺に加え全国7か所を数えるという。それで、なぜ近松の墓が唐津にあるかである。境内の石碑に説明文があるが、実情は定かではない。
境内には、小笠原家に関する資料を展示した小笠原記念館も立つ。
しかし、この寺で見ておきたいのは枯山水の禅庭である。庭には茶室もあり、織部燈篭(キリシタン燈篭)なるものもある。
*イカは呼子にかぎる
唐津の市外から海辺の町・湊(みなと)を走って、呼子へ向かった。
時刻は、もう昼の12時近くである。武雄の楼門亭の旅館は朝食がない素泊まりだったし、それに朝から何も食べなかったので、頭の中はイカでいっぱいだ。
呼子といえばイカで、いつも行くのは老舗の「河太郎」だ。ここは、店内にある生簀の中のイカを注文を受けてから取り出して調理してくれる、“活き造り”の本家である。
ところが、海辺にある河太郎の前に着くと、店の前にはかなりの人の行列だ。昼飯時だし、それに今日は土曜日だ。残念だが、こちらは空腹で、何時(いつ)イカにありつけるかわからないのに列に並ぶつもりはない。
すぐに河太郎を後に海岸通りを進むと、通りに面したホテルの1階に食事の看板が目についた。店を選んでいる暇はないので、席が空いているのを確認して、中に入った。
席について注文をしようとすると、“イカの活き造り定食”の一択だった。それで、いいのだ。
出てきたイカは大きい。ガラス細工のような透明感。体は刺身用として切り捌かれているのに、まだ脚はくねくねと動いている。(写真)
呼子の活き造りでは、普通ケンサキイカ(ヤリイカ)が出てくるが、日によって、つまりその日の収穫によって違うイカが出ることもある。今日はどうもアオリイカのようだ。
刺身としての頭と体で、ご飯(これが大盛りなのだ)を1杯。そのあとゲソ(脚)を天ぷらにしてもらい、それでご飯をお替り。
連れの友人は太っていて大食なのでこのくらい何のことはないのだが、私も空腹もあってよく食べた(もともと痩せの大食いではあるのだが)。
佐賀に来たら、呼子のイカを食べようと思ったので、“くんち”も堪能したことだし、満足というものである。
*
最初に、「呼子」と呼べば少女を思い浮かべると書いたが、もう一つ女性を思い浮かべる町がある。
それは、「松江」である。
この島根県の町(市)は、「怪談」を書いたラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が住んだ町で、私も好きな町だ。
町(街)のイメージと関係ないが、「松江」と呼ぶと、やはり女性、呼子より少し大人の女性が浮かぶ。「抒情文芸」に投稿しているような、少女というか女性である。
*再興する佐賀
この日の夜は、佐賀市に宿泊。
佐賀の駅前には、誰でも立ち寄れるフリーのテーブルや椅子を置いた広場風空間が造ってあり、駅構内の西側サイドに飲み屋などの新しい店が並び、駅前の元スーパーがあったビルには県の観光案内所ができた。
県もやっと、何もない佐賀というイメージを払拭しようと動きだしたようだ。
私はいつものように、駅の中央通りを南の佐賀城方面へ歩いてみる。
手にした1枚のチラシを見ると、この日(10月21日)は、たまたま「佐賀さいこうフェス」という祭りの日だった。「佐賀の再興」と「最高の佐賀」をテーマにした音楽とアートの催しだという。
「再興」とは、「衰えたり、滅びたりしていたものが、ふたたび興ること。また、それを興すこと…」とあるので、やはり佐賀は一度、衰えたり滅びたりしたのか?
佐賀県人には、ひそかに、幕末・明治維新の頃は佐賀(佐賀人)は輝いていたという自覚がある。
会場となっている県立博物館・美術館前に行ってみると、広い野天のなかに屋台が出ていて椅子の並んだ客席があり、人波の奥にはステージが設けられて演奏が行われている。いつの間にできたのか、広い原っぱの会場が出現している。
正確な風景は思い出せないが、以前といってもごく最近まで、ここ県立博物館・美術館前に原っぱなどなかった。おそらく、宅地整理をしたのだろう。
もうほぼ最後となる演奏を聴いて会場を後にし、中央本町に行って愛敬町から移転した中国料理店「栄志」で夕食とした。
その帰り、久しぶりに以前より人が少なくなった佐賀の繁華街・飲み屋街を歩き、久しぶりにバーに入った。
久しぶり、という感覚は気持ちがいい。













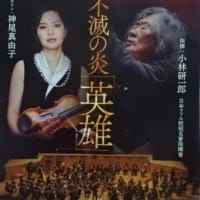

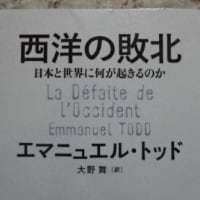









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます