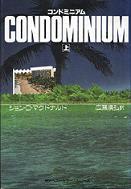アイリッシュ・ギャングのフランク・コステロ(ジャック・ニコルソン)は言う“おれたちアイリッシュは違う。誰も与えない、自分で奪うんだ。ガキの頃言われた。アイリッシュは、警官か犯罪者になるとな。俺ならこう言う銃と向き合えば違いはねえ”

コステロは、子供の頃から目をかけ育てたコリン・サリバン(マット・デイモン)をマサチューセッツ警察学校に入れ、組織の中枢へとねずみのように潜り込ませる。州警察の動きを事前に知り、自身の麻薬ビジネスを安泰なものにしようと企む。
一方州警察おとり捜査部門も、一匹のねずみをコステロの組織に放った。それはビリー・コスティガン(レオナルド・ディカプリオ)で、コリンと同期生それにおとり捜査担当上級巡査部長ディグナム(マーク・ウォールバーグ)に言わせれば“大した血筋だ。トミー・コスティガンまで伯父とはな。捜査官に銃を売り逮捕、世間からはみ出した連中ばかりだ”という適材。

この二匹のねずみが対峙するまで緊張感あふれる展開を見せる。そしてみんな故人(The Departed)になる。生き残るのは、上級巡査部長ディグナムで、コリンの頭に銃弾を浴びせて歩き去る。
私がこの映画で一番印象に残ったのは、上級巡査部長ディグナム役を演じたマーク・ウォールバーグだった。その理由は存在感を感じたせいだった。ウォールバーグはこの映画でアカデミー助演男優賞にノミネート、全米批評家協会賞では、助演男優賞を受賞している。
観る者に全身全霊を打ち込んでいる様がよく分かり、それが存在感につながっているようだ。演技とはそういうものということを改めて教えてくれた気がする。
ジャック・ニコルソンをはじめディカプリオ、デイモンも実績があるが、ウォールバーグに食われているところがある。

左マーク・ウォールバーグ 右マット・デイモン
映画芸術において、暴力の美学というものがあるとすれば、この映画もその一つといえるだろう。無残な死体や血みどろの顔、殴り合い、拳銃を撃つ場面は、顔を背けたくなるかもしれないが、これらの場面を除いては語れないだろう。
気がついたのは、拳銃の音と撃つ人体の場所だ。たいていの映画では拳銃の音を、音響効果を狙ってかなり大きくするが、この映画ではパンという小さな音になっている。おそらく実際の音に近いのではないだろうか。
そして撃つのは頭部だった。撃った瞬間血しぶきが噴出する。かなり衝撃的だが、腹を撃つよりも武士の情けの範疇に入る。頭は即死だが、腹は苦しみながら時間をかけて死んでいく。
決して後味のいい映画とはいえない。暴力シーンが多いのとセリフが下品なことから映倫R-15の指定になっている。いずれにしてもマーティン・スコセッシにお情けでアカデミー賞をあげた気がしないでもない。
スコセッシは1942年11月ニューヨーク市クイーンズ、フラッシング生れ。過去何度もアカデミー監督賞にノミネートされるが、ついに本作で‘06年の作品賞、監督賞、脚色賞、編集賞の受賞を果たす。
キャスト レオナルド・ディカプリオ1974年11月カリフォルニア州ハリウッド生れ。「タイタニック」で大ブレイクする。
マット・デイモン1970年10月マサチューセッツ州ケンブリッジ生れ。’02「ボーン・アンデンティティー」が大ヒット。
ジャック・ニコルソン1937年4月ニュージャージー州ネプチューン生れ。
マーク・ウォールバーグ1971年6月マサチューセッツ州ドーチェスター生れ。ほかにヴェラ・ファーミガ、マーティン・シーン、アレック・ボールドウィンなど。