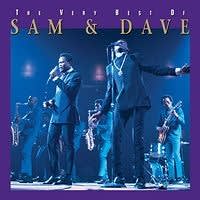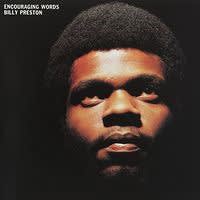Original Album Series / Donny Hathaway (2010)
最近は開き直って購入の加速度が増している簡易紙ジャケCD5枚組の「Original Album」シリーズ。今回購入したのはダニー・ハサウェイ(Donny Hathaway)。シカゴ出身だそう。今まで所有しているコンピ盤の収録曲でしか聴いたことが無く、オリジナル・アルバムは、アナログ、CD含めて1枚も持っていない。収録されている5枚は以下の通り。
・Everything Is Everything(1971)
・Donny Hathaway(1971)
・Live(1972)
・Extension Of A Man(1973)
・In Performance(1980)
70年代前半に大活躍し、その後鳴りを潜め(病気だったらしい)79年には亡くなってしまうので、実質最盛期の4枚全てが収録されていることになる。彼もスティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)やカーティス・メイフィールド(Curtis Mayfield)と同様に”ニュー・ソウル”というジャンルで括られるのだろうが、どちらかというとファンキーな要素は少なめで、ゴスペル的な落ち着いた曲が多い。カヴァー曲を歌うことも多く、これらアルバムの中にも、Ray Charles、Nina Simone、Leon Russell、Billy Preston、George Clinton、Marvin Gaye、Carole King、John Lennon、Al Cooper、などの大道のアーティストのカヴァーが収録されている。
圧巻はやはりライヴ。3枚目と5枚目がライヴ作品だが、特に1972年の名盤「Live」でのソウルフルな歌唱には心震える。彼の映像は見たことがないが、エレピの演奏も彼自身だそうだ(これがまたカッコイイ)。バックの演奏もゴキゲンで、特に名手ウィリー・ウィークス(Willie Weeks)のベース・ラインは、彼がビッグ・アーティストから引く手あまたというのが納得の気持ち良さ。有名な(つまりベタな)カヴァー曲でも本家に勝るとも劣らない名演で完全に自分のものにしている。観客を自然に取り込む手腕も抜群。必聴。
amazonにて購入(¥1,382)
- CD (2010/2/27)
- Disc : 1
- Format: Box Set, CD, Import
- Label : Warner Music