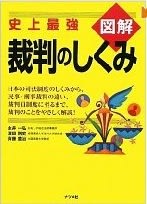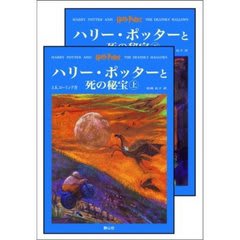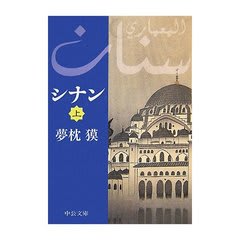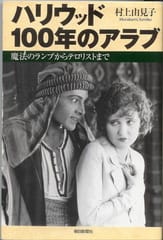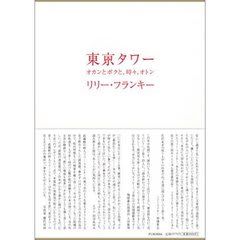ーミレニアムー
作者=スティーグ・ラーソン 訳=ヘレンハルメ美穂・岩澤雅利(2巻は山田美明)
2005年スウェーデンで発行
スウェーデン版の映画も、デヴィド・フィンチャー監督のハリウッド映画もすごく気に入った私は、原作も読んでみました。
全3巻、1巻が上下に分かれているので、かなりな長編といえますが、面白かったですよ。
久しぶりに、一気に読んでしまいました。
 ハリウッド版のリスベット(ルーニー・マーラ)
ハリウッド版のリスベット(ルーニー・マーラ)
作者のスティーブ・ラーソンはスウェーデンのジャーナリストで、全部で5巻の構想を持っていたという。
しかし、3部作を書き終えて、4部に取りかかった2004年に心筋梗塞で急死した。
確かに、いろんな伏線が張られていると感じるところが随所にあり、才能のある作家の急逝は惜しまれますね。
とくに、リスベットの双子の妹など、名前と性格しか出て来なくて、これは絶対4部5部の主要人物だと確信させるんだけどなあ。
残念です。
第1部「ドラゴンタトゥーの女」
原題は「女を憎む男」という意味のタイトルがつけられていて、内容も、女の敵といえる人物が多数描かれます。
これがハリウッドで制作された映画の原作で、スウェーデン映画より、ハリウッドの方が原作に近いと感じました。
書き出しでは、主人公のジャーナリスト・ミカエル・ブルムクヴィストが、実業家ヴェンネルストレムに名誉毀損の裁判で破れることから始まります。
いままで華々しい経歴を誇るミカエルが、ほとんど弁解らしい弁解もせず、完全に敗北し、多額の罰金と半年後に刑務所へ収監されることを受け入れた。
その上、スキャンダルを恐れ、所属していた雑誌「ミレニアム」を離れることを選択したことから始まります。
読者もまだミカエルと言う人物をよく知らないのに、いきなりこれです。
大実業家ヘンリック・ヴァンゲルが、彼の弁護士フルーデを通じて、ミントンセキュリティーのドラガン・アルマンスキーにミカエルの調査を依頼した。
この調査を担当したのが、まるで拒食症かと思うような小柄な女性で、しかもパンクロッカーのような異様な出で立ちのリスベット・サランデル。
顔にはピアスのアナだらけで、全身タトゥー、特に背中のドラゴンは見る人を恐れさせるのに十分です。
彼女が3巻を通じてのヒロインですが、これもいわゆる愛すべきヒロインからはほど遠い人物像です。
たぶん、彼女はアスペルガー症候群です。
頭脳明晰で天才ハッカーですが、見た目は知的障害者、精神障害者のように見えます。
さて、リスベットが調べ上げたミカエルが、ヘンリックにとって信頼すべき人物で、仕事もなくお金にも困っているという弱みもあり、ある事件の依頼をします。
40年も前に起こった、ヘンリックの愛した姪、ハリエットの失踪事件。
ミカエルは気乗りがしないものの、ヘンリックは最後の切り札、ヴェンネルストレムの不正の証拠を、秘密が解けた暁には渡してくれるという約束に心を動かされ、受けることを決意した。
映画よりも、はるかにたくさんの人が出てきます。
島の地図や人物関係図を参考にしながら読んで行くのはとても楽しいです。
ハリエットの事件はやがて猟奇事件へとつながって行き、思わぬ犯人が表れると言うのは映画と同じです。
そして、ヴェンネルストレムの不正はリスベットの活躍によって暴かれ、リスベットは巨額のお金を、ミカエルは名誉を回復するところで1巻の終わりです。
第2部「火と戯れる女」
ここからは、映画より遥かに面白いです。
リスベットは大金持ちで世界中を旅行しています。
そして、ストックホルムに戻ってきますが、慎重に身元を隠し、ミカエルに会うこともしません。
ミカエルは再び雑誌「ミレニアム」でジャーナリストとして活躍を始めていました。
ダグというフリーのジャーナリストが持ち込んだネタ「未成年の女性の人身売買」というテーマでセンセーショナルな特集を計画していました。
そのダクと恋人で研究者のミアが惨殺され、その凶器とされた拳銃にリスベットの指紋がついていたー!!
最重要容疑者となったリスベット。
最大の敵である彼女の父親と対決するしか、逃れる道がないことを悟ります。
リスベットの無実を確信するミカエルですが、ダグのテーマを追いかけて行くことで、ミカエルもその命を狙われます。
アルマンスキーたちと阿吽の呼吸でリスベットに協力していくようすが、とてもスリリングで面白いです。
1巻ではミカエルが窮地を助けられたように、2巻の終わりにはミカエルがリスベットの窮地を救います。
第3部「眠れる女と狂卓の騎士」
眠れる女とは、リスベットのことです。
ミカエルに助けられたものの、リスベットはひどい怪我を負って入院を余儀なくされます。
しかも、殺人の容疑で、治ったら直ちに収監されることになっているのです。
リスベットとその父親の存在そのものに国家の秘密があり、亡き者にしようと秘密の組織が動き始めました。
自ら「狂卓の騎士」を名乗り、リスベットの無実をはらそうとするミカエルたちのグループ。
ミカエルの妹で弁護士のアニカや、アルマンスキー、最初の後見人のパルムグレン、ハッカーたちが協力して、法廷闘争を繰り広げます。
ミカエルとリスベットは最後まで顔を合わせることはないんだけど、その信頼関係がユーモラスで楽しい。
リスベットがだんだん心を開いて、不幸な生い立ちの女性が、人間らしく女性らしく成長して行くところが一番のテーマでしょう。
スウェーデンって、私のイメージでは、福祉国家で、自由で知的で豊かな国という感じがしますが、第2次世界大戦では、ナチスに加担する人も多かったようです。
性犯罪や女性に対する暴力も根が深いと言うのも驚きでした。
でも、恋愛に関しては自由で平等な考え方の人もたくさんいるし、フェミニズムも浸透していることも感じました。
緻密に構築されたストーリー。
続きが読めないのは本当に残念ですが、私たちよりもずっと悔しい思いをしているのが、急に亡くなってしまった作家本人でしょう。
今は、スティーグ・ラーソンの冥福を祈るのみです。