
前田利家の立派な立像。
春日山城を後に、再びJR直江津駅から列車で移動、高岡城、七尾城を見学し、七尾で一泊、3月19日、七尾駅発07時06分の特急サンダーバード12号に乗車し金沢に向った。
金沢に向うに連れて天候が回復し北信越に来て始めて見る青空である。
08時07分に金沢駅に着いた。
金沢訪問は3回目で、以前訪れたのは、昭和天皇が崩御された時で、石川県庁で記帳をした覚えがある。
それ以来の金沢で、金沢駅に降りて驚いたのは、駅舎の立派な事、これは近々延びて来る北陸新幹線の事を考えての駅舎であった。(平成27年3月14日開業)
金沢は暑かった。バスで金沢城に向ったが車内が暖房で暑く、運転手さんに暖房を切るよう頼んだ。
兼六公園下のバス停で下車し石川門から城内に入った。入口に前田利家の立像があった。
金沢城主は、豊臣秀吉の盟友、小林勝也が演じる前田利家が築城した加賀100万石の巨城である。
さすが100万石の城跡は広い、以前は此処に金沢大学のキャンパスがあったが今は移転して50間長屋櫓・菱櫓が復元してあった。現在は鬼門の方角にある城門の復元が工事中であった。
天正11年(1583)、七尾から加賀に移り、加賀100万石の大城を築城、現存する30間長屋、長さが50mの2層2階の多門櫓は立派であった。
ガイドさんに天守台の位置を伺ったが、今は存在しないとの事であった。
金沢城の建造物の瓦は、全て鉛瓦で火災時の消化には大変であったそうだ。鉛が解け落ちて来るからである。鍋を頭にかぶり消火活動をしたとか??
金沢城は、日本100名城第35番目の指定で、私は48番目の紀行である。
この後、兼六園を散策し、列車で大阪に移動した。

金沢城のシンボル石川門、城の搦手を守る門で、左が二重櫓、高麗門、渡櫓。
当時は、城内の裏門であったが、現在は正面の門となっている。
天明8(1788)年に再建されたもので、外側に高麗門形式の門、内側に櫓門形式の二の門、そして二重櫓を配置している。
昭和25年、国指定重要文化財に指定された。
この日は天候が良く青空をバックに私の下手な写真でも映えた。

画像は石川門の二重櫓で、その左に百間掘に築かれた続塀が見事である。
前田利家は、豊臣政権の五大老の一人、利家が逝去してから豊臣家が衰退していった。
豊臣秀頼の傅役(後見人)を任じられ、秀吉の死後、対立する武断派と文治派の争いに仲裁役として働き、覇権奪取のため横行する徳川家康の牽制に尽力するが、秀吉の死の8ヶ月後に病死した。

石川門を潜ると、三之丸観光案内所がありここに金沢城を案内するガイドさんが待機している。
100名城スタンプもここにある。

よみがえる金沢城の案内板。
金沢城の天守は、5層の立派な天守があったが、慶長7年(1602)落雷で焼失。
翌年3層5階造りの御3階櫓を天守の代わりとして築城した。(天守は徳川家康に遠慮して)徳川政権から危険視されるのを恐れて天守は築城しなかった。
現在天守があれば、金沢城が引き立ち、いま以上にお城観光をする人達が感動する事だろう!!

石川門を入ると眼前に復元された50間多聞長屋と橋爪門、橋爪続櫓、海鼠塀が現れる。
平成14年1月6日~12月15日、かけて放映されたNHK大河ドラマ「利家とまつ〜加賀百万石物語」それに伴い、復元されたのが画像の「菱櫓・50間多聞長屋・橋爪続櫓・橋爪門・鶴の丸太鼓櫓・海鼠塀で平成13年7月に完成され、放映が始まると全国から多くの観光客が訪れたそうだ。
また、金沢城跡は、戦国時代一向一揆で本願寺門徒の拠点となったところでもある。

画像は、復元された橋爪一の門・橋爪続櫓と五十間長屋の一部分。
復元された建造物の瓦が白く見えるのは鉛瓦で鉛が酸化して白くなっていて、復元工事中の城門瓦は未だ新しいから普通の瓦色である。時間の経過に従い白く酸化する。・・どの位月日経過すると色が変色するのか??

橋爪門を潜り本丸に、昭和32年、国指定重要文化財「2層2階の30間多聞長屋」が現れる。

本丸から見た、二之丸で復元された橋爪門と橋爪続櫓、50間多聞長屋、奥の櫓は、菱櫓。
本丸に行ってみたが天守台はなかった。

復元された菱櫓、平面が菱形、であるからその名が付いたとされる。

河北門
金沢城三の丸の正門にあたり、橋爪門、石川門と共に三御門と呼ばれた。
私が伺った時は復元工事中で、平成23年に復元が完成されたそうです。
此の門は、安永元(1772)に再建され、明治15年(1882)頃まで残っていたと記述がある。

復元工事中であった河北門で、門はほぼ完成していたが付帯設備の工事をしていた。

金沢城見学の後、日本三名園の一つ兼六園を見学した。
初夏のような天気の下、汗を掻きながら散策、雪吊りは始めて見る光景である。
兼六園は、加賀藩主第5代綱紀が創作し歴代藩主が現在の形にしたそうだ。

日本三名園とは、金沢市の兼六園・岡山市の後楽園・水戸市の偕楽園の総称である。
見所は沢山あるが、兼六園で必ず画像に出てくる場所が霞ヶ池の北岸に燈籠が配された景観「徽軫灯籠・ことじとうろう」である。

兼六園を伺ったのは3月19日、雪から松の木を守る「雪吊り」がまだあった。
「雪吊り模様が美しい」。
季節におおじないと見られない「唐崎松、からさきまつ」の雪吊りの景観が素晴らしく外国からの観光客が盛んにカメラに納めていた。
時間も余り無いので早足で周縁し最後に今朝は、朝食抜きで来たので「07時の列車に乗るには早起でないと」兼六園で朝昼兼用の食事をした。
兼六園レストランお勧めの金沢旬の和食で・・そして好物のビールも飲んだ。・・美味しかった。
私が行った時の兼六園は、白加賀・赤加賀の梅が満開であった。

満開であった「白加賀・赤加賀」の梅。好天であったので多くの鑑賞者が来園していた。

朝昼兼用の食事をしたレストランからの眺め。
食事は、兼六園レストランお勧めの金沢旬の和食で・・そして好物のビールを飲みながら見た金沢城のシンボル石川門、青空と白い雲のコントラストが素晴らしかった飲んだビールも美味しかった。

日本100名城第35番金沢城スタンプ。
私は48番目の紀行である。










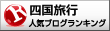


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます