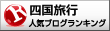秋山好古「カラー肖像画」
日本唯一、秋山好古カラー肖像画
画像は、今年7月に千葉県習志野市学園大久保商店街が特別にカラーで製作した「秋山好古」の肖像画で、本日(11月25日)まで秋山兄弟生誕地で特別展をしていた肖像画です。
今日、習志野市大久保にある薬師寺の三橋住職が秋山兄弟生誕地に来られ肖像画のレプリカの贈呈式を行った。
寄贈して頂いたレプリカは明日から秋山兄弟生誕地で常設展示します。
場所:愛媛県松山市歩行町二丁目3番地6
秋山兄弟生誕地
開館時間は午前10時~午後5時まで開館
通常は月曜日が休館だが11月から新年1月3日まで休まず開館している。
参考事項:習志野市大久保は、明治時代陸軍騎兵第13・14・15連隊があった地で、秋山好古は日露戦線にこの地から騎兵第一旅団長として出征し、凱旋した所で、現在は東邦大学・日本大学となっている。
日本唯一、秋山好古カラー肖像画
画像は、今年7月に千葉県習志野市学園大久保商店街が特別にカラーで製作した「秋山好古」の肖像画で、本日(11月25日)まで秋山兄弟生誕地で特別展をしていた肖像画です。
今日、習志野市大久保にある薬師寺の三橋住職が秋山兄弟生誕地に来られ肖像画のレプリカの贈呈式を行った。
寄贈して頂いたレプリカは明日から秋山兄弟生誕地で常設展示します。
場所:愛媛県松山市歩行町二丁目3番地6
秋山兄弟生誕地
開館時間は午前10時~午後5時まで開館
通常は月曜日が休館だが11月から新年1月3日まで休まず開館している。
参考事項:習志野市大久保は、明治時代陸軍騎兵第13・14・15連隊があった地で、秋山好古は日露戦線にこの地から騎兵第一旅団長として出征し、凱旋した所で、現在は東邦大学・日本大学となっている。