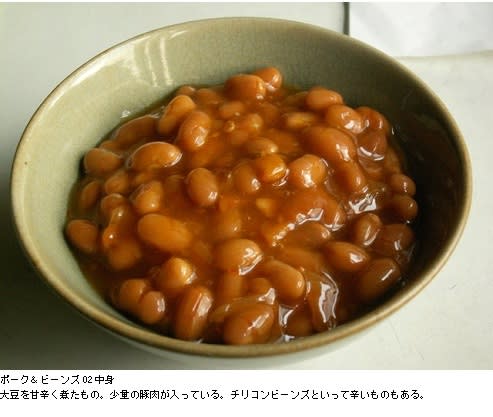失敗の無い汁物
7月下旬、母の入院生活がしばらく続くことになると病院から告げられる。2月から入退院を繰り返してきた母は、7月の初め頃までは一時的な外出もできて、車を運転し、買い物して、家に帰り、父の食事を作っていたのだが、体力がどんどん落ちて行き、7月下旬からは外出ができなくなったのだ。幸いにも、その頃、姉がアメリカから帰省してきており、父の食事は姉が面倒をみていた。その姉も7月末にはアメリカへ帰ったのだが、その数日後、義兄が入れ替わるように帰省し、その後は、義兄が父の面倒をみた。
そんなある日、これからのことを話し合うために義兄と二人、実家近くの居酒屋で飲んでいる時のこと
「義父さんに鳥の汁を作ってくれと頼まれたが、何のことかさっぱり判らない。」と義兄が言う。鳥の汁とは鶏汁のことである。豚汁や牛汁、山羊汁のようなものである。父の好物で、母が時々作ってくれていたので、私はよく知っている。
琉球料理の汁物には塩味のものが多い。豚の小腸大腸を使った中味汁、豚のあばら肉を使ったソーキ汁、豚の脛から足の部分を使った足ティビチ汁、豚のレバーを使ったチムシンジ(肝煎じ)汁、その他、山羊汁、牛汁などがある。
味噌味のものは少ない。イナムドゥチ(猪擬き)くらいしか思い浮かばない。イナムドゥチは元々宮廷料理である。味噌そのものが昔は庶民の手に入るようなものでは無かったのかもしれない。手に入るようになってからはオーハンブシーに使い、日常の味噌汁としてふんだんに使っている。だが、中味汁、ソーキ汁、足ティビチ汁、チムシンジ汁、山羊汁、牛汁などに味噌味のものはあまり見ない(牛汁ではたまに見る)。
醤油味のものも少ない。醤油を香り付けに使うことは上記の全ての汁物にもあるが、醤油をベースにした汁物は、少なくとも我が家では鶏汁しかなかった。
鶏汁は、私も好きで、たまに(年に1、2回は)自分でも作っている。作り方が簡単で失敗することも無い。いつも美味しくできあがる。鶏汁に限らず、汁物は概ね、失敗することは少ない。肉や野菜、昆布などの素材から旨味が出てくるので、塩加減さえ間違わなければ、煮込めばたいてい、美味しくできあがる。

鶏汁(トゥイヌシル):汁物
『聞き書沖縄の食事』によれば、「妊婦は・・・臨月になると体力をつけるために・・・鶏汁を食べる」とのこと。昔は妊婦の食い物だったようである。
同書に「鶏汁にはこんぶ、大根、パパイヤ、にんじんなどを加える」と、その材料が書かれてある。母が作る我が家伝統の鶏汁に、パパイヤは入っていない。
我が家の鶏汁の材料は、鶏のぶつ切り(沖縄のスーパーならたいていどこにでもある。ムネ、モモ、手羽など骨付きのもの)と、野菜はニンジンに夏場はトウガン、冬場はダイコンを用いる。その他に、昆布は必需で、揚げ豆腐などをいれる場合もある。
鶏の骨から旨味がでるが、出汁を加えるとさらにコクが増す。母はカツオだしを使っていたが、私はコンブだしを使っている。母は使わないが私は日本酒を入れる。




記:ガジ丸 2007.9.22 →沖縄の飲食目次