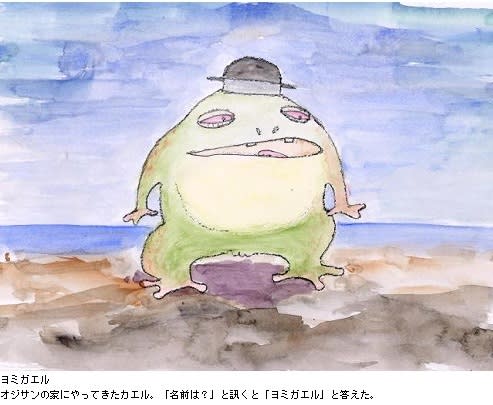周りに巨船が3つ(日本、中国、アメリカ)あり、それぞれが勝手な都合で走り回り、そこからの大波が四方八方から襲いかかる中、小さなサバニ(沖縄)はあっちの波に揺られ、こっちの波に揺られしつつ何とか踏ん張って浮かんでいる。
浮かんでいればいいのだ。上手く櫂を操り、沈まないよう努力していけばいい。沈まなければ、ウチナーンチュはその上でサンシンを弾き、唄を歌い、カチャーシーを踊り、泡盛を飲み、チャンプルーを食い、それなりに幸せに生きて行ける。

沈まなければいいのだが、東アジアの軍事バランスが崩れた時、巨船同士が諍いを起こした時、風速100mくらいの巨大最強猛烈台風にサバニは襲われることになるかもしれない。そんな時でもサバニは浮かんでいられるだろうか?
沖縄は、政治的にはそれなりの権利が保障されているが、経済的にも軍事的にも非力な島である。「言うこと聞かなかったら金やらねぇぞ」とか、「言うこと聞かなかったら殴るぞ」などと言われたら、「構わねぇよ」とは簡単には言えない。
他所からあれこれ命令されないような沖縄になるためには経済的自立と軍事的自立が必要だ。経済的自立は、沖縄の政財界の人々がそれなりに努力しているので、いつかはそれなりに達成できるかもしれない。問題は軍事的自立。
何年か前にもガジ丸通信で紹介しているが、今多くの人が知っている「命どぅ宝」という言葉の起源となった琉球史の1ページ。
「武器を持たない国があるだと!」とその昔、かのナポレオン皇帝も驚いたと言う琉球王国、中国貿易の利権に目をつけた薩摩に侵攻され、わずか十日で敗れる。
戦いがわずか十日だったのは、むろん武器の足りなさから抵抗にも限りがあったのだろうが、勝てぬ戦ならば早々と諦めた方が、その分、民や家来の命を無駄にせずに済む。尚泰王は人質として薩摩へ連れて行かれる身でありながら、皆の命を大切に思ったのであろう。首里城を明け渡す際に王が詠んだとされる琉歌がある。
いくさゆ(戦世) ん(も) すまち(済ませ)
みるくゆ(弥勒世) ん(も) やがてぃ(やがて)
なぎくなよ(嘆くなよ) しんか(臣下)
ぬち(命) どぅ(こそ) 宝
戦世も終わって、平和(弥勒世:弥勒菩薩が平和をもたらすという仏教思想に基づく)がやがて来る。(戦に負けて、城を明け渡したからといって)嘆くなよおまえ達(臣下は家来のこと)、生きているということが大事なのさ。といった意味。
こっちは戦争などしたくないのに、戦争をしたがる国が今もある。昔の薩摩侵攻みたいなことが無いよう沖縄も軍事的自立をしなければならない、・・・のか?本当に?たとえ沖縄が沖縄独自の軍備を持ったからといって、サバニに準備できる程度でしかない。巨船からの大砲一発で吹き飛んでしまうであろう。自立は不能だ。
荒波の中でもサバニが沈まないためにはどうするか?と考えて、政治にも経済にも軍事にも素人だが、平和大好きの沖縄のオジサンが一案思いついた。
先ず、沖縄にある軍事基地を今の五分の一くらいにコンパクト化する。沖縄の軍事基地の総面積は約23万7千ヘクタール、嘉手納飛行場とそれに隣接する嘉手納弾薬庫を足した面積が約4万7千ヘクタールで約五分の一。ちなみに今問題となっている普天間飛行場は480ヘクタールである。いかに沖縄の基地面積が広いかってことが判る。
五分の一くらいにコンパクト化するってことはしかし、つまり、平和運動家の方々には申し訳ないが、基地は残すってことになる。そして、嘉手納基地周辺の人々には申し訳ないが、嘉手納飛行場とそれに隣接する嘉手納弾薬庫は概ね残す。
そこは相変わらず軍事基地ではあるが、その内容は変わる。名前も、例えば「世界平和の基地」、略称BWP(Base of World Peace)などとし、国連軍に常駐してもらう。規模は現在の米軍の五分の一になるが、それでも国連軍だ、自衛隊も中国軍も米軍もロシア軍も含まれている。どの国も自国の兵隊がいる基地を襲うことは無い。テロリストも世界中を敵に回したくは無いので、ここは標的にしない。
世界中の軍隊が、例えば2年任期でBWPに赴任する。基地内にはアメリカ村、イギリス村、オランダ村、ドイツ村、ロシア村、イラク村、中国村、インド村、ミャンマー村、韓国村などなどが、それぞれ赴任する毎に代わる代わる作られる。
基地内の武器庫など厳重警戒区域の一部を除いて基地の概ねは地元のウチナーンチュにも観光客にもオープンだ。飛行場は軍民共用とし、世界中のあちこちから人々がやってくる。ウチナーンチュは沖縄にいながら世界の人々と交流ができる。

基地内の概ねはオープンなので、沖縄の子供達はアメリカ村、中国村、イギリス村、オランダ村、ドイツ村、ロシア村、イラク村、インド村、ミャンマー村、韓国村などなどへ出かけ、そこの子供達と交流する。世界の子供達が沖縄の子供たちと仲良くなる。その子供達が大人になった時、「沖縄は平和な島」という認識を持つに違いない。
「いやー、沖縄人は酒飲みで、男の多くは怠け者で、ギャンブル好きで、いい加減で、のんびりしているが、イチャリバチョデーという気分を持っている奴が多くてよ、すぐに友達になれるよ、平和で楽しい所だよ。」と思う人々が増えるであろう。
尖閣諸島だって、せっかく領土問題は棚上げして未来の英知に任せようとなっているのを、東京都が買ったりして、わざわざ諍いの種を作らなくてもいいのにと思う。
前にもこのガジ丸通信で書いた(竹島だったかも)けれど、尖閣諸島は、日本も沖縄も中国も台湾も新しく同じ名前、例えば平友島(平和友好の島の略)などと変えて、それぞれの国と地域の人々が交流できる場所とし、一年のある期間は福建祭り、別の期間は台湾祭り、また別の期間は八重山祭りなどを開き、みんなで楽しめばいい。
小さな島沖縄が平和な島であるためには、沖縄が国連軍の一大拠点となり、諍いの種になりそうな尖閣諸島は交流の島とすればいい。弱小沖縄が「沈まないサバニ」であり続けるためにはそれらが有効な手段であると、沖縄のオジサンは思う。
記:2012.5.31 島乃ガジ丸 →ガジ丸のお話目次
参考文献
『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行