「お互いは哀れだなあ」と言い出した。「こんな顔をして、こんなに弱っていては、いくら日露戦争に勝って、一等国になってもだめですね。もっとも建物を見ても、庭園を見ても、いずれも顔相応のところだが、――あなたは東京がはじめてなら、まだ富士山を見たことがないでしょう。今に見えるから御覧なさい。あれが日本一の名物だ。あれよりほかに自慢するものは何もない。ところがその富士山は天然自然に昔からあったものなんだからしかたがない。我々がこしらえたものじゃない」と言ってまたにやにや笑っている。三四郎は日露戦争以後こんな人間に出会うとは思いもよらなかった。どうも日本人じゃないような気がする。
「しかしこれからは日本もだんだん発展するでしょう」と弁護した。すると、かの男は、すましたもので、
「滅びるね」と言った。――熊本でこんなことを口に出せば、すぐなぐられる。悪くすると国賊取り扱いにされる。三四郎は頭の中のどこのすみにもこういう思想を入れる余裕はないような空気のうちで生長した。だからことによると自分の年の若いのに乗じて、ひとを愚弄するのではなかろうかとも考えた。男は例のごとく、にやにや笑っている。そのくせ言葉つきはどこまでもおちついている。どうも見当がつかないから、相手になるのをやめて黙ってしまった。すると男が、こう言った。
「熊本より東京は広い。東京より日本は広い。日本より……」でちょっと切ったが、三四郎の顔を見ると耳を傾けている。
「日本より頭の中のほうが広いでしょう」と言った。「とらわれちゃだめだ。いくら日本のためを思ったって贔屓の引き倒しになるばかりだ」
この言葉を聞いた時、三四郎は真実に熊本を出たような心持ちがした。同時に熊本にいた時の自分は非常に卑怯であったと悟った。
(夏目漱石『三四郎』より)
ああ…、『三四郎』好き!
広田先生好き!特にこの冒頭の汽車の場面が好き!
上記は読みやすい新仮名遣いで載せたけれど、旧仮名遣いの「亡びるね」が断然好き。
ちなみに辻仁成さんが最近パリで飼い始めたワンちゃんの名前は、三四郎。仁成さんも『三四郎』がお好きなんですって
さて、相変わらずストレイ・シープな私ですが、最近再び英語の勉強を始めてみたのです。最近コロナ禍であまり使ってないですけど、今の会社にいる限りはどうせずっと必要だし。
とりあえずリスニングの訓練を、とyoutubeでこの映画↓を見てみたのです(本当は現代ドラマとかの方がいいのでしょうが、好きなものじゃないと楽しくないし)。
SHERLOCK HOLMES MOVIES | THE HOUND OF THE BASKERVILLES (1939) | classic movies | Basil Rathbone
私の中でホームズというとジェレミー・ブレットのシリーズやBBCのラジオドラマシリーズなんですけど、このベイジル・ラスボーン&ナイジェル・ブルースもいいねえ
私が生まれるより40年近くも前の作品とはとても思えない。1939年というと、第二次世界大戦の開戦の年でしょう。その年にアメリカはこういう映画を作っていたのだものなあ。その後の太平洋戦争中もこのシリーズはずっと途切れずに作り続けられていたというのだから(日本が贅沢は敵だ!とか一億玉砕!とか叫んでいた頃に)、日本は戦争に負けるわけだわよ。
そしてコナン・ドイルが亡くなったのが1930年なので、そのわずか9年後の映画ということになる。
漱石がロンドン留学をしていたときに、ホームズもベーカーストリートにいたんですよね。もちろんフィクションの世界の話ですけど。しかし漱石はドイルやホームズについては完全スルーなのであった…
『バスカヴィル家の犬』の舞台はダートムーア。私、イギリスのムーアの景色が大好きでねえ。。。在英中にヨークシャームーアには行けたけれど、ダートムーアには行けなかったのが心残りです。ああいう北の荒涼とした風景が好きなんです。アイルランドもスコットランドも好き。だからスイスよりアラスカ派。いま日本で最も行ってみたいのは道東。真冬の釧路湿原とか摩周湖とか行きたい
しかし、少し英語から離れていただけで恐ろしいほど単語を忘れている自分に驚く・・・。かつて普通に使っていた単語も忘れるなんて・・・。英語の単語って忘れるものなんですね・・・。日本語の単語はどんなに長く使わなくても忘れないのに・・・。
うちの上司、昔は米国で働いていて英語も毎日苦もなさそうに話してるんですけど、外国人と食事に行くときにいつも自分一人じゃなく誰かを連れて行こうとするので一度理由を聞いたら、「食べながらずっと英語を話しているのは疲れるから」と。この上司でもそうなのか。ネイティブと同じ感覚で話せるようになるには10年向こうに住むことが必要と聞いたことがあるけど、本当にそうなんでしょうね。。。私には一生無理だ。でもまあ、頑張ります。。。
漱石アンドロイド モノローグ『Variable Reality ―虚構は可変現実』
2021年もあと2日。
ハイティンクやフレイレや吉右衛門さんが確かに生きていた2021年がもうすぐ終わり、彼らのいない新しい年が始まるというのは不思議で、どうしようもなく寂しい気持ちです。
先日友人と「年末だし蕎麦を食べに行こう!」という話になり、どうせなら行ったことのない店にと「芥川龍之介が食べたと言われる蕎麦屋」を目指して田端まで行ったのですが、改修中のためクローズ 。結局いつもの上野の藪蕎麦と相成りました。でも相変わらず美味しくて満足
。結局いつもの上野の藪蕎麦と相成りました。でも相変わらず美味しくて満足 。
。
せっかく田端まで行ったので、駅前の文士村記念館にも伺いました。入館料無料ですが、生前の芥川の珍しい映像や芥川邸の30分の1スケールのジオラマが見られたりと、思いのほか楽しむことができました。
自殺の翌朝、妻の文夫人は、芥川の安らぎさえある死に顔に「お父さん、よかったですね」と声をかけたそうです。過去2年間の夫の苦しみを傍らで見続けてきた彼女は、自然にその言葉が口から出たそうです。
自殺の直前に書かれた久米正雄宛とされる『或旧友へ送る手記』の中で、芥川はこんな風に書いています。
僕の今住んでゐるのは氷のやうに透み渡つた、病的な神経の世界である。・・・若(も)しみづから甘んじて永久の眠りにはひることが出来れば、我々自身の為に幸福でないまでも平和であるには違ひない。
芥川にとっては、死ぬよりも生きていることの方が辛かったのでしょう。でも35歳は若いな…。
田端から駒込方面に少し歩くと、子規の墓のある大龍寺があります。今回ここにも行く予定だったのだけど、蕎麦屋閉店の衝撃と空腹で頭の中はランチのことでいっぱいで、すっかり忘れて田端に戻ってきてしまいました 。どうせならロンドンから帰国後に漱石が訪れた1月27日付近に行ってみようかな。
。どうせならロンドンから帰国後に漱石が訪れた1月27日付近に行ってみようかな。
前置きが長くなりましたが、文士村記念館で友人と話しているときに、漱石アンドロイドの話題が出たんです。2016年末に完成してから一度実物を見てみたいと思いながら、なかなか機会のない漱石アンドロイド。
久しぶりにyoutubeで検索してみたところ、二松学舎大学のチャンネルに「漱石アンドロイド演劇」なるものがupされていました。それが、冒頭に載せた動画です。2019年の「アンドロイドに魂は宿るか?」というテーマで開催されたシンポジウムで上演された『Variable Reality ―虚構は可変現実』という演劇作品で、登場人物は漱石アンドロイド、脚本は『夢十夜』や『三四郎』などの漱石作品の言葉が織り交ぜられた佐藤大氏によるオリジナルです(作中の「砂漠の亀」云々等は映画『ブレードランナー』へのオマージュとのこと)。
観終わってまず感じたのは、「演劇としてよく出来てるなあ !」ということでした。
!」ということでした。
何より、出演者が虚構と現実の淡いに存在するアンドロイドであることを活かした脚本がいい。人間の俳優には演じることができない作品になっている。そしてアンドロイドの表情が、私が想像する漱石のイメージに非常に近くて、まるで本人がそこにいるようでドキリとする。もちろん表情や動きはぎこちなく、人間のそれとは全く違います。でも私はそうであるが故に、この演劇に感心し、感動しました。能や文楽と似ているものを感じたからです。能面はずっと表情が変わらないのに、時に人間の顔以上の表情を見せることがある。文楽人形も同様で、人間が演じるよりも遥かに深く豊かな感情がそこに見えるときがある。このアンドロイドも、最後にスイッチが切れるとただの人形にすぎなくなるのに(この効果も文楽と同じですね)、独白場面では魂が吹き込まれたように見え、人間のようで人間ではないその表情に、強く"漱石アンドロイドの感情"を感じてしまいました。アンドロイドが持つ可能性というのは、私が思っている以上に大きいのかもしれない。ちなみに文楽人形の感情表現はロボット工学でも注目されているそうです。
脚本を書かれた佐藤氏は、「アニメーションの世界も実は表情が乏しいので、その点はアンドロイド演劇はアニメーションに似ていると感じました」と仰っています。
しかし次に思ったのは、もしアンドロイドがこれ以上に、つまり人間と区別がつかないほどにリアルになったら、私はどう感じるだろう ?ということでした。
?ということでした。
最近のアンドロイドやAIの進化を見ていると、それはそう遠くない未来の話のような気がする。そんな心配を本気でしなければならない時代が来たということ自体、昭和生まれの私には隔世の感があるけれど。
今の漱石アンドロイドは明らかに人形であるとわかるから、何かを喋っても私達はそれを人形のものとして受け止めるし、人形であるが故の魅力を感じる余裕もある。でもこれが人間と区別がつかないほどリアルになったら?あまつさえ高度な人工知能を持つようになったら?
私達は”彼”を人間と錯覚するようになるのではないか?
頭では人形だとわかっていても、そう錯覚するのは避けられないのではないか?
でも、漱石アンドロイドは間違っても漱石そのものではない。
そうなると、夏目漱石という人間の権利はどうなるのか?
と思っていたら、既に二松学舎大が2018年のシンポジウムでその問題を取り上げていました。テーマは「誰が漱石をアンドロイドとして蘇らせる権利をもつのか?」。
漱石アンドロイドをはじめとして、人々が偉人として記憶している人を復元したロボットをここでは「偉人アンドロイド」と呼びます。多くの人は、はじめは偉人アンドロイドに違和感を感じるかもしれません。しかし、その動きに注視し、言論に耳を傾けるうちに、確かにそこに存在する偉人アンドロイドにやがては生命感を感じたり、場合によっては私達が知っている故人の偉業や実績を重ね合わせるのです。
提起された問題とは、蘇らせる権利だけではありません。
アンドロイドの制作者はそこに存在するアンドロイドに何を語らせてもいいのだろうか?
故人のダークな一面やプライバシーで覆われていた趣向などをアンドロイドで表現することで暴いてもいいのだろうか?
全くの創作、パロディとして、あたかも偉人がそれをしているかのように演じさせてもいいものだろうか?
と、次々に生まれてきます。(中略)
それらはすべて、そっくりなアンドロイドとして夏目漱石という故人を蘇らせようという試みがあったからこそ生まれた気づきでした。
(ロボスタ 2019年2月)
ここで交わされた議論の内容は上記リンクに詳しく、また『アンドロイド基本原則 誰が漱石を甦らせる権利をもつのか?』という書籍にもなっています(私は未読)。
漱石アンドロイドやマツコロイドやERICAの開発者でありアンドロイド研究の世界的権威である大阪大学教授の石黒浩さんの意見は、以下のようなものです。
石黒氏は「偉人とは一個人としての存在ではなく、社会で共有されるポジティブな側面の人格を示すもの」であり、人々の想像で作り上げられる側面も持っているとして、人の生きる支えや目的になったり、時として歴史の象徴になるものであると主張します。その意味では偉人アンドロイドは動いて”話す銅像”であり、「人間はアンドロイドになることでより進化し、尊い存在になる」と提起しました。
更に「例えば、社会的な人格を崩さない限り、誰のアンドロイドでも自由に作って良いというのはどうか。人間は個人的側面と社会的側面を持っていて、それを分離して社会的側面だけをアンドロイド化したものは、それはもう故人ではない。優れた社会的な人格をアンドロイドとして育てていけば、そのうち人権を持つようになり、優れたアンドロイドだけの世界が作られる」
(ロボスタ 2019年2月)
(役者としてのアンドロイドについて)アンドロイドが意思を持って“演技”をするわけがありません。しかし「指示された通りに動く」という能力は人間にも勝ります。完璧にコントロールできるロボットは、完璧な「役者」にはなれるんですよ。優れたディレクションによって人間の役者の演技が開花するようにね。(中略)また、本物の人間ではない、「アンドロイドならではの利点」もあります。それは、アンドロイドなら“良い面”だけを再現できること。夏目漱石にだって人間として褒められない一面はありましたが、これなら素晴らしい部分だけを再現して後世に伝えることができます。アンドロイドは銅像よりもさらに深く、その人の功績を伝える装置になるでしょうね。
(エンジニアtype 2020年8月)
・・・・・・。
はっきり言おう。
このヒト、何言っちゃってるの???
そもそも「良い面」って、「素晴らしい部分」って何よ。何をもって「優れた社会的な人格」と定義するのよ。
褒められる部分も褒められない部分も全てひっくるめて漱石という人間は構成されているのであって、それら全てをひっくるめて私達は彼を愛しているのですよ。イライラしてDV気味で鬱になって、でも繊細でユーモアもあって、死に惹かれながらもそれ以上に生に惹かれ、胃痛と闘いながら生きたのが漱石という人間でしょう?その中の”良い面”だけを再現することに何の意味があるのよ?教育的にも全くメリットを感じられないわよ。
これに関しては漱石の孫の房之介さんの下記意見に、私は賛成です。
一方で夏目房之介氏は、アンドロイドが動く銅像として偉人を理想化したり、いわば神格化することに異論を唱えました。それは「多義性」を損なうことになる、という意見です。房之介氏はパロディとしての存在を容認し、むしろパロディとしての利用を尊重する考えです。パロディやフィクション創作であることを明示すれば、偉人アンドロイドのイメージに反することでも演じさせることを許容すべき、世の中はやっぱり面白い方がいい、という旨の意見でした。
(ロボスタ 2019年2月)
漱石を理想化した人格にして蘇らせることは、「ただの夏目なにがしで暮らしたい」と言っていた漱石が最も嫌がるであろうことであり、漱石が残した文学にも反することになると思う。
そもそも実在する人物か否かに関わらず、”良い面”だけを持つアンドロイドなんて私は作るべきではないと思うけどな。
では将来的にアンドロイドが知能を持つようになって犯罪をすることになっても構わないのか?となると、もうターミネーターの映画の世界ですね
 。そういう世界が現実のものになりつつあるなんて、本当に隔世の感を禁じ得ない。。。
。そういう世界が現実のものになりつつあるなんて、本当に隔世の感を禁じ得ない。。。
というようなことを私のような巷の一介の人間が年の瀬に考えたりするのだから、そういう問題提起が生まれただけでも、漱石アンドロイドが作られたことには意味があったのではないかな、と思う。
天国の漱石は下界に生まれた自身のアンドロイドをどう思って見ているだろう。悪趣味だと顔を顰めているか、面白がってニヤニヤしているか。
漱石アンドロイド演劇『手紙』(青年団+二松学舎大学+大阪大学)
2018年のシンポジウムで上演された、漱石アンドロイド演劇の第一弾『手紙』。
ロンドンにいる漱石と東京にいる子規の最後の日々の手紙での交流を描いた演劇作品です。
子規が漱石に向かって話している言葉は、手紙だけでなく『墨汁一滴』などからの引用も織り交ぜられています。
それにしてもこの演劇、よくできている。。。。。もうすぐ死んでいく子規は人間らしく生き生きとしていて(実際にも人間が演じていて)、漱石はアンドロイドのように覇気がない(演じているのもアンドロイド)。布団から出ることさえできずに迫りくる死と闘いながら最期まで明るさを失わず『墨汁一滴』、『仰臥漫録 』、『病牀六尺』などを精力的に書き続けた子規と、体は健康でも精神は病み出口のない迷路の中で燻り続けていたこの時期の漱石。これから帰国して作家としての人生が始まっていく時期であることを思うと(そしてその時には子規はもういない…)、そこに色々な意味を見ることができて心動かされる。改めて、演劇の世界でこれほどアンドロイドの活用可能性が大きいとは、目から鱗です。
でも、これも作品を作っているのが人間だからこそではないかな。石黒教授が言うように「人間はアンドロイドになることでより進化し、尊い存在になる」とは、私は全く思わない。そもそもこの演劇に感動したのも、平田オリザ氏の脚本・演出と子規役の井上みなみさんの演技の力が最も大きい。子規の最後の手紙の場面(18:10~)の井上さんの演技には、胸が苦しくなって涙が出た。
でも、漱石アンドロイドも本当に良い表情をしているよね。。。。もしかしたらいつか私は監督アンドロイド、脚本アンドロイド、演出アンドロイド、出演者全てアンドロイドで上演される演劇に感動してしまう日が来るのだろうか。「人間よりよっぽど上手い」とか言いながら。今までの私は「絶対にそんなことはない」と言い切れたけれど、この演劇を見て、100%ないとは言い切れなくなっている自分が怖い。演劇の選択肢が増えるのはいいこと♪なんて楽観的にはとても思えない。アンドロイドのいる未来が本気で空恐ろしくなる。
ただ一つだけ確かなことは、「アンドロイドは失敗しない」ということ。「緊張してつい失敗してしまった」とか「勢いに乗りすぎてトチってしまった」とかいうことはない。あったとしてもプログラムされたものか、バグでしょう。私は演劇を見る時に、そういう人間の危うさも含めて感動するんです。そういう危うさが見えない裏側にあることに人間の愛おしさを感じるんです。絶対に間違わない、絶対に失敗しない、絶対にその日の気分や客席の影響を受けない、絶対に動揺しない、裏に一片の危うさもないアンドロイドの演技や演奏に心の底から感動することは、やはりこの先もないのではないのかなと思う。・・・・・おそらく。
今年の更新はこれで最後です。
今年も当ブログにお越しくださった皆さま、コメントをくださった皆さま(PC表示のweb拍手から拍手を下さったりコメントを下さっている方もありがとうございます!web拍手なのでご返事できていませんが、嬉しく拝見しています)、ありがとうございました。来年もマイペースに更新できたらいいなと思っていますので、時々覗いてやってくださいませ。
よいお年を







※夏目漱石アンドロイド演劇「手紙」を初上演!平田オリザ氏の作・演出、二松学舎大学で(ロボスタ 2018年8月)
※「アンドロイドに魂は宿るか?」漱石アンドロイド演劇の第二弾モノローグ公開 脚本は攻殻機動隊やエウレカの佐藤氏 テーマは「虚構と現実」(ロボスタ 2019年11月)
※演劇で使われている漱石アンドロイドの音声は、シナリオを読み上げて録音したものではなく、合成音声なのだそうです。房之介さんの声を大量に録音し、音素・音声解析を行い、電子的にコンピュータで作りだした声で、「一度、作りだしたら任意の言葉をしゃべらせることができる反面、セリフの棒読みになったり、不自然な機械的な抑揚になってしまいがち」とのこと。いやいや、既にかなり自然ですよ。もちろん人間と同じではないけれど、こういう話し方をする人間もいるし。改良が重なっていけば、どんどん自然になっていくんでしょうね。すごい時代になったものだ・・・。
谷川俊太郎『虚空へ』PV
谷川さんの新刊が出ていたこと、いま知りました。明日買いに行こう。
言葉は薄れて、そこに一人立ちつくし・・・
この世界に詩があってよかった。この世界に谷川さんがいてくれてよかった。
それだけで私の人生は十分に幸運だったと感じられる。

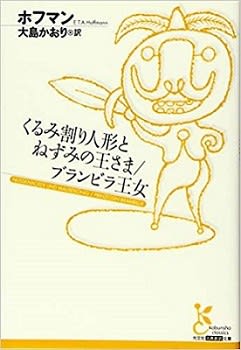
仕事が忙しくて吐きそう。超安月給なのに、納得いかん。しかし転職しても(そもそもできるかという問題もあるが)そう状況はカワラナイのではないかとも思う。うちの会社は超低給であることを除けば、おそらくそこまでブラックではないので。。
100年前に漱石が『草枕』で書いた言葉が沁みる。
住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。
人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。
越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容(くつろげ)て、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職が出来て、ここに画家という使命が降(くだ)る。あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊とい。
宮崎駿監督は、サン=テグジュペリの『人間の土地』(新潮文庫)に寄せた文章でこう書いた。
「日常だけでは窒息してしまう」。
詩的世界と日常世界。空想世界と現実世界。理想世界と現実世界。人間以外の全ての者達にとって、おそらくそれらの世界の間に境はないのだと思う。人間だけがその二つの世界を意識し、行き来する。そしてそのあわいの場所で、様々な芸術が生まれる。その往来に時に心遊ばせ、時に憩い、時に恐れ、時にその間で引き裂かれた人達が遺してくれたものが、今日も私の日常を慰める。
先月、新国立劇場バレエ団の『コッペリア(ローラン・プティ版)』のネット配信を観たんです。私が観たのは小野絢子さんの日で、小野さんの踊りは初めて観たけれど素晴らしいダンサーだなぁ!と感嘆したり、一方でプティのエスプリ味を表現するのは日本人ダンサーには難しいというSNSの感想を読んで、なるほどとも実感したり。プティの作品って以前も観たことがあるけれど、エスプリ感が本当に重要ですよね。日本人が踊るとただ「可愛い」だけになりがちで、ハードルが高い。。。
しかし私が何より衝撃だったのは、「なんだこの話・・・ 」ということでした。
」ということでした。
『コッペリア』ってこんな話だったのか、と(初めて観たんです)。
こんなストーリーを思い浮かぶ作家の頭の中って一体どうなっているのだろう??と気になり調べたところ、原作はE.T.A.ホフマンの『砂男』とのこと。ホフマンは200年前のドイツの作家で、チャイコフスキーのバレエ『くるみ割り人形』や、オペラ『ホフマン物語』(私は未見)などで有名。シューマンの『クライスレリアーナ』も、ホフマンの同名の小説に触発されて作曲されたそうです。wikipediaでは「後期ロマン派を代表する幻想文学の奇才」と紹介されています。
光文社古典新訳文庫から新訳が出ていたので早速図書館で借り、『砂男』、『クレスペル顧問官』、『大晦日の夜の冒険』、『くるみ割り人形とねずみの王さま』、『ブランビラ王女』の5作を読んでみました。
いやぁ、世の中にこんな奇妙な物語が存在したとは。。。。。
本当に世界は知らないことだらけ。
今回読んだ5作、どれもホフマン独特の感性が溢れていて面白かったけれど、とりわけ『ブランビラ王女』の印象が強烈でした。粗筋の紹介もしようがない、読んでいて頭がおかしくなりそうな、作家がどういう思考の流れで書いたのか想像もつかないような物語なんだけど、その迷宮に迷い込んだまま放られる感じがなんだかクセになるというか、頭から離れなくなる。そういう感じって、シューマンの音楽にもありますよね。シューマンがホフマンに傾倒したのがわかる気がする。
『ブランビラ王女』の主人公は若い青年の役者ですが、「ホフマンと演劇」についてググってみたところ、こんなページ↓が出てきました。
「E.T.A. ホフマン『ある劇場監督の奇妙な悩み』について」(田辺真理)
ホフマンはシェイクスピアの戯曲が好きだったようで、確かにシェイクスピアのあべこべの世界が生み出す混乱や皮肉、にもかかわらず根底に流れる世界の調和、そして失われることのない冷徹な視点はホフマンの作品と通じるところがあるように思う。
この地上における全存在の茶番を認識し、そのような認識を楽しむ、それがフモールなのです。
(『ブランビラ王女』)
ホフマンが描いた幻想世界と現実世界との行き来の物語には、常に根底に「ここ(現実世界)で生きていかねばならない私達」という認識があるように感じる。それは決してネガティブな意味だけではなく、「それが避けられないことであるならば、では私達はこの場所でどう生きるか」と現実世界に対峙する姿勢も垣間見え、それはおそらくホフマンがリアリストの視点を常に失わない人だったからなのでしょう。
『ブランビラ王女』の中で語られる「イロニー」と「フモール」(英語のアイロニーとユーモアですね)という概念が私には馴染みが薄かったので、少し調べてみました。
これ(=フモール)を、イロニー(アイロニー)Ironieと並ぶ基本的な芸術的意識態度として取り上げたのは、ドイツ・ロマン派の詩人ジャン・パウルである。彼はその著『美学入門』(1804)のなかで、これを「ロマン的滑稽(こっけい)」であり、「転倒した崇高」であるとしている。それは通常の揶揄(やゆ)のように個々の愚者や愚行をあげつらうのではなく、理念と対比された人類全体、現実の世界全体の愚かしさを際だたせる。それはまた、単に偉大なものをおとしめるパロディーParodieや、卑小なものから出発して偉大なものへと高まるイロニーとは異なって、これら偉大と卑小のいずれも、無限なものの前ではいっさいが等しく無であるとみる。そしてその限りで、個々の人間の愚かさも、愛すべき滑稽として受け入れる。ここではしたがって、滑稽とまじめ、喜劇的なものと崇高、笑うべきものとそれへの愛惜の感傷とが入り混じっている。
(日本大百科全書「フモール」)
さらに、こんなページ↓も。
ホフマンの『チビ助ツァヘス』と漱石の『吾輩は猫である』を重ね、両作品におけるイロニーとフモールについて書かれています。少し長いですが、イロニーとフモールの概念がわかりやすく、『吾輩〜』についての視点も面白かったので、覚書として引用させていただこうと思います(引用が長すぎて梅内先生に怒られちゃうかな )。
)。
ソクラテスの用いたイロニーの図式を考察してみるとき、次のような手続きが踏まれていることが分かる。まず第一に、話し手は、偽装という手段を用いて、つまり自分を無知なる者と称して低い立場に置き、同時に相手を高い立場に置くことによって、相手の警戒心を解除させ、現実世界の論理から抜けださせる。第二に、話し手は、相手に現実の世界を超えた理想の世界を対峠させ、これを認知させるのである。この図式は、簡略にすれば、テーゼーアンチテーゼージンテーゼという弁証法的発展として捉えられるであろう。
しかし、このイロニーの弁証法的発展経過においては、次の三つの構成要素が看過されてはならない。
一、話し手は、相手よりも高い認識をもっている。
二、相手は、話し手の高い認識を受け入れるだけの認識力をもっている。
三、ジンテーゼは、決して理想 (イデー) そのものとしては実現されない。
•••
イロニーの機能の本質は、テーゼに対して理想的なアンチテーゼを提示することによって、テーゼとアンチテーゼとを融合したジンテーゼを導きだすところにある。このジンテーゼが安定すると、やがてこれは再びテーゼとなり、これに新たなアンチテーゼが対峙させられることになる。このようにして、弁証法的発展が螺旋状に繰り返されるのである。しかしながら、最終的ジンテーゼである理想ないしイデーは、決して到達されることはありえない。従って、イロニーは、実現されることのありえない理想に向かって、永遠にテーゼに対してアンチテーゼを提示してゆく図式から逸脱できないのである。この意味において、時として弱く、はかない地上的存在にとってイロニーは、非情とも、冷酷とも見えかねない。最終的に、理想そのものを地上化することは不可能なのである。ここに至ると、理想的なものを地上化する機能をもつものがフモールであると考えられるのである。
地上的存在である人間が、イロニーの図式によって天上的存在にまで駆り立てられるとき、そこにはやはり、非人間的な状況が生まれると思われる。つまり、地上的存在である人間は、その生命の大前提として空気を、そして水を必要とする。ところが、天上に近づくと、空気は希薄になり、水分も少なくなり、さらに上昇すると、真空の状態になって、人間は生きてゆくことができなくなる。肉体をもつ人間は、イデーの中に生きることはできないのである。そこまでしてイデーを追求することは、生身の人間には求められていない。この極端に進むイロニーの軌道を修正し、天上への方向性を再び地上へと向けて、地上での理想を実現させるものが、フモールに他ならない。この意味において、フモールは、イロニーを前提として生まれるものであると言って差し支えないであろう。
厳しい批評眼からすると、このようなフモールは、一種の妥協という印象を受けるかも知れない。しかし、それは妥協というよりは、むしろ現実と理想の「調和」と呼ぶべきである。あるいは、人類の「智恵」とも呼びうるかも知れない。
そして『吾輩〜』の猫は「勇気をもって、完全に自由な個人主義的立場から、西洋文明を模倣しようとする当時の文化人たちを批判するのである。猫の批判は、超越的なものであって、人間の側からの批判は全く受け付けない。この意味において、猫の批判は、一方通行的なものであって、現実を正反対に映しだす「イロニーの鏡」の機能を果たしている。漱石は、『ガリバー旅行記』に見られるスウィフトの容赦なき諷刺ないしイロニーを高く評価していたと言われる。とはいっても、猫の諷刺ないしイロニーは、スウィフトのそれと比べると、それほど徹底したものではない。つまり、猫のイロニーは、完全に冷たいものではなく、そこには常に一抹の温かみと湿り気、すなわちフモールが潜んでいるのである。
•••
死によって変容するツァヘス、そして溺死によって成仏する猫の姿を観察するとき、その湿り気、すなわちフモールは、いずれの場合にもアンチテーゼとしてのイロニーを超え、一つの調和的なジンテーゼをもたらしている。ツァヘスにしろ猫にしろ、いずれもイロニーの力に駆り立てられ、自分の限りない理想を求めたのであったが、自らの、あるいは地上的存在としての限界に達し、ついには再び地上へと降下し、最終的には溺死する運命にあった。しかし、そこには限界に挑戦したという満足感が生じている。それは、生を享けた者の充実感であり、生の一回性を体験したものすべての喜びでもある。それゆえ、そこには生を無限に肯定する弥勤菩薩か仏陀のごとき「死の微笑」が、必然的に浮かんでくるのである。
漱石にとっての西洋文明と日本文化は単純にテーゼとアンチテーゼとして対峙されうるものではないようにも思うけれど、『吾輩~』の猫が溺死していくときの心情は確かにここに書かれてあるものに近いかもしれない、と感じました。『現代日本の開化』の結論も決して諦念や敗北だけではない何かがそこにはあり、それは梅内先生が書かれている「それは妥協というよりは、むしろ現実と理想の「調和」と呼ぶべきである。あるいは、人類の「智恵」とも呼びうるかも知れない。」と似たものを感じます。絶望だけではない何かを漱石は残してくれている。
話をホフマンに戻します。『大晦日の夜の冒険』や『クライスレリアーナ』が収められているのは『カロ風幻想曲集』というタイトルの作品集で、また『ブランビラ王女』もカロの版画からインスパイアされて書かれた作品です。ジャック・カロは400年前のフランスの版画家で、マーラーの交響曲第1番「巨人」の3楽章もカロの版画がもとになっていました。私はカロについては詳しくないけれど、マーラーの音楽はカロを通してホフマンの世界にも通じているように思う。ホフマンの作品をそのまま音符にしたら、マーラーのような音楽になるはず。グロテスクさ、病的になりかねない混沌、脈絡なく話が跳び、そして回収されない。なのに世界の統一感があって、都会的。wikipediaによると、マーラーの交響曲第一番の3楽章はホフマンの『カロ風幻想曲集』にヒントを得たともいわれているそうです。
エルンスト・テオドール・ホフマンはアマデウス・ホフマン、すなわち「お化けのホフマン」と呼ばれた。いや、自分で好んでアマデウスを名のった男であった。敬愛してやまないモーツァルトに肖(あやか)ったのである。
46歳の短い生涯であったが、その多彩奇才の表現力はなぜか老ゲーテや同時代のヘーゲルに嫌われ、ハイネに褒められ、のちには後期ロマン派の代表作家として、バルザック、ジョルジュ・サンド、リラダン、プーシキン、デュマ、ドストエフスキー、ネルヴァル、モーパッサン、ボードレールに絶賛された。
この通信簿は悪くない。とくにプーシキンとリラダンが兜を脱いだところが上々だ。
(松岡正剛の千夜千冊)
この通信簿は参考になる。ホフマンを絶賛した作家の本を、今度は読んでみたくなる。
と、ここまで書いてきて、謎が謎のまま残っているのに何故か世界の調和を感じさせる妙な説得力があるのって、宮崎監督の映画と似てね?きっと宮崎監督もホフマンお好きな気がする!と思い「宮崎駿 ホフマン」とググってみたら。
三鷹の森ジブリ美術館企画展示
クルミわり人形とネズミの王さま展 ~メルヘンのたからもの~(2014年5月31日~2015年5月17日)
なんですとーーーーー




こんな企画展があったなんて・・・・・・・・


当時はホフマンを読んでいなかったとはいえ、後悔してもしきれん。。。。せめて企画展のパンフレットだけでも手に入らないかと調べてみたら、めっちゃプレミアム化していて手が出ない。。。仕方がないので当時のアエラの特集号を図書館で予約しました。宮崎監督の絵、すごく素敵だなぁ。行きたかったなぁ。。。。。。
宮崎監督とホフマン作品との出会いは『風立ちぬ』の制作中だったそうで、読書家の宮崎監督がそれまでホフマンを読んだことがなかったというのは意外。でも宮崎監督って、本や映画を最後まで読んだり見たりしなくて平気な人なんですよね。途中で想像の翼が羽ばたいて、続きの物語を自分で作ってしまうそうで。高畑監督はそうではないらしいが(ほぼ日新聞)。宮崎監督、『くるみ〜』はちゃんと最後まで読まれたのかしら
内覧会では、東京・三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文氏が今回の“クルミわり人形とネズミの王さま展”が企画された経緯について語ってくれた。
中島氏によると、宮崎駿監督は企画・監修だけでなく、イラストつきのパネル10数枚を描いており、今回の企画展示は、宮崎監督の長編映画製作における引退後の、初仕事とも言ってもよいとのことだ。
なぜ今回の企画が始まったのか、ということだが、これは宮崎監督がロンドン在住のイラストレーター、アリソン・ジェイ氏がイラストを手がけた絵本『くるみわりにんぎょう』に出会ったことがきっかけとのこと。
宮崎監督がこの作品に触れたのは、ちょうど『風立ちぬ』の製作の真っ最中で、ヘトヘトに疲れていたときのこと。何度も何度も、毎晩この絵本を見ているうちに、作品が好きになった宮崎監督は、3人の女の子にこの絵本をプレゼントしたという。
絵本の評判は上々で、それに気をよくした宮崎監督は、さらにネットでドイツ製のくるみ割りを購入して女の子にプレゼント。えこひいきにならないようにするために8体も購入し、「おかげでおこづかいがなくなった」とこぼしていたそうだ。
とはいえ、そこで宮崎監督はおもしろいことがわかったようだ。男の子は、人形の口をがちゃんがちゃんと開けたりしてロボットのように遊ぶのだが、女の子は人形をぎゅっと抱きしめてくれたそうだ。
女の子はたいそうくるみ割り人形を気に入ってくれたそうだが、宮崎監督は「なぜ、女の子はこんなにくるみ割り人形が好きなんだろう」と不思議に思い、E・T・Aホフマンによる原作本『クルミわり人形とネズミの王さま』を読むことにしたのだという。
一読して宮崎監督は困惑したらしい。それは、話が理解できないからだった。「この人形は人間なのか? それとも人形なのか。つじつまがあっていないぞ」と混乱したという。しかし、周りで本を読んだ女性たちは「え? そうでした?」という感じでとくに気にしていなかったそうだ。そこで、「なぜなんだ、なぜこのつじつまがあわない世界を理解できるのだ」と宮崎監督は疑問に思い、さらに作品にのめり込んだらしい。
現在、おもに流通している『クルミわり人形とネズミの王さま』は、19世紀後半にフランスで刊行された改訂版であり、物語のつじつまが合うように整理されているものだそうだ。その後にはバレエ版も作られていたが、E.T.A.ホフマンによる原作本はあまり読まれてはいなかったようだ。
そのような経緯もあり、宮崎監督はいま一度、「ホフマンの世界を読み解こう」、「みんなにも読んでもらおう」と考えたのだという。そもそもなぜ主人公はくるみ割り人形なのか、当時のくるみ割り人形はどんなものだったのか……、と疑問に思って調べたのが、今回の企画展示の出発点となったそうだ。
宮崎監督は、自身の作品には“ここからは現実であり、ここからは異世界である”などという明確な“ルール”を決めているらしい。しかし、E・T・Aホフマンが書いた原作はつじつまが合わず、そのようなルールが見えなかったという。
とはいえ、宮崎監督はE.T.Aホフマンによる原作の特徴を肯定する。なぜなら、子どもとっては、現実も幻想も空想もいっしょくたで、ひとつの物語になっているからだ。それこそメルヘンと呼べるものであり、この本は“メルヘンのたからもの”なのだとー。そこで、「このメルヘンのたからものを、みんなにも読んでもらいたい、みんなにも知ってもらいたい」という想いを持ったという。その想いが、最終的にこの展示へつながったのだそうだ。
(ファミ通.com「宮崎駿監督“引退後”の初仕事 三鷹の森ジブリ美術館“クルミわり人形とネズミの王さま展”をリポート」)
こんなに長く書いてきてすみませんが、ホフマンと宮崎監督について、最後にもう一つだけ書かせてください。
彼(ホフマン)は俗物を徹底的に嫌った。それは彼自身が俗物であったからである。・・・ホフマンが芸術家たるためには、いな芸術家であればあるだけ、市民的練達と事務的な仕事とを愛し、それを必要としたといわねばならない。・・・ホフマンに於ける俗物の世界は日常の世界である。この日常の世界に安住せんとするホフマンを他のホフマンが否定しようとする。それは魔法の世界、即ち不思議の国に住むホフマンである。この二つの世界はホフマンに於ては並立するのではなくして、二つは互に前後上下の関係にある。日常の世界の背後或は底に不思議の世界が隠されて居り、日常凡俗の現実の上により高い現実世界が予感される。ここにホフマンが浪漫派の人であると同時に浪漫派を超えて現実主義の世界に踏み入ろうとしている詩人である根拠がひそんでいる。浪漫派の人々にとって「青い花」は永遠に花として咲き、いたるところに咲いていると共にどこにも咲いていない花であるが、ホフマンにとってはそれは「青い花」として永遠の彼岸に咲き匂う花であると同時に日常の現実に於て咲きまた実を結ぶ花でもある。それはホフマンに於ては日常の世界はそのまま芸術の世界に変えられるからである。そしてここにホフマンの「現実」の秘密がひそんでいる。
(渡辺竜雄「エ・ア・テ・ホフマンと「現実」の問題」)
これを読んで、なんとなく宮崎監督が『風の帰る場所』で宮沢賢治について仰っていたことを思い出しました。宮沢賢治がホフマンと同じというわけではなく、なんとなく思い出したので、覚書として書いておきます。ちなみにインタビュアーはロッキング・オンの渋谷陽一さん。渋谷さんは表現者・宮崎駿を「本当に大好きで、もう死ぬほど好き」なのだそう。
「人を殺した人間だから、殺すことの痛みがわかった人間だから。それで膝を曲げるんじゃなくて、それを背負って歩いてる人間だから、この娘は描くに値するんじゃないかと僕は思ってたんですよ。純潔であるとか、汚れてないことによって、それが価値があるっていうふうな見方というのはね、なんかものすごくくだらないんじゃないかっていう気がするんですね。その泥まみれで汚れてて、それで傷だらけだから。だから、宮沢賢治を僕は好きなんですよ」
――うん。
「宮沢賢治が聖人でね、彼が言ってるとおりの人生を歩んだとは、僕は思えないですよ。やっぱりオナニーもしたんじゃないかと思うんですよね。だからっていって、僕は宮沢賢治をますます好きになるだけでね。そういう葛藤はあるはずですよ、当然です!」
――そうです、うんうん。
「で、非常に愚劣なね、もう少しいい男に生まれたらよかったのにとかね、そういうことを全然思わなかったはずないですよ!」
――ははははは。
「そういう無数の複合体だから、人間って。ただ、生き物っていうのは動態だからね。動いてる。静的な存在じゃないから。だから、同じ人物でもね、ものすごく愚劣な瞬間があったり、それからなんかやたらに高揚してね、あるいは実に思いやりに満ちたり、そういうふうに揺れ動いてるものなんですよ」
※このページ↓の『ブランビラ王女』の解釈、とてもわかりやすいし共感できる。
創作された夢 E.T.A.Hoffmannの『ブランビラ王女』の解読(木野光司)
同じ方の書かれたこの本も、読んでみたいです。
『ロマン主義の自我・幻想・都市像―E.T.A.ホフマンの文学世界』
少なくともわたしの世代ではすべての横浜市民が横浜市歌を歌えた。と思うくらい、みんな横浜市歌好きだった。今はどうなのか知らないけど。いーまはももふねもーもちっふっねーー
— 谷山浩子 (@taniyama_) April 15, 2021
先ほど何気なく谷山浩子さんのtwitterを遡って読んでいたところ、驚きの事実が。
横浜市歌って、森鴎外作詞だったのか

1909年(明治42年)7月1日に行われた、横浜港の開港50周年記念祝祭にて披露されて以来、市民に歌い継がれています。作詞は森林太郎(森鴎外)、作曲は、当時東京音楽学校(現、東京藝術大学)助教授だった南能衛(よしえ)氏です。
(横浜市HP)
ワタクシ小学校を卒業してから三十ン年たちますが、浩子さんと同じく、いまだにこの歌をソラで歌えます。
浩子さんは「すべての横浜市民が歌えた」と書いておられますが、おそらく正確には「すべての横浜市立小学校の子供達が歌えた」かと。
小学校では6月2日の開港記念日や色々な学校行事の際に、6年間数え切れないほど歌いました。中学校ではどうだったかなぁ。市立中学だったけれどあまり記憶にない
大人になってから両親がこの歌の存在さえ知らないことを知り、衝撃を受けました。しかし両親は横浜市出身ではないので、考えてみたら当然なのであった。たとえ市民でも大人は普段の生活で市歌なんぞ歌わないし、聴く機会も殆どない。もっとも子供の頃の私は家でよくこの歌を歌っていたのだが(浩子さんと同じく、私もこの歌がなぜか好きだったので)、娘が歌っているこの暗号のような歌詞の歌を親は何だと思っていたのだろう。
そういう歌なので、「ハマっ子か否かの分かれ目は、横浜市歌を歌えるか否か」と言われているとかいないとか。
子供の頃の私が特に好きだったのは、浩子さんが書かれている「昔はド田舎だったけどね(2行)」の部分です
むかし思えば とま屋の煙 (むかしおもえばとまやのけむり)
ちらりほらりと立てりしところ (ちらりほらりとたてりしところ)
土と緑と海しかない鄙びた漁村 にポツンポツンと藁ぶき屋根の家があって、そこから煙が出ている昔の横浜村の長閑な風景が目に浮かぶようで、好きだったなあ
にポツンポツンと藁ぶき屋根の家があって、そこから煙が出ている昔の横浜村の長閑な風景が目に浮かぶようで、好きだったなあ
そして浩子さんと同じく、褒めているのが港だけなところが妙な歌詞だな、と子供心に思っていた。これじゃあ横浜市歌というより横浜港歌やんけ、と。
鴎外って実は横浜に全く興味がなかったんじゃ と疑いwikiを読んでみると、なんと横浜市歌のみならず横浜商業高等学校(Y校)の校歌まで作詞しているではないですか。
と疑いwikiを読んでみると、なんと横浜市歌のみならず横浜商業高等学校(Y校)の校歌まで作詞しているではないですか。
鴎外にとって横浜はどんな街だったのだろう。
ググってみたら、こんな素敵なページを見つけました。
『森鴎外と舞姫事件研究』森鴎外と一八八八年秋の横浜
鴎外にとって横浜は特別な思い出のある街なのだ、と。鴎外は1884年にドイツへ留学した際に横浜から旅立ち、1888年に横浜に帰国。その4日後にドイツから彼を追って来た恋人のドイツ人女性が横浜に着きました。このドイツ人女性が誰かについては諸説あるそうですが、エリーゼ・ヴィーゲルトというのが定説だそうです。ひと月後、鴎外とその弟達はエリーゼとの最後の夜を横浜で共に過ごし、翌日彼女の船はドイツへと出港したそうです。1年後、鴎外は彼女をモデルとした処女作かつ代表作『舞姫』を発表。
鴎外にとって「横浜=横浜港」であった理由がなんとなくわかったような気がして、まぁ許してやるか、と思った100年後のハマっ子の私でありました。
などとエラそうに書いておりますが。
実は改めて横浜市歌の歌詞を眺めていたところ、鴎外作詞と同じくらいの衝撃の事実が発覚。子供の頃に覚えた歌アルアルですが。
あ~さっひただよぅう~み~に~ ⇒ 「朝日かがよう海に」だった。朝日は海に漂ってはいなかった。。
と~まるところぞみ~よ~や~ ⇒ みよやって全く意味がわからず歌っていた。「見よや」だった。
む~かし~思えば~ とま~やの~けむ~ぅり~ ⇒ とまやって「泊屋」(宿屋)かと思っていた(そんな日本語は存在しない)。「苫屋」(苫葺きの粗末な小屋)だった。藁葺きの家のイメージは間違っていなかったけれど。
小学校の先生は歌詞の意味をちゃんと教えてくれていたはずだが、子供ってこんなもん。
浩子さんのおかげで誤解したままで人生を終わらずに済みました。
まあ意味をわからず歌っていても、のんびり大らかで明るくて、今も昔も好きな歌です


この先もずっと、横浜の子供達に歌い継がれていきますように。
そういえば友人が「顔は漱石の方がモテそうなのに、留学生活を満喫して現地の女性にモテたのは鴎外なのが面白いよね」と言っていたなぁ。職場の食堂でその話をした席も覚えている。うーん、最近どうも鬱っぽくていけないな(主な理由はわかっている。仕事が忙しすぎるから)。。久しぶりにお墓参りに行って来ようかな。。

昨夜から新しいNHK大河が始まり渋沢栄一がトレンドのようなので、以前ご紹介した1868年(明治元年)パリでの渋沢の言葉を再掲
-----------------------------
一体あんた方は今の御国元の事を何と思って居られるか。
御国の大変で留学の送金が絶え、喜望峰廻りで帰され様とするのを、ともかくそうしたみじめな目にあはないやうにと計ってあげた。
これを、ただにあなた方の苦しさをすくほうと云ふ猫っかはいがりから出た事だとうぬぼれて居なさるなら、大きな間違ひで、日本から留学生を派遣しておきながら、国内の騒動に夢中になって帰国の始末もつかず、荷物扱ひで送り帰されたとあっては、日本の名誉にかかはると思へばこそ、当方でも今後御国元からどの程度に送金のあるものやら、無いものやら知れず。・・・・・・
そこらの意味も苦衷も御察し出来ないか。
失礼ながら学問と云ふものはそんなもので無い筈だ。ただ知識を多く集得なさっただけで得々として居られるか。そんな思慮の足りぬ性根の腐った人を作ろうと、日本は苦しい中から留学生を派遣しなかった筈だ。私は日本の為になげきます。
ここで厭ならすぐさま出て行ってもらいましょう。御国の大乱のこのさい、よしんばどんなやはらかい床へ寝られたにもせい、心には臥薪嘗胆の〆めくくりがあってしかるべきだに、まして何のベッドの上で産まれやしまいし、わづかの歳月ヨーロッパの風にふかれたと思うと、フロアの上もないものだ。
(宮永 孝『慶応二年幕府イギリス留学生』)
徳川幕府が崩壊し、日本に帰ることになった幕府派遣の欧州留学生一行(イギリス、オランダ、フランス)。
しかし帰国費用さえままならない。
世話人ロイドはイギリス留学生達を賃金先払いで喜望峰廻りの貨物船に載せ、横浜で金と引き換えに引き渡す計画を立てた。
当時徳川昭武(慶喜の弟)の付き添いでパリにいた渋沢栄一は、そのことを知り、昭武の留学費用からどうにか金を都合し、彼らをマルセイユから船に乗せるよう取り計らう。
こうして欧州留学生達はパリに集合し、昭武の借家の広間が彼らの宿となった。
しかし英国組の林董らは、「人をフロアに寝かして豚扱いしている」とブツブツ文句を言う始末。
渋沢はそれを聞き、彼らのところへ刀を下げて怒鳴り込んで行き、叱り飛ばした。
上記はそのときの言葉。
林らは道理が道理だから一言もなく謝り、後々もこのときのことを思い出しては「激しい小言だった」と笑ったそうである。
ちなみにこのときの渋沢の年齢は、28歳。
立派なものです。。。
※N響のtwitterで知りましたが、指揮者の尾高忠明さんって渋沢栄一のひ孫だったんですね !今回のテーマ音楽も指揮されています。
!今回のテーマ音楽も指揮されています。

ビオトープというのは、地道に自然を造っていくものなので時間がかかります。とても興味はあるものの、これから何年生きていられるか分からないのに、今から造っても無駄かなとも思ったのです。そんなある日、そのことを話した友人が「やるべきよ、やらないよりずっといいいじゃない」と強く後押ししてくれました。・・・
今現在も作っている最中ですから、生きている間に私が思い描くような光景を眺めることはできないかもしれません。でも、ビオトープを作るという新しい挑戦は、これまでに十分過ぎるといっていいほどの感動をもたらしてくれました。めだかや蛙、虫たちが集まってくるのを眺めていると、童心に返ったようなわくわくとする気持ちを味わうことができて、今ではあのときの決心は間違っていなかったのだと実感しています。
考えてみれば、どんな年齢の方も、先のことは分かりません。何かを始めても、もしかしたら志半ばで、終えてしまうこともあるでしょう。でも、だからといって臆してしまい、そこで諦めてしまえば、人の可能性はそこで止まってしまいます。
たとえ最後までできなくても、その過程で得られる喜びを噛み締めながら、新しいことへの挑戦を楽しみたいと思います。
(八千草薫『あなただけの、咲き方で』)
2019年に亡くなられた八千草薫さんの『あなただけの、咲き方で』(幻冬舎。2015年1月)を読みました。
書店で平積みになっていたのを立ち読みしたら素敵な文章だったので図書館で予約したところ、なんと数か月待ち
先日、ようやく読むことができました。
シャイな八千草さんが女優を続けてこられたことのお話、自然や旅行が大好きで19歳上のご主人と登られた冬山の静けさのお話、木の温もりを感じさせる家具を大切に使われているお話、クラシック音楽がお好きだというお話、お庭に造られたビオトープのお話、自然に囲まれた暮らしがしたくて富良野の倉本聰さんのお宅の隣の土地を買われたり(結果的にはその土地は倉本さんに譲り、八ヶ岳に別荘を買われたそうです)。
ドラマなどで拝見する八千草さんの雰囲気そのままの飾らなく、上品で、凛とした文章たち。こういう女性になりたいな、こんな風に年齢を重ねられたら素敵だな、こんな風に人生を生きられたらいいな、と感じる本でした。
私の好きなテレビドラマ『愛し君へ』(2004年)で、八千草さんは視力を失っていく病に冒されたカメラマン(藤木直人さん)の母親役を演じられていました。以下は、最終回のドラマの中での言葉。原作はさだまさしさんの『解夏』です。
あの二人の結婚式を見ながら考えていたことがあります。それは、もしも俊介が病気になっていなかったらどうしていただろうということです。俊介は写真の仕事を続け、四季さんは病院で働き、別の人生を別の幸せを手にしていたのでしょうか。ところが、病気という経験を通して、二人は同じ道を共に歩むことになりました。私は夫を亡くし、次男を亡くし、自分の人生を恨んだこともありました。でも、二人の結婚式を見ながら思ったのです。どんな人生にも行き止まりはなく、道は続いていくのだと。前に進めば必ずそこには道がひらけているのだと。
それは今、四季さんと俊介の笑顔が証明しているのではないでしょうか。私は幸せな人生を送ってきたのだと、今、心から思います。
(『愛し君へ』 第11話)

1月12日に半藤一利さんがお亡くなりになったそうです。年末に『こころ』についての記事でそのお名前を書いたばかりでしたが、宮崎駿監督との少年のような大人な対談が大好きだったなあ。ああいうタイプの方達はこれからの日本には少なくなっていってしまうのではないか、と感じています。ご冥福を心よりお祈りいたします。
さて、先日、姜尚中さんの『NHK「100分de名著」ブックス 夏目漱石 こころ』という本を読んだのです。
姜さんが漱石について語られているのはテレビでは幾度か拝見したことがありましたが、本として読むのは今回が初めて。
拝読して、やっぱり姜さんの漱石像は私のイメージととても近いなと感じました。
不愉快に充ちた人生をとぼとぼ辿りつつある私は、自分の何時(いつ)か一度到達しなければならない死といふ境地に就いて常に考へている。
(『硝子戸の中』)
『硝子戸の中』の頃には身体的にも”死”について考えざるを得なくなっているけれど、漱石は若い頃から厭世的に”死”について思いを巡らす人だった。それは決して軽い気持ちからのものではない。
でもそうでありながら、漱石は生来的に”生”の価値を知っていた、”生”を愛していた人だと私は思う。
『こころ』の先生は、常に”死”を思いながらも”生”に惹かれ、思い切りがつかず、今日まで生きてきてしまった人。そして最終的に自死を選択した先生を、漱石が100%肯定的に描いているとは私には思えない。『こころ』という小説の芯の部分は”先生の死”にあるのではなく、先生の心を受け継いで未来を生きていく”私”が存在しているところにあるのだと私は思うのです。これは、姜さんも本書の中で同じように書かれていました。
ではなぜ漱石は先生を死なせたのか。未来へと向かう話にするのなら、先生を生かすストーリーにもできたはず。
私は、漱石の中では先生という人は死ぬ以外のストーリーはあり得なかったのではないか、とそんな風に思うんです。そもそも新聞連載が始まったときの題名からして『先生の遺書』ですし、最初から死ぬことが前提となっている。なぜなら、当時の漱石自身の中に先生を死なせる必要があったのではないか、と。漱石は『こころ』を書いたことで、その中で先生を殺してバトンを”私”へと繋げだことで、自分の中の何かに区切りをつけ、前へと進もうとしていたのではないか、と。”私”という存在には先生だけでなく漱石自身の希望も託されているのではないか、とそんな風に思うんです。不愉快に充ちた人生の中で身体的にも”死”に近づいていながら、それでも”生”に惹かれ、自身やこの国の人々の未来を見つめている漱石自身の姿が、この小説の構成にも表れているのではないでしょうか。
姜さんは『こころ』をデス・ノベルであると仰っていて、登場人物がことごとく死ぬ、死に満ちた作品であると。私はそういう見方でこの小説を読んだことはなかったのだけれど、言われてみれば確かにそのとおりなんですよね。もともと登場人物の多い作品ではないけれど、それでも生き残るのはお嬢さんと私だけ。こんなに登場人物が死んでいく作品は他の漱石作品の中にはない。
漱石は、あるとき小学生の少年から(おそらく「『こころ』の先生はどうなったのですか」という内容の)手紙をもらって、こんな風に返事をしています。
あの「心」とい小説のなかにある”先生”といふ人はもう死んでしまひました、名前はありますがあなたが覚えても役に立たない人です、あなたは小学の六年でよくあんなものをよみますね、あれは子供がよんでためになるものぢゃありませんからおよしなさい、あなたは私の住所をだれに聞きましたか、
(松尾寛一宛て書簡、大正3年4月24日)
ここで漱石が言いたかったこと、わかる気がするんです。『こころ』は子供が読んで悪影響があるとまでは言わないけれど、人生経験の少ない子供の頃に読んで理解できる内容では全くない(つまり、ためになる内容では全くない)本だと思う。漱石は「あなたは子供なのだから、今こんな本を読んでいちゃだめですよ。読む必要のある本ではありませんよ」と言いたかったのでしょう。子供に対して「”先生”は死んでしまいました」と書くのさえ、漱石は辛かったろうと思う。でも子供相手だからと誤魔化したりしないのが、漱石のいいところですよね。
こういう漱石の”生”に対するどこか本質的な肯定感は、おそらく漱石の生まれながらの人間的性質なのだろうと私は思っています。太宰がどんなに望んでも持つことができなかったもの。私は”死”に惹かれながらも積極的な自死の実行というものは一度も考えたことがないことを以前ここに書きましたが、おそらく漱石も同じような人だったのではないか、と私は思っているのです。
で、前置きが長くなってしまったけれど(そう、ここまでの文章は前置きだったのですよ)、本書に書かれてある『こころ』についての姜さんの解釈は私の解釈と完全に同じではないものの殆どの部分で同じだったのですが、そんな中で特に「ほぉ 」と新鮮に感じた部分を自分用覚書として書いておきたいと思います。
」と新鮮に感じた部分を自分用覚書として書いておきたいと思います。
それは「血まみれの二人」という部分。
姜さんは、Kと先生の親密さには友情という言葉では表現しきれないものが含まれているけれど、それを単純に”同性愛”と呼んでしまうのは違うように思うと書かれています。そして『こころ』をポーの『ウィリアム・ウィルスン』(私は未読)というドッペルゲンガーを描いた小説と重ね、Kと先生の関係は一心同体のようなものなのではないか、と仰っています。
この物語になぞらえると、Kは一人の人格の「善の側面(グッドサイド)」を体現し、先生は「悪の側面(ダークサイド)」を体現しているという構図になります。
そして二人が一心同体の存在であることは彼らが暮らしている居住空間にも象徴されているのではないか、と。彼らの部屋は襖一枚でしか隔てられておらず、その襖を開けば一つの部屋になります。姜さんは書きます。
意味深長なことに、Kが自殺した夜、襖は少し開いていました。Kがわざわざそうして命を絶ったのです。これは何を意味するのでしょうか。二人がウィリアム・ウィルスン的な一心同体であったとするならば、「おまえが見つけてくれ」「おまえが看取ってくれ」「おまえに俺のすべてを託す」という気持ちの表れだったのではないか、とわたしは考えます。だから遺書も「先生」宛てだったのです。みなさま宛でもなく、お嬢さん宛でもなく、「先生」宛てだったのです。・・・恨むも恨まないもありません。許すも許さないもありません。そもそも二人はそのような次元のつながりではないのです。
そして、こうも書きます。
それは、「もともと先生とKという極めて親密なペアがあった。そこに突然、お嬢さんという闖入者が現れたために、二人の蜜月関係がかき乱された」という読み方です。・・・
「先生」とKの間にはしばしば「血潮」だとか「心臓」とかいった表現が使われます。・・・この生温かい血の感じは、Kの死後は「私」との関係に引き継がれます。
また、「先生」はKの自殺の現場においても、恐ろしいと言いながらわりに恐れげなく踏み込んで、Kの頭を両手で抱えあげて顔を覗いてみたりしています。このようなことは、普通はやらないのではないでしょうか。頸動脈をかき切っての失血死ですから、現場は血の海だったはずです。布団がかなり吸収してくれたとありますが、Kは血まみれだったと思われ、その身体を抱えたりすれば「先生」も血まみれになったと思います。
そこで、はたと気づくのです。その「赤く生々しいつながり」は、「純白のまま汚さずにおきたい」というお嬢さんとのよそよそしいつながりと、鮮やかな対比をなしていることに――。
そのように読んでいくと、お嬢さんがふと漏らす嘆息も、ことさらなものに見えてしまいます。
妻はある時、男の心と女の心とは何(ど)うしてもぴたりと一つになれないものだらうかと云ひました。
ことほどさように、『こころ』の三角関係は単純ではないのです。にっちもさっちもいかない不毛なトライアングルなのです。
姜さんご自身が「少々踏み込みすぎたようです」と書かれていますし、小説を読み返すと微妙な部分もあるのだけれど、それでもこの3人の関係を思うときに、強い説得力のある解釈だと感じました。
他に本書で興味深かったのは、Kと藤村操青年を重ねている部分、漱石の「高等遊民」感の考察、そして年齢表
私、先生が死んだときの年齢っていくつだったんだろうとずっと気になっていたんですよね。なので、この年齢表は本当に参考になりました。小説の文章から想定される先生の凡その年齢は、次のような感じとのこと。
明治8年、新潟生まれ。明治26年(18歳)、両親が病死。明治29年(19歳)、東京の高等学校に進学。明治28年(20歳)夏、帰省時に叔父に結婚を勧められる。明治29年(21歳)夏、従妹との結婚を強要され、断る。明治30年(22歳)、叔父が遺産を横領していたのを知り、残った遺産を換金して故郷を捨てて上京。東京帝国大学に入学し、下宿に移る。この夏、Kは実家から勘当。明治31年(23歳)、この年の暮れか翌年の初めにKを下宿に引き取る。明治32年(24歳)、夏にKと房州旅行に出る。明治33年(25歳)、2月中旬にKが自殺。6月に大学を卒業。暮れにお嬢さんと結婚。二、三年後に”奥さん”死去。その後、高等遊民生活を送る。明治41年(33歳)、高等学校生の”私”(19歳)と鎌倉で知り合う。明治42年(34歳)、”私”(20歳)が東京帝国大学に入学。明治45年(37歳)夏、自決を決意する。このとき”私”は23歳。
先生、自死したときは37歳位だったのか。
若いのだろうとは思っていたけれど、やはり若いですね。
この本、とてもいい本なので、漱石がお好きな方にはオススメです。
今夜は関東平野部でも雪という予報だけど、降るのかなあ


大雪の地方の方にはふざけるなと言われてしまうかもしれないけれど、一年に一度くらい、ちゃんとした雪を見たいなあ。今年はまだ一度も見られていないもの。
それでは皆さま、どうか温かくしてお過ごしくださいね

※追記
本書について、もう一点。
姜さんが『こころ』とトーマス・マンの『魔の山』に共通点を見出していることが興味深かったです。なぜならピアニストのグレン・グールドが『草枕』と『魔の山』を愛読書とし、その二作に共通点を見出していたからです。以前にご紹介した『草枕』のラジオ朗読に先立って、グールドはこんな風に解説しています。
「『草枕』が書かれたのは日露戦争のころですが、そのことは最後の場面で少し出てくるだけです。むしろ、戦争否定の気分が第一次大戦をモチーフとしたトーマス・マンの『魔の山』を思い出させ、両者は相通じるものがあります。『草枕』は様々な要素を含んでいますが、とくに思索と行動、無関心と義理、西洋と東洋の価値観の対立、モダニズムのはらむ危険を扱っています。これは20世紀の小説の最高傑作のひとつだと、私は思います」
マンの『魔の山』、未読なんですよね・・・。読まねば。
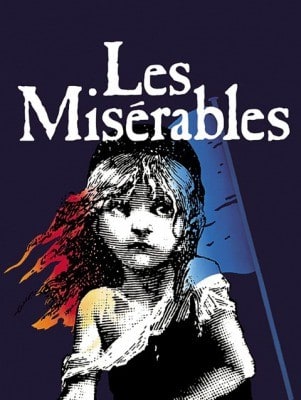

皆さま、あけましておめでとうございます


年末年始はいかがお過ごしでしたか?
私は元旦の朝に近所のデパートに福袋を買いに出た以外は、おせちを食べだり、日本酒を飲んだり(獺祭と司牡丹 獺祭の大吟醸おいしいねえ!)、休みに入る前に図書館で借りた『レ・ミゼラブル』を読んだりしながら、ひたすら食っちゃ寝な正月でございました
獺祭の大吟醸おいしいねえ!)、休みに入る前に図書館で借りた『レ・ミゼラブル』を読んだりしながら、ひたすら食っちゃ寝な正月でございました
なぜレミゼかというと、先日ご紹介したヒュー・ジャックマンのインタビューを読んで、原作を読み返したくなったからです。以前に抄訳は読んだことがあるけれど、全訳は初めて。
いやあ、全訳版は忍耐が必要ですね~ 。ストーリー部分はスリリングでサクサク読めちゃうけれど、合間合間に挿入されている作者自身のマニアックな蘊蓄は、フランスの地理や歴史の知識がない私にはなかなかキツい
。ストーリー部分はスリリングでサクサク読めちゃうけれど、合間合間に挿入されている作者自身のマニアックな蘊蓄は、フランスの地理や歴史の知識がない私にはなかなかキツい 。しかしその部分を読み飛ばしてしまうとレミゼという作品を真に理解できないように感じられて(実際そうだと思う)、めげずに読む。ということが文庫本の1~5巻まで繰り返されるのであった。
。しかしその部分を読み飛ばしてしまうとレミゼという作品を真に理解できないように感じられて(実際そうだと思う)、めげずに読む。ということが文庫本の1~5巻まで繰り返されるのであった。
そして知ったのですが、ミュージカルの最後で歌われる"To love another person is to see the face of God.(誰かを愛することは、神の顔を見ること)"の言葉は、原作には登場しないんですね。あえてあげるなら、ユゴーの死後に出版された『La fin de Satan(サタンの終わり)』という未完の詩集の中の"l'essence de Dieu, c'est d'aimer.(神の本質は、愛すること)"という言葉が最も近いもののようです。でもレミゼの作品全体で言いたかったことはまさにそのことだと思うので、英語版作詞者のKretzmerさんはちゃんとそれをわかっておられたのだな。
以下、感想です。小説についてというより、小説を通して語られているユゴーの思想についてを中心に。自分用覚書と頭の整理のために書いているので、長いです。
『レ・ミゼラブル』は1864年から1962年の98年間カトリック教会の禁書リストに入っていたそうで、ユゴーが教会に批判的な文章を書いていることが理由のようです。もっとも彼はキリスト教という宗教自体を批判しているわけではないんですよね。ただ、ユゴーが理想とする宗教と、教会が説くキリスト教の姿は違った。ユゴーが考える神と、教会が考える神の姿は違った。彼の心の中には彼自身の神、彼自身の宗教というべきものがあった。そういう思想は、教会の出世街道から外れた道を歩んだミリエル司教の人物造型にも表れているように思います。
ここで書いておかなければならないと思うことは、司教がいわば信仰の外部に、信仰の彼方に、過度の愛を持っていたということである。・・・この過度の愛とは、なんであったか?それは前に示したように、人間からあふれ出て、ときには事物にまでひろがっていく、澄みきった好意である。・・・
この人を光り輝かせていたのは、心情であった。彼の知恵は、心情から出てくる光でつくられていた。体系は全くなくて、行為が多かった。・・・このつつましい魂は、ただ愛した。それだけなのである。・・・彼は嘆いている者や、罪を償う者の上に、身をかがめた。彼には世界が大きな病気のように思われた。いたるところに熱を感じ、いたるところに痛みを聴診し、謎を解こうとはせずに、傷に包帯をしようとした。・・・存在するものは、このまれにみる善良な司祭にとっては、慰めを求めている、永久に悲しいものなのであった。
金の発掘に働いている人びとがいる。彼の方は、憐みの発掘のために働いていた。一般的な悲惨が、彼の鉱山であった。いたるところにある悲惨は、いつも親切の機会にすぎなかった。「互いに愛し合うべし」彼はこれを完全なことだと述べ、これ以上のことは何も願わなかった。そしてこれが彼の教理のすべてであった。・・・ビヤンヴニュ閣下は、神秘な問題を、検討したり、いじくり回したりして、自分の精神を混乱させたりせずに、それを外からみとめて、魂の中にその暗黒にたいする真面目な尊敬の念をいだいていた、単なる一人の人間であった。
(第1部第1章13、14)
また第1部で元革命議会議員のGがミリエルに言う、”神”の姿。
Gは革命派の多くの同類と同じく、無神論者と呼ばれる種類の人でした。
ミリエルは、死にかけているGに「進歩は神を信じるべきです。善は不信のしもべを持つことはありえない。無神論者は、人類の悪い指導者です」と言います(ミリエルって大人しい性格の人じゃないよね )。
)。
Gは何も答えず、それから涙をいっぱいにためて空をながめ、独り言のようにこう言いました。
「おお、お前!理想よ!お前だけが存在する!」
司教はなんとも言えない一種の衝動を覚えた。
ちょっと沈黙してから、老人は空の方に一本の指をあげて、言った。
「無限は存在する。あそこにある。無限が自我を持たないとすれば、自我が無限の限界になるだろう。無限は無限でなくなる。言いかえれば、無限は存在しないだろう。ところが無限は存在する。だから無限は自我を持っている。無限の持つ自我、これが神だ」
(第1部第1章10)
これは、第2部第7章で語られる作者自身の思想と重なります。
われわれの外部に無限なものがあると同時に、われわれの内部にも無限なものがあるのではないか?この二つの無限なものは、互いに重なり合っているのではないか?・・・下にある無限の中に自我があるように、上にある無限の中にも自我があるはずである。下にある自我、それが魂であり、上にある自我、それが神である。思惟によって、下の無限を上の無限に接触させること、それが祈りと呼ばれる。
人間の精神からは何ものも取上げまい。取上げることは悪いことである。改革し、変形させねばならい。人間のある種の能力、思惟や夢想や祈りなどは、未知なものに向けられる。未知なものとは一つの大洋である。良心とは何か?未知なものへの羅針盤である。思惟、夢想、祈り、それこそ偉大な神秘的な輝きである。それを尊重しよう。この魂の荘厳な光は、どこへ進んで行くのか?闇へ向って、つまり、光明に向って進むことである。
デモクラシーの偉大さは、何も否定しないことであり、人間性を何一つ否認しないことである。人間の権利のそばに、少なくともそのわきに、魂の権利がある。
狂信を打破し、無限を崇拝すること、それが法則である。・・・
無限なものの意志、すなわち神を否定することは、無限を否定しないかぎり不可能である。虚無は存在しない。ゼロも存在しない。すべては何ものかである。・・・すなわち、信仰と愛という二つの原動力なしには、人間を出発点と考えることもできず、進歩を目的と考えることもできないと。進歩は目的である。理想は典型である。理想とは何か?神である。理想、絶対、完全、無限、どれも同じ言葉である。
外部(上)の世界に存する自我が神であり、内部(下)の世界に存する自我が魂である、と。人間=出発点であり進歩=到達点であると理解するためには、信仰と愛という2つの原動力が必須である、と。
ただ、「進歩は目的である。理想は典型である。」という部分の意味が、どうもよくわからない・・・。そこで原文の仏語版と英訳版の同じ箇所を読んでみました。
Le progrès est le but, l'idéal est le type.(Progress is the goal, the ideal is the type.)
Qu'est-ce que l'idéal? C'est Dieu.(What is the ideal? It's God.)
Idéal, absolu, perfection, infini; mots identiques.(Ideal, absolute, perfection, infinite; identical words.)
「進歩はゴール(目標)である。理想は化身である。理想とは何か?神である。」
うん、この方がわかりやすい 。といって全巻を英語で読む気力も語学力もないですが。
。といって全巻を英語で読む気力も語学力もないですが。
ミリエル司教が王党派という設定も面白いですよね。この場面の司教、人間くさくて好き
フランス革命について「あなたがたは破壊した。怒りを含んだ破壊は信用できません」と言うミリエル司教に、Gは言います。
「さあ!神父さん、あなたは真実のなまなましさがお好きではない。キリストはそれが好きでしたよ。彼は鞭を取って、神殿を清めた。その光にみちた鞭は、真理をきびしく、告げ知らせた。彼が〈幼な子らをわれらのところに〉と叫んだとき、子供たちに区別をつけなかった。バラバの子とヘロデ王の子を、平気で近づけた。罪のないこと自身が、王冠なのです。罪のないことには、身分の高さなどどうでもいいのです。それは、ぼろをまとっていても、王家の百合花をまとっていても、同じように荘厳なのです」
「そのとおりです」司教は低い声で言った。
「重ねて言いたいのは」と革命議会議員はつづけた。「あなたはルイ十七世の名をあげた。いいですね、われわれは罪のない人たち、殉教者たち、子供たち、上の者も下の者も、みんなに同情するのだね?賛成じゃ。だが、それなら、前にも言ったが、93年以前にさかのぼるべきだ。われわれが同情をはじめるべきなのは、ルイ十七世以前だ。わしはあなたと一緒に王子たちに同情する、あなたがわしと一緒に民衆の子に同情してくださるならば」
「わたしはすべての人に同情します」と司教は言った。
「平等にですよ!」とGは叫んだ。「もし秤がどちらかに傾くべきなら、民衆の方であって欲しい。民衆はずっと長いこと苦しんでいる。・・・大革命は、全体的に言って、偉大な人間的肯定だが、それは別として、93年は、残念ながら一つの返答なのだ。あなたはそれを苛酷だと思っているが、それでは君主制全体はどうなのか?・・・わしは大公妃で、王妃だったマリー・アントワネットに同情する。だが、新教徒の哀れな女にも同情する。この女は1685年、ルイ大王の治世に、子供に乳をやっている最中に捕らえられた。腰まで裸にされて、柱にしばられ、子供は引離された。乳房は乳にあふれ、心は悲しみでいっぱいだった。子供は空腹で青ざめ、乳房を見て、死にかけながら、泣きわめいた。刑の執行人は、乳飲み子の母である女に、子供の死か、良心の死かを選ばせて、改宗しろ!と言った。母親に適用されたこのタンタロスの刑罰を、あなたはなんと言いますか?よく覚えておいてください、フランス大革命には、正当な理由があったのです。その怒りは将来許されるでしょう。その結果は、よりよい世界です。その最も恐ろしい打撃から、人類にたいする愛情が出てくるのです。・・・いかにも、進歩の激しさは、革命と呼ばれている。それが終ったとき、人類は苛酷な目にあった。だが進歩した、ということがみとめられるのだ」
革命派(共和派)のGの言葉はミリエルを驚嘆させますが、Gが彼に与えたのは政治的影響などではなく、より大きな意味での人間的影響だったのだと思います。彼がGと出会った後に「前より優しくなった」というのは、彼の人間的な一つの”進歩”だったのでしょう。
ここでも、Gの革命や人類の進歩に関する考え方は、ユゴーの思想に重なります。
第4部第10章「1832年6月5日」の中で、ユゴーはこう書いています。
暴動というものと、反乱というものがある。それは二種の怒りである。一方はまちがっており、他方は正しい。・・・権利が行動している物音は、自然にわかるものであり、いつも混乱した群衆の戦慄から生ずるとはかぎらない。狂気じみた怒りがあり、ひびの入った鐘がある。警鐘がすべて青銅の音を出すとはかぎらない。情熱と無知の振動は、進歩の動揺とは異なる。立て、と言うのもすべてまちがっている。暴力的な後退はすべて暴動である。後退は人類にたいする暴力行為である。反乱は真理の発作的な怒りである。反乱が動かす敷石は、権利の火花を散らす。これらの敷石も、暴動の際には泥しか残さない。ルイ十六世に反抗するダントンは反乱であり、ダントンに反抗するエベールは暴動である。だから、ラファイエットが言ったように、反乱はときによって最も神聖な義務となりうるが、暴動は最も悲しむべき暴行となるかもしれないのである。・・・武力によるあらゆる抗議は、最も合法的なものでも、8月10日(1792年)でも、7月14日(1789年)でも、初めは同じように混乱する。権利が解き放たれる前には、喧噪と泡立ちがある。初めは、河も急流であるように、反乱も暴動である。一般に、それは革命という大洋に達する。・・・
だが、これらはすべて過去のことである。未来はまた違う。普通選挙にはすばらしいところがあり、暴動をその原則によって取消し、反乱に投票権を与えることによって、その武器を奪ってしまう。市街戦であろうと、国境戦であろうと、戦争の消滅、それが必然の進歩である。今日がどのようなものであれ、平和、それが「明日」なのである。
なお、反乱と暴動、この両者の微妙な相違点を、いわゆるブルジョワはほとんど知らない。彼らにとっては、すべてが暴動であり、単純な反逆であり、主人にたいする番犬の反抗であり、鎖と犬小屋で罰しなければならぬ傷害の試み、吠え声、鳴き声である。それも、犬の頭が突然大きくなり、暗闇の中でライオンの顔のように、ぼんやりと浮び上がってくる日までのことだ。そのときブルジョワは叫ぶ、「民衆万歳!」と。
以上の説明のあとで、さて歴史にとって、1832年6月の運動とは、なんであろう?暴動か?反乱か?
それは反乱である。
この1832年の運動は、急激に爆発し、悲壮に消滅したが、そこには多くの偉大さがあり、それを暴動としかみとめない人びとでも、尊敬の気持ちなしにはそれについて語れないほどである。
この1832年6月の反乱は失敗に終わりますが、ユゴーは革命時の民衆とブルジョワを比較して、こんな風に書いています。
1793年には、そのころ流れていた思潮の善意によって、それが狂信の日か、感激の日かによって、フォブール・サン・タントワーヌから、野蛮な群衆が出たり、勇壮な部隊が出たりした。
野蛮。・・・あの髪を逆立てた人たち、革命の混沌における創世記的な日々に、ぼろを着て怒鳴り散らし、たけだけしく、棍棒を振上げ、鶴嘴をかざして、うろたえた古いパリに襲いかかった人たちは、何を望んでいたのか?圧制の終末を、暴政の終末を、君主の生殺権の終末を、男には職を、子供には教育を、女には社会の温情を、万人に自由、平等、友愛を、パンを、万人に思想を、世界の楽園化を、進歩を、望んだのであった。そしてこの神聖で優しく甘美なものである進歩を、彼らは、圧迫されて、われを忘れて、恐ろしい形相で、半裸体で、棍棒を握りしめ、唸り声を立てながら、要求したのだ。なるほど野蛮人に違いない。だが、文明の野蛮人だったのである。
彼らは狂ったように権利を宣言した。たとえ戦慄と恐怖によってでも、人類を楽園に追いこもうとした。彼らは野蛮人のように見えても、実は救い主だったのである。闇の仮面をつけて光を要求していたのである。
こうした、たしかに残忍だと言えるが、善のために残忍になった人たちと対照的に、別の、にこやかな、刺繍や黄金やリボンで身を飾り、宝石をちりばめ、絹靴下をはき、白い羽飾りをつけ、黄色い手袋をはめ、エナメル靴をはいて、大理石の暖炉の隅のビロード張りのテーブルに肘をつき、過去の、中世の、神権の、妄信の、無知の、奴隷の、死刑の、戦争の、維持と保持を穏やかに主張し、サーベルと火刑台と断頭台を、小声で上品にたたえる人たちがいる。私に言わせれば、文明の野蛮人と野蛮の文明人のどちらかを選ばせられたなら、私は野蛮人の方をとるだろう。
だが、幸いなことに、もう一つ別の選択が可能である。前進するにしろ、垂直に飛び降りる必要はない。専制主義もテロリズムも必要はない。われわれは傾斜のなだらかな進歩を望む。
神がそれを準備する。傾斜をなだらかにすること、それが神の政治のすべてである。
(第4部第1章5)
多くの血が流されて失敗したこの1832年6月の反乱も、進歩の傾斜をなだらかにさせる神の政治であった、という意味になるのでしょうか。そして私達の世界は今もまだその道程の途中にあるのだ、と。
ユゴーの筆は、共和派を描くときだけでなく、王統派やボナパルト派を描くときにも非常に鮮やかに踊っています。
読んでいると「ん?ユゴーは王党派だったっけ?」とか「帝政を支持してる?」と錯覚してしまうほど。それは、そのどれもを、良い面も悪い面も含め、彼自身が身をもって、心をもって体験してきたからでしょう(執筆時には共和派になっていたユゴーも、この作品の舞台の頃はそうではなかった。また彼はナポレオン一世の熱烈な支持者だった)。だから上記のGの言葉だけでなく、マリユスの思想が王党派→ボナパルト派→共和派へと変化していく過程の描写も、ものすごくリアルで説得力がある。これは歴史小説ではなく、同時代に書かれたものであることを感じさせる。そしてユゴーがそんな風に自身の政治観を目まぐるしく変化させることに柔軟であった理由は、ユゴーがそれを"変化"ではなく人間的な”進歩”と捉えていたからではないかと思う。彼には宗教の宗派や政治の党派を超えた所にまず彼自身が理想とする人間や世界の姿があって、それを実現するための道程を彼自身が歩んでいる、という感覚だったのではないでしょうか。その根底を成しているのは人間の愛であり、それはイコール神である、とそういう考え方だったのではないかと思います。"To love another person is to see the face of God."という軸こそが彼の根底にあったのだろうと。彼は1881年の遺書の中で「私は教会での祈りはすべて拒絶する。すべての人々の魂のために祈ってもらいたい」と書いています。
ところで、圧倒的不利な状況の中で学生達がバリケードに立てこもっているときに、周囲の家々が次々と彼らに対して戸を閉じていく場面。彼らは市民のために命を投げ出して戦っているにもかかわらず、その市民達が彼らに対して戸を閉じる場面。そして彼らを見殺しにする場面を読みながら、そういう面がある世の中というものを思いながら(あるいはそれが世の中であると思いながら)、作者の俯瞰した視点からの描写を読みながら、中島みゆきさんの『世情』を思い出していました。
『世情』の詞って私にとってみゆきさんの歌の中で断トツで難解な詞なのですが(正確なところは今も理解できていない)、なんとなくこの場面の描写に重なったのでした。
望むより早く、人民を不意に前進させることができるものではない。人民を強制しようとする者に災いあれ!人民は思いどおりには動かされない。そんなとき、人民は暴動をほうっておく。暴徒はペスト患者ということになる。家屋は絶壁となり、戸口は拒絶となり、正面入口は壁となる。その壁は見たり、聞いたりするが、望みはしない。戸口をちょっとひらいて、救ってくれないだろうか。いや、その壁は、裁判官だ。見守り、そして断罪する。閉ざされた家々は、なんと陰気なものか!家々は死んだように見えても、生きている。そこで生活が停止されたようでも、根強くつづいている。ここ二十四時間、誰もその家から外出した者はいないが、一人の住人も減ってはいない。その岩の内部で、人びとは行き来し、寝起きしている。そこには家庭があり、飲み食いし、おびえている。恐ろしいことだ!恐怖があの恐ろしい冷淡さを正当化する。そこに臆病がまじっていることが、その罪を軽くさせる。しかも、恐怖が情熱に変ることが、ときには見受けられた。恐慌が激怒に一変し、用心が憤怒に一変することもある。・・・「あの連中は何を要求しているのか?奴らは決して満足することがない。平和な人たちまで巻き添えにする。これでも革命が足りないといわんばかりだ!奴らはここに何をしに来たんだ?うまくいったらお慰みだ。奴らには気の毒だが、自業自得だ。当然の報いを受けるだけだ。あれはごろつきの集まりだ。何より戸口をあけちゃいかん」。そして家屋は墓のような姿になる。暴徒たちは、その前で、死の苦しみを味わう。散弾や抜き身のサーベルが押寄せるのを見る。悲鳴をあげても、聞く者はあるが、誰も来てくれないと知っている。彼らをかくまえる壁もあり、救うことのできる人びともいる。しかもその壁は生身の耳を持ち、その人びとは石の心を持っている。
誰をとがめればよいのか?
誰でもなく、しかもみんなをである。
われわれが生きるこの不完全な時代をである。・・・
進歩とは人間の在り方である。人類全般の生命が"進歩"と呼ばれ、人類の集団的な歩みが"進歩"と呼ばれる。進歩は前進し、天上的なもの、神的なものに向って、人間的で地上的な大旅行をする。遅れた連中と一緒になるため、ときどき休止する。・・・
絶望する者は、正しくない。進歩は必ず目ざめる。また結局、進歩は眠りながらも前進したのだと言えるだろう。なぜなら進歩は成長したからである。それが再び立ち上がったのを見ると、前より高くなったのがわかる。いつも平穏でいるかどうかは、川の責任でもないし、同様に進歩の責任でもない。そこにダムを建てたり、岩を投げこんではいけない。障害物は水を泡立たせ、人類を沸騰させる。そこから混乱が生ずるが、その混乱のあとで、前進したことがみとめられる。普遍的平和にほかならない秩序が確立されるまでは、調和と一致が君臨するまでは、進歩は段階として革命を伴うであろう。
では、進歩とは何か?それは今述べたとおりである。人民の永遠の命である。
ところで、ときには個人の一時的な生命が、人類の永遠の生命の妨げになることがある。
きっぱり言うならば、個人にはそれぞれ異なった利害があり、その利害のための契約をし、それを擁護したところで、反逆罪にはならない。現在、容認しうるほどのエゴイズムを持っている。一時的な生にも権利があり、絶えず未来のために犠牲となる義務はない。・・・「わたしは生存している」と”万人”という名の者がつぶやく。「わたしは若く、恋をしている。わたしは年寄りだし、休息したい。わたしは一家の父で、働き、成功し、商売も順調だ。貸家もある。金は国に預けてある。わたしは幸福だ。妻子があり、それらすべてを愛している。わたしは生きたいのだ。わたしにかまわないでくれ」――そこから、あるときには、人類の高潔な前衛にたいする、奥深い冷淡が生ずる。
ところで、ユートピア思想も、戦いを起せば、光輝ある領域からははみだすことをみとめよう。明日の真理であるユートピア思想は、昨日の虚偽から、戦闘という方法を借りる。未来でありながら、過去のように行動する。純粋な思想でありながら、暴力となる。自己の英雄主義に暴力を混入させ、当然その責任を負わされる。・・・
このような保留をつけたうえで、しかもそれを厳重につけたうえで、私は、未来の光栄ある闘志たち、ユートピア思想の司祭たちが成功しても、しなくても、彼らを讃えずにはいられない。たとえ失敗したとしても、彼らは尊敬すべきである。いや、おそらく不成功の中でこそ、彼らの尊敬は増すのだ。勝利は、進歩の方向に沿っているとき、人民の称賛に価する。一方、英雄的敗北は人民の感動に価する。一方は壮大であり、他方は崇高である。・・・敗者の味方になる者も必要だ。・・・
あらゆる要請に応じて、ユートピア思想が要求するたびに、戦いをはじめることは、どんな人民にもできるものではない。国民は、必ずしも、四六時中、英雄や殉教者の気質をそなえているわけではない。
国民は実際的である。先天的に反乱をきらう。第一に、反乱の結果は破局であることが多いし、第二に、必ず抽象的観念を出発点としているからである。・・・
進歩のための戦いは、失敗することが多いが、その理由は今述べたとおりである。大衆は遍歴騎士の誘いを拒む。大衆というこの重い巨塊は、自分の重さのためにこわれやすく、冒険を恐れる。ところが、理想の中には、冒険がある。
それに、これも忘れてはならぬが、利害がそこにかかわり、理想や感傷にはあまり好意を示さないことである。ときに胃袋が心を麻痺させることがある。・・・
物質は存在し、瞬間は存在し、利害が存在し、腹が存在する。しかし、腹だけが唯一の知恵であってはならない。束の間の生にも、権利があることはみとめよう。しかし、永遠の生にも権利があるのだ。・・・
私が今語っているような戦闘は、理想への痙攣にほかならない。拘束された進歩は病的であり、悲劇的な癲癇を起すものである。われわれは、進歩の病気、つまり内乱に、話の途中で出会わなければならなかった。それは、社会的断罪を受けた一人の男を軸とするドラマの、進行中でもあり、幕間でもある、宿命的な段階である。そのドラマの真の題名は、「進歩」である。
”進歩”!
私がしばしば発するこの叫びが、私の全思想である。・・・
今読者が読んでいる本は、端から端まで、全体的にも、部分的にも、中断、例外、欠陥があるにしても、すべて悪から善への、不正から正義への、虚偽から真実への、夜から昼への、欲望から良心への、腐敗から生命への、獣性から義務への、地獄から天国への、虚無から神への前進である。出発点は物質、到達点は魂である。初めの怪物は、終りでは天使となる。
(第5部第1章20)
そんななかで、ただ一人ヴァルジャンはバリケードの中にいるが戦闘には参加せず、誰も殺さず、バリケードの修理をしたり、ひたすら傷ついた者達の手当てをする。そして自分の敵であるはずのジャヴェールの命を救い、マリユスの命を救う。この作品の中でユゴーがヴァルジャンに与えたかった役割が、わかる気がします。そしてヴァルジャンがその人生の中で幾度も直面している心の葛藤に、人間の人生というのは常に自分の中に住むサタンとの闘いなのだな、と感じたのでした。
以上、長々と書いてしまいましたが、「レミゼってこういう内容だったのか
 」と新たな発見も多かった、充実した読書でした。本当に、世界は知らないことであふれている。。。
」と新たな発見も多かった、充実した読書でした。本当に、世界は知らないことであふれている。。。
以下は、小説の内容以外のことを簡単に。
・ユゴーはロマン主義の時代の作家ですが、その時代のパリというと、、、ショパン!(ということは、リストもワーグナーもシューマンもメンデルスゾーンも同時代ということになる。)しかしショパンがユゴーについて触れているのは、1845年にユゴーがレオニー・ビヤールと姦通している現場を警察に押さえられたスキャンダルについてユゴーをボロクソに書いているルドヴィカ宛の手紙だけのようで 。一方、ユゴーとジョルジュ・サンドは親しく交流があって、サンドが亡くなった際にはユゴーは弔辞を送ったりしています。ちなみにサンドも「カトリック教会はキリスト教の教義を歪曲している」と批判をし、教会との間に確執があったとのこと。
。一方、ユゴーとジョルジュ・サンドは親しく交流があって、サンドが亡くなった際にはユゴーは弔辞を送ったりしています。ちなみにサンドも「カトリック教会はキリスト教の教義を歪曲している」と批判をし、教会との間に確執があったとのこと。
・ナポレオン三世と袂を分かったユゴーが亡命した先が、ブリュッセルだったんですね。ユゴーがグラン・プラスを「世界で最も美しい広場」と讃えたのは、亡命しているときだったのか。旅行中とかかな、と呑気に思ってた
・ユゴーについて調べていると「〈テーブル〉が言うには…」という文章がやたらと出てくるので調べてみたら、〈テーブル〉は何かの比喩ではなく、家具のテーブルそのものなのであった(正確には、テーブルに降りてきた霊)。ユゴーは晩年にオカルティスムに傾倒していたんですね。
・本は断然電子ではなく紙派な私ですが、調べものをするにはオンラインは便利ですねー。「レミゼではロベスピエールについてどんな風に書かれていたんだっけ?」と知りたかったら、レミゼの英訳ページでRobespierreとページ内検索をすればいいので、すごく楽でした。
・読もうと思っている本:『レ・ミゼラブル』の世界 (西永良成著)
・アンジェイ・ワイダ監督の『ダントン(Danton)』というフランス・ポーランド合作の映画があることを知りました。youtubeで英語の字幕版と吹き替え版の両方を見つけたので、観てみたいと思います。
・原作を読み返して、レミゼ25周年の最大の拾い物はハドリーのグランテールだよな~
 と改めて思ったのであった(あとガブローシュ。ラミンアンジョももちろんよき)。今年のGWに延期されたラミン&シエラとの "The Reunion"、ぜひともぜひともぜひとも実現してほしいものです。。。。。。。。
と改めて思ったのであった(あとガブローシュ。ラミンアンジョももちろんよき)。今年のGWに延期されたラミン&シエラとの "The Reunion"、ぜひともぜひともぜひとも実現してほしいものです。。。。。。。。
人生を近くからながめてみよう。人生はいたるところで刑罰を感じさせるようにできている。
あなたがたは人から幸福だと言われるような人であろうか?しかもあなたがたは毎日悲しんでいる。毎日それぞれ大きな苦しみや、小さな心配がある。昨日は親しい人の健康を気づかい、今日は自分の健康を心配する。明日は金銭上の心配が、明後日は中傷者の非難が、その次の日は友人の不幸がやってくるかもしれない。それから天気のこと、次にこわれた物やなくした物のこと、次に良心や背骨から責められる快楽のこと、あるいは世間の成り行き。心の悩みは言うまでもない。こんなふうにつづいていくのだ。一つの雲が散っても、またほかの雲が生じる。百日のうち一日だって、完全な喜びと完全な太陽はほとんどない。しかもあなたがたは少数の幸福な人たちの一人である。他の人々の上には、よどんだ夜がかぶさっている。
考え深い人たちは、幸福な人とか不幸な人という言葉をあまり使わない。明らかにあの世への入口ともいうべきこの世には、幸福な人などは存在しない。
人間の真の区別は、こうである。輝く人と、暗黒の人。
暗黒の人間の数を減らして、輝く人間の数をふやすこと。それが目的である。教育!学問!と人びとが叫ぶ理由はそこにある。読むことを学ぶことは、灯りをつけることである。拾い読みをしたすべての綴りが、光を放つのである。
しかも輝きは、必ずしも喜びということではない。輝きの中でも人は苦しむ。過度の輝きは燃える。炎は翼の敵だ。飛ぶことをやめないで燃える、そこに天才の神秘がある。
あなたがたが何かを認識しても、また何かを愛しても、やはり苦しむだろう。光は涙の中に生れる。輝く人は、暗黒の人間にすぎないような人にたいしても、涙を流すのである。
(第4部第7章1)











 三省堂書店ですよ
三省堂書店ですよ いくらオフィス街とはいえ三省堂が谷川さんの新作を置かないって、あり得ますか
いくらオフィス街とはいえ三省堂が谷川さんの新作を置かないって、あり得ますか