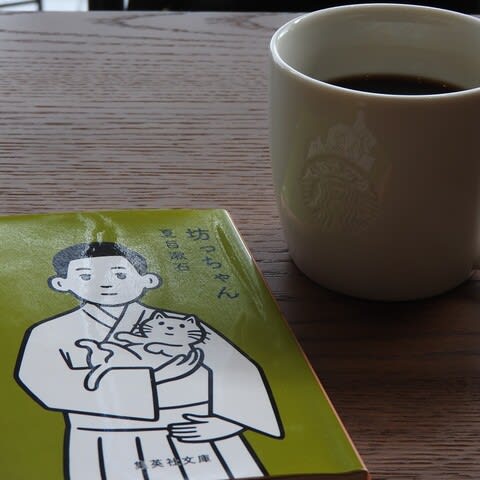 360
360
■ 松山といえば坊っちゃん。道後温泉駅前の広場にある坊っちゃんカラクリ時計を見ていて、ふと思った。坊っちゃんにとって清(きよ)はどういう存在だったんだろう・・・。
松山旅行から帰ってきて『坊っちゃん』(集英社文庫1991年第1刷、2019年第48刷)を再読した。
坊っちゃんは両親に可愛がられなかった。**おやじはちっともおれを可愛がってくれなかった。母は兄ばかりを贔屓にしていた。**(9頁)そんな坊っちゃんにお手伝いさんの清は愛情を注ぐ。両親に可愛がられない分を埋め合わせるかのように。
**母が死んでから六年目の正月におやじも卒中で亡くなった。その年の四月におれはある私立の中学校を卒業する。**(15頁)とあるから、坊っちゃんが母親を亡くしたのは11,2歳の頃だろう。漱石はどうか。生後まもなく里子に出された漱石、その後のことは巻末の年譜に詳しく載っているが省略する。14歳の時、母親を亡くしたことだけ記しておく。
坊っちゃんは松山の旧制中学校に数学の教師として赴任していく。停車場で坊っちゃんを見送る清。**「もうお別れになるかもしれません。ずいぶんご機嫌よう」と小さな声で言った。目に涙がいっぱいたまっている。**(20頁)
坊っちゃんは松山で大騒動を繰りひろげる。そんな時、坊っちゃんがふと思い出すのは清のこと。**(前略)それを思うと清なんてのは見上げたものだ。教育もない身分もない婆さんだが、人間としてはすこぶる尊い。今まではあんなに世話になって別段ありがたいとも思わなかったが、こうして、一人で遠国へ来てみると、始めてあの親切がわかる。(中略)何だか清に逢いたくなった。**(50頁)
松山での一年足らずの教員生活の後、東京に戻ってきた坊っちゃん。**(前略)革鞄を提げたまま、清や帰ったよと飛び込んだら、あら坊っちゃん、よくまあ、早く帰って来て下さったと涙をぽたぽたと落とした。おれもあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない、東京で清とうちを持つんだと言った。**(173頁)
これはもう母と息子の涙の再会シーンではないか。読んでいてそう思ったら涙が出た。漱石は坊っちゃんに我が身を重ね、清に母親を求めていたのではないか。そう、坊っちゃんにとって、そして漱石にとって清は母親だったのだ。
で、ラスト。**死ぬ前日おれを呼んで坊っちゃん後生だから清が死んだら、坊っちゃんのお寺へ埋めてください。お墓のなかで坊っちゃんが来るのを楽しみに待っていますと言った。**(174頁) 悲しくて泣いた。
もちろん『坊っちゃん』を痛快な青春小説として読むこともできるだろう。でも僕は今回は母と息子の愛情物語として読んだ。









