


■ 旧三松屋の蔵座敷の移築工事が終わり、昨日(11日)から一般公開が始まった。この蔵は重要文化財の旧開智学校を手掛けた立石清重の設計・施工だと新聞記事で知った。
早速見学に出かけた。蔵は2間半×5間の大きさで、1階が和室3室、2階が大きな洋室という構成になっている。この擬洋風建築は一般的な蔵とは外観の趣がかなり違う。
漆喰仕上げの外壁を下見板張りで覆っている。このような手法は珍しくはないが、屋根を寄棟にして外壁4面を軒までそっくり覆っているのはいままで見たことがなかった。出入口には洋風の破風が設えてある。2階の縦長の窓には両開きの鉄扉が付けられ、内側には木製の上げ下げ窓が付けられている。この窓はバランサーを壁の中に仕込んだ優れものだと以前施工者から聞いたと記憶する。
受付で渡されたパンフレットに載っている解体中の内観写真をよく見ると、洋小屋であることが分かる。「洋」は構造にも取り込まれているのだ。この蔵は1894(明治27)年の竣工で、1829年生まれの立石はこの年に亡くなっている。この蔵は遺作なのかもしれない。ちなみに旧開智学校は立石40代半ばの作。

■ この塩倉は千国街道(塩の道)の信州側の入口に位置する小谷村大網にあったものを移築したものだという。塩倉という名前の通り、階上に塩を保管し、階下(半地下)に牛を繋いだものだそうだ。塩の道にはこんな倉が多分いくつもあったのだろう。
建築当初は屋根は茅葺の寄棟、壁は土壁であったことが確認されているとのことだが、移築後はこのように切妻屋根、板壁になっている。なぜ建築当初の姿に復元しなかったのか、理由は分からない。
3尺ピッチで柱を建てその間に板を縦にはめて貫ではさみこんで固定している(という理解でいいのか、どうか・・・)。きちんと観察してこなかったが、貫の柱際に栓が写っているので、そうしてあるのではないか、と思う。貫は板を固定するだけでなく現在の木造軸組みの筋交いの役目も果たしている(はずだけど)。
■ まだまだ日中は残暑が厳しい。セミの鳴き声には風鈴の音も負ける。「昼間っからビール」で過ごす。
『民家巡礼』溝口歌子・小林昌人/相模書房 を再読。
1950年代から60年代にかけて日本全国に民家を訪ね歩いた記録。東日本篇と西日本篇の2巻からなるこの本は写真も豊富で今ではほとんど姿を消してしまった民家の記録として貴重だ。
「諏訪平のスズメオドリ」の章に出てくる「タテグルミ」に関する記述。
**諏訪には、一つ屋根の下に、塗籠造りの蔵を北にしその南に住戸を配して、寒い北西風を防ぐようにした、タテグルミの家が非常に多い。**
やはりそうなのかな。藤森さんも同様の理由を挙げていた。**おそらく寒さと関係を深くしていると思います。これを北側へつくったりすると、ここが暖かいですからね。寒さのためだと思いますけども、変わっています。**(藤森照信展のカタログより)
ホントなのかな・・・。
ボクは・・・、ン! 母親が出くわした熊に背を向けて幼い子どもを守ろうと包み込むようにする姿に似ているように思う。♪あるぅ日 森の中 熊さんに 出会った なんてことはめったにないだろうが、他にいい喩えが浮かばない。
余談だが、この日本人の母親の自己犠牲的な守りの形に対し、欧米人の守りの形は、子どもを後ろにまわして熊と正対して戦う姿となるという・・・。
タテグルミは蔵に納めた大切なモノをさらに蔵ごと守ろうとする日本人の守りの姿、守りの形なのではないか。これがボクの眉つばな説。くるむ(守る)対象は住居ではなく蔵なのだから。そうでしょう?。

19790504撮影
■ 建てぐるみ 耐火構造の蔵を可燃材でできた家屋で「くるんで」います。別棟にして蔵を火災から守るというのが本来の姿ではないか、と思うのですが・・・。なぜ蔵をこのようにくるんでいるのか、分かりません。
これが諏訪地方に見られる建てぐるみ(←過去ログ:今回載せた写真と同日の撮影)です。既に何回か紹介しましたが、地元産の鉄平石で屋根を葺いています。寒冷地では焼きの甘い瓦は凍害で割れてしまいます。
石がずれないように軒先の鼻隠し、妻側の破風の外側にせき板を取り付けています。妻側のせき板を頂部で交差させて×の形にしています。ここを飾ったものがすずめおどりです。過去ログの写真にはすずめおどりが写っています。
1979年の5月4日、茅野駅から上諏訪駅まで歩いて観察したことが当時の記録で分かります。あの頃はあちこち歩き回っていました。若かったな~。
19790504撮影
■ すずめおどり せき板の交差のさせ方には右手前、左手前 どちらもありますから、とくに決まりは無いようです。
200608撮影
■ 妻垂れ 先日観た「藤森照信展」で展示されていた妻垂れと同じもの。4年前に撮りました。藤森さんは心に残る高部の風景と素材としてこの「シブキヨケ」も挙げています。
19790504撮影
■ 鉄平石一文字葺き 棟に小さな祠があります。妻飾りは「からすおどし」。諏訪地方には「すずめおどり」とこの「からすおどし」、両方あります。
以上、諏訪地方の民家の特徴を示す写真をまとめて載せました。

諏訪の蔵 091101撮影
三郷の繭蔵 090211撮影
■ 土蔵は木造で板の表面に耐火被覆として土が塗られていることが分かります。柱と柱の間に厚い板を落とし込み、その表面に堅木や竹のくさびを打ち込みます。上の写真でくさびの跡が規則的に並んでいることが分かります。くさびに縄をかけて土壁に塗り込むことで剥落を防いでいることが下の写真で分かります。二度三度と重ね塗りをするんですね。時間のかかる仕事です。
さてこの先どう書きすすめるか・・・、考えていませんでした。
ガウディのサグラダ・ファミリアは調べてみると着工が1882年で、完成は2256年と予想されています。着工から完成まで約370年!今話題の東京スカイツリーは着工が2008年7月で、完成予定が2011年12月です。たった3年数か月で高さ634(武蔵国に因んだとか)メートルの電波塔を造ってしまうというプロジェクトです。
「大きいことはいいことだ」というチョコレートのテレビCMがむかし流行りましたが、今は「速いことはいいことだ」という風潮ですね。建築も然りです。建設工期の短縮が必ずと言っていいほど課題になります。東京スカイツリーはサグラダ・ファミリアの100分の1の工期です!
上の蔵にはあんこが、じゃなかった、時間がぎっしり詰まっているような気がします。今のインスタントな建築には時間をストックすることなどできそうにありません。
「♪のんびりゆこうよ俺達は」 やはりむかし流行ったCMソングの歌詞のような社会、経済、文化にはもう戻れないでしょうね。 

■ 通常は上の例のように蔵の地棟の小口には妻飾りが施される。既に書いたことを繰り返すが、水を吸って腐朽しやすい小口を保護するためだ。次第に鏝絵などで飾られるようになり、意匠的な意味合いが強まった。
下の写真は前稿で取り上げた火の見櫓(?)のすぐ近くで見かけた蔵。太鼓落としをした太い丸太の地棟、その小口がむき出しになっている。妻飾りが施されておらず、このように小口がむき出しのものは珍しいのではないか。これはこれで簡素で美しい。飾りの無い素形の美。
松本市梓川にて(100704)
壁が白くて明るいので露出を補正しないと地棟の小口がはっきり写らない。


■ 路上観察 諏訪の蔵 100508
下諏訪駅から諏訪大社下社に向かう途中で見かけた蔵。火の見櫓の路上観察を始めちまったが、民家も忘れちゃならねェ~。
屋根が今では珍しい鉄平石の菱葺きということと、破風板が交叉してX印になっていることに注目した。鉄平石を使った屋根の棟納めや破風と鼻かくしとの取り合いなども本来の姿を留めている。
ずっと継承して欲しいこの地方の蔵づくりの技と意匠。


■ 路上観察 塩尻の蔵 100412
1 妻垂れは漆喰の壁を雨から保護するために設けられる。別に珍しいものではなく、塩尻市内でも見かける。長野県では諏訪地方から南信(県の南部)方面に多い。
この妻垂れはまだそれ程年数が経っていない。このように木が使われ、本来の姿が継承されているものを見ると嬉しくなる。金属サイディングなどに替えられてしまうこともあるが、それだと蔵にマッチしないし、美しくない。
2 平側の壁に設けられた上下ふたつの窓はそれほど大きくはないが、なかなか存在感がある。換気や採光のために最小限の窓は必要、防犯・防火上窓は不要。この相反する条件にどのように折り合いをつけるか。
両開きの戸と鉄格子がその答え。

□ まだ雪の残る北安曇郡小谷村、千国の集落で見かけた蔵。撮影100409
小谷の蔵は既に数回取り上げたが、このような蔵を見かけるとつい路上観察してしまう。腰壁の取り外し可能な木製パネル、軒先を補強する木組み、妻壁を保護する板壁(名称は不明、妻垂れとは呼ばないだろう)。これらは雪深い山里に暮らす人々の長年の知恵と工夫の成果。やはり民家には「うそ」がない。
■ このところ路上観察をしていません。で、過去の記録を載せます。 

■ 諏訪の蔵 撮影20091101
この蔵は昨年11月に諏訪で見かけました。屋根は諏訪地方に見られる鉄平石の菱葺き(一文字葺きの一種)。棟も石を重ねていますが、これは一般的な棟納めです。
漆喰仕上げの腰壁に押縁下見板張りのパネルを取り付けています。漆喰は火に強くても雨にはあまり強くないですから。昨年修復工事が終わり、春に公開された松本市内の高橋家住宅も板張りのパネルを壁に掛けていました。同じ理由でしょう。
この蔵はかなり傷んでいて、妻側の土壁が剥落して、下地板が露出していました。なかなか立派な蔵なのに放置されたままになっているのは残念です。
■ 茅野の民家の屋根 鉄平石一文字葺き 撮影197905
諏訪の隣り茅野出身の藤森照信さんも鉄平石をよく使っています(下の写真)。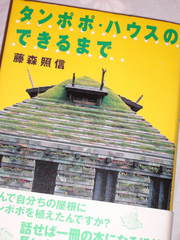
■ 鉄平石の屋根と壁(藤森さん家(チ) タンポポ・ハウス)

■ このところ蔵をいくつも取り上げてきました。で、今回も蔵にお付き合いを。
いままで注目してきたのは妻壁の開口部です。妻側を前面道路に向けている蔵が多いですから路上観察しやすいのです。出入口を平側に付けることが多いですからこのような配置になります。ただし敷地の状況にもよります。また店蔵の場合は平側を前面道路に向けることが多いですが。
この蔵の開口部は随分大きいですね。開口部に建具がない場合もありますが、この大きさだと建具がないと雨仕舞上支障があります。よくある建具は外開きで、片開きも両開きもあります。それから鉄板の突き上げ戸もあります。
ではこの蔵の開口部は一体どうなっているんでしょう・・・。塞いでしまった? 塞いでしまうことはまず無いと思いますが、塞ぐとすれば施工上、壁と同面に納めるのでは?
蔵の出入口の建具には開き戸も片引き戸もあります。でも、窓に引き戸を設けた例は記憶にありませんが、建築探偵失格な私が考えるに、これは片引き戸ではないかと思います。他の開閉方式がこの場合思い浮かびません・・・。
持ち主に訊ねてみれば分かると思うのですが、所用で移動中の場合、時間的に余裕がなくてできません(というのは言い訳かな)。数分あればできますから。


せいろう倉 木曽郡木曽町(旧開田村)にて 200904撮影
■ 板倉の壁の構法(壁の仕組み、構成システム)としては「落とし板倉」と「せいろう倉」があります。他にも柱・梁の骨組みの両面に板を張る構法もありますが、これは新しい構法でしょう。
前稿で「落とし板倉」を取り上げましたので、本稿では「せいろう倉」を取り上げます。
今年の3月、木曽の旧開田村で路上(ではないです、畑から)観察しました。右の写真を見ればあの正倉院の校倉造りと同じ構法であることが分かります。古くからある構法ですね。
落とし板倉をせいろう倉として紹介している資料もありますが、両者は全く異なる構法です。前稿の全景写真と比べればそのことが分かると思います。
せいろう倉という名称は蒸し器のせいろうに由来しているのでしょう。この倉を偶然見つけたときはうれしかったです。なにしろ初めて見たのですから・・・。

■ 近江八幡の街中で見かけた蔵。腰は幅広の板の縦張り、シンプルな窓廻り、薄い庇。端整なデザイン。
今現在活躍している建築家にこんなデザインをすると思われる人を探すなら誰だろう・・・、谷口吉生さんあたりか。

■ 路上観察、今回は塩尻市洗馬の蔵。もっと正面から写真を撮りたかったが、手前の木が邪魔をしていた。
資料には表日本では簡素なものが多く、裏日本では装飾過剰なものが多い、とある。裏日本は冬、雪に覆われて無彩色の世界になってしまうことと無関係ではないかもしれない。そういえば九谷焼も色彩が豊かだ。
松本平辺りは両者の中間的な意匠なのだろう。蔵の窓廻りの意匠は無彩色、形はシンプルだが洗練されたものが多い、と思う。
この蔵はまぐさ(窓上の梁形)が曲線で構成されていて、濃い黄色が使われている。塩尻市洗馬では何棟もの蔵を見かけているが、彩色された蔵を他には知らない。
探せばまだまだいろんな蔵と出会うことが出来そうだ。

















