今日から3日間短い夏休みに入った。
今日、久しぶりに文学書を読んだ。
選んだのは芥川龍之介の小説、「秋」。
10年以上前に古本で全集を買ったが、殆ど読まずに本棚に収まっていた。
本棚から取り出した時、函の上部に夥しい量の埃が付着していた。
主人公の信子は、女子大学にいた時から、才媛の名声を担っており、彼女が早晩作家として文壇に打って出ることは殆ど誰も疑わなかった。
彼女には俊吉という従兄がいたが、彼もまた大学の文学部に籍を置き、将来作家を目指していた。
彼女は文学という共通の関心からかいつしかこの従兄と親しくなり、周囲の同窓たちからも彼らが将来結婚するものとして羨望の目で見られていた。
しかし信子が大学を卒業するとまもなく彼女は大阪の商事会社に近々勤務することになった高商出身の青年と突然結婚してしまう。
それは、彼女の妹である照子も俊吉に恋心を抱いていることを知って、妹に対する愛情から自ら身を引いたためであった。
結婚後しばらくは新婚の夫婦の如く、幸せな日々を送っていたが、夫が次第に本性を現わし始め、彼女の文学に対する関心や創作や、日常の些細なことにねちねちとけちをつけたり文句を言うようになっていった。
彼女は夫のそのような態度に口答えもせず、忍耐し、むしろ夫に努めて優しく振舞うようになる。
しかし彼女の文学の創作はしだいに進まなくなっていった。
そんな頃、妹の照子が俊吉と結納を済ませたことを知らせる便りが送られてきたが、信子は式に出れない返事を返す。
翌年の秋、信子は夫の東京出張に同伴した際、結婚以来会っていなかった妹夫婦に会いにいくために、彼らの新居を訪れた。
信子は久しぶりに俊吉と会い、話をしていくうちに懐かしさがこみあげ、文学の話題になると学生時代のように心がときめくのを感じる。
その日の夜遅く、俊吉は雨戸を開けて信子を外に連れ出し、交わした言葉はわずかであったが、庭や鶏小屋の前で2人だけの時間を共有する。
翌日俊吉は亡友の一周忌の墓参をするために外出する際に、昼までに帰ってくるから待っているように信子に念を押した。
俊吉がいなくなってから信子と照子はお茶を飲みながら世間話をするが、信子は照子の幸福そうな生活の話を聞くうちに次第に生返事をしている自分に気付く。
夫の愛に飽き足りている妹の姿を見て、自分の境遇に陰鬱にならざるを得なかった。
その気持ちに気が付いたのか、照子は信子の夫婦関係を心配する。
そして照子はいつのまにか泣き出してしまう。
信子はとうとう俊吉が帰ってくる前に、家を出て幌車に乗って駅に向かっていた。
途中、信子は正面から向かって歩いてくる俊吉の姿をとらえる。
信子はすれ違いざまに一瞬、俊吉に声をかけようとしてためらった。
「秋」だと、信子はうすら寒い幌の下、全身で寂しさを感じながら、しみじみと思わずにはいざれなかった。
あらすじはこんな感じであるが、この小説は登場人物の繊細な心理描写の変化を鑑賞するものなので、あまり役に立たない。
興味のある方は、青空文庫で旧文体のまま読めるのでお勧めしたい。
この小説を読んで最も感じたのは、主人公である信子の結婚後の気持ちの変化と、宿命的に不幸に向かわざるを得ないとまで感じさせる、彼女のその心理的動機についてであった。
何故信子は好きだった俊吉を妹に譲るために、卒業後すぐに早々と縁談を決めてしまったのか。
自分の人生の幸福を犠牲にして、妹の幸福を願う気持ちは真なのか。それともそれとは異なる、本人にも見えない動機に動かされての決断なのか。
「彼女の結婚は果して妹の想像通り、全然犠牲的なそれであらうか。さう疑を挾む事は、涙の後の彼女の心へ、重苦しい気持ちを拡げ勝ちであつた。信子はこの重苦しさを避ける為に、大抵はぢつと快い感傷の中に浸つてゐた。」
信子は次第に本性を現わし始めた夫の冷たさにも耐え忍び、仕打ちを受けた後でも仲直りする努力を見せる。
「信子はそれ以来夫に対して、一層優しく振舞ふやうになつた。夫は夜寒の長火鉢の向うに、何時も晴れ晴れと微笑してゐる彼女の顔を見出した。」
この「晴れ晴れと微笑してゐる彼女の顔」という表現は別の箇所でも出てくる。
母や照子が信子が大阪に向けて出発するのを見送るために、中央停車場へ来たときだ。
この表情が彼女の性質の一面を理解させるものとして、重要なものになっていると感じられる。
彼女は瑣末な経済的なことしか関心を示さない夫との生活に次第に同化していき、文学への創作意欲を無くしていく。
そんな折り、彼女は俊吉と照子に再会する機会を得る。
俊吉と久しぶりに再会した信子は、かつてのように気持ちが高揚してくるのを感じる。
「その談論風発が、もう一度信子を若返らせた。彼女は熱のある眼つきをして、「私も小説を書き出さうかしら。」と云つた。」
俊吉も出来るだけ信子との二人だけの時間を持てるようしていたことが、信子の到着時や、歓談が終ったあとの夜更けに庭に連れ出したことなどから伺われる。
俊吉はもしかすると、照子よりも姉の信子との会話に魅力や満たされるものを感じていたのかもしれない。だから自ら意図的ではないにしても無意識的にそのような行為に出たのではないか。
それは次の箇所で一層明確になる。
「「好いかい。待つてゐるんだぜ。午頃ひるごろまでにやきつと帰つて来るから。」――彼は外套をひつかけながら、かう信子に念を押した。が、彼女は華奢きやしやな手に彼の中折なかをれを持つた儘、黙つて微笑したばかりであつた。」
俊吉が外出している間に、信子は照子との会話で自分の現在置かれている境遇に対する現実の気持ちに一層直面せざるを得なくなる。
そのうち照子が激しく泣きだすが、後でその涙は自分に対する不憫な思いからくるのではなく、姉と俊吉との関係に対する嫉妬と夫を奪われる不安から来ているものであることを悟る。
妹の気持ちを察した信子は、俊吉が帰ってくる前に帰る決心をする。
「彼女の心は静かであつた。が、その静かさを支配するものは、寂しい諦めに外ならなかつた。照子の発作が終つた後、和解は新しい涙と共に、容易たやすく二人を元の通り仲の好い姉妹に返してゐた。しかし事実は事実として、今でも信子の心を離れなかつた。彼女は従兄の帰りも待たずこの俥上に身を託した時、既に妹とは永久に他人になつたやうな心もちが、意地悪く彼女の胸の中に氷を張らせてゐたのであつた。」
彼女はここで完全に俊吉への想いを断ち切ろうとする。妹の幸せのために。
しかしそう決心したことで、これまでずっとつながっていた妹に対する思いにも終止符が打たれる。
彼女は駅に向かって走っていた幌車の中で、俊吉とすれ違いざまに声をかけようとしたが出来なかった。
何故出来なかったのか。
声をかけようとした瞬間までは、消えかかる炎のようにかろうじて残っていたかつての信子そのものであった。
しかしつぎの瞬間、俊吉への思いにけじめをつけた自分がそこにいた。
俊吉や照子に対する気持ちを断ち切ったあとで待ち受けていたのは、「秋」のような冷たく寂しい現実であった。
この小説は、読者に強いメッセージを示唆したり、何かを訴えかけるというような性質は感じられない。むしろ平凡な日常のよくありがちな人間関係での心理描写が主題となっている。
しかし私はこの信子という女性に対し魅力を感じつつも、何とも言えない切なさ、いたたまれなさを感じた。
当時は珍しかったであろう女子大学で才媛と見られ、周囲がうらやむほどの文筆活動を行うほどのヴァイタリティの持ち主であった彼女が、何故、妹の幸福のために自分の人生を犠牲にする選択をしたのか。
彼女は従兄と一緒にいることが何よりも幸せに感じていた。本当は小説家になりたかった。文学を読んだり、話したりすることに生きがいを感じていた。本当は早くに縁談により結婚したくなかった。
何故そういう自分の本当の気持ちに従えなかったというところが、この小説を読んで最も深く考えさせられたことである。
何が彼女をそのような選択に向かわせたのであろか。
恐らくではあるが、「自分のことよりも他人を優先させる生き方をしなさい」という暗黙のメッセージが、彼女の深い深層心理に刷り込まれ、あたかもそれが人生脚本のように潜在的に運命づけられていたのではないかと思うのである。
彼女は大学時代までは自分の才能を開花させることができた。
しかし妹の幸せを優先させるために、自ら自己犠牲的生き方を選択した。
自己犠牲的行為は、愛や賞賛を求める受け身的動機ではなく、相手に対する能動的な愛情から来る動機が源になければ、自分を苦しめる以外の何物でもない。
受け身からくる自己犠牲は、次第に自己無価値観を心にはびこらせ、怒りや憎しみを無意識に堆積させる恐ろしいものである。
信子のとったこの自己犠牲の選択は、表向き能動的ではあるのだが、何か自分の本心とは異なる所から出ているようにも感じる。
信子の自己犠牲的選択の真意は結局のところこの小説から完全に読み取ることは出来なかったが、信子がこれからの長い人生を幸福に生きるにはどうしたらよいのか、ということについて考えずにはいられなかった。
強いて言うならば、次のようなことが頭に浮かんでくる。
・自分の選択の過ち、自分の心に潜在的に埋め込まれた人生脚本への気付き、そこからの脱却。
・耐え忍ぶという価値観からの解放
・本来の自分への気付きと回帰
・自己実現への道
根源的に素晴らしい才能、人間的な優しさを持っていながら、不幸な人生を送っている人間は多い。
不幸な人生という自分ではどうすることも出来ないシナリオに従って生きていくうちに、それらの才能や優しさが枯渇していき、それらが自分の記憶からも遠ざかっていくことは思うに忍びない。
しかし作者は信子という主人公に対し、暖かい眼差しを向けているように感じる。
作者は様々な登場人物に対し、自分の価値観を入れていない。ただありのままに描写するのみである。どんな人物に対してもその生き様を受容しているように思われるのである。
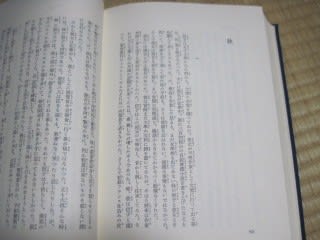
【追記20210814】
芥川龍之介全集第4巻の「私の好きな私の作」というタイトルのエッセイ?に、「「秋」が好きです。」とだけ書かれていた。
この時大正10年(1921年)。
芥川龍之介お気に入りの小説だった、ということだろうか。
ちなみに「秋」が書かれたのはその前年の大正9年(1920年)。
【追記202108141200】
信子が何故、俊吉と照子との結婚式に出席しなかった理由が気になっていた。
推測ではあるが、信子はまだ俊吉への未練の気持ちが自分でも意識できないまま残っていたからではないか。
思いが完全に断ち切れていたならば、二人に対し迷いの気持ちなく祝福できたはずである。
また、俊吉も信子に対して未練を感じていると思われる箇所が、随所に読み取れる。
今日、久しぶりに文学書を読んだ。
選んだのは芥川龍之介の小説、「秋」。
10年以上前に古本で全集を買ったが、殆ど読まずに本棚に収まっていた。
本棚から取り出した時、函の上部に夥しい量の埃が付着していた。
主人公の信子は、女子大学にいた時から、才媛の名声を担っており、彼女が早晩作家として文壇に打って出ることは殆ど誰も疑わなかった。
彼女には俊吉という従兄がいたが、彼もまた大学の文学部に籍を置き、将来作家を目指していた。
彼女は文学という共通の関心からかいつしかこの従兄と親しくなり、周囲の同窓たちからも彼らが将来結婚するものとして羨望の目で見られていた。
しかし信子が大学を卒業するとまもなく彼女は大阪の商事会社に近々勤務することになった高商出身の青年と突然結婚してしまう。
それは、彼女の妹である照子も俊吉に恋心を抱いていることを知って、妹に対する愛情から自ら身を引いたためであった。
結婚後しばらくは新婚の夫婦の如く、幸せな日々を送っていたが、夫が次第に本性を現わし始め、彼女の文学に対する関心や創作や、日常の些細なことにねちねちとけちをつけたり文句を言うようになっていった。
彼女は夫のそのような態度に口答えもせず、忍耐し、むしろ夫に努めて優しく振舞うようになる。
しかし彼女の文学の創作はしだいに進まなくなっていった。
そんな頃、妹の照子が俊吉と結納を済ませたことを知らせる便りが送られてきたが、信子は式に出れない返事を返す。
翌年の秋、信子は夫の東京出張に同伴した際、結婚以来会っていなかった妹夫婦に会いにいくために、彼らの新居を訪れた。
信子は久しぶりに俊吉と会い、話をしていくうちに懐かしさがこみあげ、文学の話題になると学生時代のように心がときめくのを感じる。
その日の夜遅く、俊吉は雨戸を開けて信子を外に連れ出し、交わした言葉はわずかであったが、庭や鶏小屋の前で2人だけの時間を共有する。
翌日俊吉は亡友の一周忌の墓参をするために外出する際に、昼までに帰ってくるから待っているように信子に念を押した。
俊吉がいなくなってから信子と照子はお茶を飲みながら世間話をするが、信子は照子の幸福そうな生活の話を聞くうちに次第に生返事をしている自分に気付く。
夫の愛に飽き足りている妹の姿を見て、自分の境遇に陰鬱にならざるを得なかった。
その気持ちに気が付いたのか、照子は信子の夫婦関係を心配する。
そして照子はいつのまにか泣き出してしまう。
信子はとうとう俊吉が帰ってくる前に、家を出て幌車に乗って駅に向かっていた。
途中、信子は正面から向かって歩いてくる俊吉の姿をとらえる。
信子はすれ違いざまに一瞬、俊吉に声をかけようとしてためらった。
「秋」だと、信子はうすら寒い幌の下、全身で寂しさを感じながら、しみじみと思わずにはいざれなかった。
あらすじはこんな感じであるが、この小説は登場人物の繊細な心理描写の変化を鑑賞するものなので、あまり役に立たない。
興味のある方は、青空文庫で旧文体のまま読めるのでお勧めしたい。
この小説を読んで最も感じたのは、主人公である信子の結婚後の気持ちの変化と、宿命的に不幸に向かわざるを得ないとまで感じさせる、彼女のその心理的動機についてであった。
何故信子は好きだった俊吉を妹に譲るために、卒業後すぐに早々と縁談を決めてしまったのか。
自分の人生の幸福を犠牲にして、妹の幸福を願う気持ちは真なのか。それともそれとは異なる、本人にも見えない動機に動かされての決断なのか。
「彼女の結婚は果して妹の想像通り、全然犠牲的なそれであらうか。さう疑を挾む事は、涙の後の彼女の心へ、重苦しい気持ちを拡げ勝ちであつた。信子はこの重苦しさを避ける為に、大抵はぢつと快い感傷の中に浸つてゐた。」
信子は次第に本性を現わし始めた夫の冷たさにも耐え忍び、仕打ちを受けた後でも仲直りする努力を見せる。
「信子はそれ以来夫に対して、一層優しく振舞ふやうになつた。夫は夜寒の長火鉢の向うに、何時も晴れ晴れと微笑してゐる彼女の顔を見出した。」
この「晴れ晴れと微笑してゐる彼女の顔」という表現は別の箇所でも出てくる。
母や照子が信子が大阪に向けて出発するのを見送るために、中央停車場へ来たときだ。
この表情が彼女の性質の一面を理解させるものとして、重要なものになっていると感じられる。
彼女は瑣末な経済的なことしか関心を示さない夫との生活に次第に同化していき、文学への創作意欲を無くしていく。
そんな折り、彼女は俊吉と照子に再会する機会を得る。
俊吉と久しぶりに再会した信子は、かつてのように気持ちが高揚してくるのを感じる。
「その談論風発が、もう一度信子を若返らせた。彼女は熱のある眼つきをして、「私も小説を書き出さうかしら。」と云つた。」
俊吉も出来るだけ信子との二人だけの時間を持てるようしていたことが、信子の到着時や、歓談が終ったあとの夜更けに庭に連れ出したことなどから伺われる。
俊吉はもしかすると、照子よりも姉の信子との会話に魅力や満たされるものを感じていたのかもしれない。だから自ら意図的ではないにしても無意識的にそのような行為に出たのではないか。
それは次の箇所で一層明確になる。
「「好いかい。待つてゐるんだぜ。午頃ひるごろまでにやきつと帰つて来るから。」――彼は外套をひつかけながら、かう信子に念を押した。が、彼女は華奢きやしやな手に彼の中折なかをれを持つた儘、黙つて微笑したばかりであつた。」
俊吉が外出している間に、信子は照子との会話で自分の現在置かれている境遇に対する現実の気持ちに一層直面せざるを得なくなる。
そのうち照子が激しく泣きだすが、後でその涙は自分に対する不憫な思いからくるのではなく、姉と俊吉との関係に対する嫉妬と夫を奪われる不安から来ているものであることを悟る。
妹の気持ちを察した信子は、俊吉が帰ってくる前に帰る決心をする。
「彼女の心は静かであつた。が、その静かさを支配するものは、寂しい諦めに外ならなかつた。照子の発作が終つた後、和解は新しい涙と共に、容易たやすく二人を元の通り仲の好い姉妹に返してゐた。しかし事実は事実として、今でも信子の心を離れなかつた。彼女は従兄の帰りも待たずこの俥上に身を託した時、既に妹とは永久に他人になつたやうな心もちが、意地悪く彼女の胸の中に氷を張らせてゐたのであつた。」
彼女はここで完全に俊吉への想いを断ち切ろうとする。妹の幸せのために。
しかしそう決心したことで、これまでずっとつながっていた妹に対する思いにも終止符が打たれる。
彼女は駅に向かって走っていた幌車の中で、俊吉とすれ違いざまに声をかけようとしたが出来なかった。
何故出来なかったのか。
声をかけようとした瞬間までは、消えかかる炎のようにかろうじて残っていたかつての信子そのものであった。
しかしつぎの瞬間、俊吉への思いにけじめをつけた自分がそこにいた。
俊吉や照子に対する気持ちを断ち切ったあとで待ち受けていたのは、「秋」のような冷たく寂しい現実であった。
この小説は、読者に強いメッセージを示唆したり、何かを訴えかけるというような性質は感じられない。むしろ平凡な日常のよくありがちな人間関係での心理描写が主題となっている。
しかし私はこの信子という女性に対し魅力を感じつつも、何とも言えない切なさ、いたたまれなさを感じた。
当時は珍しかったであろう女子大学で才媛と見られ、周囲がうらやむほどの文筆活動を行うほどのヴァイタリティの持ち主であった彼女が、何故、妹の幸福のために自分の人生を犠牲にする選択をしたのか。
彼女は従兄と一緒にいることが何よりも幸せに感じていた。本当は小説家になりたかった。文学を読んだり、話したりすることに生きがいを感じていた。本当は早くに縁談により結婚したくなかった。
何故そういう自分の本当の気持ちに従えなかったというところが、この小説を読んで最も深く考えさせられたことである。
何が彼女をそのような選択に向かわせたのであろか。
恐らくではあるが、「自分のことよりも他人を優先させる生き方をしなさい」という暗黙のメッセージが、彼女の深い深層心理に刷り込まれ、あたかもそれが人生脚本のように潜在的に運命づけられていたのではないかと思うのである。
彼女は大学時代までは自分の才能を開花させることができた。
しかし妹の幸せを優先させるために、自ら自己犠牲的生き方を選択した。
自己犠牲的行為は、愛や賞賛を求める受け身的動機ではなく、相手に対する能動的な愛情から来る動機が源になければ、自分を苦しめる以外の何物でもない。
受け身からくる自己犠牲は、次第に自己無価値観を心にはびこらせ、怒りや憎しみを無意識に堆積させる恐ろしいものである。
信子のとったこの自己犠牲の選択は、表向き能動的ではあるのだが、何か自分の本心とは異なる所から出ているようにも感じる。
信子の自己犠牲的選択の真意は結局のところこの小説から完全に読み取ることは出来なかったが、信子がこれからの長い人生を幸福に生きるにはどうしたらよいのか、ということについて考えずにはいられなかった。
強いて言うならば、次のようなことが頭に浮かんでくる。
・自分の選択の過ち、自分の心に潜在的に埋め込まれた人生脚本への気付き、そこからの脱却。
・耐え忍ぶという価値観からの解放
・本来の自分への気付きと回帰
・自己実現への道
根源的に素晴らしい才能、人間的な優しさを持っていながら、不幸な人生を送っている人間は多い。
不幸な人生という自分ではどうすることも出来ないシナリオに従って生きていくうちに、それらの才能や優しさが枯渇していき、それらが自分の記憶からも遠ざかっていくことは思うに忍びない。
しかし作者は信子という主人公に対し、暖かい眼差しを向けているように感じる。
作者は様々な登場人物に対し、自分の価値観を入れていない。ただありのままに描写するのみである。どんな人物に対してもその生き様を受容しているように思われるのである。
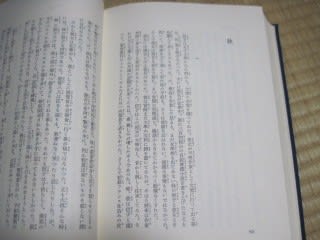
【追記20210814】
芥川龍之介全集第4巻の「私の好きな私の作」というタイトルのエッセイ?に、「「秋」が好きです。」とだけ書かれていた。
この時大正10年(1921年)。
芥川龍之介お気に入りの小説だった、ということだろうか。
ちなみに「秋」が書かれたのはその前年の大正9年(1920年)。
【追記202108141200】
信子が何故、俊吉と照子との結婚式に出席しなかった理由が気になっていた。
推測ではあるが、信子はまだ俊吉への未練の気持ちが自分でも意識できないまま残っていたからではないか。
思いが完全に断ち切れていたならば、二人に対し迷いの気持ちなく祝福できたはずである。
また、俊吉も信子に対して未練を感じていると思われる箇所が、随所に読み取れる。
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます