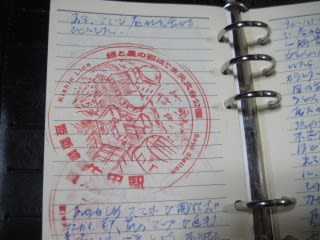この年末年始、実家に1年ぶりに帰省したが、いつもの飛行機ではなく、列車の旅を兼ねて北海道まで行くことにした。
【ルート】
12月28日
関東某所⇒仙台⇒石巻⇒女川⇒前谷地⇒気仙沼(宿泊)
12月29日
気仙沼⇒一ノ関⇒盛岡⇒新函館北斗⇒北海道某所
以下、小旅行の記録である。
12月28日
5:58発、自宅最寄のバス停からJR某駅に向かう。
通勤時に利用するのと同じ時刻のバスだ。
JR某駅、6:25発普通列車に乗車、関東某駅着。
30分以上時間があるので、明日の北海道内特急の指定席券を購入した。
自動販売機では買えなかったので、みどりの窓口で直接購入。2,960円。
窓口は空いていた。しかし新幹線改札口を出ると、帰省客らしき人々が大勢いた。
あとスノボを背負った若者たちの姿も多く見かけた。もうコロナ前と同じくらいの混雑さだ。
待合室で時間をつぶす。
7:33、はやぶさ3号、新青森行きに乗車。



列車内は意外に空いていた。外は晴天だ。気持ちのいい冬の日の朝日。
旅はこれだからいい。昨日は4時間くらいしか寝ていない。その前の日もそうだ。
昨日は寝る前にコーヒーとビールを飲んだからトイレに3回も起きてしまった。だから余計寝不足だ。
しかし頭は冴えている。
仙台まで約1時間。あっという間だ。
仙台から先、石巻か女川のどちらで時間を長く過ごそうか。
スマホで両町の情報を調べる。女川の方が何となく良さそうだ。
魚介類の何かおいしいものでも食べることにしよう。
仙台方面の天気はどうなのだろう。今日の朝刊の天気予報では晴れマークだったが、テレビの天気予報では雪マークだった。
栃木あたりの田んぼは一面、霜が降りているように見えた。
そうだ。CDプレーヤーに、さっき駅で買った電池を入れておこう。これでチャイコの「悲愴」を聴くのだ。
これで旅情気分は倍化だ。
ふと車窓を見たら雪景色に変わっていた。場所はどこだろう。福島あたりか。
トンネルに入ると圧力で耳が痛くなる。
8:25、福島駅通過。かなり雪が積もっている。雪も降っているようだ。
仙台駅からの乗り換えは大丈夫だろうか。
しかし大きなトンネルを抜けると晴れだった。何という変わりよう。仙台の天候はそう悪くないに違いない。場所によってだいぶ違うものだ。
8:40、仙台着。
次の列車の乗り換えまでわずか。
新幹線改札を出て在来線の切符を買おうとしたが、販売機が混んでいる。
仕方ない。改札がスイカ対応だったのでスイカで入る。
エスカレーターを降りて、仙石線に乗り換える。


8:55発、高城町行き普通列車に乗車。電車だ。
陸前〇〇(メモ見逃す)までは地下を走行する。
地上に出ると晴れ、しかし雪はだいぶ積もっている。
同じ車両内に、半ズボンの小学生がいた。またミニスカートで素肌の中学生もいた。
この寒さなのに!。いったいどういう温度感覚なのだ。自分はタイツまで履いているというのに。
途中、今日気仙沼で再会する講習会で親しくなった宮城県在住の友人が住んでいる町の付近を通る。
神社が見える。
本塩釜から海が見えてきた。東塩釜から雪がちらついてきた。
今日は1日雪か?。天気予報はあまりあてにならない。
ホームでの停車時間は長めだ。ドアは開いたままなので寒い。
「陸前」で始まる駅がけっこうある。
海に小さな島がいくつか浮かんでいた。
陸前浜田に着くと雪がかなり降ってきた。女川では外に長くいられないだろう。
屋内で時間をつぶす所を見つけなければならない。
松島海岸駅で多くの乗客が降りた。観光客風だ。この寒いのに海岸を歩くというのか?。
松島と言えば日本三景の1つだったっけ?。
9:40、高城町着。

駅改札を出てトイレに急行。外はめちゃくちゃ寒く、雪がちらつく。
9:49発、石巻行きの快速、ディーゼル6両編成に乗り換える。


ここからは景色がかなり田舎となる。
右手に海が見えてきた。この路線は海沿いを走るようだ。
ディーゼルカー特有のエンジン音が響き渡る。ああ、最高にいい気分だ。
東松島を過ぎると少し晴れてきた。今日は天候が安定しない。
先日行ってきた山陰地方と違い、山は無い。ひたすら平地を走っていく。
田んぼと住宅地がほとんどで、工場のような大きな建物は無い。
10:14,定刻に石巻駅に到着。

一旦改札を出る。結構大きな町だ。
ここで女川行きに乗り換えるが、掲示板を見ると女川行きは9:33となっている。これはおかしい。
たまたまそばにいた女性車掌に聞いてみたら遅れているとのこと。
すると丁度その遅れている列車がホームに入ってきた。2両編成のディーゼルカー(単線)だ。

この駅で切符を買った(330円)。10:36発車とのこと。事前に調べた時刻と同じ発車時刻だ。
女川行きは昨日からの大雪の影響で大幅に遅れているとの車内アナウンスがあった。
しかし今は雪は止み、晴れていた。
10:36発車。
「女川」を何と読むか。最初、「めかわ」と読むものだと思っていたが「おながわ」が正解だった。
石巻を出た頃には晴天に変わっていた。気温も上がってくることだろう。
朝早くから行動しているせいか、午前中がいつもより何倍も長く感じる。
普段の休日も夜更かしをしないで早寝早起きの方が健康で充実した時間を過ごすのが本当はいいのかもしれない。
大きな川を渡る。川の面に日光が反射してきらきら光っている。
晴天、実に気持ちのいい1日だ。
コーヒーのせいだろうか、トイレが近い。利尿作用が強いのであろう。だから乾燥肌になったに違いない。コーヒーをたくさん飲むようになってからだ。かゆくて夜も眠れない。
車内で写真を撮ることは避けよう。
あの津山行きワンマンカーでのトラウマ体験の二の舞は踏みたくない。
写真の代わりに録音するのがいいかもしれない。
車窓から見える住宅の多くが新しい。震災の後で再建されたのであろう。
「渡波(わたのは)」という駅で大量の客が降りた。
客が運転士に訊ねごとをしていた。この運転士は温厚のようだ。あの津山のヤツとは大違いだ。
やはりディーゼルカーの音はいい。車もそうだけど。
車窓からは海は見えない。
けっこう住宅が多い。どんな産業で生計を立てているのか。
万国浦、沢田を過ぎたら右手に海が見えてきた。何かの養殖をしているようだ。
海岸線は山で囲まれている。のどかだ。思わず安堵のためいきが出てくる。
海で浮きがたくさん浮いていた。
(次回に続く)
【ルート】
12月28日
関東某所⇒仙台⇒石巻⇒女川⇒前谷地⇒気仙沼(宿泊)
12月29日
気仙沼⇒一ノ関⇒盛岡⇒新函館北斗⇒北海道某所
以下、小旅行の記録である。
12月28日
5:58発、自宅最寄のバス停からJR某駅に向かう。
通勤時に利用するのと同じ時刻のバスだ。
JR某駅、6:25発普通列車に乗車、関東某駅着。
30分以上時間があるので、明日の北海道内特急の指定席券を購入した。
自動販売機では買えなかったので、みどりの窓口で直接購入。2,960円。
窓口は空いていた。しかし新幹線改札口を出ると、帰省客らしき人々が大勢いた。
あとスノボを背負った若者たちの姿も多く見かけた。もうコロナ前と同じくらいの混雑さだ。
待合室で時間をつぶす。
7:33、はやぶさ3号、新青森行きに乗車。



列車内は意外に空いていた。外は晴天だ。気持ちのいい冬の日の朝日。
旅はこれだからいい。昨日は4時間くらいしか寝ていない。その前の日もそうだ。
昨日は寝る前にコーヒーとビールを飲んだからトイレに3回も起きてしまった。だから余計寝不足だ。
しかし頭は冴えている。
仙台まで約1時間。あっという間だ。
仙台から先、石巻か女川のどちらで時間を長く過ごそうか。
スマホで両町の情報を調べる。女川の方が何となく良さそうだ。
魚介類の何かおいしいものでも食べることにしよう。
仙台方面の天気はどうなのだろう。今日の朝刊の天気予報では晴れマークだったが、テレビの天気予報では雪マークだった。
栃木あたりの田んぼは一面、霜が降りているように見えた。
そうだ。CDプレーヤーに、さっき駅で買った電池を入れておこう。これでチャイコの「悲愴」を聴くのだ。
これで旅情気分は倍化だ。
ふと車窓を見たら雪景色に変わっていた。場所はどこだろう。福島あたりか。
トンネルに入ると圧力で耳が痛くなる。
8:25、福島駅通過。かなり雪が積もっている。雪も降っているようだ。
仙台駅からの乗り換えは大丈夫だろうか。
しかし大きなトンネルを抜けると晴れだった。何という変わりよう。仙台の天候はそう悪くないに違いない。場所によってだいぶ違うものだ。
8:40、仙台着。
次の列車の乗り換えまでわずか。
新幹線改札を出て在来線の切符を買おうとしたが、販売機が混んでいる。
仕方ない。改札がスイカ対応だったのでスイカで入る。
エスカレーターを降りて、仙石線に乗り換える。


8:55発、高城町行き普通列車に乗車。電車だ。
陸前〇〇(メモ見逃す)までは地下を走行する。
地上に出ると晴れ、しかし雪はだいぶ積もっている。
同じ車両内に、半ズボンの小学生がいた。またミニスカートで素肌の中学生もいた。
この寒さなのに!。いったいどういう温度感覚なのだ。自分はタイツまで履いているというのに。
途中、今日気仙沼で再会する講習会で親しくなった宮城県在住の友人が住んでいる町の付近を通る。
神社が見える。
本塩釜から海が見えてきた。東塩釜から雪がちらついてきた。
今日は1日雪か?。天気予報はあまりあてにならない。
ホームでの停車時間は長めだ。ドアは開いたままなので寒い。
「陸前」で始まる駅がけっこうある。
海に小さな島がいくつか浮かんでいた。
陸前浜田に着くと雪がかなり降ってきた。女川では外に長くいられないだろう。
屋内で時間をつぶす所を見つけなければならない。
松島海岸駅で多くの乗客が降りた。観光客風だ。この寒いのに海岸を歩くというのか?。
松島と言えば日本三景の1つだったっけ?。
9:40、高城町着。

駅改札を出てトイレに急行。外はめちゃくちゃ寒く、雪がちらつく。
9:49発、石巻行きの快速、ディーゼル6両編成に乗り換える。


ここからは景色がかなり田舎となる。
右手に海が見えてきた。この路線は海沿いを走るようだ。
ディーゼルカー特有のエンジン音が響き渡る。ああ、最高にいい気分だ。
東松島を過ぎると少し晴れてきた。今日は天候が安定しない。
先日行ってきた山陰地方と違い、山は無い。ひたすら平地を走っていく。
田んぼと住宅地がほとんどで、工場のような大きな建物は無い。
10:14,定刻に石巻駅に到着。

一旦改札を出る。結構大きな町だ。
ここで女川行きに乗り換えるが、掲示板を見ると女川行きは9:33となっている。これはおかしい。
たまたまそばにいた女性車掌に聞いてみたら遅れているとのこと。
すると丁度その遅れている列車がホームに入ってきた。2両編成のディーゼルカー(単線)だ。

この駅で切符を買った(330円)。10:36発車とのこと。事前に調べた時刻と同じ発車時刻だ。
女川行きは昨日からの大雪の影響で大幅に遅れているとの車内アナウンスがあった。
しかし今は雪は止み、晴れていた。
10:36発車。
「女川」を何と読むか。最初、「めかわ」と読むものだと思っていたが「おながわ」が正解だった。
石巻を出た頃には晴天に変わっていた。気温も上がってくることだろう。
朝早くから行動しているせいか、午前中がいつもより何倍も長く感じる。
普段の休日も夜更かしをしないで早寝早起きの方が健康で充実した時間を過ごすのが本当はいいのかもしれない。
大きな川を渡る。川の面に日光が反射してきらきら光っている。
晴天、実に気持ちのいい1日だ。
コーヒーのせいだろうか、トイレが近い。利尿作用が強いのであろう。だから乾燥肌になったに違いない。コーヒーをたくさん飲むようになってからだ。かゆくて夜も眠れない。
車内で写真を撮ることは避けよう。
あの津山行きワンマンカーでのトラウマ体験の二の舞は踏みたくない。
写真の代わりに録音するのがいいかもしれない。
車窓から見える住宅の多くが新しい。震災の後で再建されたのであろう。
「渡波(わたのは)」という駅で大量の客が降りた。
客が運転士に訊ねごとをしていた。この運転士は温厚のようだ。あの津山のヤツとは大違いだ。
やはりディーゼルカーの音はいい。車もそうだけど。
車窓からは海は見えない。
けっこう住宅が多い。どんな産業で生計を立てているのか。
万国浦、沢田を過ぎたら右手に海が見えてきた。何かの養殖をしているようだ。
海岸線は山で囲まれている。のどかだ。思わず安堵のためいきが出てくる。
海で浮きがたくさん浮いていた。
(次回に続く)