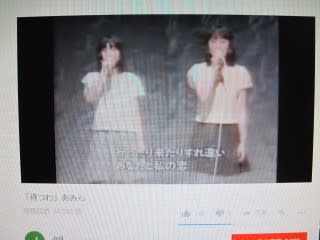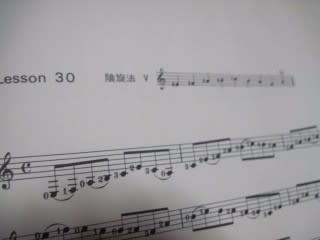五音音階陰旋法の曲で何かいい曲がないかと探していた。
日本の古くからある独自の楽器によるものがいいと思った。
直ぐに思いついたのは「篠笛」。
篠笛による演奏で、いい曲を見つけた。
「青葉の笛」。
作曲 田村虎蔵 (1873~1943)
すごくシンプルであるが、とても心に響く。
日本にしかない音楽。世界中のどこを探ししてもこのような音楽は無い。
こういう音楽を作れた昔の日本人は、素晴らしい感性を持っていたと思う。
篠笛ってすごく心に響いてくる。リコーダーやフルートとは全然違う。
いつかやってみたいと思っていた楽器。
たったひとつの楽器、単一の音でここまで人の気持ちを動かせるのは、楽器と演奏者の気持ちが微塵も乖離すことなく一体となっているからだと思う。
篠笛 青葉の笛
日本の古くからある独自の楽器によるものがいいと思った。
直ぐに思いついたのは「篠笛」。
篠笛による演奏で、いい曲を見つけた。
「青葉の笛」。
作曲 田村虎蔵 (1873~1943)
すごくシンプルであるが、とても心に響く。
日本にしかない音楽。世界中のどこを探ししてもこのような音楽は無い。
こういう音楽を作れた昔の日本人は、素晴らしい感性を持っていたと思う。
篠笛ってすごく心に響いてくる。リコーダーやフルートとは全然違う。
いつかやってみたいと思っていた楽器。
たったひとつの楽器、単一の音でここまで人の気持ちを動かせるのは、楽器と演奏者の気持ちが微塵も乖離すことなく一体となっているからだと思う。
篠笛 青葉の笛