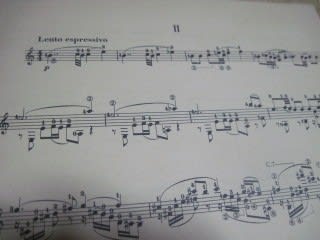時代劇史上、最高の作品「大江戸捜査網」のテーマ曲をYoutubeで見つけた。
1970年代半ばににテレビ東京で放映された不朽の名作だ。
初代の杉良太郎と2代目の里見浩太郎の時代が最も面白かった。というか、凄く感動した。
これ以上の出来の時代劇は無い。
時代劇を見るのあれば杉良太郎と里見浩太郎の時代の「大江戸捜査網」だけを見るに限る。
内容もさることながら、テーマ曲や数々の挿入音楽が素晴らしかった。もう最高だ。
今回はオープニングテーマ曲と、里見浩太郎の時代の初期のエンディングテーマ曲を貼り付ける。
里見浩太郎の時代の後期のエンディングテーマ曲が見つかったら、追加したい。
(挿入音楽ももしあったらそれも)
まず、初代の杉良太郎のオープニングテーマ曲。
大江戸捜査網 杉良太郎 1973年 - オープニング
次に里見浩太郎の時代の初期のオープニングテーマ曲。
大江戸捜査網 1974年 - オープニング
二刀流が最高にかっこいい。
次に里見浩太郎の時代の後期オープニングテーマ曲とエンディングテーマ曲。
大江戸捜査網 里見浩太朗版(お竜&風Ver) OP&ED
里見浩太郎の時代の初期のエンディングテーマ曲。
私の記憶では里見浩太郎が歌っていたように思ったが。
大江戸捜査網 里見浩太朗版 ED2(特殊) ながれ橋
1970年代半ばににテレビ東京で放映された不朽の名作だ。
初代の杉良太郎と2代目の里見浩太郎の時代が最も面白かった。というか、凄く感動した。
これ以上の出来の時代劇は無い。
時代劇を見るのあれば杉良太郎と里見浩太郎の時代の「大江戸捜査網」だけを見るに限る。
内容もさることながら、テーマ曲や数々の挿入音楽が素晴らしかった。もう最高だ。
今回はオープニングテーマ曲と、里見浩太郎の時代の初期のエンディングテーマ曲を貼り付ける。
里見浩太郎の時代の後期のエンディングテーマ曲が見つかったら、追加したい。
(挿入音楽ももしあったらそれも)
まず、初代の杉良太郎のオープニングテーマ曲。
大江戸捜査網 杉良太郎 1973年 - オープニング
次に里見浩太郎の時代の初期のオープニングテーマ曲。
大江戸捜査網 1974年 - オープニング
二刀流が最高にかっこいい。
次に里見浩太郎の時代の後期オープニングテーマ曲とエンディングテーマ曲。
大江戸捜査網 里見浩太朗版(お竜&風Ver) OP&ED
里見浩太郎の時代の初期のエンディングテーマ曲。
私の記憶では里見浩太郎が歌っていたように思ったが。
大江戸捜査網 里見浩太朗版 ED2(特殊) ながれ橋