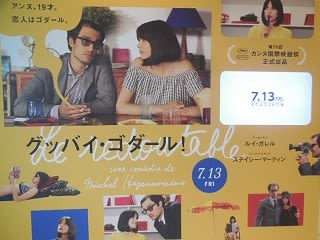
ジャン・リュック・ゴダールは、往年の映画ファンにとっては特別の名前だ。フランスのヌーヴェルヴァーグと言えば、まずこの人の名があがる。
最も好きな映画、影響を受けた映画のベスト3をあげろと言われれば、若いときは僕は次の3つを躊躇(ためら)いなくあげていた。
・「気狂いピエロ」(Pierrot le fou 監督:ジャン・リュック・ゴダール、1965年)
・「去年マリエンバートで」(L'Année dernière à Marienbad 監督:アラン・レネ、1961年)
・「大地のうた」(Pather Panchali 監督:サタジット・レイ、インド映画、1955年)
いずれも学生時代に見た映画だ。こうして並べてみれば、いずれもATG(アートシアター)の新宿文化で見たものだ。
年齢を重ねるにしたがい、いくつかの捨てがたい映画が出てきたが、ゴダールの「気狂いピエロ」のナンバーワンは変わらない。
*
では、ジャン・リュック・ゴダール作品のなかでの僕のベスト3をあげると、次のようになる。
①「気狂いピエロ」(Pierrot le fou、1965年)
アンナ・カリーナとジャン・ポール・ベルモンド主演の、僕にとっては普遍的な感動を持った映画だ。
最後の場面(シーン)は、強烈な印象だった。
恋人マリアンヌ(A・カリーナ)を銃殺したあと、顔をペンキで塗りたくりダイナマイトを自分の頭に巻き付けて火をつけたフェルディナン(J・P・ベルモンド)は、われに返り慌てて火を消そうとするが間に合わない。
煙の上がる岩壁の先に広がる地中海の青い海に、アルチュール・ランボーの詩「永遠」の一節が流れる。
また、見つかった、
何が、
永遠が、
海と溶け合う太陽が。
(小林秀雄訳)
僕は幕が下りた後も、しばらく立ち上がれなかった。
②「軽蔑」(Le mépris、1963年)
「B・B」(べべ)ことブリジット・バルドー主演の、地中海での映画撮影現場を舞台に、脚本家(ミシェル・ピッコリ)の妻で女優の揺れ動く女心を描いた映画。
それまでバルドーといえば「裸でご免なさい」や「素直な悪女」など、コケティッシュでセクシーだけが売りものと思っていたが、この映画では違った。
最初この映画を観たときは、まだ僕が女というものに対してよくわかっていなかったせいもあってか(今でもよくわかってはいないが)十分理解したとは自分でも思えなかった。それでアルベルト・モラヴィアの原作(大久保昭男訳)を読んで、なるほどと感動し直した経緯の映画である。
それで、「le mépris」という言葉がすっかり気に入って、「ル・メプリ…」を繰り返し呟いたりしたのだった。
③「勝手にしやがれ」(À bout de souffle、1959年)
ジャン・ポール・ベルモンドとジーン・セバーグ主演のヌーヴェルヴァーグを決定づけた映画で、ゴダールを一躍有名にした映画である。それにこの映画で、ベルモンドもアラン・ドロンに肩を並べるぐらいの人気スターにした。
僕が今でも面白いなと思っている場面は、前にも「勝手にしやがれ」の項で書いた、ベルモンドとセバーグのやりとりだ。
ベルモンドがセバーグに「ニューヨークでは、何人の男と寝た?」と訊く。
セバーグは、少し考えて、片方の指を広げ、もう片方の指を2本立てる。つまり、7人ということだ。
「あなたは?」と問われたベルモンドは、寝そべったまま、握った片方の手を広げて、また閉じて広げてを繰り返したのだった。
何人かわからないのだ。まあ、多くて数えてもいなかったのだろう。
思わず笑ってしまったが、ベルモンドは、そのあと、「多くはないな」と呟くのだった。
そして最後は、「最低だ」と呟き、自分の手で瞼(まぶた)をおろして、路上で死ぬ。
*
今月の7月初旬、新聞広告に「グッバイ・ゴダール!」(原題はLe Redoutable)のタイトルを見たとき、胸が躍った。
ゴダール……名前だけで胸に波を打たせる人間がどれほどいようか。
キャッチコピーに、「アンヌ、19才。パリに住む哲学科の学生。そして恋人はゴダール。――1968年、映画、恋、五月革命、少女が駆け抜けた青春の日々」とある。
そして、映画公開当日の7月13日の広告のヘッドコピーは、「ゴダールに恋した、1968年のパリ――。」
これで分かるようにこの映画は、1968年、フランス五月革命当時、すでにヌーヴェルヴァーグの旗手として特別な存在となっていたゴダールの当時の恋人、アンヌ・ビアゼムスキーの目から見たゴダールを描いたものである。実際この映画は、アンヌの自伝的小説「それからの彼女」(Un an après)にもとづいている。
監督はミシェル・アザナヴィシウス。ゴダール役にルイ・ガレル、アンヌ役にステイシー・マーティン。
1966年、女子学生のアンヌと知りあったゴダールは、フランスにおける毛沢東主義を描いた「中国女」(La Chinoise 、1967年)の主役に彼女を抜擢し、映画公開前に結婚する。
その前に、ゴダールは「女は女である」「女と男のいる舗道」「気狂いピエロ」などいくつものゴダールの映画に主演しているアンナ・カリーナと結婚して離婚している。
「アンナAnna」から「アンヌAnne」へとゴダールは移ったが……。
当時、アンヌ20歳。ゴダール37歳。
アンヌは16歳でロベール・ブレッソンの映画で女優としてデビューしたあと、ゴダールの「中国女」(1967年)の主演女優として脚光を浴び、そしてゴダールの妻として、熱い時代を走り抜けることになる。
「中国女」の作成には、当時毛沢東による中国文化大革命が起こり、中国を大きく揺れ動かしていた背景がある。
「グッバイ・ゴダール!」は、アンヌと天才といわれ時代の寵児だったゴダールとの愛を、1968年のパリ五月革命前夜の時代背景を通して描いていく。フランスの各地の大学では体制に反対する学生が立ち上がり、大規模なデモが行われて、文化や政治をも巻き込んだ大きな動きになっていく。
二人でデモに参加し、学生集会へ出向いて持論を放つゴダールだが、次第に学生たちとも乖離していく。
カンヌ国際映画祭を中止に追い込もうとするゴダールは、映画と政治を包括しようとするし、商業映画と決別すると言い放つ。そして、次第に周りともアンヌとも微妙な溝が生じ始める。
しかし、ゴダールは自分の生き方を変えようとはしない。映画は、そのゴダールの姿を辛辣に描いていく。あの熱い時代とともに。
*
この映画の時代のあと、72年ごろからアンヌとゴダールは事実上別離し、79年に正式に離婚している。
「グッバイ・ゴダール!」(Le Redoutable)は2017年のカンヌ国際映画祭にて主要部門のパルム・ドールに出品されたのち、同年9月にフランスで公開。
そしてアンヌ・ビアゼムスキーは、この映画が公開された2017年10月に死去している。
政治的に生きるとはどうあるべきなのか。
政治の季節だったあの時代。その後、政治や社会は変わったのか。
変わったのなら、どう変わったのか。それは、いい方向へ向かっていると言えるのか。
ジャン・リュック・ゴダールは、今でも問い続けているように思えるし、ゴダールは実際生き続けている。
あの時代の熱気はどこから来て、どこへ行ったのだろうか。
今年(2018年)のカンヌ国際映画祭のポスターは、ジャン・ポール・ベルモンドとアンナ・カリーナが互いの車中からキスをするシーンの、ゴダールの「気狂いピエロ」が用いられている。
1968年には、ゴダールを中心としたフランソワ・トリュフォーなどの映画人に中止に追いやられたカンヌ国際映画祭であるが、それでもゴダールは無視できない突出した映画監督であることの証左であろう。
ジャン・リュック・ゴダール、現在87歳。なおいまだ現役である。
今年のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に最新作「The Image Book」を出品し、スペシャル・パルムドールを受賞している。
*
1968年といえば、アメリカのベトナム反戦運動が世界的に広がり、フランスでは反体制を掲げて各地でゼネストが広まった「パリ五月革命」が、社会主義圏のチェコスロバキアでは「プラハの春」が起こった。
日本でも60年安保で萌芽した学生運動は全国の大学に深く根づいていた。それは、ベトナム反戦運動などとあい絡まって、1968年から翌69年にかけて大学の自治と解放に向かって東大闘争や、日大をはじめとする全共闘の闘争に広がっていく。
当時、学生生活が終わろうとしていた僕は、先鋭化する学生運動にとおについていけず、のちに歌われた「「いちご白書」をもう一度」のような心情で最後の学生生活を送っていた。
ゴダールやレネや大島渚、吉田喜重などの、いわゆるヌーヴェルヴァーグの映画を自分の心に映し出すことで、精神的なカタルシスを行っていたのかもしれない。
当時の時代や学生運動を扱った評論や回顧譚は小熊英二の「1968」から亀和田武の「60年代ポップ少年」や中野翠の「あのころ、早稲田で」まで何冊かあるが、政治の季節だった学生時代の心情は、僕は今でも素直に吐露することができない。
やはりまだ棘が刺さっているのだ。
1968年……。あの頃の時代は世界各地で確かに燃えていた。そして、傷も残した。
最も好きな映画、影響を受けた映画のベスト3をあげろと言われれば、若いときは僕は次の3つを躊躇(ためら)いなくあげていた。
・「気狂いピエロ」(Pierrot le fou 監督:ジャン・リュック・ゴダール、1965年)
・「去年マリエンバートで」(L'Année dernière à Marienbad 監督:アラン・レネ、1961年)
・「大地のうた」(Pather Panchali 監督:サタジット・レイ、インド映画、1955年)
いずれも学生時代に見た映画だ。こうして並べてみれば、いずれもATG(アートシアター)の新宿文化で見たものだ。
年齢を重ねるにしたがい、いくつかの捨てがたい映画が出てきたが、ゴダールの「気狂いピエロ」のナンバーワンは変わらない。
*
では、ジャン・リュック・ゴダール作品のなかでの僕のベスト3をあげると、次のようになる。
①「気狂いピエロ」(Pierrot le fou、1965年)
アンナ・カリーナとジャン・ポール・ベルモンド主演の、僕にとっては普遍的な感動を持った映画だ。
最後の場面(シーン)は、強烈な印象だった。
恋人マリアンヌ(A・カリーナ)を銃殺したあと、顔をペンキで塗りたくりダイナマイトを自分の頭に巻き付けて火をつけたフェルディナン(J・P・ベルモンド)は、われに返り慌てて火を消そうとするが間に合わない。
煙の上がる岩壁の先に広がる地中海の青い海に、アルチュール・ランボーの詩「永遠」の一節が流れる。
また、見つかった、
何が、
永遠が、
海と溶け合う太陽が。
(小林秀雄訳)
僕は幕が下りた後も、しばらく立ち上がれなかった。
②「軽蔑」(Le mépris、1963年)
「B・B」(べべ)ことブリジット・バルドー主演の、地中海での映画撮影現場を舞台に、脚本家(ミシェル・ピッコリ)の妻で女優の揺れ動く女心を描いた映画。
それまでバルドーといえば「裸でご免なさい」や「素直な悪女」など、コケティッシュでセクシーだけが売りものと思っていたが、この映画では違った。
最初この映画を観たときは、まだ僕が女というものに対してよくわかっていなかったせいもあってか(今でもよくわかってはいないが)十分理解したとは自分でも思えなかった。それでアルベルト・モラヴィアの原作(大久保昭男訳)を読んで、なるほどと感動し直した経緯の映画である。
それで、「le mépris」という言葉がすっかり気に入って、「ル・メプリ…」を繰り返し呟いたりしたのだった。
③「勝手にしやがれ」(À bout de souffle、1959年)
ジャン・ポール・ベルモンドとジーン・セバーグ主演のヌーヴェルヴァーグを決定づけた映画で、ゴダールを一躍有名にした映画である。それにこの映画で、ベルモンドもアラン・ドロンに肩を並べるぐらいの人気スターにした。
僕が今でも面白いなと思っている場面は、前にも「勝手にしやがれ」の項で書いた、ベルモンドとセバーグのやりとりだ。
ベルモンドがセバーグに「ニューヨークでは、何人の男と寝た?」と訊く。
セバーグは、少し考えて、片方の指を広げ、もう片方の指を2本立てる。つまり、7人ということだ。
「あなたは?」と問われたベルモンドは、寝そべったまま、握った片方の手を広げて、また閉じて広げてを繰り返したのだった。
何人かわからないのだ。まあ、多くて数えてもいなかったのだろう。
思わず笑ってしまったが、ベルモンドは、そのあと、「多くはないな」と呟くのだった。
そして最後は、「最低だ」と呟き、自分の手で瞼(まぶた)をおろして、路上で死ぬ。
*
今月の7月初旬、新聞広告に「グッバイ・ゴダール!」(原題はLe Redoutable)のタイトルを見たとき、胸が躍った。
ゴダール……名前だけで胸に波を打たせる人間がどれほどいようか。
キャッチコピーに、「アンヌ、19才。パリに住む哲学科の学生。そして恋人はゴダール。――1968年、映画、恋、五月革命、少女が駆け抜けた青春の日々」とある。
そして、映画公開当日の7月13日の広告のヘッドコピーは、「ゴダールに恋した、1968年のパリ――。」
これで分かるようにこの映画は、1968年、フランス五月革命当時、すでにヌーヴェルヴァーグの旗手として特別な存在となっていたゴダールの当時の恋人、アンヌ・ビアゼムスキーの目から見たゴダールを描いたものである。実際この映画は、アンヌの自伝的小説「それからの彼女」(Un an après)にもとづいている。
監督はミシェル・アザナヴィシウス。ゴダール役にルイ・ガレル、アンヌ役にステイシー・マーティン。
1966年、女子学生のアンヌと知りあったゴダールは、フランスにおける毛沢東主義を描いた「中国女」(La Chinoise 、1967年)の主役に彼女を抜擢し、映画公開前に結婚する。
その前に、ゴダールは「女は女である」「女と男のいる舗道」「気狂いピエロ」などいくつものゴダールの映画に主演しているアンナ・カリーナと結婚して離婚している。
「アンナAnna」から「アンヌAnne」へとゴダールは移ったが……。
当時、アンヌ20歳。ゴダール37歳。
アンヌは16歳でロベール・ブレッソンの映画で女優としてデビューしたあと、ゴダールの「中国女」(1967年)の主演女優として脚光を浴び、そしてゴダールの妻として、熱い時代を走り抜けることになる。
「中国女」の作成には、当時毛沢東による中国文化大革命が起こり、中国を大きく揺れ動かしていた背景がある。
「グッバイ・ゴダール!」は、アンヌと天才といわれ時代の寵児だったゴダールとの愛を、1968年のパリ五月革命前夜の時代背景を通して描いていく。フランスの各地の大学では体制に反対する学生が立ち上がり、大規模なデモが行われて、文化や政治をも巻き込んだ大きな動きになっていく。
二人でデモに参加し、学生集会へ出向いて持論を放つゴダールだが、次第に学生たちとも乖離していく。
カンヌ国際映画祭を中止に追い込もうとするゴダールは、映画と政治を包括しようとするし、商業映画と決別すると言い放つ。そして、次第に周りともアンヌとも微妙な溝が生じ始める。
しかし、ゴダールは自分の生き方を変えようとはしない。映画は、そのゴダールの姿を辛辣に描いていく。あの熱い時代とともに。
*
この映画の時代のあと、72年ごろからアンヌとゴダールは事実上別離し、79年に正式に離婚している。
「グッバイ・ゴダール!」(Le Redoutable)は2017年のカンヌ国際映画祭にて主要部門のパルム・ドールに出品されたのち、同年9月にフランスで公開。
そしてアンヌ・ビアゼムスキーは、この映画が公開された2017年10月に死去している。
政治的に生きるとはどうあるべきなのか。
政治の季節だったあの時代。その後、政治や社会は変わったのか。
変わったのなら、どう変わったのか。それは、いい方向へ向かっていると言えるのか。
ジャン・リュック・ゴダールは、今でも問い続けているように思えるし、ゴダールは実際生き続けている。
あの時代の熱気はどこから来て、どこへ行ったのだろうか。
今年(2018年)のカンヌ国際映画祭のポスターは、ジャン・ポール・ベルモンドとアンナ・カリーナが互いの車中からキスをするシーンの、ゴダールの「気狂いピエロ」が用いられている。
1968年には、ゴダールを中心としたフランソワ・トリュフォーなどの映画人に中止に追いやられたカンヌ国際映画祭であるが、それでもゴダールは無視できない突出した映画監督であることの証左であろう。
ジャン・リュック・ゴダール、現在87歳。なおいまだ現役である。
今年のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に最新作「The Image Book」を出品し、スペシャル・パルムドールを受賞している。
*
1968年といえば、アメリカのベトナム反戦運動が世界的に広がり、フランスでは反体制を掲げて各地でゼネストが広まった「パリ五月革命」が、社会主義圏のチェコスロバキアでは「プラハの春」が起こった。
日本でも60年安保で萌芽した学生運動は全国の大学に深く根づいていた。それは、ベトナム反戦運動などとあい絡まって、1968年から翌69年にかけて大学の自治と解放に向かって東大闘争や、日大をはじめとする全共闘の闘争に広がっていく。
当時、学生生活が終わろうとしていた僕は、先鋭化する学生運動にとおについていけず、のちに歌われた「「いちご白書」をもう一度」のような心情で最後の学生生活を送っていた。
ゴダールやレネや大島渚、吉田喜重などの、いわゆるヌーヴェルヴァーグの映画を自分の心に映し出すことで、精神的なカタルシスを行っていたのかもしれない。
当時の時代や学生運動を扱った評論や回顧譚は小熊英二の「1968」から亀和田武の「60年代ポップ少年」や中野翠の「あのころ、早稲田で」まで何冊かあるが、政治の季節だった学生時代の心情は、僕は今でも素直に吐露することができない。
やはりまだ棘が刺さっているのだ。
1968年……。あの頃の時代は世界各地で確かに燃えていた。そして、傷も残した。












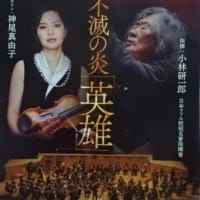

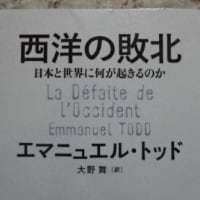










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます