
富山といえば、昔から薬売りが有名だ。
僕が小さい頃は、何種類かの薬がセットになっているのを各家庭に置いて行き、時々家を周っては、使った分だけ料金を取り、なくなった薬は補充して帰っていく行商人のおじさんがいた。富山の薬売りだった。
いつの頃からか薬の行商人は見なくなったが、各地にドラッグストアーができ薬が簡単に入手できるようになったので、職が奪われたのだろう。それでも、少なくなったが今でも残っているという。
そういえば10年位前であろうか、母が生きていたときのことだ。僕が佐賀の実家に帰ったときのこと、若い男が「こんにちは」とやってきた。そして、家の玄関脇に置いてあるドリンク剤(数本の小瓶)を交換しますという。聞けば栄養ドリンクのような小型の飲料水(瓶)で、飲んだ分だけ料金をもらいますが、飲んでいなくても定期的に新しいのと交換に伺っていますという。
僕は母に確認して、飲まないからもう置かないでくださいと言って断ったのだが、飲まなくても構いませんからとか契約されたものは本社の了承がないと私個人では解約は難しいとか、相当粘られた記憶がある。あれは、新しい形を変えた薬の行商人かもしれない。
*
富山には八尾の「おわら風の盆」を見に来たのだが、富山の市内も見るつもりではいた。
風の盆の踊りは夕方からなので、富山に着いた次の日の9月2日の午前中は、駅から北西にある丘陵のふもとの富山市民俗民芸村に行くことに。
まず、民俗民芸村の近くにある五百羅漢の像を見ることにした。石像が段状に整然と並んでいる。おそらく500体以上あるようだ。
若いとき、大分県中津市の耶馬渓(やばけい)に行ったとき、羅漢寺に五百羅漢があった。五百羅漢は、各地にあるようだ。
陶芸館は、市内に建てられた豪農の住宅の一部を移築した建物だが、頑強な構造ながら木の造りが美しい。なかで、全国各地の暮らしのやきものを紹介している。
売薬資料館は、その名の通り富山の薬の歴史と資料を展示してある。
別館の「旧密田家土蔵」は、富山を代表する売薬商家であった密田家に残されていた資料を展示してあるもので、顧客名簿や行商において守らなければならないことなどが書かれた資料など興味深い資料があった。
ここの資料館で貰った折りたたんだ紙風船は、かつて行商のときに土産として配ったものであった。油紙の色付きの紙風船を手に取った途端、僕の遠い記憶を甦らせた。確かに、薬の交換のときに、薬売りのおじさんが置いていった。僕ら子供は、それを膨らませて遊んだことがある。今の子どもなら喜びそうもない他愛ないものだが、当時の子どもには嬉しかった。
*
9月1日、2日と越中八尾に「風の盆」を見に行ったので(前ブログ「富山の旅①」参照)、9月3日は富山市内見物とした。
富山市の北、富山湾に面した町、岩瀬に行くことにした。
岩瀬は、かつて江戸から明治時代にかけて栄えた北前船文化が色濃く残る港町である。
富山駅の正面に当たる南口から、地下道で北口に出る。この北口に新型路面電車ともいえるライトレールの出発停車場がある。アムステルダムを走るトラムのようなこのライトレールは、富山駅北から港の岩瀬浜までを約25分で往復している洒落た電車である。
このライトレールに乗り、終点岩瀬浜の一つ手前の東岩瀬で降りて、街を散策することに。
街は道に沿って古い家並みが続き、一昔前の町に迷い込んだかのようである。特に北前船廻船問屋の明治11年に建造されたという森家はそのままの形で開放されていて(ただし入館料大人100円)、往時の生活を見ることができる。
港の近くにあるカナル会館で昼食をとったあと、運河を走る船で富山市内へ戻ることにした。「冨岩(ふがん)水上ライン」といって、岩瀬浜から富山駅北の冨岩運河環水公園までの5.1kmを約70分で遊覧し、料金1500円である。(写真)
僕は列車が好きだが、船も好きだ。旅の途中、舟廻り、舟遊びがあると乗りたくなる。
このクルーズは、海辺から街中へのゆったりとした船航である。
船のなかでは、季節柄だろう、船のガイドの女性が風の盆の格好をしていて、踊りも披露してくれた(おそらく25歳を超えていたが)。
この運河は上流と下流の水位差が2.5mあり、その水位の調整門である中島閘門(こうもん)を通るので、段差の調整段階をじかに見ることができた。ガイドの人が、パナマ運河を例に説明してくれるのが何とも面白い。
水郷潮来に行ったときは、「潮来花嫁さん」の歌を聴きながら川を下る舟廻りをしたが、そのときも閘門があった。といっても、冨岩運河は潮来より規模が違って大きい。パナマ運河よりはるかに小さいが。
終点の冨岩運河環水公園は、富山市民の憩いの場のようだったが、暑いのでとりあえずホテルに戻る。
夜は、駅の南口の繁華街のなかの和食屋で富山料理を。
八尾で鱒寿司は食べたので、これはパス。
何といっても魚が美味い。白エビは富山ではどこでも付きもののようだ。これはカラ揚げがいい。
僕が小さい頃は、何種類かの薬がセットになっているのを各家庭に置いて行き、時々家を周っては、使った分だけ料金を取り、なくなった薬は補充して帰っていく行商人のおじさんがいた。富山の薬売りだった。
いつの頃からか薬の行商人は見なくなったが、各地にドラッグストアーができ薬が簡単に入手できるようになったので、職が奪われたのだろう。それでも、少なくなったが今でも残っているという。
そういえば10年位前であろうか、母が生きていたときのことだ。僕が佐賀の実家に帰ったときのこと、若い男が「こんにちは」とやってきた。そして、家の玄関脇に置いてあるドリンク剤(数本の小瓶)を交換しますという。聞けば栄養ドリンクのような小型の飲料水(瓶)で、飲んだ分だけ料金をもらいますが、飲んでいなくても定期的に新しいのと交換に伺っていますという。
僕は母に確認して、飲まないからもう置かないでくださいと言って断ったのだが、飲まなくても構いませんからとか契約されたものは本社の了承がないと私個人では解約は難しいとか、相当粘られた記憶がある。あれは、新しい形を変えた薬の行商人かもしれない。
*
富山には八尾の「おわら風の盆」を見に来たのだが、富山の市内も見るつもりではいた。
風の盆の踊りは夕方からなので、富山に着いた次の日の9月2日の午前中は、駅から北西にある丘陵のふもとの富山市民俗民芸村に行くことに。
まず、民俗民芸村の近くにある五百羅漢の像を見ることにした。石像が段状に整然と並んでいる。おそらく500体以上あるようだ。
若いとき、大分県中津市の耶馬渓(やばけい)に行ったとき、羅漢寺に五百羅漢があった。五百羅漢は、各地にあるようだ。
陶芸館は、市内に建てられた豪農の住宅の一部を移築した建物だが、頑強な構造ながら木の造りが美しい。なかで、全国各地の暮らしのやきものを紹介している。
売薬資料館は、その名の通り富山の薬の歴史と資料を展示してある。
別館の「旧密田家土蔵」は、富山を代表する売薬商家であった密田家に残されていた資料を展示してあるもので、顧客名簿や行商において守らなければならないことなどが書かれた資料など興味深い資料があった。
ここの資料館で貰った折りたたんだ紙風船は、かつて行商のときに土産として配ったものであった。油紙の色付きの紙風船を手に取った途端、僕の遠い記憶を甦らせた。確かに、薬の交換のときに、薬売りのおじさんが置いていった。僕ら子供は、それを膨らませて遊んだことがある。今の子どもなら喜びそうもない他愛ないものだが、当時の子どもには嬉しかった。
*
9月1日、2日と越中八尾に「風の盆」を見に行ったので(前ブログ「富山の旅①」参照)、9月3日は富山市内見物とした。
富山市の北、富山湾に面した町、岩瀬に行くことにした。
岩瀬は、かつて江戸から明治時代にかけて栄えた北前船文化が色濃く残る港町である。
富山駅の正面に当たる南口から、地下道で北口に出る。この北口に新型路面電車ともいえるライトレールの出発停車場がある。アムステルダムを走るトラムのようなこのライトレールは、富山駅北から港の岩瀬浜までを約25分で往復している洒落た電車である。
このライトレールに乗り、終点岩瀬浜の一つ手前の東岩瀬で降りて、街を散策することに。
街は道に沿って古い家並みが続き、一昔前の町に迷い込んだかのようである。特に北前船廻船問屋の明治11年に建造されたという森家はそのままの形で開放されていて(ただし入館料大人100円)、往時の生活を見ることができる。
港の近くにあるカナル会館で昼食をとったあと、運河を走る船で富山市内へ戻ることにした。「冨岩(ふがん)水上ライン」といって、岩瀬浜から富山駅北の冨岩運河環水公園までの5.1kmを約70分で遊覧し、料金1500円である。(写真)
僕は列車が好きだが、船も好きだ。旅の途中、舟廻り、舟遊びがあると乗りたくなる。
このクルーズは、海辺から街中へのゆったりとした船航である。
船のなかでは、季節柄だろう、船のガイドの女性が風の盆の格好をしていて、踊りも披露してくれた(おそらく25歳を超えていたが)。
この運河は上流と下流の水位差が2.5mあり、その水位の調整門である中島閘門(こうもん)を通るので、段差の調整段階をじかに見ることができた。ガイドの人が、パナマ運河を例に説明してくれるのが何とも面白い。
水郷潮来に行ったときは、「潮来花嫁さん」の歌を聴きながら川を下る舟廻りをしたが、そのときも閘門があった。といっても、冨岩運河は潮来より規模が違って大きい。パナマ運河よりはるかに小さいが。
終点の冨岩運河環水公園は、富山市民の憩いの場のようだったが、暑いのでとりあえずホテルに戻る。
夜は、駅の南口の繁華街のなかの和食屋で富山料理を。
八尾で鱒寿司は食べたので、これはパス。
何といっても魚が美味い。白エビは富山ではどこでも付きもののようだ。これはカラ揚げがいい。











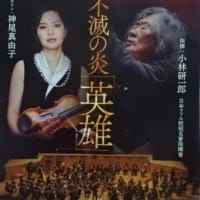

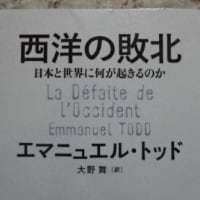











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます