
指宿を出発して、終着駅の枕崎に着いたのは昼の12時52分だった。僕のようにバッグを持った旅行者も含めて、数人が下車した。
静かに列車が止まっている線路の先に目をやれば、これから先は線路はないという印の、標的のようなマークの「車止め」がある。
列車(電車)も、車止めがあるので、これ以上進めないし、進むことに気を配る必要もないという感じで、すっかり気が抜けたように誰もいないホームに停車している。
枕崎の駅は、無人駅なのにきれいな建物だ。
駅前は広いロータリーになっていて、人はあまり見かけないが開放感がある。
これから鹿児島中央駅に戻る列車の時刻を見ると、次の13時18分はあまりにも時間がないので、その次は16時3分であった。
バスの切符売り場の窓口があったので、のぞいてみると親切なおばさんがいて、鹿児島中央駅に行くバスが1時間に1本出ていると教えてくれた。来たのと同じコースをJRで戻るのも策がないので、バスで薩摩半島を縦断するのもいいなあと、バスにすることにした。
枕崎の先に坊津(ぼうのつ)という港町がある。遣唐使船の寄港地だったという古い港である。
僕が坊津には行けますかと訊くと、窓口のおばさんはここからバスが出ていますが、本数が少ないので帰るのが遅くなりますよ、と言う。僕が、それでは坊津に行くのは無理かなと言って考えていると、これから坊津を循環してここに戻ってくるバスがありますよと教えてくれた。
なるほど、坊津に降りなくとも坊津の街一帯を周ってくれば観光周遊バスみたいで、それもいいアイディアだと、坊津を循環するバスに乗ることに決めた。
次の循環バスは14時25分発で、枕崎には15時18分に戻ってくるのだった。それに、1日5本しかなく最終の循環バスだった。
まだバスの出発まで1時間ぐらいあるので、案内所に行って、昼食のためにこの辺で美味しい店はありませんか、と訊くと、威勢のいいおばさんが、すぐ前の店を指さした。そして、少し考えて付け加えた。バスにはまだ時間があるのだから、海辺まで歩いて「お魚センター」へ行けばいいよ。その近くにバスの停留所もあるから、バスはそこから乗るといい、と言って町の地図をくれた。
地図を見ながら、枕崎の街中を歩き港へ出た。枕崎の港は静かだった。
港のなかほどに、「お魚センター」はあった。建物の中に入ると、魚介類や海産物を売る店が並んでいた。その中に、食事を出す小さな店があった。その店に入ったら、もう終わったよと店の人が言った。そして、厨房をのぞきこんで、丼物が一つぐらいあるかな、と言った。僕は丼物は何ですかと訊くと、カツオ丼だと答えた。
枕崎はカツオの産地だ。願ってもないものが残っていた。
カツオ丼を食べて、バス通りへ出た。橋の麓の郵便局の前がバス停だった。
バス停のベンチには、初老の男性が座っていた。立っている僕のところへ、そのおじさんは近づいてきて、誰かと話したかったのか、僕にどこから来たのですか、と訊いた。
僕は、東京からと答えたら、へぇー、東京から、そらまた、どうして、と驚いた顔をした。旅行ですと答えたら、これからどこへ行くのですかと言うので、坊津へと答えたら、さらに驚いた顔をして、東京から坊津へねえ、へえ、坊津へねえ、と呆れたのか感心したのか分からない調子で、珍しいと盛んに言った。
おじさんは、私は坊津へ住んでいますけど、坊津はなんもなかですよ、人口はどんどん減っていますし、空き家が増えてばかりで、と嘆くように寂しく言った。
僕が、前の会社勤め時代の同僚が坊津出身で、その彼の父親は長いこと地元で町長だったそうなんです。そう言って、彼の名字を告げると、おじさんは、よく知っていますよ、今も家がありますが、誰かほかの人が住んでいますよ、と感慨深そうに言った。私が住んでいるところは、そこから少し離れていますが、と付け加えた。
そして、今は一人で住んでいると言った。息子が一人いるが、今は鹿児島市に住んでいる。だから、会おうと思えば会えるんだがね、と独り言のようにつぶやいた。
僕が坊津の町を見たかったのは、実際、出版社時代の同僚の故郷がどんなところか見たかったのだ。僕は彼と同じ部署にいたこともあって気が合い、よく食事をしたり飲みに行ったりした仲だった。ところが、会社を辞めたあと彼は急逝した。
彼が、坊津は町に信号が一つもないんだよ、と言っていたのを思い出す。海に沿って道が周っているから、といった理由が、どんな町だろうと僕の想像をかきたてた。僕は佐賀の実家の田舎の町とて信号はあるなあと考えたのを思い出す。
今は信号があるのか知らないが、坊津は鄙びた港町だと思い描いていた。その古い町、坊津町は、今は合併して南さつま市となっている。
*
バスは枕崎を出発して山道に入ったあと、海辺に出た。そこが坊津だ。坊津の町に入ったあとは、バスは曲がりくねって街中を通った。
バスの窓からは、海を囲うように家々が並んでいるのが見えた。海に寄り沿った家並みを見下ろしていたから、バスが走る道は高台といえる。坊津は、僕が考えていたような鄙びた街ではなく、きれいな街だった。平地が少ないせいか、家と家は密接しているが、こぎれいな家が建ち並んでいる。(写真)
入り江がいくつも入り組んでいるのか、港は一つではなくいくつか分かれてあった。家並も港ごとに分かれて存在していた。
枕崎から乗った例のおじさんが次に下車すると目で挨拶をした。僕が、彼の家は?と慌てて訊くと、あっ、もう過ぎてしまった、教えなくて悪かった、と言って、バスを降りた。僕も、では、お元気で、と別れの挨拶をした。
おそらく、あのおじさんとはもう二度と会うことはないだろう。坊津の街も、また来るかどうかわからない。
もうこの街並みと景色は、二度と見ることはないかもしれないと思った。
バスは海辺から迂回するように離れて、田畑のなかを走った。海ではないここも坊津の町だと思うと、意外な感じがした。
バスは、再び枕崎の街中に戻った。最初に乗った郵便局の前で降りて、また港へ出た。ゆっくり枕崎の港沿いに歩いた。
海辺で、運送会社の運転手だろうか、大型トラックの横で若い男たちが数人座り込んで話しこんでいた。ここにも、青春の悩みと喜びがあるのだろう。
バスの出発の時刻に合わせて、枕崎の駅に戻った。
鹿児島中央駅を通る金生町行きのバスは、枕崎の駅前を16時に出発した。
バスは、薩摩半島を斜めに縦断するように山間部を走った。そして、17時52分に鹿児島中央駅に着いた。
すぐさま18時03分発の新幹線「さくら」に乗った。列車に乗ったあと、鹿児島にもう1泊すればよかったと思ったが、列車は1時間20分余で新鳥栖に着いた。
そこから佐世保線で佐賀駅で降りて、見慣れた佐賀の街の、見慣れた中華屋に入って、夜の食事をした。
静かに列車が止まっている線路の先に目をやれば、これから先は線路はないという印の、標的のようなマークの「車止め」がある。
列車(電車)も、車止めがあるので、これ以上進めないし、進むことに気を配る必要もないという感じで、すっかり気が抜けたように誰もいないホームに停車している。
枕崎の駅は、無人駅なのにきれいな建物だ。
駅前は広いロータリーになっていて、人はあまり見かけないが開放感がある。
これから鹿児島中央駅に戻る列車の時刻を見ると、次の13時18分はあまりにも時間がないので、その次は16時3分であった。
バスの切符売り場の窓口があったので、のぞいてみると親切なおばさんがいて、鹿児島中央駅に行くバスが1時間に1本出ていると教えてくれた。来たのと同じコースをJRで戻るのも策がないので、バスで薩摩半島を縦断するのもいいなあと、バスにすることにした。
枕崎の先に坊津(ぼうのつ)という港町がある。遣唐使船の寄港地だったという古い港である。
僕が坊津には行けますかと訊くと、窓口のおばさんはここからバスが出ていますが、本数が少ないので帰るのが遅くなりますよ、と言う。僕が、それでは坊津に行くのは無理かなと言って考えていると、これから坊津を循環してここに戻ってくるバスがありますよと教えてくれた。
なるほど、坊津に降りなくとも坊津の街一帯を周ってくれば観光周遊バスみたいで、それもいいアイディアだと、坊津を循環するバスに乗ることに決めた。
次の循環バスは14時25分発で、枕崎には15時18分に戻ってくるのだった。それに、1日5本しかなく最終の循環バスだった。
まだバスの出発まで1時間ぐらいあるので、案内所に行って、昼食のためにこの辺で美味しい店はありませんか、と訊くと、威勢のいいおばさんが、すぐ前の店を指さした。そして、少し考えて付け加えた。バスにはまだ時間があるのだから、海辺まで歩いて「お魚センター」へ行けばいいよ。その近くにバスの停留所もあるから、バスはそこから乗るといい、と言って町の地図をくれた。
地図を見ながら、枕崎の街中を歩き港へ出た。枕崎の港は静かだった。
港のなかほどに、「お魚センター」はあった。建物の中に入ると、魚介類や海産物を売る店が並んでいた。その中に、食事を出す小さな店があった。その店に入ったら、もう終わったよと店の人が言った。そして、厨房をのぞきこんで、丼物が一つぐらいあるかな、と言った。僕は丼物は何ですかと訊くと、カツオ丼だと答えた。
枕崎はカツオの産地だ。願ってもないものが残っていた。
カツオ丼を食べて、バス通りへ出た。橋の麓の郵便局の前がバス停だった。
バス停のベンチには、初老の男性が座っていた。立っている僕のところへ、そのおじさんは近づいてきて、誰かと話したかったのか、僕にどこから来たのですか、と訊いた。
僕は、東京からと答えたら、へぇー、東京から、そらまた、どうして、と驚いた顔をした。旅行ですと答えたら、これからどこへ行くのですかと言うので、坊津へと答えたら、さらに驚いた顔をして、東京から坊津へねえ、へえ、坊津へねえ、と呆れたのか感心したのか分からない調子で、珍しいと盛んに言った。
おじさんは、私は坊津へ住んでいますけど、坊津はなんもなかですよ、人口はどんどん減っていますし、空き家が増えてばかりで、と嘆くように寂しく言った。
僕が、前の会社勤め時代の同僚が坊津出身で、その彼の父親は長いこと地元で町長だったそうなんです。そう言って、彼の名字を告げると、おじさんは、よく知っていますよ、今も家がありますが、誰かほかの人が住んでいますよ、と感慨深そうに言った。私が住んでいるところは、そこから少し離れていますが、と付け加えた。
そして、今は一人で住んでいると言った。息子が一人いるが、今は鹿児島市に住んでいる。だから、会おうと思えば会えるんだがね、と独り言のようにつぶやいた。
僕が坊津の町を見たかったのは、実際、出版社時代の同僚の故郷がどんなところか見たかったのだ。僕は彼と同じ部署にいたこともあって気が合い、よく食事をしたり飲みに行ったりした仲だった。ところが、会社を辞めたあと彼は急逝した。
彼が、坊津は町に信号が一つもないんだよ、と言っていたのを思い出す。海に沿って道が周っているから、といった理由が、どんな町だろうと僕の想像をかきたてた。僕は佐賀の実家の田舎の町とて信号はあるなあと考えたのを思い出す。
今は信号があるのか知らないが、坊津は鄙びた港町だと思い描いていた。その古い町、坊津町は、今は合併して南さつま市となっている。
*
バスは枕崎を出発して山道に入ったあと、海辺に出た。そこが坊津だ。坊津の町に入ったあとは、バスは曲がりくねって街中を通った。
バスの窓からは、海を囲うように家々が並んでいるのが見えた。海に寄り沿った家並みを見下ろしていたから、バスが走る道は高台といえる。坊津は、僕が考えていたような鄙びた街ではなく、きれいな街だった。平地が少ないせいか、家と家は密接しているが、こぎれいな家が建ち並んでいる。(写真)
入り江がいくつも入り組んでいるのか、港は一つではなくいくつか分かれてあった。家並も港ごとに分かれて存在していた。
枕崎から乗った例のおじさんが次に下車すると目で挨拶をした。僕が、彼の家は?と慌てて訊くと、あっ、もう過ぎてしまった、教えなくて悪かった、と言って、バスを降りた。僕も、では、お元気で、と別れの挨拶をした。
おそらく、あのおじさんとはもう二度と会うことはないだろう。坊津の街も、また来るかどうかわからない。
もうこの街並みと景色は、二度と見ることはないかもしれないと思った。
バスは海辺から迂回するように離れて、田畑のなかを走った。海ではないここも坊津の町だと思うと、意外な感じがした。
バスは、再び枕崎の街中に戻った。最初に乗った郵便局の前で降りて、また港へ出た。ゆっくり枕崎の港沿いに歩いた。
海辺で、運送会社の運転手だろうか、大型トラックの横で若い男たちが数人座り込んで話しこんでいた。ここにも、青春の悩みと喜びがあるのだろう。
バスの出発の時刻に合わせて、枕崎の駅に戻った。
鹿児島中央駅を通る金生町行きのバスは、枕崎の駅前を16時に出発した。
バスは、薩摩半島を斜めに縦断するように山間部を走った。そして、17時52分に鹿児島中央駅に着いた。
すぐさま18時03分発の新幹線「さくら」に乗った。列車に乗ったあと、鹿児島にもう1泊すればよかったと思ったが、列車は1時間20分余で新鳥栖に着いた。
そこから佐世保線で佐賀駅で降りて、見慣れた佐賀の街の、見慣れた中華屋に入って、夜の食事をした。













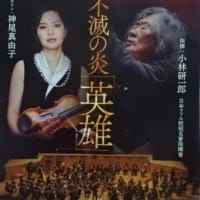

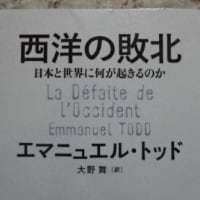









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます