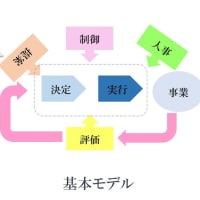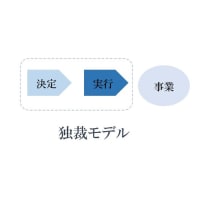パレスチナガザ地区の完全制圧を企図しているイスラエルは、同地区に対する核兵器の使用をも視野に入れているのかもしれません。同地区の地下に張り巡らされているトンネルは最も深い箇所で地下80メートルともされ、通常の地中貫通爆弾では破壊できないからです。戦術核を使用すれば目的を達成できるのですから、少なくともイスラエル軍の核戦略上の選択肢の一つではあるのでしょう。何と申しましても、公表はされてはいないものの、イスラエルは、核兵器を保有しているのですから。
先日、核兵器使用を‘選択肢の一つ’として仄めかしたアミハイ・エリヤフエルサレム問題・遺産相は、ネタニヤフ首相によって一時停職の処分を受けたのも、‘フェイク発信’が咎められたというよりも、迂闊にも極秘作戦を漏らしてしまったからなのかもしれません。しかも、同発言は、イスラエルが核保有国であることを、暗に認めたことをも意味します。何れにしましても、イスラエルは、核保有国という立場にあり、同兵器をめぐる発言は、自ずと国際社会全体に強い衝撃を与えてしまうのです。
イスラエルは、核保有国とはいえNPTにおいて認められている合法的な‘核兵器国’ではありません。そもそも、NPTの締約国でさえないのです。言い換えますと、イスラエルは、NPT体制の枠外にあって、同法の拘束力の及ばないところにいるのです。しかしながら、非加盟国であることは、必ずしも同体制から切り離されていることを意味しません。同国の行動を観察しておりますと、意外なことに、NPT体制から最も大きな利益を得ている国は、イスラエル、あるいは、国境を超えたネットワークを擁するユダヤ系勢力であるようにも思えてくるのです。非加盟国、かつ、‘隠れ核兵器国’という地位は、ある意味において‘最強’なのです。
それでは、何故、‘最強’であるのかと申しますと、自国のみは、密かに核兵器を保有することで抑止力を有する一方で(もっとも、それ故にテロ攻撃を受けてしまう・・・)、周辺諸国に対しては、‘核開発の疑い’をもって攻撃の口実を得る、もしくは、中東地域における対立軸を形成するチャンスを得ることができるからです。例えば、イスラエルは、1981年6月に、先制的自衛を根拠としてイラクに対して建設途中にあったオシラク原子力発電所を空爆しています。これは、オペラ作戦(バビロン作戦)と呼ばれていますが、この時、‘先制的自衛’とはいえ、イスラエルは先制攻撃を行なっています。同攻撃に対しては国際社会において批判の声が上がり、国連においても批難決議が成立するものの、異すられるに対して厳しい制裁が化されることはありませんでした。同事件は、その後のイラク戦争の前哨戦としても位置づけられるかもしれません(因みに、対イラクに関しては、イスラエルとイランは共闘関係にあり、オペラ作戦に先立つ1980年9月に、イランも、オシラク原子力発電所を奇襲攻撃している・・・)。
そして、イランとの関係を見ましても、核開発が一つの両国間の関係悪化の転機となっています。2002年8月にイランによる核開発疑惑が浮上しますと、イスラエルは、イランに対する軍事攻撃を主張するようになるからです。アメリカをはじめ、イギリスやフランス等がイランとの核合意を急いだのも、その背景には、これらの諸国の政界に深く根を張るユダヤ系勢力の積極的なロビー活動があったからなのでしょう。昨年の8月に中東諸国を訪問した際に、バイデン大統領も、ネタニヤフ首相の前任者であるヤイル・ラピド首相との間でイランの核開発の阻止を約する共同宣言に署名しています。かくして、イスラエルとイランとの対立は深まり、イランもまた、レバノンのイスラム教シーア派組織であるヒズボラなどを支援するなど、イスラエルとの対立姿勢を強めてゆくのです。
中東における核兵器開発をめぐる状況からしますと、核保有国となったイスラエルが、他のアラブあるいはイスラム諸国の核開発阻止を根拠として(核拡散の阻止・・・)、軍事的な行動計画を策定し、かつ、自らの軍事行動を正当化してきた様子が窺えます。しかも、同動きに対するリアクションとして、イラン等の支援を受け、反イスラエルを掲げる過激武装集団が生み出されることともなったのです。そしてそれは取りも直さず、中東地域における混乱と新たな対立軸の形成をも意味したとも言えましょう(中東の重大な不安定要因に・・・)。
今日、イスラエル・ハマス戦争において、国境を接していない遠方のイランの介入、あるいは、参戦が懸念されるのも、NPT体制における加盟国と非加盟国との間のいびつな非対称性にその原因を求めることができましょう。平和のために成立したはずのNPT体制が、その実、戦争をもたらしているという現実は、NPT体制のパラドクスとも言えるのではないかと思うのです。