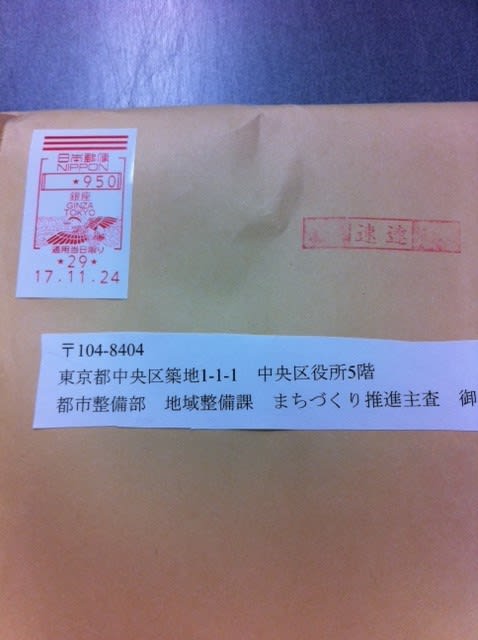東京都市計画月島三丁目地区地区整備計画区域を定める根拠条例「中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を見ておきます。
別表第一に、月島の他の町と同様に、月島三丁目地区も規定がなされています。
条例においては、第18条があり、規定を受けないようにもできます。
ただ、第18条の例外を行う場合は、中央区建築審査会の同意が必要です(第19条)。
別表第一
東京都市計画月島三丁目地区地区整備計画区域:都市計画法第二十条第一項の規定により告示された東京都市計画月島三丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域
○都市計画法 20条
(都市計画の告示等)
第二十条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
2 都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。
3 都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。
○都市計画法 14条1項(1項のみ表示)
(都市計画の図書)
第十四条 都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。
○建築基準法 68条の2第1項(1項のみ表示)
第七節 地区計画等の区域
(市町村の条例に基づく制限)
第六十八条の二 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。
○建築基準法 68条の5の5
(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)
第六十八条の五の五 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条第二項の規定は、適用しない。
一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域であること。
イ 都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の五、地域歴史的風致法第三十二条又は沿道整備法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度
ロ 建築物の容積率の最高限度
ハ 建築物の敷地面積の最低限度
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。
2 前項第一号イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で前項第一号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。
○建築基準法 52条2項⇒52条は、容積率に関する規定です。
***********************************
○中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成五年七月一日
条例第十八号
中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づき、地区計画の区域内において、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第二条 この条例の規定は、別表第一に掲げる地区整備計画の区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第三条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。)内においては、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の容積率の最高限度)
第四条 建築物の容積率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ロ欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として算入しない。
(一部改正〔平成九年条例二七号・三六号・一〇年四六号・一三年三二号〕)
(建築物の容積率の最低限度)
第五条 建築物の容積率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ハ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積について準用する。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一三年三二号〕)
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第六条 建築物の建ぺい率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ニ欄に掲げる数値以下でなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一三年三二号〕)
(建築物の敷地面積の最低限度)
第七条 建築物の敷地面積は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ホ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地
二 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
3 第一項の規定は、法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第一項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第一項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地
二 第一項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地
(一部改正〔平成九年条例三六号・一八年二五号〕)
(壁面の位置の制限)
第八条 道路境界線その他の境界線又は道路中心線から建築物の壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ヘ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、地盤面下の部分については、この限りでない。
(一部改正〔平成九年条例二七号・三六号〕)
(建築物の高さの最高限度)
第九条 建築物の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ト欄に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは十二メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
3 前項の規定は、この条例に特別の定めがある場合には、適用しない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一八年三九号〕)
(建築物の高さの最低限度)
第十条 建築物の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表チ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない高さの部分を有する建築物で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の二分の一未満であるものについては、適用しない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の形態又は意匠の制限)
第十一条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表リ欄に掲げるものとしなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(垣又はさくの構造の制限)
第十二条 垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)の構造は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ヌ欄に掲げるものとしてはならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合等の措置)
第十三条 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第三条及び第七条第一項の規定を適用する。
2 建築物の敷地が第二条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第三条及び第七条第一項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
3 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、第四条第一項、第五条第一項又は第六条の規定による制限を、それぞれ法第五十二条第一項及び第二項の規定による建築物の容積率の限度又は法第五十三条第一項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、法第五十二条第七項又は法第五十三条第二項の規定を準用する。
4 建築物の敷地が第八条から前条までの規定による制限を受ける計画地区の二以上にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分について、これらの規定をそれぞれ適用する。
(一部改正〔平成七年条例一二号・九年二七号・三六号・一三年三二号・一四年三六号・二〇年一一号〕)
(一定の複数建築物に対する制限の特例)
第十四条 一団地内に二以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、区規則で定めるところにより、区長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第四条第一項又は第十七条の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。
2 区長は、前項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、区規則で定める事項を公告しなければならない。
3 前項の規定による公告があった日以降、第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「同一敷地内建築物」という。)に係る一団地(以下「一団地認定区域」という。)内において同一敷地内建築物以外の建築物を建築しようとする者は、区規則で定めるところにより、当該建築物の位置及び構造が当該一団地認定区域内の他の同一敷地内建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の区長の認定を受けなければならない。
4 区長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 第一項の規定は、一団地認定区域内の第三項の規定による認定を受けた建築物及び当該建築物以外の当該一団地認定区域内の建築物について準用する。
6 一団地認定区域内に第三項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を同一敷地内建築物とみなす。
(一部改正〔平成二年条例二一号〕)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第十五条 法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、第三条、第四条第一項又は第五条第一項の規定の適用を受けない建築物について、区規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず第三条、第四条第一項又は第五条第一項の規定は、適用しない。
2 法第三条第二項の規定により、第八条の規定の適用を受けない建築物について、区規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、当該建築物のうち同条の規定に適合しない既存部分について、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず第八条の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成一八年条例二五号〕)
(用途変更の制限)
第十六条 計画地区内において、法第六十八条の五の四又は法第六十八条の五の五の規定の適用を受けた建築物について、その用途を変更しようとする者は、区規則で定めるところにより、当該変更内容について区長の認定を受けなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一四年三六号・二〇年一一号〕)
第十七条 削除
(削除〔平成一六年条例一六号〕)
(特例による許可)
第十八条 この条例の規定の適用に関して、次の各号に掲げる建築物及びその敷地は、許可の範囲内において当該規定は適用しない。
一 区長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地
二 区長が、当該計画地区内における土地利用状況等に照らして総合的に配慮し、第一条に規定する目的に則した計画と認めて許可した建築物及びその敷地
(一部改正〔平成九年条例三六号・一六年一六号〕)
(建築審査会の同意)
第十九条 区長は、前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、中央区建築審査会の同意を得なければならない。
(一部改正〔平成一一年条例二一号〕)
(罰則)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条又は第七条第一項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
二 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第七条第一項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
三 第四条第一項、第六条、第八条又は第九条第一項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
四 法第八十七条第二項において準用する第三条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第三号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第一項の罰金刑を科する。ただし、その法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
別表第一に、月島の他の町と同様に、月島三丁目地区も規定がなされています。
条例においては、第18条があり、規定を受けないようにもできます。
ただ、第18条の例外を行う場合は、中央区建築審査会の同意が必要です(第19条)。
別表第一
東京都市計画月島三丁目地区地区整備計画区域:都市計画法第二十条第一項の規定により告示された東京都市計画月島三丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域
○都市計画法 20条
(都市計画の告示等)
第二十条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
2 都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。
3 都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。
○都市計画法 14条1項(1項のみ表示)
(都市計画の図書)
第十四条 都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。
○建築基準法 68条の2第1項(1項のみ表示)
第七節 地区計画等の区域
(市町村の条例に基づく制限)
第六十八条の二 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。
○建築基準法 68条の5の5
(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)
第六十八条の五の五 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条第二項の規定は、適用しない。
一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域であること。
イ 都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の五、地域歴史的風致法第三十二条又は沿道整備法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度
ロ 建築物の容積率の最高限度
ハ 建築物の敷地面積の最低限度
二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。
2 前項第一号イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で前項第一号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。
○建築基準法 52条2項⇒52条は、容積率に関する規定です。
***********************************
○中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成五年七月一日
条例第十八号
中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づき、地区計画の区域内において、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第二条 この条例の規定は、別表第一に掲げる地区整備計画の区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第三条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。)内においては、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の容積率の最高限度)
第四条 建築物の容積率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ロ欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として算入しない。
(一部改正〔平成九年条例二七号・三六号・一〇年四六号・一三年三二号〕)
(建築物の容積率の最低限度)
第五条 建築物の容積率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ハ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積について準用する。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一三年三二号〕)
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第六条 建築物の建ぺい率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ニ欄に掲げる数値以下でなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一三年三二号〕)
(建築物の敷地面積の最低限度)
第七条 建築物の敷地面積は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ホ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地
二 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
3 第一項の規定は、法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第一項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第一項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地
二 第一項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地
(一部改正〔平成九年条例三六号・一八年二五号〕)
(壁面の位置の制限)
第八条 道路境界線その他の境界線又は道路中心線から建築物の壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ヘ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、地盤面下の部分については、この限りでない。
(一部改正〔平成九年条例二七号・三六号〕)
(建築物の高さの最高限度)
第九条 建築物の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ト欄に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは十二メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
3 前項の規定は、この条例に特別の定めがある場合には、適用しない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一八年三九号〕)
(建築物の高さの最低限度)
第十条 建築物の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表チ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない高さの部分を有する建築物で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の二分の一未満であるものについては、適用しない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の形態又は意匠の制限)
第十一条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表リ欄に掲げるものとしなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(垣又はさくの構造の制限)
第十二条 垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)の構造は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ヌ欄に掲げるものとしてはならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号〕)
(建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合等の措置)
第十三条 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第三条及び第七条第一項の規定を適用する。
2 建築物の敷地が第二条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第三条及び第七条第一項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
3 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、第四条第一項、第五条第一項又は第六条の規定による制限を、それぞれ法第五十二条第一項及び第二項の規定による建築物の容積率の限度又は法第五十三条第一項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、法第五十二条第七項又は法第五十三条第二項の規定を準用する。
4 建築物の敷地が第八条から前条までの規定による制限を受ける計画地区の二以上にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分について、これらの規定をそれぞれ適用する。
(一部改正〔平成七年条例一二号・九年二七号・三六号・一三年三二号・一四年三六号・二〇年一一号〕)
(一定の複数建築物に対する制限の特例)
第十四条 一団地内に二以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、区規則で定めるところにより、区長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第四条第一項又は第十七条の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。
2 区長は、前項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、区規則で定める事項を公告しなければならない。
3 前項の規定による公告があった日以降、第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「同一敷地内建築物」という。)に係る一団地(以下「一団地認定区域」という。)内において同一敷地内建築物以外の建築物を建築しようとする者は、区規則で定めるところにより、当該建築物の位置及び構造が当該一団地認定区域内の他の同一敷地内建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の区長の認定を受けなければならない。
4 区長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 第一項の規定は、一団地認定区域内の第三項の規定による認定を受けた建築物及び当該建築物以外の当該一団地認定区域内の建築物について準用する。
6 一団地認定区域内に第三項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を同一敷地内建築物とみなす。
(一部改正〔平成二年条例二一号〕)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第十五条 法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、第三条、第四条第一項又は第五条第一項の規定の適用を受けない建築物について、区規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず第三条、第四条第一項又は第五条第一項の規定は、適用しない。
2 法第三条第二項の規定により、第八条の規定の適用を受けない建築物について、区規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、当該建築物のうち同条の規定に適合しない既存部分について、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず第八条の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成一八年条例二五号〕)
(用途変更の制限)
第十六条 計画地区内において、法第六十八条の五の四又は法第六十八条の五の五の規定の適用を受けた建築物について、その用途を変更しようとする者は、区規則で定めるところにより、当該変更内容について区長の認定を受けなければならない。
(一部改正〔平成九年条例三六号・一四年三六号・二〇年一一号〕)
第十七条 削除
(削除〔平成一六年条例一六号〕)
(特例による許可)
第十八条 この条例の規定の適用に関して、次の各号に掲げる建築物及びその敷地は、許可の範囲内において当該規定は適用しない。
一 区長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地
二 区長が、当該計画地区内における土地利用状況等に照らして総合的に配慮し、第一条に規定する目的に則した計画と認めて許可した建築物及びその敷地
(一部改正〔平成九年条例三六号・一六年一六号〕)
(建築審査会の同意)
第十九条 区長は、前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、中央区建築審査会の同意を得なければならない。
(一部改正〔平成一一年条例二一号〕)
(罰則)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条又は第七条第一項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
二 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第七条第一項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
三 第四条第一項、第六条、第八条又は第九条第一項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
四 法第八十七条第二項において準用する第三条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第三号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第一項の罰金刑を科する。ただし、その法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。