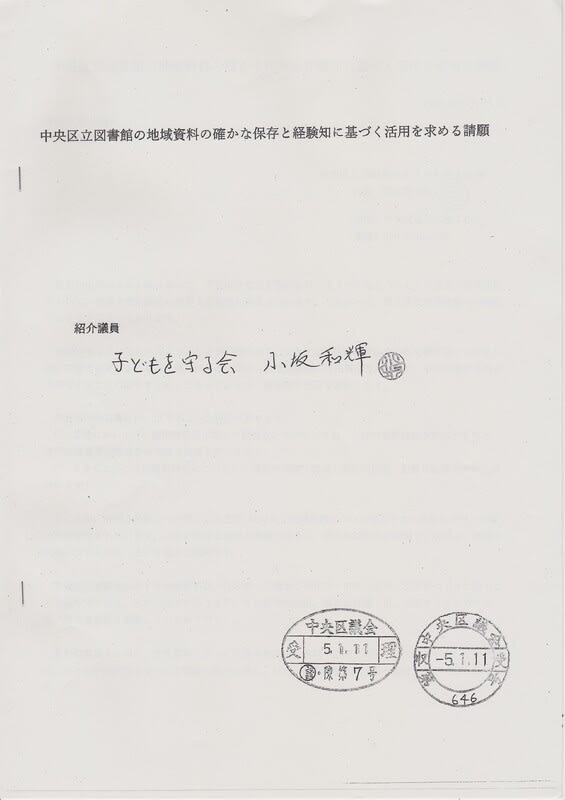本日の議会、起きた事実を、記載します。
一般質問で一回目の質問をした。
質問の該当箇所のみピックアップ:
①公的資金を投入し、大規模な面的整備を図るタワーマンション建設の手法を持ち得ないとして、では、どのようなまちづくりができるか、前回の第三回定例会一般質問の場で、私の再質問に対し、区長からも研究する旨のご答弁をいただいたが、その後の進捗は、いかがか。
参照:第三回定例会一般質問 録画
最後の方で、区長がまちづくりの研究をされる旨、再質問に対し、答弁されています(36:10あたりから)。
https://chuo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=323
区長が答弁。
6月補正で予算付がされた無接道敷地の区による買取の検討をしている旨を答弁された。
区長答弁に対し、再質問。
6月補正の無接道敷地の検討がなされていることはわかっているが、第三回定例会での再質問で答弁された研究すると述べられていたことについて進捗を教えてほしい。
私がまだ壇上にいる状態で、いきなり吉田副区長が挙手して、発言を求め、議長に指名される。
吉田副区長が、答弁。
区長の研究されていることについての言及がなかった。
区長からの答弁なし。
再々質問として、区長から意見がなされていないことを指摘し、答弁を求めた。
再々質問には、もうひとつ別件で、社人研の30年後の人口推計で用いた際、中央区民の人口推計は何人であったかについて答弁漏れがあったので答えて欲しい旨述べた。
区長が挙手し、議長に発言許可を求めようと挙手。
それを遮るように、議会運営委員会委員長が動議を求め、休憩に入る。
一時間以上経過。
再々質問に対する答弁として、区長が登壇。
「先ほど副区長が述べたことと同じです。」と答弁。
社人研のデータの答弁漏れに対しては、部長が答弁。
私の一般質問終了。
故意に区長発言が遮られているように私は感じました。
でなければ、私の再々質問への答えとして、「先ほど副区長が述べたことと同じです。」というために、一時間以上の休憩は、ありえないと考えるからです。
私の本音は、中央区の最大の課題とも言えるこれ以上、タワーマンションの手法を用いるには学校はじめ受け入れる社会インフラの余力のない中央区において、では、どのようなまちづくりができるのか、本会議という公開の場で、区長ご本人と、ご議論させていただきたかった。
そして、区長ご本人も、その思いを持たれておられたと私は信じています。