丸山眞男氏から学ぶべき点は多くあると考えています。
新春の一冊として、購入準備しました。
**********アマゾン********
https://www.amazon.co.jp/dp/4121028376?psc=1&smid=AN1VRQENFRJN5&ref_=chk_typ_imgToDp
目 次
まえがき――科学としての政治学の百年
序 章 本書の方法
第1章 民主化を調べる――占領から逆コースまで
1 蠟山政道グループの選挙調査
2 岡義武グループの政治過程分析
第2章 英雄時代――講和独立から高度成長期へ
1 石田雄の圧力団体論
2 升味準之輔の一九五五年体制論
3 京極純一の政治意識分析
第3章 近代政治学の低迷と挑戦者――豊かな社会の到来・・・
1 田口富久治のマルクス主義政治学
2 三宅一郎の投票行動研究
第4章 新しい流れ――一九八〇年代の断絶と連続
1 レヴァイアサン・グループ
2 佐藤誠三郎の自民党研究
第5章 制度の改革――平成の時代へ
1 政治改革の模索
2 新制度論
第6章 細分化の向かう先――二一世紀を迎えて
1 ジェンダー研究
2 実験政治学
終 章 何のための科学
あとがき
参考文献
主要人名索引
『苦海浄土』に関連した書籍の書評。
水俣病が拡大した背景には、医師も関わっています。もちろん、なんとかしようとした医師もおられます。
大いに反省し、決して繰り返さぬように、それぞれの持ち場で頑張らねばなりません。
*****毎日新聞 2024.7.6********
世界一わかりやすく書かれた哲学の本。
大学入学あたりで、出会いたかった。
何歳から読んでも遅くない。
この本が、日本の民主主義を守る力も持っているとも感じます。
筆者も、考えることの究極の目的に、「幸せ」を置いています。その「幸せ」は、民主主義によって達成されるものと解します。
考えるを考える。その先にある民主主義。
この本、まさに、以下の調子で書かれています。
ある読書会での課題本を共有します。
『弱いままのキミでパズる』静岡の元教師すぎやま、著
1.『弱いままのキミでバズる』を読んだ直後の正直な感想を一文で表してください。
先生不足の中で一人でも先生をやめてほしくないけど、やめるにはやめるなりの理由のある方がおられることが分かりました。
2.『弱いままのキミでバズる』のポップコピーを考えてください。
元教師が語る最もわかりやすい「情報リテラシー」指南書。これ一冊で、誰もが、バズれる。
3.読み聞かせをしたいと思う3箇所を選んでください。
- いつまで経ってもやらない人は、いまやれない理由を並べ立てるのがとても上手なんです。(103頁)
- ①ゴール設定:なんのために発信するのか?②ターゲット設定:誰のために発信するのか?③コンセプト設定:何を発信するのか?この3つです。この中で、私が特に大事にしているのは②ターゲットです。(161頁)
- 多くの人が勘違いしていることがあります。それは「あの人は夢を持っているから、それでがんばることができる」ということです。…キミがちょっと得意なことは?キミがちょっと好きなことは?そしてワクワクすることは?…心配しなくて大丈夫。夢なんて後からついてきます。(200-203頁)
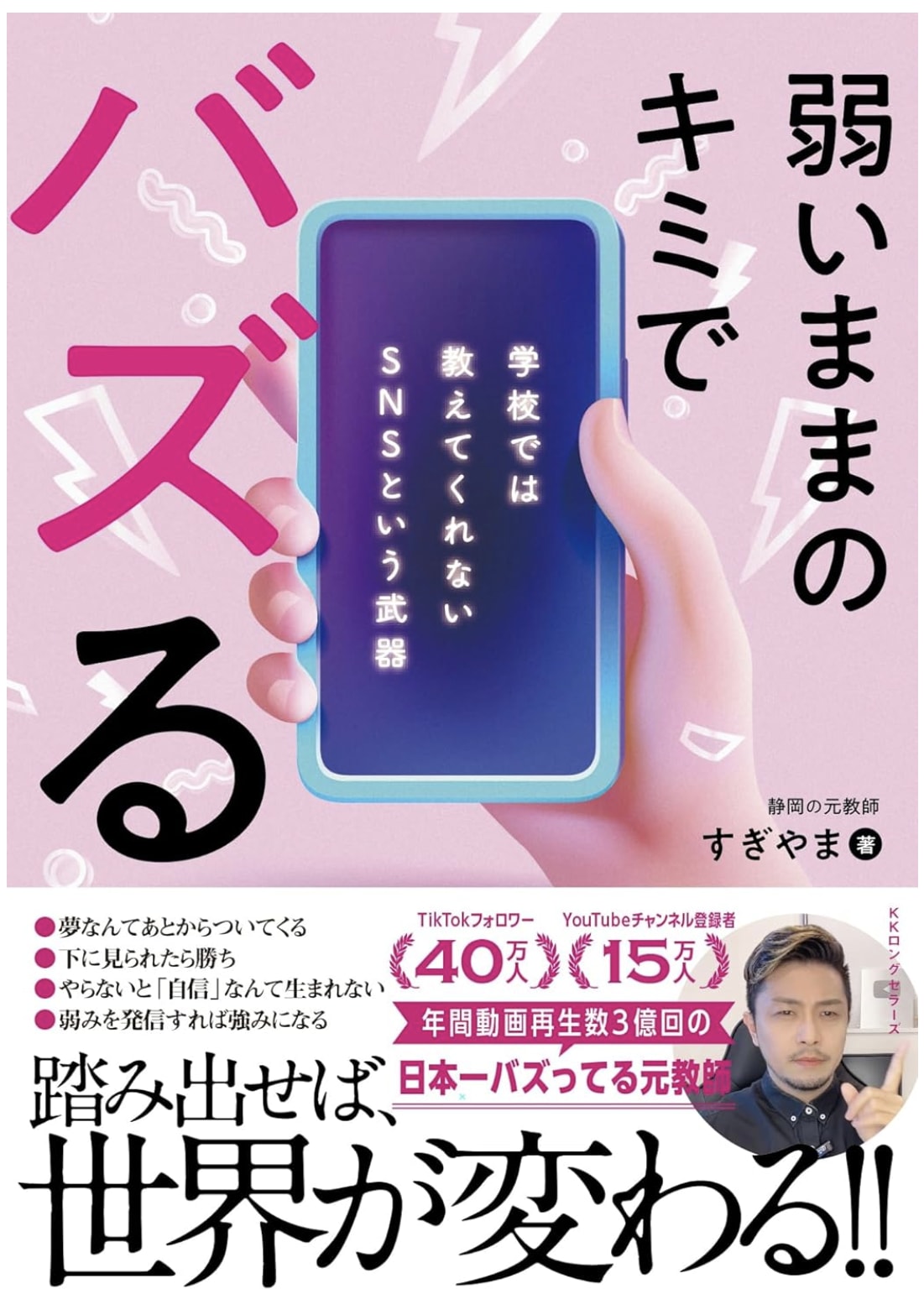
4.SNSについて
SNSは、Xとフェースブックそしてブログを使っています。2024年能登半島地震で始まりましたが、「ボランティアは入らないで。」という中、その医療支援に入れたのも、能登町の避難所からXで発信されたSOSとSNSを介しつながることができたからです(後掲)。入ってみると発災から1週間の現地ではやるべきことは、医療の観点からは山のようにありました。その際も、バズる投稿をよく目にしました。バズっていたからこそ、つながることができたのだと思います。
ネットの恩恵により、第一線の研究者や経験者ら一次情報源たる現場のひとと直接繋がることができるのは、とてもありがたいことと考えます。
政策を作るにあたっては、科学的な根拠を元に、政策を作っていきたいし、また、現場の声をうまく反映させて作っていきたい。そのためにもネットの情報発信や情報収集は欠かせないと考えています。
今後とも、ネットとリアルとをうまく活用していきたいです。そして、リアルとバーチャルの二つの世界をどのように生きるのか、これからの子ども達にもその技術を伝えていければと思います。
-
後掲:私がつながったSNSはこちら

-
2007年(平成19年)に自分が書いた文章。
書いたことさえ覚えてないけど、『社会認識の歩み』を手にとった覚えはあります。
****自分の過去のブログ 2007-09-09 18:33:27 | シチズンシップ教育 ***
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/32627b75a9a9f6a8622d4e7c58852701
「世の中を読む」(難しくいうと「社会認識」)ことを、だれもが、うまくしたいと思っている。
うまく「世の中を読む」方法は、次の3つのステップを踏むこと。
【ステップ1】自分を賭ける=主体の自覚
知らず知らず、皆さんは行動する時、選択をしている。無意識にしているので、感じないかもしれないが、どちらかの行動を選ぶにあたって、「賭け」をしているわけである。
「賭け」ている自分に気づくと、だれでもその賭けに負けたくはないわけで、そのために事実の客観的な認識をするであろう。事実の情報収集などをして、事実の客観的な認識後、賭ける先を決めて生きていくのである。賭けると考えると、事物の客観的認識が、自分の問題として迫ってくるのではないか。社会認識の歩みの第一歩がこうして始まる。
「賭けている自分」の自覚こそ、主体的に生きている自分を自覚することである。
ダンテが言うが人間の最低の条件は、「自分の責任において自分の行動をきめること」であり、主体的に生きることを意味する。
ちなみに、マキアヴェリの『君主論』によると、人は、運命に縛られ、支配されている。どうあがいても、運命の定めから抜け出せ得ない。うまく生きていけるかは、たまたま運命が幸運であったからであり、運命は、人間に絶えず襲い掛かってくる存在なのである。しかし、自身の努力で、運命を切り開くことが、出来る部分もある。人生の、運命に定められている部分が半分で、運命を切り開くことができる部分が、半分の割合である。自分を賭けたら、果敢に行動し、運命を切り開いて行くことをマキアヴェリは強調している。
【ステップ2】制度を疑え!=主体の自覚の深まり(空間的認識の広がりへ)
次のステップは、ある決められて制度の中で、主体的に考えていた存在から、制度そのものを作り直す主体になっていくことである。
制度で決まっているからという分析から、なぜ、そういう制度があるのか?と考え、必要であれば、制度のあるべき姿を再提案していくのである。
今やいけないことであるが、国家とか制度が自己目的化されて、人間が手段化されがちである。制度やルールの存在根拠を人間の側で問うて行くことがなければ、社会科学は生きてこない。ホッブスが、「挙証責任の所在の転換」をもたらした点は、すなわち、制度の存在理由を証明するのは、制度をつくった側にあるとしたことは、非常に意義深い。
ちなみに、マキアヴェリの『君主論』の書き方は、統治者が民衆とは別に始めからあるという前提から始まっているため、制度ありきなのである。
【ステップ3】歴史を発掘しろ!=時の流れに埋もれない(時間的認識の広がりへ)
最後のステップとして、社会が歴史的存在であるということを認識する必要がある。気づかないうちに主体も客体も時の流れに埋もれてしまうものである。埋もれることなく歴史から抜け出して歴史を省りみるという主体の側での行為を契機にして、歴史的存在として社会認識できるようになる。
特に日本人は、個体という概念が希薄な上、「自(おのず)から然(しか)る」という風に「宿命的歴史感」を自然に有しているため、社会科学も育ちにくかった。
「歴史的事象の始原の探求」をすることで、社会科学の「時間的考察」ができるようになる。大胆に、歴史の中から、ある歴史事象の始原(始まり)を発掘するのである。
例えば、
①社会科学の結節点をあげ、ヨーロッパ学問史の始原を抜き出すとすれば、
マキアヴェリ(1469、イタリア)『君主論』
↓
(約1世紀後)
ホッブス(1585、英)『リヴアイアサン』
(汝自身を知れ:自分を知ることで、自然状態の人間の心を知る。その集合として一つの意志をもった国家形成がなされている。人間の研究から、国家研究が始まるとした。)
↓
(約1世紀後)
ルソー(1712、仏)『社会契約論』『人間不平等起源論』
(ホッブズの想定した自然人は私有財産制により、実は想定できないとした。利己心と自愛心。)
アダム・スミス(1723、英)『国富論』(ルソー批判とホッブスへの回帰)
(利己心は自己への関心であり、人間の普通に持つ本性である。同じ利己心をもつとして、他人への同感、共感を人間は持ち、一定の制度のうえでは、利己的行動が社会的善につながる。)
<<この18世紀中葉にヨーロッパ学問史の始原がある!!>>
↓
(約1世紀後)
マルクス(1818、独)『資本論』
②日本で言う「市民社会」の始原は?
太平洋戦争中にある。
③太平洋戦争の始原は?
家永三郎氏によると、
柳条湖事件か?
盧溝橋事件か?
ハワイ空襲か?
以上。
三つのステップを行い、多くの人に「世の中をうまく読んでいただきたい」(社会的認識の歩みをしていただきたい)と思う。
今や、学問といえば、管理の学となる時代、それに埋もれることなく、多くの人が社会認識の歩みができるのであれば、必ずや人間が人間らしく生きる社会の実現ができると信じる。
それにしても、大学時代に上記代表作は、読んでおくべきだったと後悔している。
『社会認識の歩み』(内田義彦著、岩波新書1971年第1刷発行、2006年第48冊発行)を自分なりに解釈し、メッセージ化した。
1、『モモ』を読んだ直後の正直な感想を一文で表してください。
小学生のころ、出会って置きたかった。遅まきながら、今であえて、幸運だった。
2、『モモ』のポップコピーを考えてください。
小学校の卒業記念で、全員にプレゼントしたい本。この一冊で人生乗り切れるほどに大切なことがつまっている。
3、読み聞かせをしたいと思う3箇所を選んでください。
●ほんとうに聞くことができる人は、めったにいないものです。そしてこのてんでモモは、それこそほかにはれいのないすばらしい才能をもっていたのです。(23頁)
●いちどに道路ぜんぶのことを考えてはいかん、わかるかな?つぎの一歩のことだけ、つぎのひと呼吸(いき)のことだけ、つぎのひと掃きのことだけを考えるんだ。いつもただつぎのことだけをな。…するとたのしくなってくる。これがだいじなんだな、たのしければ、仕事がうまくはかどる。(53頁)
●もし人間が死とはなにかを知ったら、こわいとは思わなくなるだろうにね。そして死をおそれないようになれば、生きる時間を人間からぬすむようなことは、だれにもできなくなるはずだ。(237頁)
4、ご自身の見解、ご意見を記載してください。
(1) モモの話を聞く力(相手が話をするだけで変っていくほど)の秘訣は何だろう?
本人のことを思って、自身の価値観を入れずにずっと聴くこと。
(2) 灰色の男たちが登場してから、退治するまでの間で、モモ自身にも内面の変化があったの?
もともと、解決する力はあったが、変化はあった。自分はどんな困難であっても立ち向かえる「勇気」という力を気づけた変化。
(3) 時間貯蓄銀行とは 何のメタファーなの?
現代社会の美徳とみなされる効率性。
(4) 灰色の男達は、元は人間なの?違うの? 人間だとしたら、いつ、どうして灰色の男になったの?
元は人間。工業化が進みだしたころ、人の心を持てなくなったため、灰色になってしまった。他人を不幸にして儲けようとしているという点で、人の心を持ててない。
(5) 時間貯蓄銀行は、また、いつか、どこかで産まれるものなの?
いつか、どこかでというよりも、現代社会で、すでに蔓延っている。
以上
2023.12.13今日、詩集『会社の人事』中桐雅夫 1979 晶分社 を題材にした読書会に参加します。
心に響く詩の数々でした。
その中でも、感銘を受けた一番の詩が、『白いハンカチ』です。
前から撃たれることは、慣れています。
でも、とてもつらいことは、後ろから撃たれることです。
仲間と信じていた者から撃たれてしまうこと。
だからと言って、怯んではならないとも思っています。
この士官のように、やるべきことは、何が何でもやりきること。
その勇気を、この詩は、私に与えてくれます。
「本を読んだ方がいいと思いますか?」と小学生に質問されたら、何と答えますか。
小学生のみなさんへ
本は、どんどん読んでください。それも、楽しんで読んでください。
もしも、いじめにあっている子がいたら、本が、きっとあなたを守ってくれるよ。本は、決して裏切らないから安心して。
大人になると、うまく生きていかなくちゃならないから、職業柄、バランスよくインプットすることも必要になります。それは、正解に辿り着く力である「情報処理力」と、創造的な問題解決力である「情報編集力」で、この二つは車の両輪となります。そのバランスよくインプットするものは、実は、学校で教わっています。
国語・英語で、ひととのコミュニケーション力を身につけている。その場合のポイントは、「人の話をよく聴く」という技術だけど、読書をすることで高められるよ。
算数で、論理的な思考を。常識や前提を疑いながら柔らかく複眼思考するんだ。
理科で、推論する力を。頭の中でモデルを描き試行錯誤しながら類推するんだ。
社会で、ロールプレイする力を。他者の立場になり、考えや思いを想像するんだ。ママゴト遊びの延長だね。
そして、実技教科である音楽、美術、体育、技術で、相手とアイデアを共有するための表現、プレゼンテーションするんだ。
300冊を超えて読むと、自然と自分の言葉で語り出したくなると藤原和博氏は言います。私は、その域には達してはいないけど、心に残る一冊はあります。中学生のころ夢中で読んだ『三国志』、その登場人物が、今でもアドバイスくれるんだ。リアル社会で親友に出会えるように、あなたの一冊に、どうか出会いますように。
本を読んで学びインプット、それを仕事や活動でアウトプット、そしてまた、仕事や活動でぶつかった悩みや疑問を解くために読書や学びをし、そしてアウトプット、その循環ができることが理想です。学びがワクワクを生んだり、癒しになったりします。一生この循環が続けられるとよいですね。
*参照
『本を読む人だけが手にするもの』藤原和博著 日本実業出版社 
*『教育DXで未来の教室をつくろう』浅野大介著 学陽書房
1,『星の王子さま』を久々に読んだ。読んだ直後の感想は、
「いつ読んでも新鮮だなあ。何回読んでも、たいせつなことを教えてくれる、理屈っぽくない形で。」
2,本書に、『星の王子さま』の帯のポップコピーを与えるなら、
「あなたの心の中を、星の王子さまといっしょに探検に行きませんか。素敵な景色にきっと出会えます。」
3,読み聞かせをしたいと思う3箇所を選んでみるとすると、
- 王子さまは、なにがたいせつかということになると、おとなとは、たいへんちがった考えを持っていました。ですから、あらためてこういいました。
「ぼくはね、はなを持ってて。毎日水をかけてやる。火山も三つ持ってるんだから、七日に一度すすはらいをする。火を吹いてない火山のすすはらいもする。いつ爆発するか、わからないからね。ぼくが、火山や花を持ってると、それがすこしは、火山や花のためになるんだ。だけど、きみは、星のためには、なってやしない…」(69-70頁)
- あの男は、王さまからも、うぬぼれ男からも、呑み助からも、実業家からも、けいべつされそうだ。でも、ぼくにこっけいに見えないひとといったら、あのひときりだ。それも、あのひとが、じぶんのことでなく、ほかのことを考えているからだろう。(74頁)
- 「きみの住んでいるとこの人たちったら、おなじ一つの庭で、バラの花を五千も作ってるけど、…じぶんたちがなにがほしいのか、わからずにいるんだ」と王子さまがいいました。
「うん、わからずにいる…」と、ぼくは答えました。
「だけど、さがしてるものは、たった一つのバラの花のなかにだって、すこしの水にだって、あるんだがなあ…」
「そうだとも」と、ぼくは答えました。
すると、王子さまが、またつづけていいました。
「だけど、目では、なにも見えないよ。心でさがさないとね」(114頁)
4,生活している星に、王子さまがやってきたら、、で短編のお話しを作ってみるとすると、
そこは、地球の中の日本。夜中に街角で泣いている子に王子さまは気づいて、走り寄りました。
「家族は、どこに?」王子さまは問いかけると、「家族はいない…」とその子は、つぶやきました。小さいころ親から繰り返し虐待にあって、とうとう施設に保護され、両親の親権は消されてしまいました。
「今は、どこで生活をしているの?」
「新しい家にお世話になって暮らしてきたのだけど、その家からも毎日虐待を受けて、行き場がもうなくなって、どうしていいのかわからなくて…きっと僕が、ぜんぶ、悪いんだ。おとうさん、おかあさんがいなくなったのも。あたらしいおとうさん、おかあさんにいじめられるのも…」
星の王子さまは、自分もいまはひとりであること、ひとりでいろんな星を旅してきたこと、旅でいろんな変わったおとなとであってきたことを夜通し話しました。もちろん、世の中には怖い動物がいること、その子は、象をものみこむウワバミの絵に、たいへん驚きを隠せませんでした。
明け方、その子は、決心しました。「これからは、一人で生きていくよ。」
王子さまは、約束しました。「僕の帰りを待つはながあるから、星に帰るけど、寂しくなったら、いつでも、戻ってくるからね。」
地図が好きだったその子は、それから、王子さまからの紹介の手紙を持って、地理学者のところへ行き、無事に助手にしてもらったそうです。
以上
ある読書会での課題本『小川未明童話集』(新潮文庫昭和26年発行、平成14年75刷)、読んだ直後は、なんかトーンが重くて、楽しい・愉快というよりは、悲しい話が多いけど、それが美しく描かれているなあ。という感じを受けました。
しかし、この本に出会えて、本当に良かったと心から思っています。
「日本のアンデルセン。ぜひ、子どもと一緒に童話文学をご堪能下さい。」とお勧めをしたいと思います。
私が、印象に残る箇所。
●「赤いろうそくと人魚」18ページおばあさんは、燈のところで、よくその金をしらべてみると、それはお金ではなくて、貝がらでありました。
●「飴チョコの天使」91ページ三人の天使は、青い空に上ってゆきました。
●「百姓の夢」104ページあの牛は、どうして水音もたてずに、この池を泳いでいったろう?百姓は、とにかく子供たちが無事なので、安心しました。
そして、
●「野ばら」25ページ敵の兵でありながら、その兵を思う老人に、青年が現れる夢のシーン。
2022年は「日本のアンデルセン」と呼ばれた未明の生誕140年にあたる年だったといいます。
未明は生涯、薄幸な存在に思いを寄せ続け、「弱き者の為に立ち 代弁なき者のために起つ我これを芸術の信条となす」という言葉を残しました。
ぜひぜひ、ご一読を!!!
余談ですが、「童話は文学か?」と解説で書かれており、そのたとえで、小児科医が比較に上げられています。
******小川未明童話集232ページ*******
小川未明氏に関し、坪田譲治氏の解説抜粋

『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』 著者川内有緒、集英社、2021年第1刷、2022年8月第7刷。
お読みになられましたでしょうか。
お勧めします。
2022年を素敵な気持ちで締めくくれる一冊です!
私が勧めるまでもなく、2022年『本屋大賞ノンフィクション本』大賞受賞作でもあります。
私が、イイナ!と思った文章を3か所、引用します。
●アイマスクをすると、いったんは視覚障碍者みたいになるじゃない?それを見るとね、あなたはどこかのテレビゲームみたいなことをお遊びでやってんですか、って思いました。…このとき画面上のホシノさんに対し、画面のこちらにいるわたしが反論をしたくなった。でもさあ、ホシノさん、見えるひとがアイマスクをつけて過ごしてみることは、想像力を働かせるきっかけくらいにはなるんじゃないですか?…しかし画面の中のホシノさんは続けてそれを力強く否定していく。僕らはほかの誰にもなれない。…彼が伝えたいということは、想像力よりももっと手前にある部分だった。寄り添うことしかできない?いや、それもそうなんだけど、そのあと。―この世界で、笑いたいんですよー(318-320頁)
●―けんちゃんは目が見えないんだから、人の何倍も努力しないといけないんだよー
ただでさえ障害があるひとの風当たりが強い社会で、「頑張らない障害者」への風当たりはどんなものになるのか、と想像をすると心底恐ろしくなる。
しかし、本当は別に障害者が過剰な頑張りなど強いられない、人々の心の余裕がある社会を作るほうを目指すべきなのだ。(211-213頁)
●自分の場合、死に対する恐怖は、ただ一点に集約されることに気がついた。それは、まだ幼い娘の将来を見ずに死にたくないということに尽きた。…それを聞いた白鳥さんは、吐息で紙吹雪でも散らすように「俺はどっちでもいいな。明日死んでもいい」と言った。…「いやあ、どの時点で死んでも、結局は後悔するような気がするの。…結局のところ、ちゃんと自分がわかっているのは『いま』だけなんだ。だから、俺は『いま』だけでいいかな。過去とか未来とかじゃなくて『いま』だけ。だから、俺は明日死んでもいいと思う」(74-75頁)
https://www.hontai.or.jp/
2022年、新たな出会いと共に、ポスト・コロナの時代に、精一杯生きたいです。
新たな出会い、ひととの出会いが楽しい。
その次に楽しい出会いは、本。
2021年の本との出会いも楽しかったです。
多読ではないけれど、心に残った本です。
1月 『13歳からのアート思考』
2月 『学問からの手紙』『善の研究』
3月 『LGBTを読みとく クィア・スタディース入門』『善とは何か』
4月 『火の鳥・鳳凰編』
5月 『スマホ脳』
6月 『手の倫理』
7月 『大人問題』
8月 『コンビニ人間』
9月 『悲しみの秘義』
10月 『ケーキの切れない非行少年たち』
11月 『テロリストのパラソル』
12月 『苦海浄土』『水俣病は終わっていない』
何を読むとよいか、他人の推薦も、結構役に立ちます。
最近発売中の『ニュートン』が、企画をしてくれているようです。
まだ、夏休みの課題が見つけきれなかったら、気になる一冊を見つけて、課題にしてみては?
『国家はなぜ衰退するのか』
ダロン・アセモグル ジェイムズ・A・ロビンソン 著 鬼澤 忍訳
http://www.jiid.or.jp/ardec/ardec49/ard49-bookinfo.html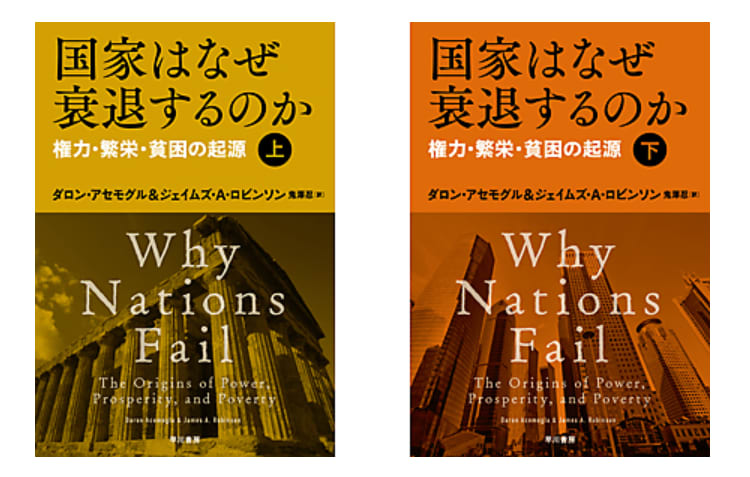
毎日新聞社 新聞研究本部 位川一郎 氏の論評より。
●繁栄と貧困を分けるのは政治と経済における「制度」
●国家の制度は、権力が社会に広く配分され大多数の人々が経済活動に参加できる「包括的制度」と、限られたエリートに権力と富が集中する「収奪的制度」に分けることができる(「包括的」という言葉はやや分かりにくいが、一般的な感覚では「民主主義的」に近いだろう)。
包括的制度のもとでは、法の支配が確立し、所有権が保護され、イノベーションが起こりやすい。
収奪的な政治制度と経済制度のもとでは、その反対のことが起きる。
そして、「経済的な成長や繁栄は包括的な経済制度および政治制度と結びついていて、収奪的制度は概して停滞と貧困につながる」と著者は主張する。
●1346年のペスト襲来という「決定的な岐路」
●産業革命がイングランドで始まり大きく前進したのは、1688年の名誉革命が包括的政治制度をもたらしたためだった。
●現代においても、ジンバブエ、コロンビア、北朝鮮、ウズベキスタンなど多くの国で収奪的制度の悪循環が繰り返されている。(第11章~第13章)
●収奪的な政治制度から包括的政治制度への移行がなければ、中国の成長はいずれ活力を失うだろう。(第15章)
●収奪的制度から包括的制度に移行するにはどうすればよいか。著者は「移行をたやすく達成する処方はない」と言い切る。
●第15章の最終節で、包括的制度の強化に成功した国に共通するのは「社会のきわめて広範かつ多様な集団への権限移譲に成功したことだ」と指摘している。困難ではあっても、各国の内側で政治的な多元主義が育つのを期待するしかないということだろう。納得できる見解といえる。
●本書は主に一国内の収奪的制度に着目しているが、国際的な収奪構造も無視するわけにいかない。だとしたら、先進国の側も貧困の克服のために、従来とは異なる関与の仕方を探るべきではないだろうか。















