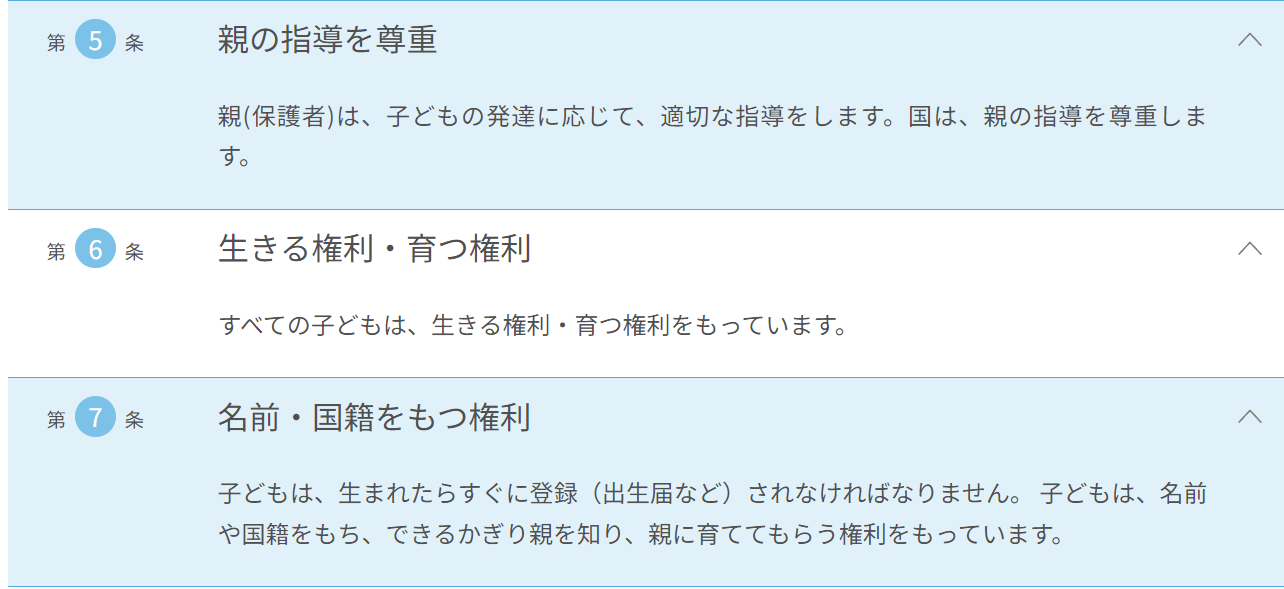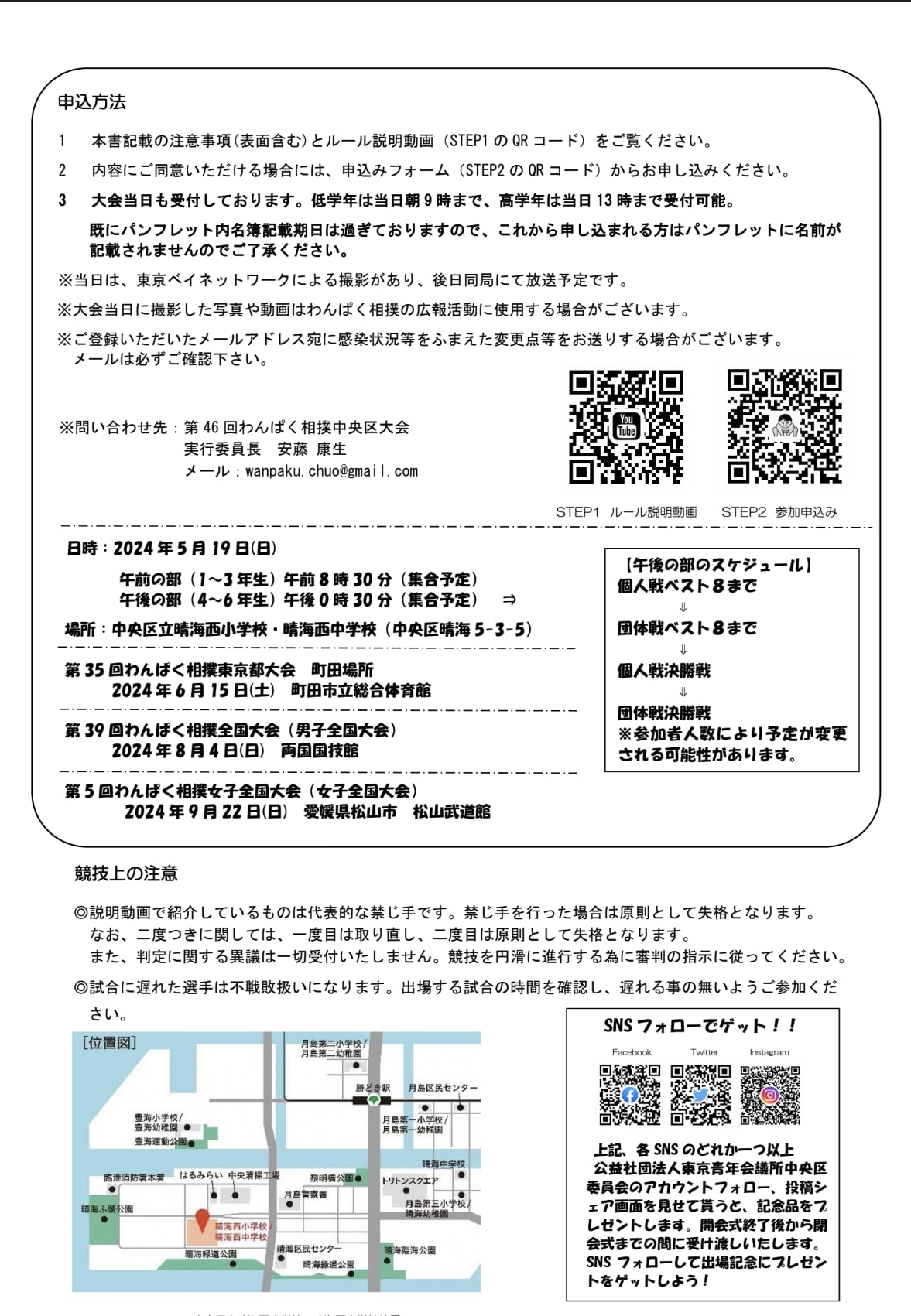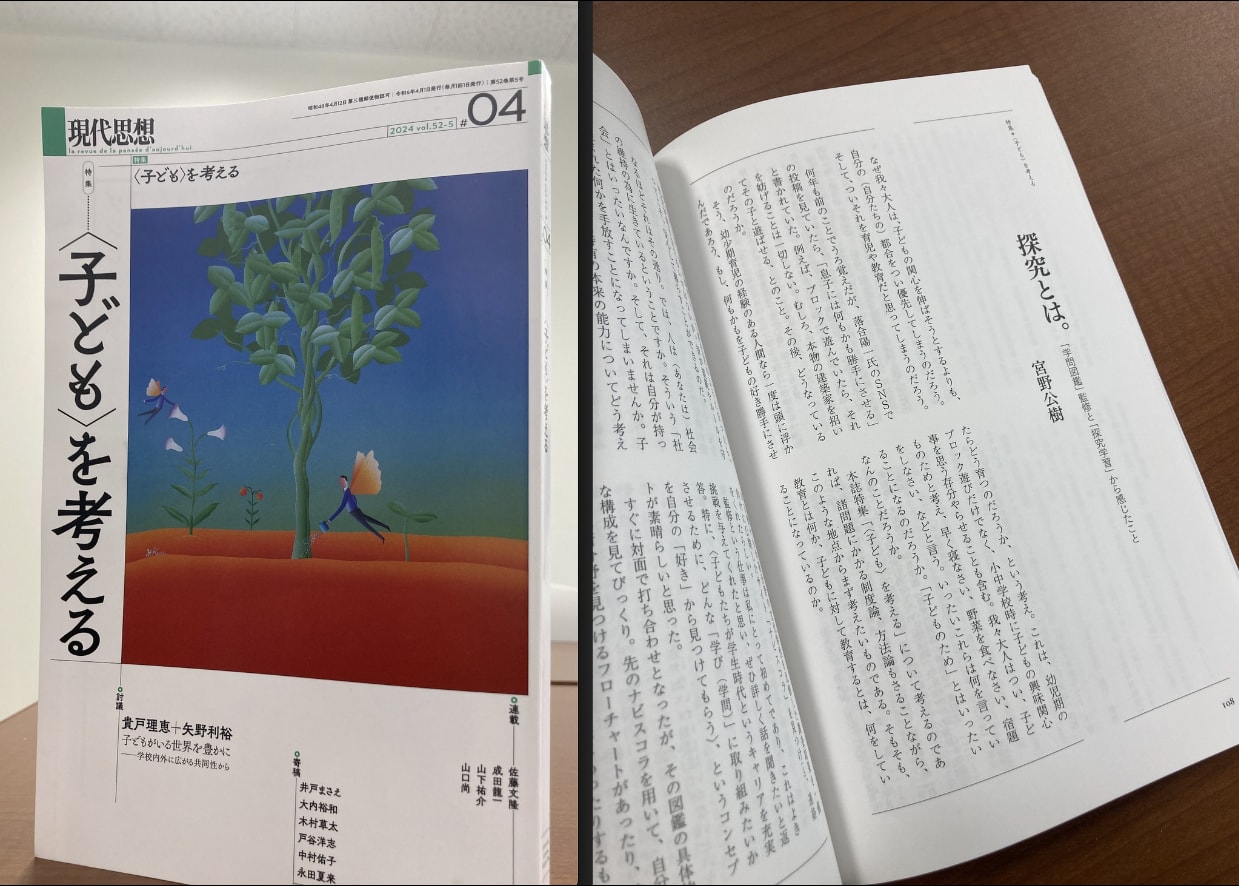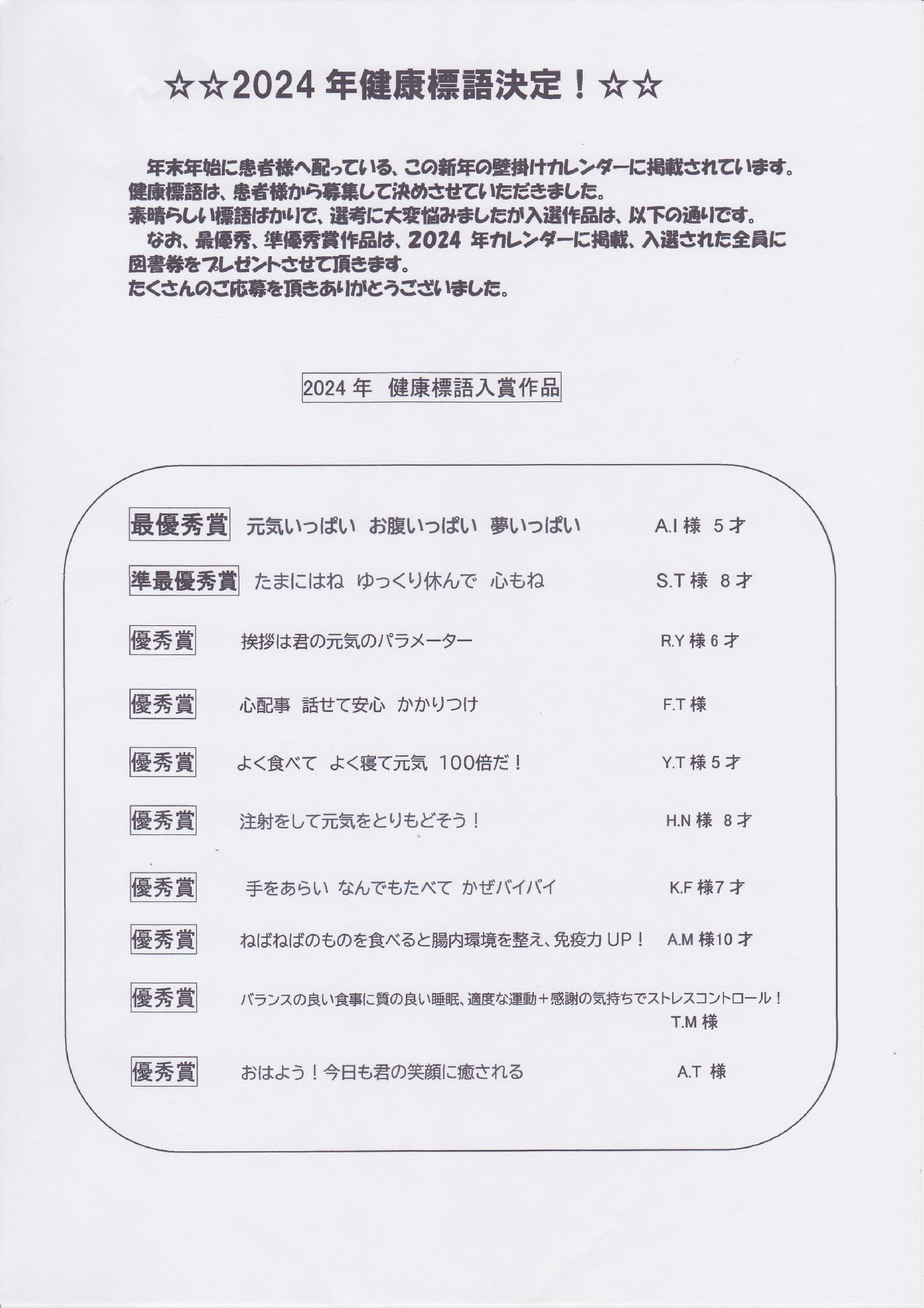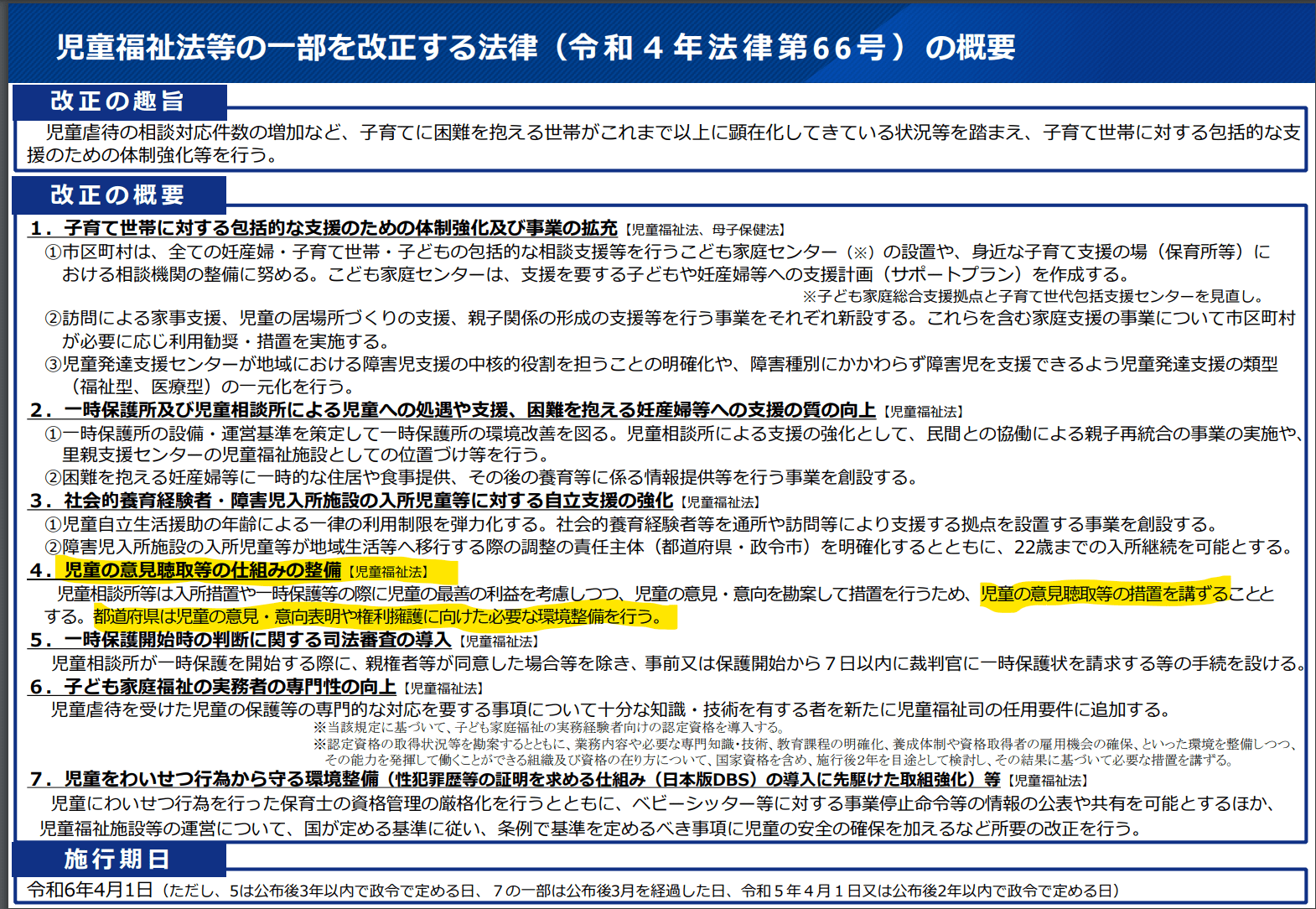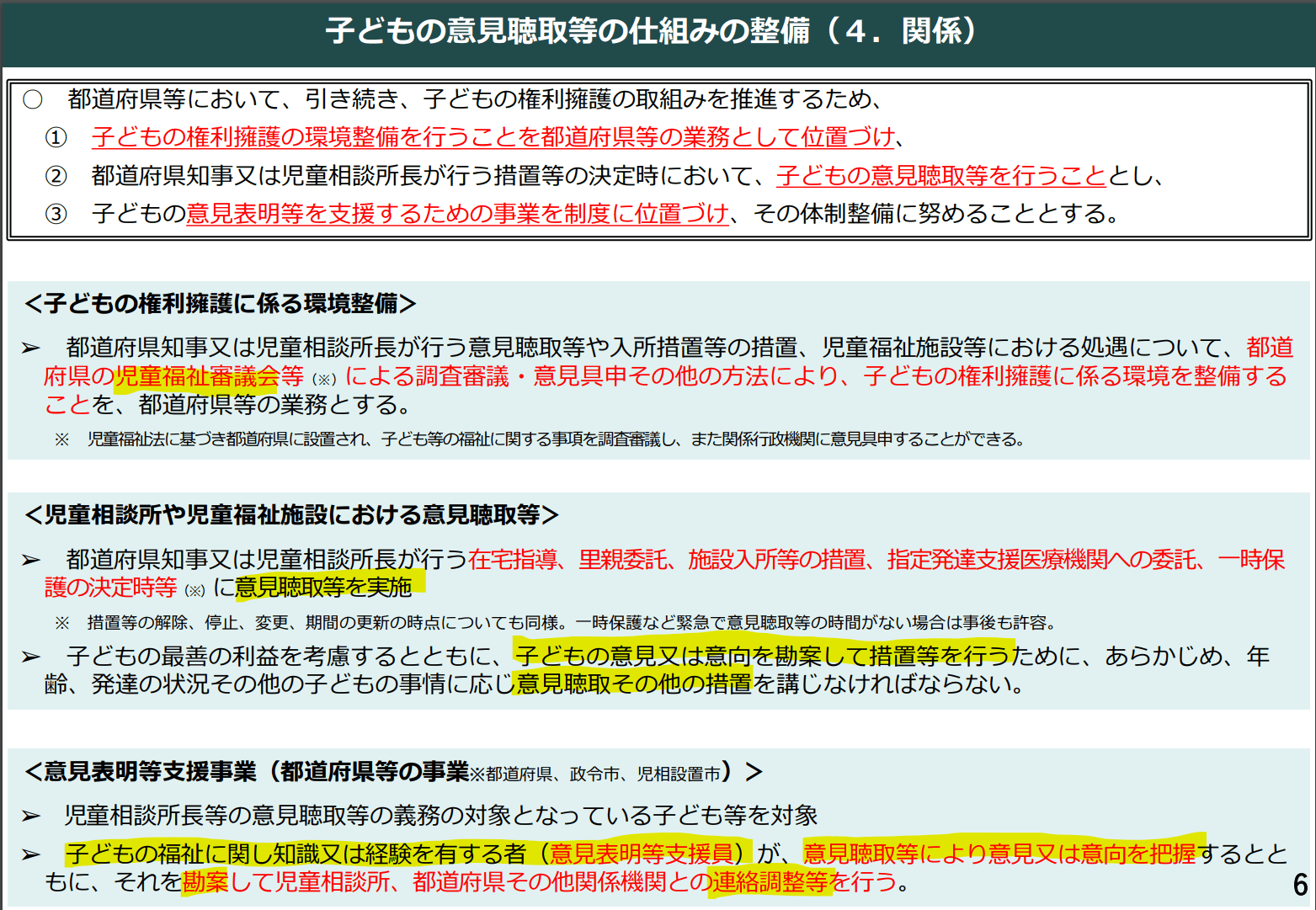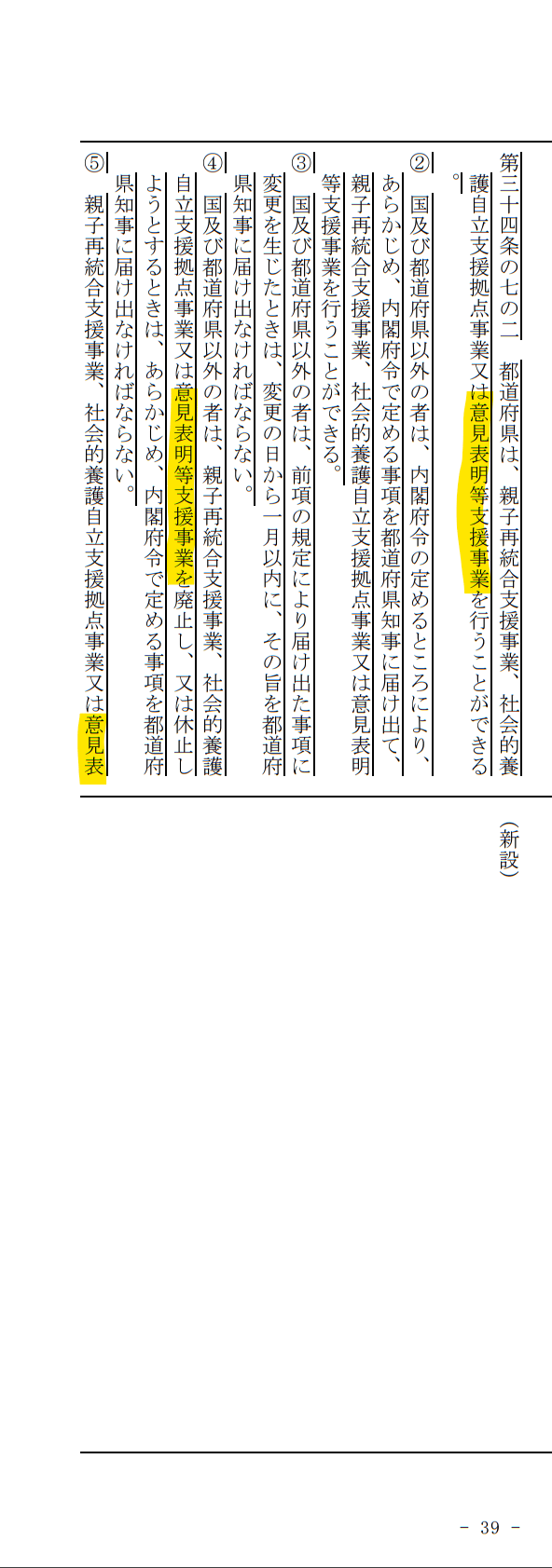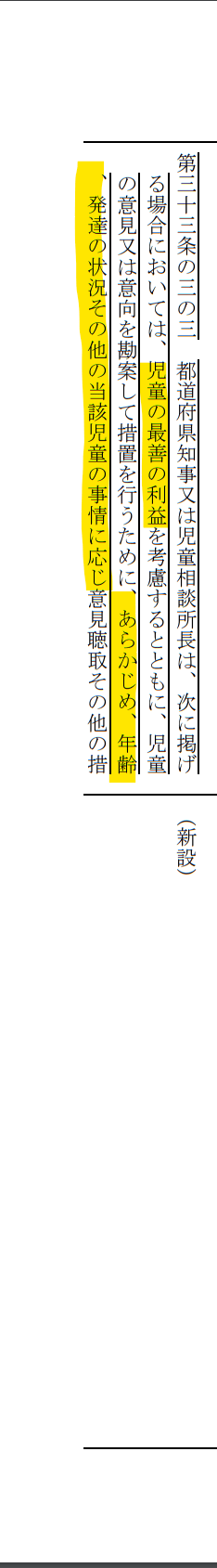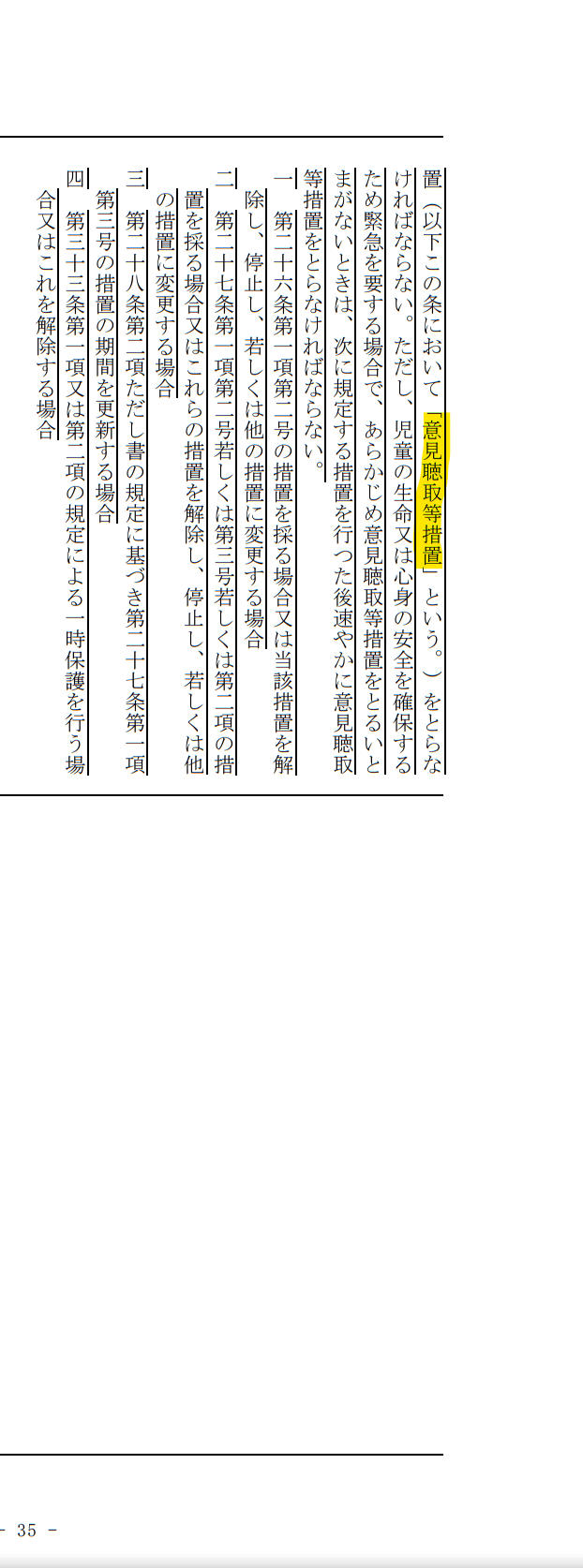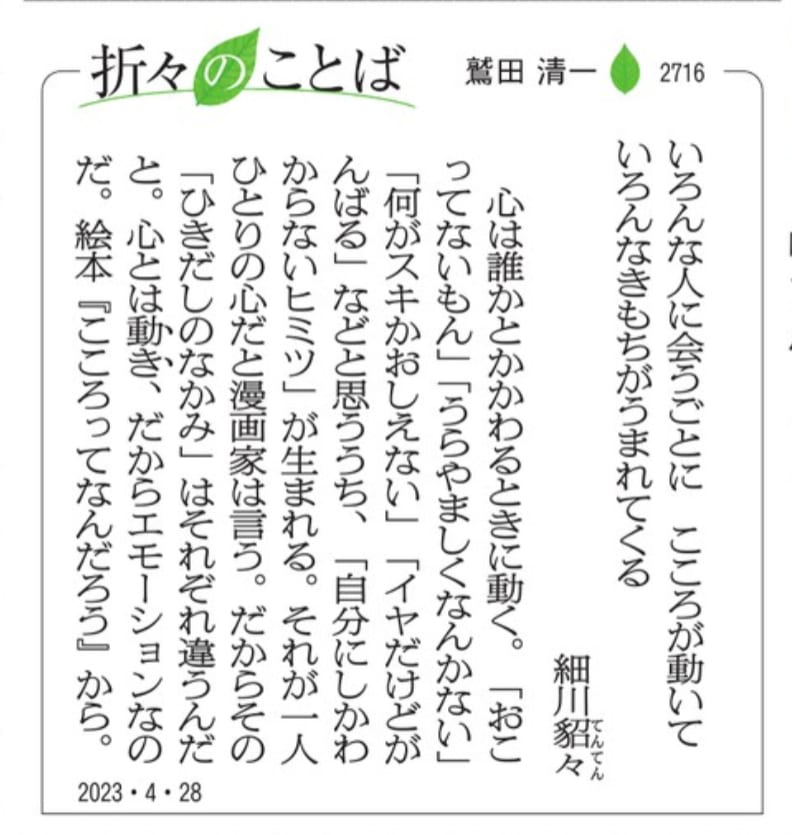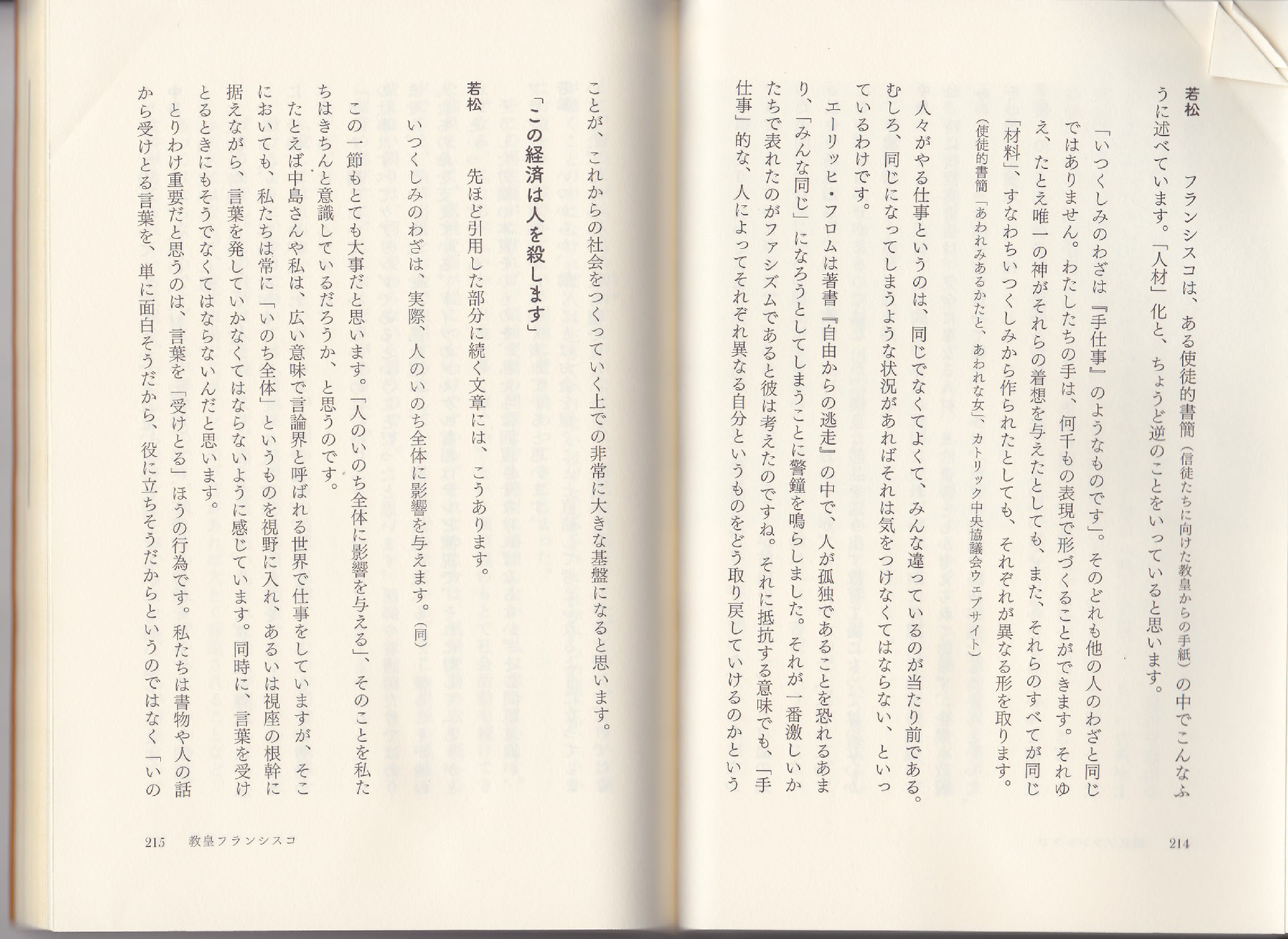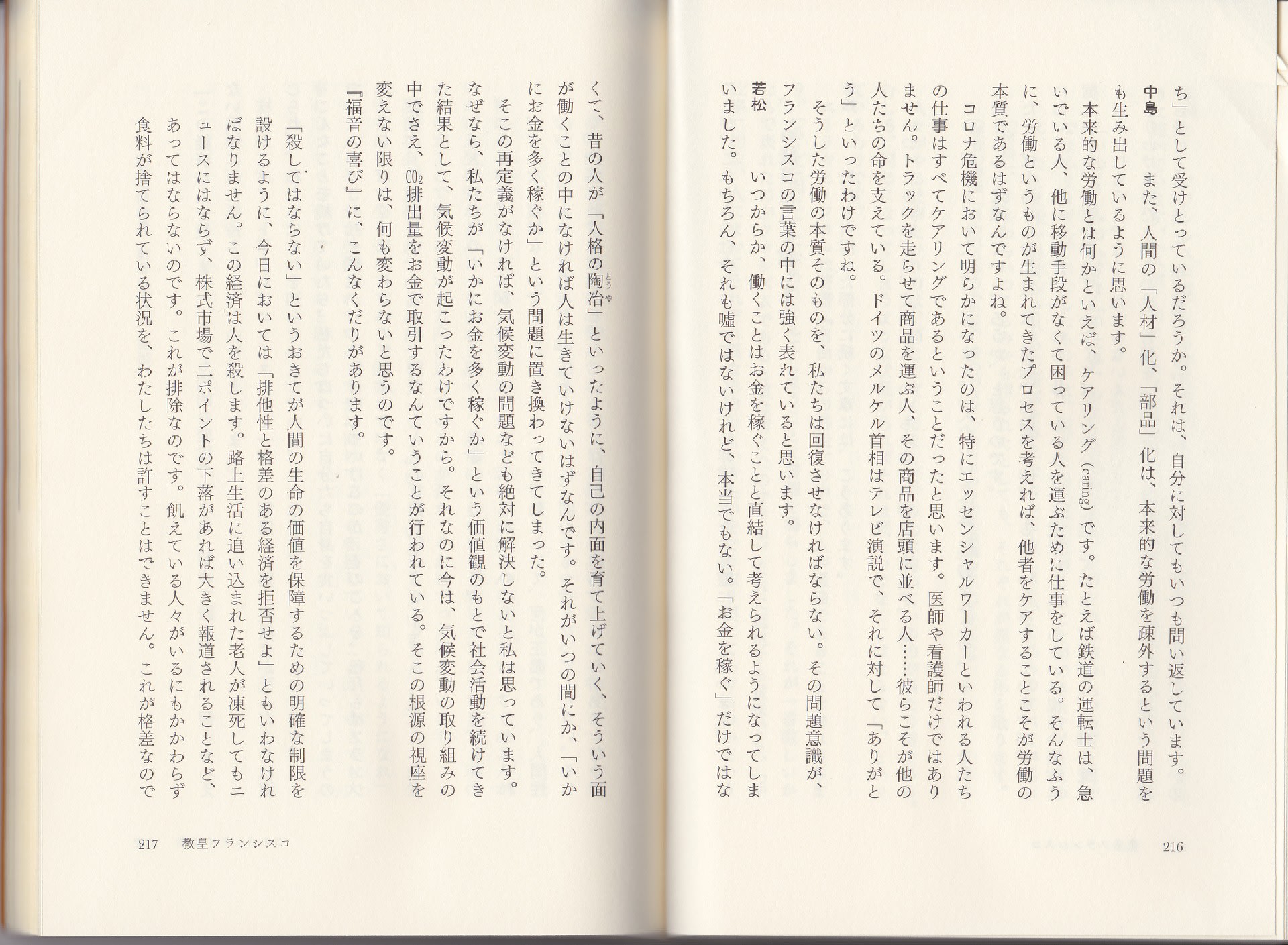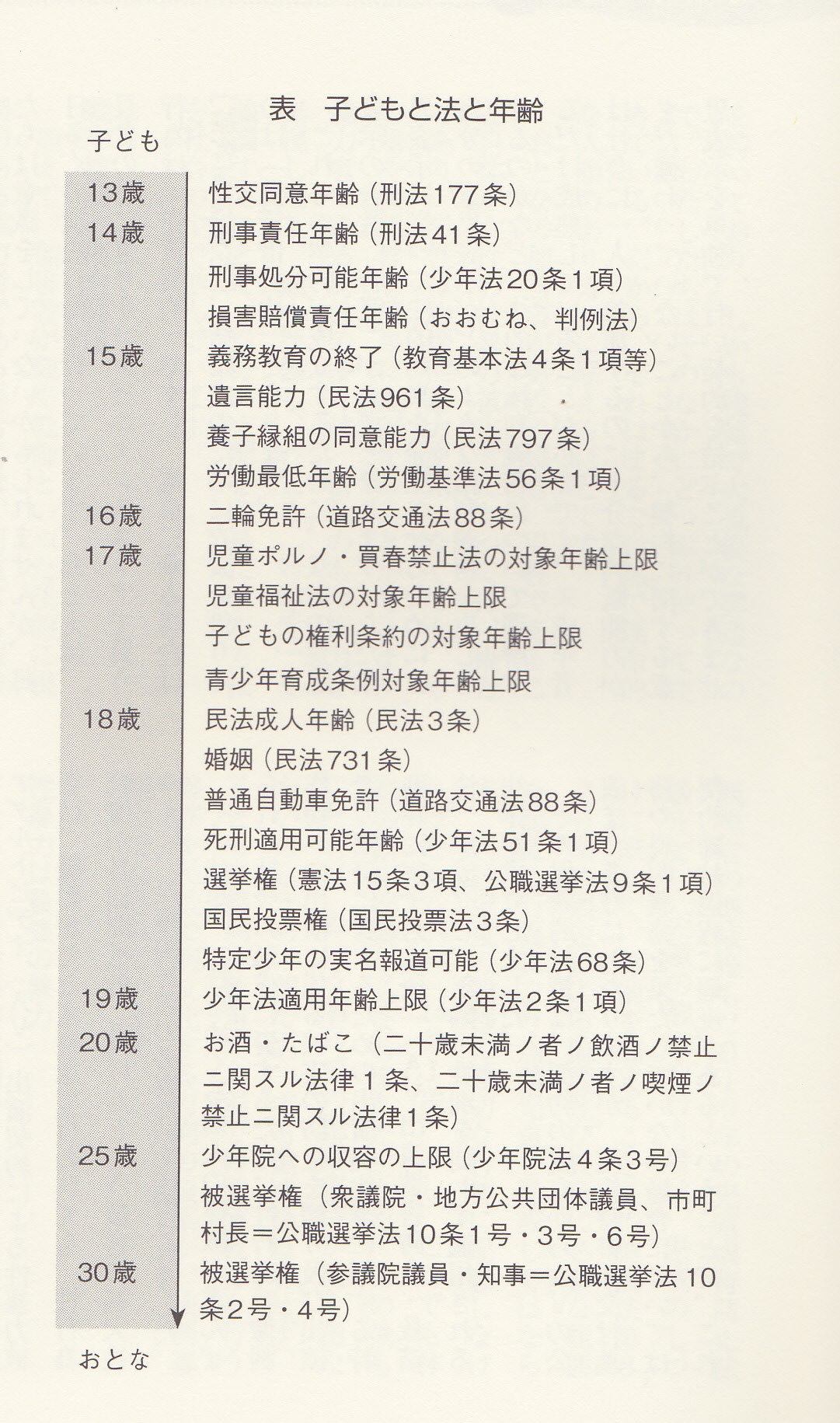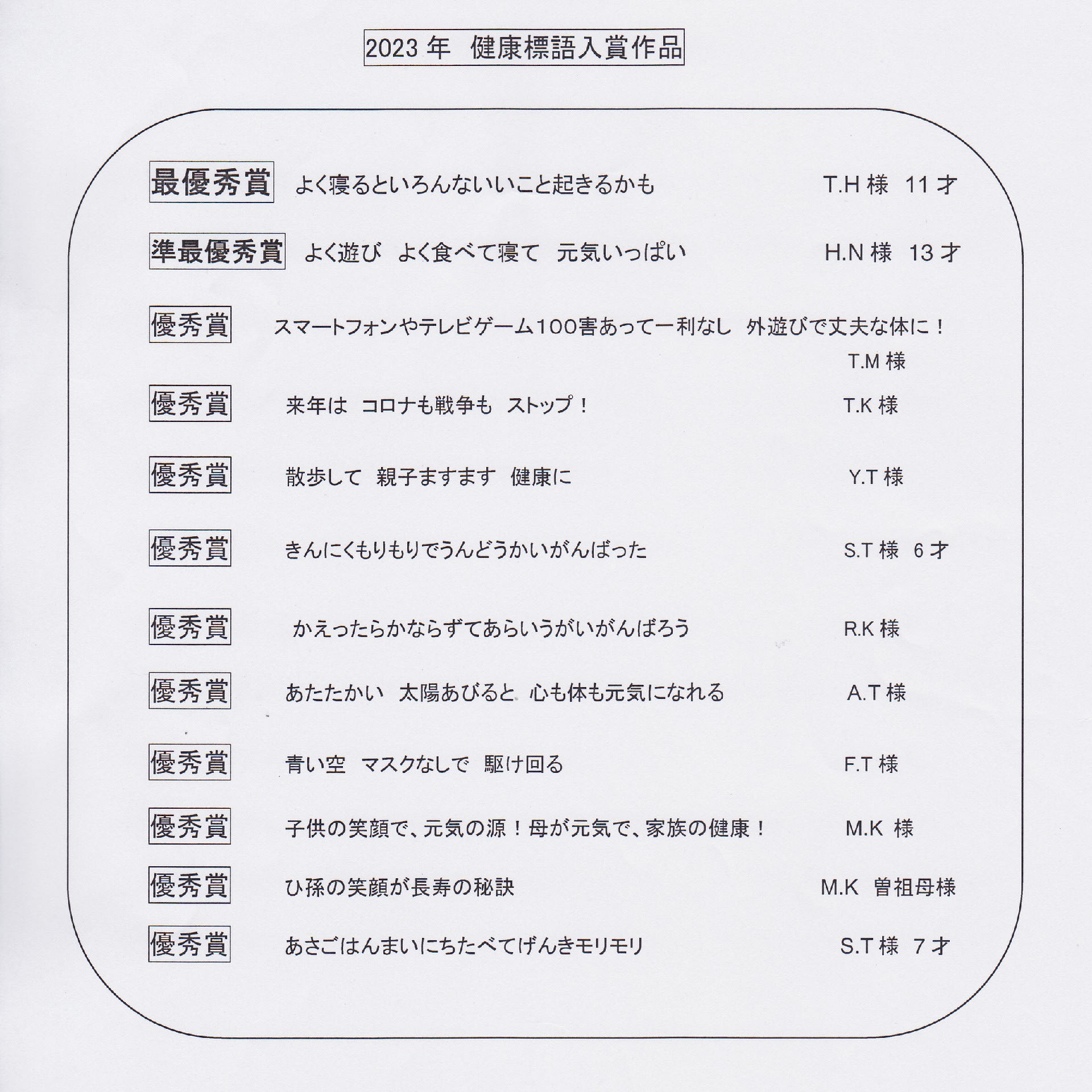子どもの権利条約
1989年11月20日国連総会採択、1994年日本批准。
第1条 18歳になっていない人を子どもといいます。
♠第2条 すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっていて差別されません。
第3条 日本は、子どもにもっともよいことはなにかを第一に考えます。
第4条 日本は、この条約に書かれた権利を守るために、法律を作り政策を実行します。
第5条 親(保護者)は、子どもの発達に応じて、適切な指導をします。
❤♦第6条 すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。
♦第7条 子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育てられる権利をもっています。
♦第8条 名前や国籍、家族の関係など、自分が自分であることのしるしを、大切にされます。
♦第9条 子どもには、親と引き離されない権利があります。ただし、親が子どもに暴力を振るうなどの場合は別です。
♦第10条 別々の国にいる親と子どもが会ったり、一緒にくらしたりするために、国を出入りできるよう日本は配慮します。
♦第11条 日本は、子どもが国の外へ連れさられたり、自分の国にもどれなくなったりしないようにします。
♣第12条 子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表明する権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
♣第13条 子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。
♣第14条 子どもは、思想・良心・宗教の自由についての権利をもっています。
♣第15条 子どもは、ほかの人びとと一緒に団体をつくったり、集会を行ったりする権利をもっています。
♣第16条 子どもは、プライバシーが守られます。また、その名誉を傷つけられない権利をもっています。
♦♣第17条 子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れる権利をもっています。日本は、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。
♦第18条 子どもを育てる責任は、まずその両親(保護者)にあります。日本はその手助けをします。
♠第19条 どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、不当な扱いなどを受けたりすることがないように、日本は子どもを守らなければなりません。
♦第20条 家庭を奪われた子どもや、その家庭環境にとどまることが子どもにとってよくないと判断され、家庭にいることができなくなった子どもは、かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。
♦第21条 子どもを養子にする場合には、その子どもにとって、もっともよいものであるように、作られなければなりません。
♠第22条 難民となった子どもは、のがれた先の国で守られ、援助を受けることができます。
♦第23条 心やからだに障がいがある子どもは、尊厳が守られ、自立し、社会に参加しながら生活できるよう、特別な支援を受ける権利をもっています。
❤第24条 子どもは、健康でいられ、必要な医療や保健サービスを受ける権利をもっています。
❤第25条 施設に入っている子どもは、その扱いがその子どもにとってよいものであるかどうかを定期的に調べてもらう権利をもっています。
❤第26条 子どもは、生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、日本からお金の支給などを受ける権利をもっています。
❤第27条 子どもは、心やからだがすこやかに成長できるような生活を送る権利をもっています。
♦第28条 子どもは教育を受ける権利をもっています。学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方からはずれるものであってはなりません。
♦第29条 教育は、子どもが自分のもっている能力を最大限のばし、人権や男女平等、平和、環境を守ることなどを学ぶためのものです。
♦第30条 少数民族や先住民族の子どもは、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利をもっています。
♦第31条 子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加したりする権利をもっています。
♠第32条 子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利をもっています。
♠第33条 日本は、子どもが麻薬から保護するためにあらゆる方法をとります。
♠第34条 日本は、子どもが性的欲望の手段としてこき使われたり、ひどいめにあわされたりしないようにします。
♠第35条 日本は、子どもが誘拐されたり、売り買いされたりすることのないように守らなければなりません。
♠第36条 日本は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
♠第37条 どんな子どもに対しても、拷問や人間的でない扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたりすることは許されません。もし、罪を犯し、たいほされても、尊厳が守られ年れいにあった扱いを受ける権利をもっています。
♠第38条 日本は、15歳にならない子どもを軍隊に参加させないようにします。また、戦争にまきこまれた子どもを守るために、できることはすべてしなければなりません。
❤♦第39条 虐待、人間的でない扱い、戦争などの被害にあった子どもは、心やからだの傷をなおし、社会にもどれるように支援を受けることができます。
♠第40条 罪を犯したとされた子どもは、ほかの人の人権の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たせるようになることを考えて、扱われる権利をもっています。
以下、略。
**************
日本ユニセフ抄訳:https://www.unicef.or.jp/crc/childfriendly-text/
定者吉人氏抄訳:https://koad-hiroshima.net/?page_id=1422
日本政府訳:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html
原文:https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.jinken-kodomo.net/english/