2024.8.22朝のラジオ体操、ふるさと和歌山県の御坊市から。
市制70周年、「ええわらよ!御坊市」
ホームページを見て、トップページから、その市の歴史に飛べるのは、私は、初めて見ました。
子どものころ、なかなか理解ができなかった道成寺の杏珍清姫の民話があるまちで、子どもの頃から、なじみのある市でした。
市町村ではじめて、地域版認知症希望大使を「あがらの総活躍希望大使」として任命しています。
*****ホームページより******
https://www.city.gobo.lg.jp/index.html


●市政概要
https://www.city.gobo.lg.jp/sisei/gaiyou/1383178699173.html
















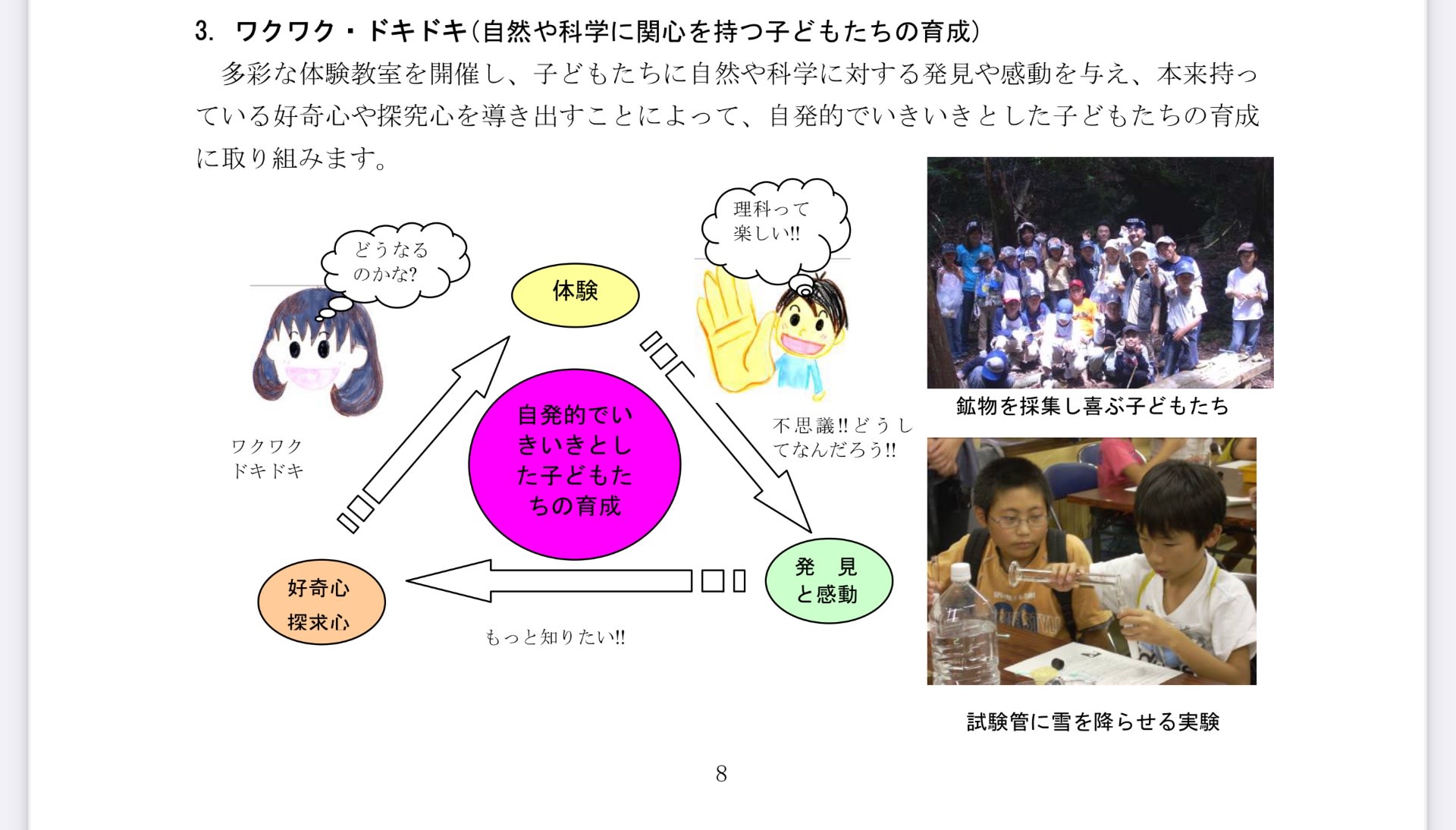








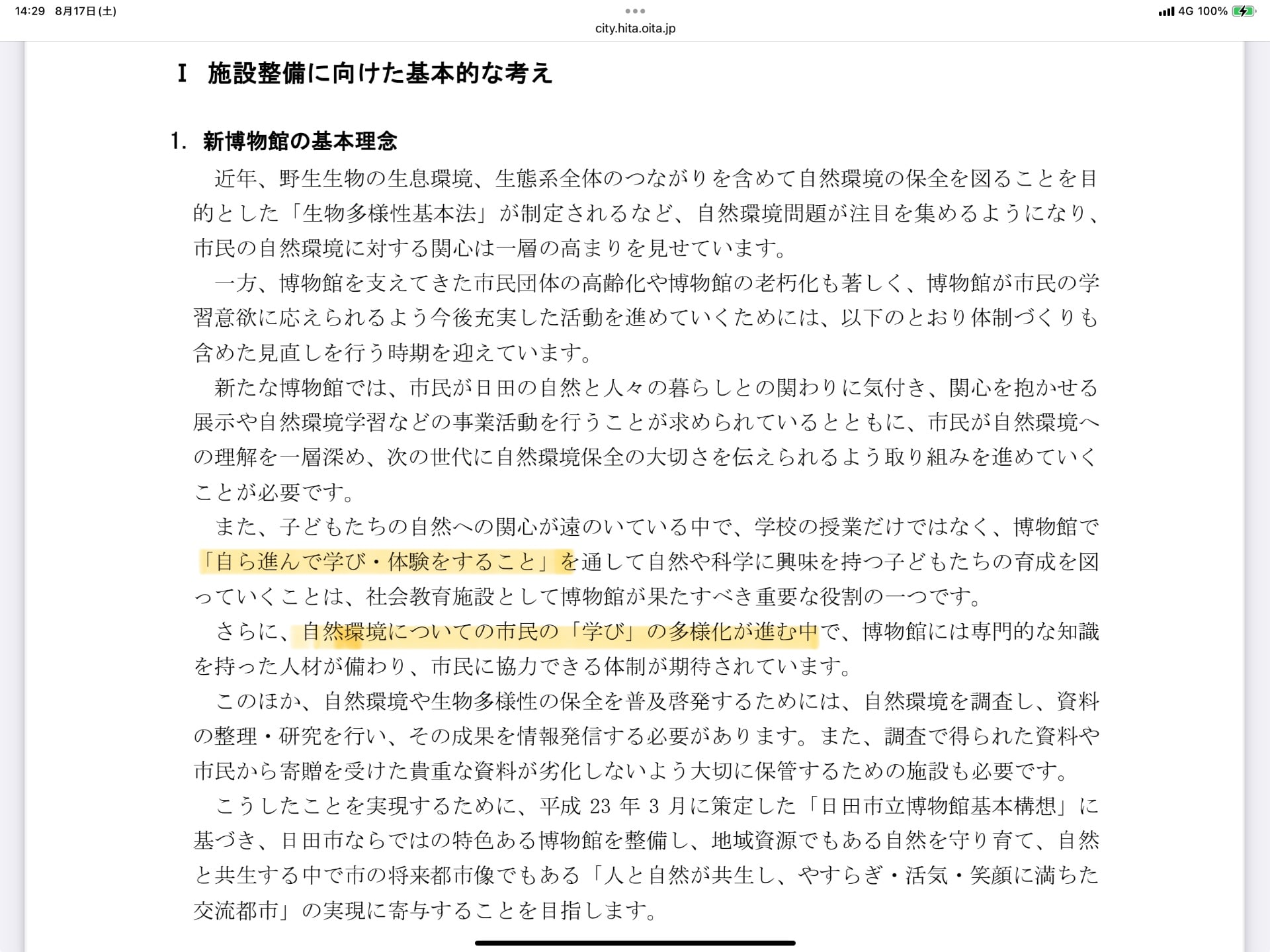














































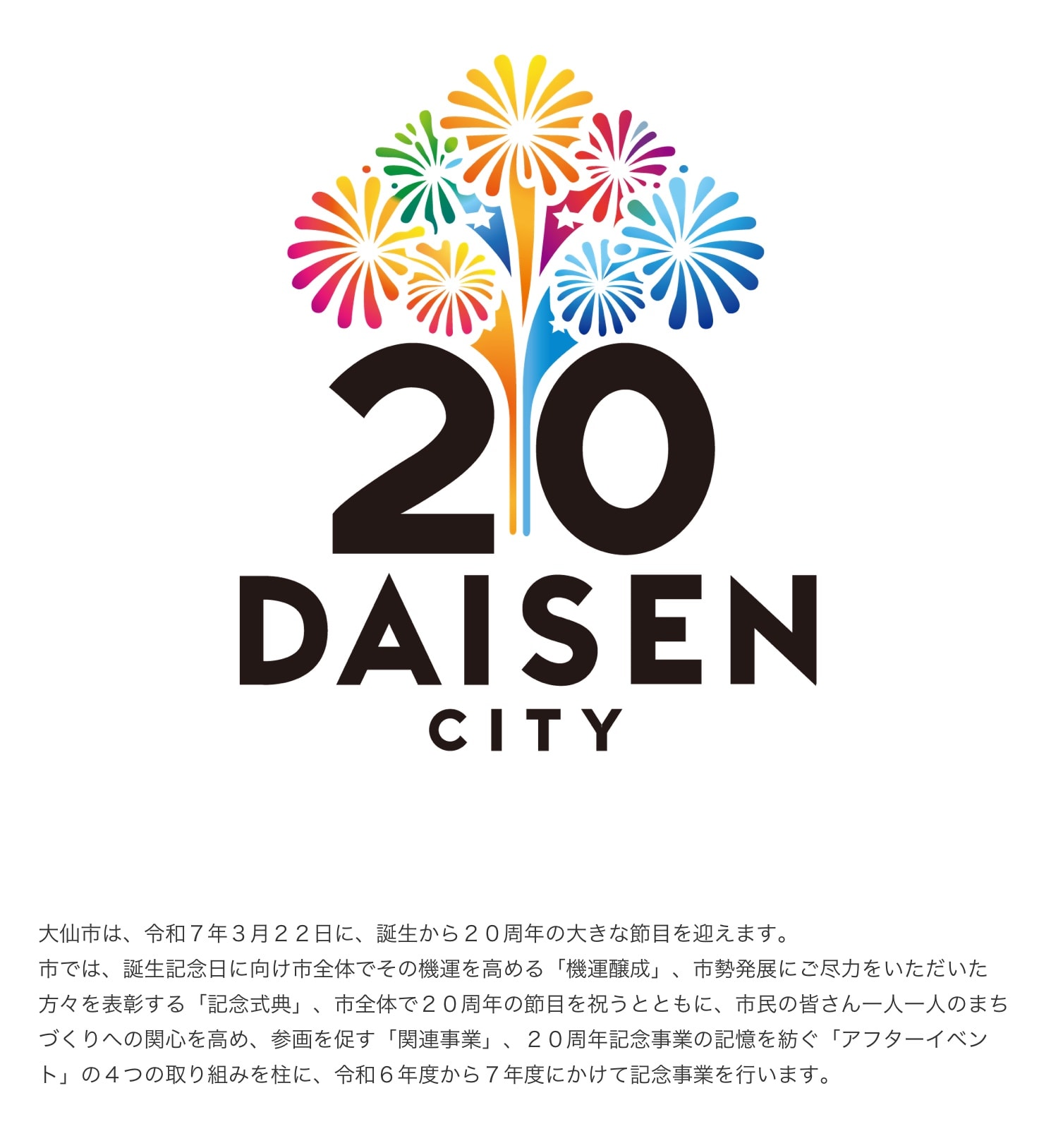


















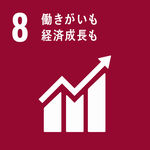





 せ
せ














