朝日八幡神社は、松山八社八幡第6番目の神社で、旧社格は郷社である。
祭神は、品陀和気命、帯中津彦命、息長帯比売命、市杵島比売命、多紀理比売命、多岐津比売命である。
社伝によると、持統天皇の代に仲哀天皇神功皇后の行宮後に足頬地主神を祭り、沼戸明神と称えたことに始まるという。のちに山城国山崎八幡神(現離宮八幡宮)を勧請し山城八幡と改称した。
貞和年間(1345~1349)に兵火に会い、延文6年(1361)伊予守護河野通尭の命によって、平範有が今の朝日谷の地に社殿を再築し、さらに応永19年(1412)に河野通成が社殿を増築した。
慶長8年(1603)伊予松山藩初代藩主加藤嘉明が松山城の固めとした近郷の八社八幡の一つとして武運長久の祈願所となる。明治3年(1870)に、朝日八幡神社と改称された。
隣接して大宝寺がある。松山市内に国宝の建造物は3件あり本堂がその一つ、建立は鎌倉前期ごろといわれ愛媛県下では最古の和様建築とされている。
本堂前に、市指定天然記念物「姥(うば)桜(ざくら)」がある。松山地方で二番目に早く開花する。毎年多くの観桜者とカメラマンが来る松山の名所である。

神社の所在は、松山南江戸五丁目12番1号に位置する。
注連石手前に社号碑がある。

注連石は、明治216月吉日と刻印されている。

注連石、鳥居を潜り128の石段を上り社殿参拝する。

石段を上りきると本殿が見えてくる。
巫女さんがいた。正月初祈祷にこられる氏子さんを待っていた。

拝殿内部、正月3日の初詣、家族で参拝に来て初祈祷を受ける準備が整っている。

拝殿と神殿、神社の全景。

朝日八幡神社のお守り、お札。

神社、注連石手前に「国宝大宝寺」の寺号碑があり、左に行くと大宝寺がある。

鎌倉前期創建の国宝大宝寺本堂で愛媛県最古の和様建築とされている。

国宝大宝寺本堂前にある「姥(うば)桜(ざくら)」で開花時期は3月中旬頃、画像は昨年3月29日撮影。根回り2,8m、高さは低いが枝張りよく、その姿態は美しい。
姥桜(うば桜)の由来は、角(すみ)木(き)長者の娘が病に倒れたとき、姥の袖が自分の命と引き替えに娘の命を助けた。娘は全快したが、袖が急病になり「袖は、お嬢様の身代わりを薬師様にお願いしたのだから歎かぬように、ただお嬢様のお礼に寺に桜を植えて欲しい」と遺言して世を去った。それでこの桜を「姥桜」という。品種は、エドヒガン。
祭神は、品陀和気命、帯中津彦命、息長帯比売命、市杵島比売命、多紀理比売命、多岐津比売命である。
社伝によると、持統天皇の代に仲哀天皇神功皇后の行宮後に足頬地主神を祭り、沼戸明神と称えたことに始まるという。のちに山城国山崎八幡神(現離宮八幡宮)を勧請し山城八幡と改称した。
貞和年間(1345~1349)に兵火に会い、延文6年(1361)伊予守護河野通尭の命によって、平範有が今の朝日谷の地に社殿を再築し、さらに応永19年(1412)に河野通成が社殿を増築した。
慶長8年(1603)伊予松山藩初代藩主加藤嘉明が松山城の固めとした近郷の八社八幡の一つとして武運長久の祈願所となる。明治3年(1870)に、朝日八幡神社と改称された。
隣接して大宝寺がある。松山市内に国宝の建造物は3件あり本堂がその一つ、建立は鎌倉前期ごろといわれ愛媛県下では最古の和様建築とされている。
本堂前に、市指定天然記念物「姥(うば)桜(ざくら)」がある。松山地方で二番目に早く開花する。毎年多くの観桜者とカメラマンが来る松山の名所である。

神社の所在は、松山南江戸五丁目12番1号に位置する。
注連石手前に社号碑がある。

注連石は、明治216月吉日と刻印されている。

注連石、鳥居を潜り128の石段を上り社殿参拝する。

石段を上りきると本殿が見えてくる。
巫女さんがいた。正月初祈祷にこられる氏子さんを待っていた。

拝殿内部、正月3日の初詣、家族で参拝に来て初祈祷を受ける準備が整っている。

拝殿と神殿、神社の全景。

朝日八幡神社のお守り、お札。

神社、注連石手前に「国宝大宝寺」の寺号碑があり、左に行くと大宝寺がある。

鎌倉前期創建の国宝大宝寺本堂で愛媛県最古の和様建築とされている。

国宝大宝寺本堂前にある「姥(うば)桜(ざくら)」で開花時期は3月中旬頃、画像は昨年3月29日撮影。根回り2,8m、高さは低いが枝張りよく、その姿態は美しい。
姥桜(うば桜)の由来は、角(すみ)木(き)長者の娘が病に倒れたとき、姥の袖が自分の命と引き替えに娘の命を助けた。娘は全快したが、袖が急病になり「袖は、お嬢様の身代わりを薬師様にお願いしたのだから歎かぬように、ただお嬢様のお礼に寺に桜を植えて欲しい」と遺言して世を去った。それでこの桜を「姥桜」という。品種は、エドヒガン。










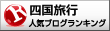

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます