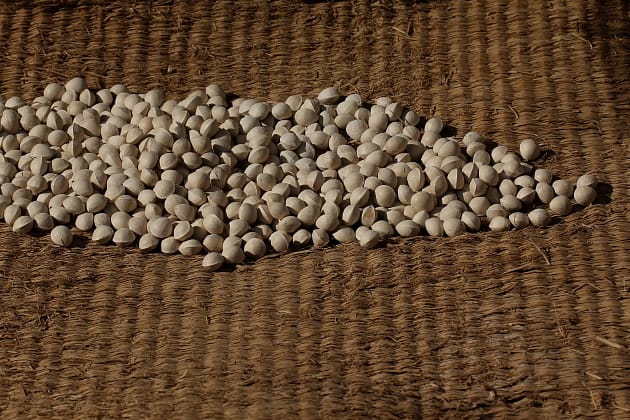紅葉巡りの番外編
実は
愛知県の紅葉巡りは
前回紹介した祖父江町と決めていた
訪れた翌々週
ひょんなことで犬山市を訪れることとなり
紅葉シーズン終了で静かさを取り戻した街で
もしかしたら紅葉が残っているかもと
木曽川をもう少し遡上した
この神社を訪れてみたのだ

愛知県の珍スポット
桃太郎神社

シャレではなく至って真面目な話

この地方に伝わる伝説では
桃太郎は
この神社の建つ土地
来栖の地で育ち

鬼退治に出掛けた島は
木曽川水系のひとつ
可児川にある
小島だったと伝えられている

境内には
知る人ぞ知る
浅野祥雲作の
桃太郎伝説にまつわる
像が置かれている

洒落っ気
たっぷりのコンクリート製の像を眺めての参拝

珍しい風景
いわゆる珍スポットの
紹介となってしまった

実は
愛知県の紅葉巡りは
前回紹介した祖父江町と決めていた
訪れた翌々週
ひょんなことで犬山市を訪れることとなり
紅葉シーズン終了で静かさを取り戻した街で
もしかしたら紅葉が残っているかもと
木曽川をもう少し遡上した
この神社を訪れてみたのだ

愛知県の珍スポット
桃太郎神社

シャレではなく至って真面目な話

この地方に伝わる伝説では
桃太郎は
この神社の建つ土地
来栖の地で育ち

鬼退治に出掛けた島は
木曽川水系のひとつ
可児川にある
小島だったと伝えられている

境内には
知る人ぞ知る
浅野祥雲作の
桃太郎伝説にまつわる
像が置かれている

洒落っ気
たっぷりのコンクリート製の像を眺めての参拝

珍しい風景
いわゆる珍スポットの
紹介となってしまった