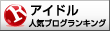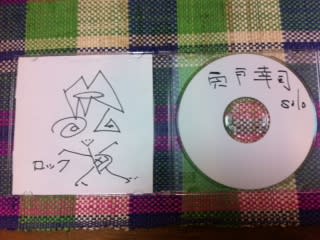以前からお伝えしていた元ヘンリー・カウのメンバー3人を含む即興ロック・バンド、アルトー・ビーツの来日ツアーが6/8豊橋を皮切りに始まっている。メンバーはクリス・カトラー(ds)、ジョン・グリーヴス(b,p,vo)、ジェフ・レイ(fl,synth,vo)、ユミ・ハラ・コークウェエル(p,vo)の4人。ユミさんはイギリス在住、1990年代から現代音楽を中心に音楽活動を開始、2007年から即興演奏活動を本格的にスタート、デヴィッド・クロス、チャールズ・ヘイワード、ヒュー・ホッパー、坂田明、吉田達也、梅津和時などの大物アーティストと共演を重ねてきた。何度も来日し、コンサートと共に各地で即興ワークショップを開催している。2009年からジェフ・リーとデュオ演奏を始め、このデュオで日本ツアーもしている。同年8月ドイツの「アヴァンギャルド・フェスティバル」に出演した時、ピーター・ブレグヴァド・トリオで出演していたクリス・カトラーとジョン・グリーヴスと共に急遽ユニットを組み演奏したのがアルトー・ビーツの誕生だった。その時のユニット名はファウストのジャン-エルヴェ・ペロン命名の「Not Henry Cow」(!)だった。2011年「アルトー・ビーツ(The Artaud Bests)」としてノルウェーのNødutgang Festivalに出演、そして今回の来日ツアーで本格活動を始めた。
この日はユミさんによる即興ワークショップ&ライヴ。私が参加した経緯は「フルート特集」で書いた通り。前日になってフルートだけでは物足りなくなり、家中を探しまわって楽器や音の出るおもちゃをかき集めた。サックスのマウスピース、ブリットポップ・バンドのドッジーから貰ったタンバリン、オーストラリアの原住民アボリジニの木製の筒状の波の音がする楽器、おもちゃの鉄琴、中国土産のお経オルゴールなど。さらに会場へ向かう途中で100均でいくつかおもちゃを購入。
ルースターはブルース/ジャズ系のライヴハウス。30人くらいのキャパのそこそこの広さのお洒落な店。この日は「貸し切り」となっていた。会場ではワークショップ参加者が各自楽器を準備している。アルトー・ビーツのメンバーがうろうろしており「この人がクリス・カトラーか!」と昔からのアイドルというか神の姿に感激する。
楽器のセッティングが終わるとステージ前に参加者が半円形に椅子を並べてアルトー・ビーツの4人を囲む。参加者は全部で9人。以前灰野さんと石川浩二氏とのトリオでライヴをしたことのある臼井淳一氏(笙、vln)や佐藤允彦さんや広瀬淳二氏と共演する凄腕ベーシスト池上秀夫氏、ダモ鈴木さんとも共演予定がある女性ギタリスト吉本裕美子嬢といったベテランから、即興は初めてという若者まで音楽経験はまちまち。ベースが4人、フルートが2人というのが今回の来日メンバーらしくて面白い。
まずはアルトー・ビーツの模範演奏から。ユミさんのミニマルな旋律を重ねるピアノに表情豊かなクリスのドラムが歌い、ジェフはシンセを使ってフルートの音を変調させる。ジョンはベースは勿論ヴォーカルでも達者なところを見せる。初めて生で聴く神々の演奏に一同呆然。演奏後質疑応答があるが、即興演奏とは何かという問いにクリスが「演奏者は役者と同じで演奏場面毎に別の役を演じている。真似するんじゃなくて役になり切るんだ」と応えたのが印象的だった。彼はかなりの理論家で、灰野さん同様一言一言が金言である。
[8/1訂正:ユミさんから『これの質問は、クリスに向けて、「クリスさんとフレッド・フリスとの即興の録音を聴きなれているが、アルトー・ビーツの即興ではビートがある。演奏する上で意識の違いとかはあるんでしょうか」という池上さんのご質問でした。』との訂正をいただきました。]
その後全員で音出し。お互い遠慮して恐る恐るの演奏。私もフルート中心に少しおもちゃ類を鳴らす。だんだん30年前の感覚が戻ってきた。演奏→質疑応答/メンバーからのアドバイス→演奏の繰り返しで全部で4セッション。あっという間にワークショップの終了時間になる。本番のライヴはベース4人を割り振って4つの少人数セッション+全員のセッションという構成に決まった。昨年のオーケストラTOKYO-FUKUSHIMAは観客はいたけれど野外だし100人以上の大所帯だったので平気だったが、真っ当なライヴハウスで知らない観客を前に少人数のグループで演奏するのは17年ぶりである。チケットはSold Out、満席の観客。武者震いしてくる。
第1部はアルトー・ビーツだけの演奏。ユミさん、ジェフ、ジョンの3人のヴォーカル・パフォーマンスで始まり徐々に大きなうねりのある展開へ突入。ユミさんのヴォーカルは少しダグマー・クラウゼを思わせる。神3人の演奏は言わずもがなで凄過ぎ。ワークショップでは手抜きじゃないけどレベルを参加者に合わせていたことを実感。2曲目にスペシャル・グストとして梅津和時さんが参加。前日の所沢でのライヴで飛び入り参加し、クリスは梅津さんの家に泊まったとのこと。梅津さんを迎えての演奏はますます気合いが入り感動的。もうこれだけ観れば充分でしょ。お客さん帰ってくれないかな~なんて思ってしまう。
15分の休憩の後、ワークショップ参加者を交えての演奏。1セット目に即興が初めてという可愛い顔の青年がフルートで出演。これがなかなか上手い。アドリブ云々以前に音に現役ならではの芯のある力強さがある。それを観て「同じフルートじゃ敵わない」と作戦変更。そこへユミさんが手招きし「飛び道具は音量に気をつけてね」とのアドバイス。さていよいよ私の出番だ。こんなブログ書いてるくらいだから基本的に目立ちたがりなので人前で緊張することはないが、逆にハイになってやり過ぎてしまうのが悪い癖。しかもどうやってお客さん(および演奏者)を驚かせるか、なんてことを考えてしまう。昼間のワークショップでユミさんが「即興と言ってもあくまでグループのアンサンブルだからひとり目立とうとしないように」と言っていたことなど頭から完全に飛んでいた。フルートの代わりにサックスのマウスピースをくわえる。そしてマイクに近づけて思い切り「ピーーーーーーーッ!」と吹き鳴らす。30年前にいつもやっていた得意技(芸?)だ。ふと見るとユミさんが両耳を塞いでいる。ハッと我に帰り「ヤバい」とばかりマイクを遠ざけるが始めてしまったものは止められない。ピーピー吹き続けてクリスが乗って来るのを期待する。案の定激しいフィルインで絡んできた。このままオーヴァーハング・パーティ(阿部薫+豊住芳三郎)状態に突入だ!と思ったところで、ユミさんが大らかなヴォーカルで牽制する。ひとり突っ走る訳に行かないのでタンバリンや鉄琴、おもちゃのラッパとひよこ(これはイマイチ失敗)、お経オルゴールと楽器を取っ替え引っ替えついて行くが、個人的には最初の3分で既に終わっていた、というのが本当のところ(汗。何とか10分くらいで演奏が終わるが、私は終演のSEのつもりでiPodでノイズを垂れ流し続けた。一番前の席にこの来日情報を教えてくれたTAKE's Home Pageのタケダさんが座っていたので反応を伺っていたが笑っていたし楽しんでもらった様子。レイヴレポでも「面白かった」と感想をいただいた。
残り二組もそれぞれ個性的な演奏だったが、アルトー・ビーツのメンバーがどんな演奏にも動じずそれと分からないように音楽の方向をコントロールしているのが素晴らしい。最後は参加者全員に梅津さんと梅津さんのバンドの女性サックス奏者、多田葉子嬢を加え全員でセッション。「渋さ知らズみたいだな~」と客席から声が上がりウケる。図らずも梅津さんのすぐ隣で演奏することに。さっきの失敗を反省してフルートで勝負。「テクスチャーを大切に」というユミさんの指示通りに抑えめで演奏するが、盛り上がって来るとまたゾロ遊び心に火が付き、用意してきた最後の飛び道具のクラッカーを取り出して演奏者の方へ向けて「パーン」「パーン」と鳴らす。ユミさんがまたビックリして睨んでいる。ほどほどにして大セッション終了。
終演後はお客さんも参加しての懇親会。プログレ・マニアのお客さんばかりで、ヘンリー・カウやアート・ベアーズのアナログ盤を持参してサインを貰っているのが面白い。お店の人や他の出演者から「ジェイミー・ミューアのようだった」と言われいい気になっていたら、ユミさんから「言ったこと全然守らなかったじゃないの!」と大目玉を喰らいしばし凹むが、他のお客さんとのプログレ話や若い参加者を捕まえての昔話を楽しむ、ただの蘊蓄好きのおっさんと化してしまった。
灰野さんが高円寺で映画前夜祭ライヴをしていたのでスタッフにメールすると、打ち上げをやっているので来ませんか?との誘い。クリスに灰野さんに会いに行くのでメッセージはないか、と尋ねると自分のソロCDと簡単なメモ書きを託された。皆に別れを告げ高円寺に向かう。会場の高円寺HIGHでは灰野さんとスタッフが静かに盛り上がっていた。灰野さんにクリスのメッセージを渡す。奥のテーブルに亀川千代氏がいたので隣に座る。イベントは超満員で大盛況だったらしい。不失者の演奏に涙した、とデザイナーの北村氏。しかし、理由は分からないがそこはかとなく妙な気持ちがした。
お開きになり同じ中央線の亀川氏とスタッフのnorao氏達と下り電車に乗る。世間話をしている時ふと気が付いた。「もしかして今日の不失者って亀川さんとKiyasu君だったんですか?」と尋ね、「え~っ今まで気が付かなかったんですか?」と呆れられた。あらま~大ボケかましてしまった。道理でナスノさんも幾郎さんもいない筈。打ち上げで感じた不思議な気分はこれだったのだ。我ながらお間抜けでした。
出来の善し悪しはともかく神々と共演して、灰野さんにも挨拶できて充実した一日だった。翌日のBar Issheeではプレッシャーなしに神々=アルトー・ビーツの演奏を楽しむぞ!
神降臨
伝説の夜
更けて行く
「毎秒が伝説」である。from ザ・クロマニヨンズ「グリセリン・クイーン」