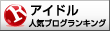Facebookの友人がパブロ・ピカソという1980年代のインディ・バンドの音源を紹介していたのに刺激されて、YouTubeで探してみたら当時の自主制作ソノシートや7インチ/LPの音源を色々発見した。高校時代そんなに小遣いがなかった頃は、吉祥寺や下北沢の輸入・中古レコード店を巡り少しでも安くレコードを手に入れようとエサ箱を漁ったものだが、1枚300円程度のソノシートは金のない高校生にはうってつけで、ジャケットとレコード店員の手書きコメントを参考に買い漁った。無名のバンドでもかなり面白いものも多く、文字通り擦り切れるまで聴いた。「Fool's Mate」「ZOO」「宝島」といったサブカル音楽誌とイラストレーターの八木康夫(現ヤギヤスオ)さんが「Player」誌に書いていた「PIPCO'S」という連載、それに坂本龍一さんや佐藤薫さんが深夜のFMでやっていたインディーズ紹介番組が頼りだった。
その多くは15年くらい前インディーズ・ブームの頃に売り払ってしまったか、段ボールに詰めて押し入れの奥に眠っているかで聴くことが出来ないのでYouTubeはたいへん便利である。また新生PASS RECORDSやテレグラフ・レコードやいぬん堂、PSFなどのレーベルが当時の音源をCDリイシューしてくれるのも嬉しい。そこから再評価されEP-4やアレルギーのようにバンド自体が再活動始めるのも歓迎したい。
中3の時金沢から東京へ引っ越し初めて吉祥寺へ遊びに行った時ジョージアJr.というレコード店で見つけたインディー・レーベルの先駆者ゴジラ・レコードの第1弾シングル。「Player」誌のニュース欄に紹介されていて気になっていたものだったが、そこに「泉谷しげるを思わせる」と書いてあり、当時は泉谷さんはフォークの人というイメージが強かったのでイマイチ買う気にならなかった。後に買っとけば良かったと何度後悔したことか分からない。今ではPASS RECORDSからのコンピレーションCDで音を聴くことが出来る。ミラーズは東京ロッカーズの中では一番好きで何回もライヴハウスへ観に行った。
MIRRORS - Live at 新宿LOFT_1978.3.31
主に吉祥寺でレコード店巡りをしていたこともあり、吉祥寺マイナーの店長佐藤隆史さんが設立したピナコテカ・レコードの作品情報が豊富だった。最初に出たのがオムニバスの「愛欲人民十時劇場」で次が灰野敬二さんの「わたしだけ?」。灰野さんは当時吉祥寺に住んでいたので街中で時々見かけることがあったが、実際のライヴは観たことがなかった。LPは購入せず、当時流行り始めた貸しレコード店で借りてきてカセットにダビングした。黒字に黒い文字で印刷された歌詞をノートに丁寧に書き写した覚えがある。内なる衝動が、音だけじゃ物足りないと駆り立てたのかもしれない。
ピナコテカの特徴的作品に三角ジャケットのEPがあった。具体的には2作品「ANODE/CATHODE」と「コクシネル」である。アメリカの実験音楽ユニットの70年代半ばの極秘セッション音源と紹介されていた「ANODE/CATHODE」にはおまけでメジャーなアーティストのシングル盤が同封されており、私が買った盤には矢沢永吉のシングルが入っていた。友人は演歌のシングルが入っていて「永ちゃんが当たってラッキーだな」と羨ましがられた。このバンドが実は京都のどらっぐすとうあ周辺に活動していた「第五列」だったという真相を知ったのはつい数年前。
「コクシネル」の三角ジャケ、通称「福助ジャケ」はその友人が好きで購入したのをダビングさせてもらった。PHEWのように凛とした存在感のある女性ヴォーカルとヴァイオリンの調べが郷愁を誘う曲調が好きでよく聴いていたが、数年後にメジャー・レーベルからリリースされた12インチ「ボーイズ・トゥリー」では如何にもニューウェイヴ的な単調なビートが主導権を握っていてちょっとガッカリした。両作ともいぬん堂からCD再発済。
もうひとつ印象的だったのはノイズ・ユニットNORDのLPである。当時イギリスではスロッビング・グリッスルやキャバレー・ヴォルテールなどがインダストリアル・ミュージックとして話題になっており、アメリカでもロサンゼルスのLAFMSの活動が伝えられ、ノイズや電子音楽への興味が刺激されていた。そこへ日本からの回答としてリリースされたのがNORDだった。これも最初は貸しレコードで聴いたのだが想像以上の刺激的ノイズに痺れまくった。特にB面全体を占める「Utopie」という曲のノンメロディで展開されるドラマチックなサウンドスケープにはそれまで聴いてきたプログレ・バンドの組曲よりも遥かに感動した。未CD化。この頃のNORDは片山智氏と及川洋氏のデュオだったが、その後片山NORDと及川NORDに分裂し、片山NORDに伊藤まく氏が参加、メルツバウやKK NULLと共演を重ね活躍した。伊藤まく氏はjapanoise.netを主催、日本のノイズの普及に尽力する重要人物である。
ピナコテカ最大のヒットは山崎春美さんの「タコ」だろう。当時春美さんはいろんな名前のユニットで活動していたので、私が果たしてタコを観たことがあるかは判然としないが、このアルバムは「タコ」の名前を使いつつ、坂本龍一さんをはじめ当時のサブカル系を代表する多数のゲストを集めたプロジェクト作品である。初回盤には歌詞カードが入っていたが、差別用語問題でセカンド・プレスからは入っていない。私が買ったものも歌詞カードのないLPだったので貸しレコード店で借りてきて歌詞カードをコピーした。昨年セカンド12インチと一緒に紙ジャケ再発され詳細な関係者の証言を収めた解説書で当時の事情が明らかにされた。
「PUNGO」は八木康夫さんの連載で知った。パンク+タンゴ=パンゴ、というこれまた不定形ユニットで、菅波ゆり子(accordion)、 篠田昌巳(as)、佐藤隆史(ds)、 佐藤幸雄(g)、 今井次郎(b)、 石渡明廣(g) 、久下恵生(ds)など故・篠田さん以外は今なお現役で活躍中のミュージシャン中心。レコードのレーベル面は1枚毎に違う模様の壁紙が貼られていて10数ページの写真集が付いている。これも「WALTZ」というタイトルでCD化されている。
PUNGO - 新テーマ( New Theme / 1981)
ピナコテカから出す予定だったのがある理由で別の自主レーベルからリリースされた竹田賢一さん率いるA-Musik(アームジーク)の「E Ku Iroju」も忘れがたい。チリの有名なプロテスト・ソング「不屈の民」をはじめ世界各国の革命歌・大衆歌を収録した重厚な存在感のある作品で、楽曲解説や各地の抵抗運動の写真を掲載した豪華なブックレット付。何故ピナコテカから出さないか、ということについてはピナコテカ発行のフリーペーパー「アマルガム」に佐藤隆史氏が長文の声明文を書いていた。CD化が望まれる名作である。
残念ながらYouTubeでもニコニコ動画でも音源が見つからなかったが、芳賀隆夫氏の「Piyo Piyo」というサックス・ソロのLPには同じサックス吹きとして大きな影響を受けた。阿部薫さんの弟子とのことで、1980年代は時々ライヴハウスで名前を見かけたがそれ以降全く見なくなってしまった。「芳賀隆夫」で検索したら、1979年11月4日明大"駿台祭"に於けるVedda Music Workshop(竹田賢一, 鈴木健雄, 風巻 隆, 河原淳一, 臼井弘之, 大里俊晴, 園田佐登志 ほか)の貴重な音源がSoundcloudに上がっていたのでリンクしておく→ココ。
まだまだ紹介したい音源は残っているのだが、ピナコテカで字数を使い過ぎた。続きはまた後日。
ピナコテカ
雑貨屋さんも
ありまする
懐かしブログの連発だな~。
[6/28追記]
▼ピナコテカ・レコードのフリーペーパー「アマルガム」
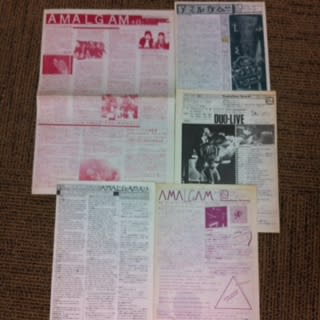
▼ぎゃていの機関誌「GATTY通信」