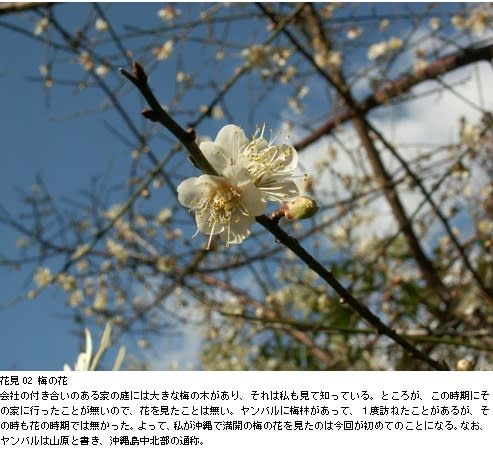農繁期(のうはんき)とは「田植え・稲刈りなど、農事が忙しい時期」(広辞苑)のことで、その対語は農閑期(のうかんき)「農作業のひまな時期」(〃)となる。
「農家の男は冬になると出稼ぎに出る」と若い頃聞いたことがあるので、おそらく、倭国の農閑期は冬季であろう。倭国の冬季の気温では植物の多くもお休みするのでそうなると思う。ところが、沖縄の冬季の気温では、植物の多くはお休みしない。お休みしないどころか、冬季に良く育つ作物が多くある。したがって、沖縄の冬季は農繁期となる。その逆に、沖縄の夏季はあんまり暑くて、植物も元気がでないようだ。よって、沖縄の農閑期はどちらかというと夏季となる。もちろん、暑いの大好き植物もいる。
私は今、少々焦っている。畑小屋作りに時間を取られ(台風で小屋が吹き飛ばされたせいもある)て、畑仕事が大幅に遅れているからだ。9月に植える予定だった作物がいくつもあり、8月中には畑を耕して畝を作って、9月に種蒔きという予定だった。それが台風対策、その後始末、小屋の修復、小屋の建て直しなどに追われ、10月下旬になってやっと2畝を耕したばかり。そこにはニンジンとホウレンソウを植える予定。
『沖縄季節のしおり』なる脱サラ農家の友人Tから貰った表がある。確認はしていないがたぶん、沖縄の農協が出しているもので、主な作物の「品種」、「種の蒔き時」、「苗の植え時」、「収穫期」などが記載されている。その表によるとやはり、9月~11月に「種の蒔き時」、「苗の植え時」となる作物が多くある。
キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ハクサイ、シュンギク、ミズナ、レタス、タマネギ、ラッキョウ、ジャガイモ、ダイコン、ハツカダイコン、ゴボウ、トマト、ミニトマト、セロリ、パセリ、インゲンマメ、ウズラマメ、エンドウマメ、エダマメ、トウモロコシなどなど。毎日苗作りをし、毎日苗を植えなければ間に合わない。
そんな忙しい時期に、台風が来る。ビニールハウス農家はビニールを剥がしたり張ったりしなければならない。塩水を被った作物を洗わなければならない。今年(2012年)は特に台風襲来が多く、しかも、17号は最強台風だった。この最強台風には私も参ったが、沖縄の多くの農家が甚大な被害を蒙ったとのことである。
台風は概ね夏から秋にやってくる。よって、台風の多い年は沖縄の農家に農閑期は無いってことになる。台風が来なくても夏季の農作業は収穫が多くある。トウガン、オクラ、ゴーヤー、ヘチマ、モーウイ、ウンチェーバー、マンゴーなどがその時期となる。雑草も夏場は伸びが早い。したがって、沖縄は年中農繁期と言えるかもしれない。

記:2012.10.26 ガジ丸 →沖縄の生活目次
参考文献
『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行