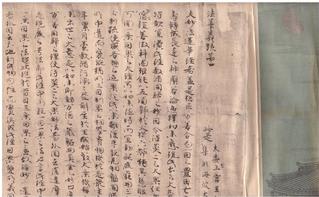「ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない」を渋谷のシネクイントで見ました。
予告編で品川ヒロシがすごくいい感じを出していて、これは面白そうな映画だと思ったので、早速見に行ってきました(品川ヒロシが監督した「ドロップ」が思い出されます)。
主人公・小池徹平が、ニートを脱却してやっとのことで就職したのがIT産業の底辺を構成する零細ソフトウエア会社。高校中退で閉じこもり生活を長く続けていた主人公は、それでもプログラマーの資格試験(おそらく「情報処理技術者試験」でしょう)に通っているので、なんとかこの会社にも正社員として就職できたようです。
ですが、その会社の5人の社員は一人を除いてどうしようもない者ばかり。主人公は、入社早々、とても出来そうもない仕事の山をリーダー・品川ヒロシから押しつけられたりして、すぐにも辞めようと思ったところ、唯一のまともな先輩・田辺誠一からいろいろサポートを受けたりして、結局はこの会社で頑張っていこうと決意するに至るといったストーリーです。
主役の小池徹平は“草食系”とされ〔「2009 ユーキャン新語・流行語大賞」において「草食男子」で受賞〕、まさにうってつけの役柄を大変うまく演じており、また品川ヒロシなども持ち味をよく発揮していると思いました。
甚だ現代的な話題をコメディータッチで描いていて、まずまずの出来栄えと言えるでしょう。
ただ、この会社で社員は実際には何を具体的にやっているのか、上の会社から要求されていることは実際にどんなことなのか、なぜ徹夜を続けなくてはならないほど忙しいのか、それほど忙しいにもかかわらず社員は高給を食んでいるとは思えないのはどうしてなのか、などの点、要すればブラック会社の実態が、この映画で十分描き出されているとは思えません。
加えて、産業の底辺を形成するこうした企業は、なにもIT産業だけでなく他の産業にも見出され、様々のシワ寄せがそうした企業で働く若い従業員に及んでいます。
それを解決すべく、政府が、最低賃金の引き上げとかサービス残業の規制(あるいは製造業への派遣の禁止など)を行ったとしても、上の企業からの高い圧力は変わりませんから、闇に逃げるか、正規社員を派遣等に切り替える(最終的には海外へ出ていく)かして、そうした企業は逃げおおせてしまうでしょう。
とすると、そういう職場にしか行きようがない若者(フリーターやニートの生活から脱却しようとする者も含めて)は無限に我慢するほか仕方がないことになってしまいます。
ですから、こうした映画で何か教訓めいたことを読み取ろうとしても、それはお角違いだと思われます。なにしろ、仕事の実態は類型的・表面的にしか描かれてはいませんから。
にもかかわらず、こういう笑い飛ばすしか対応のしようのない映画を見て、前田有一氏は、この映画の「素晴らしいところ」は、「いま、若い人たちに必要な」こと、すなわち「「働くものの心構え」を表現している」点で、その「心得」とは、「社会に出るものは、強く、たくましくなければいけない」ということであり、「その強さを身に着けるための時間が残っている若い人たち」に「ぜひ本作の鑑賞をすすめたい」と、一人でシャッチョコばってしまうのです。
「働くものの心構え」が足りないから、今の若者の姿になっているというのでしょうか?「強く、たくましく」さえあれば現状から脱却できるというのでしょうか?
世間知らずの者が、わかったようなことを述べてしまいましたが、中年過ぎの評論家たちがこういう映画を見て何か教訓めいたことを言ったりしているのを見て、少しチョッカイを出してみたくなってしまいました。
なお、前田氏以外の「映画ジャッジ」の面々は、次のようです。
福本次郎氏は、「社員数人の小さな企業でよくもこれだけ非常識な人間が集まったかと思えるほど、先輩社員は不思議な人ばかり」だが、「彼らの過剰な言動にユーモアのあるオチが用意されているわけでもなく、コメディとしても中途半端なもどかしさを感じてしまう」などとして40点しか与えません〔いうまでもないことながら、「軍隊や「三国志」といったデフォルメされた彼の心象風景がいちいち押し付けがましくて興を殺ぐ」との評価を下すような人は、始めからこの映画を見なければいいのです!〕。
ですが、他方で、
渡まち子氏は、「思わず、山崎豊子センセイに小説化してもらいたくなる業界の実情なのだが、映画はあくまでも軽さを忘れない。ここが若者にアピールできる点だ」と、相変らず手堅い論評で65点を、
小梶勝男氏は、「 「キサラギ」でワン・シチュエーション・コメディーに手腕を見せた佐藤祐市監督は、本作でも非常にテンポよく物語を進めて行く。よどみのない語り口は見事といっていいだろう」として69点を、
佐々木貴之氏は、「ブラック会社の厳しさ、ダルさ、腹立たしさを描く一方で面白可笑しさを押し出し、テンポ良く描いて魅せつけた一級のエンターテイメント作品として仕上がっている」として75点もの高得点を、
それぞれ与えています。
小梶氏や佐々木氏が言うように、この映画は、コメディーとして、あるいはエンターテインメントとして楽しむべきではないかと思います。
象のロケット:ブラック会社

予告編で品川ヒロシがすごくいい感じを出していて、これは面白そうな映画だと思ったので、早速見に行ってきました(品川ヒロシが監督した「ドロップ」が思い出されます)。
主人公・小池徹平が、ニートを脱却してやっとのことで就職したのがIT産業の底辺を構成する零細ソフトウエア会社。高校中退で閉じこもり生活を長く続けていた主人公は、それでもプログラマーの資格試験(おそらく「情報処理技術者試験」でしょう)に通っているので、なんとかこの会社にも正社員として就職できたようです。
ですが、その会社の5人の社員は一人を除いてどうしようもない者ばかり。主人公は、入社早々、とても出来そうもない仕事の山をリーダー・品川ヒロシから押しつけられたりして、すぐにも辞めようと思ったところ、唯一のまともな先輩・田辺誠一からいろいろサポートを受けたりして、結局はこの会社で頑張っていこうと決意するに至るといったストーリーです。
主役の小池徹平は“草食系”とされ〔「2009 ユーキャン新語・流行語大賞」において「草食男子」で受賞〕、まさにうってつけの役柄を大変うまく演じており、また品川ヒロシなども持ち味をよく発揮していると思いました。
甚だ現代的な話題をコメディータッチで描いていて、まずまずの出来栄えと言えるでしょう。
ただ、この会社で社員は実際には何を具体的にやっているのか、上の会社から要求されていることは実際にどんなことなのか、なぜ徹夜を続けなくてはならないほど忙しいのか、それほど忙しいにもかかわらず社員は高給を食んでいるとは思えないのはどうしてなのか、などの点、要すればブラック会社の実態が、この映画で十分描き出されているとは思えません。
加えて、産業の底辺を形成するこうした企業は、なにもIT産業だけでなく他の産業にも見出され、様々のシワ寄せがそうした企業で働く若い従業員に及んでいます。
それを解決すべく、政府が、最低賃金の引き上げとかサービス残業の規制(あるいは製造業への派遣の禁止など)を行ったとしても、上の企業からの高い圧力は変わりませんから、闇に逃げるか、正規社員を派遣等に切り替える(最終的には海外へ出ていく)かして、そうした企業は逃げおおせてしまうでしょう。
とすると、そういう職場にしか行きようがない若者(フリーターやニートの生活から脱却しようとする者も含めて)は無限に我慢するほか仕方がないことになってしまいます。
ですから、こうした映画で何か教訓めいたことを読み取ろうとしても、それはお角違いだと思われます。なにしろ、仕事の実態は類型的・表面的にしか描かれてはいませんから。
にもかかわらず、こういう笑い飛ばすしか対応のしようのない映画を見て、前田有一氏は、この映画の「素晴らしいところ」は、「いま、若い人たちに必要な」こと、すなわち「「働くものの心構え」を表現している」点で、その「心得」とは、「社会に出るものは、強く、たくましくなければいけない」ということであり、「その強さを身に着けるための時間が残っている若い人たち」に「ぜひ本作の鑑賞をすすめたい」と、一人でシャッチョコばってしまうのです。
「働くものの心構え」が足りないから、今の若者の姿になっているというのでしょうか?「強く、たくましく」さえあれば現状から脱却できるというのでしょうか?
世間知らずの者が、わかったようなことを述べてしまいましたが、中年過ぎの評論家たちがこういう映画を見て何か教訓めいたことを言ったりしているのを見て、少しチョッカイを出してみたくなってしまいました。
なお、前田氏以外の「映画ジャッジ」の面々は、次のようです。
福本次郎氏は、「社員数人の小さな企業でよくもこれだけ非常識な人間が集まったかと思えるほど、先輩社員は不思議な人ばかり」だが、「彼らの過剰な言動にユーモアのあるオチが用意されているわけでもなく、コメディとしても中途半端なもどかしさを感じてしまう」などとして40点しか与えません〔いうまでもないことながら、「軍隊や「三国志」といったデフォルメされた彼の心象風景がいちいち押し付けがましくて興を殺ぐ」との評価を下すような人は、始めからこの映画を見なければいいのです!〕。
ですが、他方で、
渡まち子氏は、「思わず、山崎豊子センセイに小説化してもらいたくなる業界の実情なのだが、映画はあくまでも軽さを忘れない。ここが若者にアピールできる点だ」と、相変らず手堅い論評で65点を、
小梶勝男氏は、「 「キサラギ」でワン・シチュエーション・コメディーに手腕を見せた佐藤祐市監督は、本作でも非常にテンポよく物語を進めて行く。よどみのない語り口は見事といっていいだろう」として69点を、
佐々木貴之氏は、「ブラック会社の厳しさ、ダルさ、腹立たしさを描く一方で面白可笑しさを押し出し、テンポ良く描いて魅せつけた一級のエンターテイメント作品として仕上がっている」として75点もの高得点を、
それぞれ与えています。
小梶氏や佐々木氏が言うように、この映画は、コメディーとして、あるいはエンターテインメントとして楽しむべきではないかと思います。
象のロケット:ブラック会社