信長 と アレッサンドロ・ヴァリニヤーノ


二人の思惑? が一致した。
ヴァリニヤーノには、信長には話せない真の理由。
前述の「二つの目的」を達成するために「遣欧使節」を思いつき提案し
信長は同意した。
そのために、彼ら少年たちの教育が必要と説き、長崎に近い有馬の地に
「セミナリヨ」神学校を設立、キリシタン武家の子息たちを学ばせ、
名代としてその中から選抜したいと・・・。
・・・信長の威光を西欧の人々に正しく伝えることである。 と・・。

有馬のセミナリヨ跡

「有馬セミナリオ」図
◆セミナリヨ=戦国時代~江戸時代の日本に、キリスト教を広めにやって来たイエズス会の
宣教師たちが設立したカトリック教会の司祭(神父)を養成するための全寮制の学校。
キリシタンの10~18歳までの男子が学びました。
1580年、安土とともに日本に初めてセミナリヨが有馬の地に建てられた。
有馬晴信の領地
このセミナリオにおいて、使節の一員として選ばれた
マルティーノ、マンショ、ミゲル、ジュリアンたちは日々の信仰とキリスト教の教義、
また西欧の礼儀作法をも習得していった。
信長は、
さらに、西欧での知識や文物を持ち帰り特殊な技能を持った少年も加え、
その者に「技術」を学ばせよ。 そして余が元へ届けよ。
いったいどうゆうものか、見当もつかぬが・・・
ヴァリニヤーノの口から「タイポグラフィア(印刷)」という言葉が出た。
この技術がもたらされれば・・・と、 その重要性を信長に説いた。
*1400年の半ばに活版印刷はグーテンベルグによって発明されヨーロッパでの本生産に
一大変革を起こした。そして、ヨーロッパ、さらに世界中に広まっていった・・・。
印刷技術は、羅針盤、火薬とともに「ルネサンス三大発明」の一つ。
グーテンベルグ 印刷機 印刷した「42行聖書」



◆この天正使節の一行が教皇との謁見の後、少年使節に関する印刷物がヨーロッパ各地に50種類
以上も発行され、はるか極東の未知の国日本は、ヨーロッパ全土に認知されていった。
話は、前に戻りますが~この特殊な技能を持った少年を加える・・・
それが、宗達だったのだ。
ローマの「洛中洛外図」を描いて来い! は。
信長は、既に天下をほぼ手中にした。 が、万事安泰と思ってはおらぬ。
「次なる一手」を探っている。
彼の、そのために、彼らとの接触があるのだと。
信長の妄想は膨らむ一方だった~・・・
それにつけても・・・行ってみたい、ローマへ。
見てみたい、この目で。
ローマ行きを誰よりも渇望しているのは、・・・・でもなく・・・
実のところ、織田信長だった。
*いやいやいや・・・もうこれ以上の、空想はないよね~素晴らしい発想。
よくこんな・・・どこから生まれてくる 発想なの?
1582年 (天正十年) 二月二十日。
岬の先端、長崎港の上には、きりりと冷たい青空が広がっていた。
季節風が海を渡って吹いてくる。
ゆるやかに、ときに強く。
この風に乗って帆船は大海原へと漕ぎ出すのだ。
出港にはうってつけの日であった。
港には~この使節の団長(司祭兼イエズス会東インド管区巡察師)
アレッサンドロ・ヴァリニヤーノ 

正式に遣欧使節となった
伊東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリアン、そして 原マルティノ。

四人の脇にはパードレ、修道士、世話役など、引率・随行団がずらりと並ぶ。
彼(ヴァリニヤーノ)の賛同者で、彼の通詞として安土から同行してきた神父
デイオゴ・デ・メスキータ
日本人修道士で、日本語とラテン語の双方得意な少年たちの教育係
中浦ジュリアン デイオゴ・デ・メスキータ神父 伊東マンショ

原マルティーノ 千々石ミゲル
ジョルジヨ・ロコラ・・・ ほか、・・・船の乗組員。
これからの長い船旅~
「南蛮船」

*当時、日本人が描いた南蛮船

*ヨーロッパ人が描いた帆船(ナウ船)
*「ナウ船」は、ポルトガルでの呼称。
神戸市立博物館にある「南蛮屏風」 港の風景 「帆船」と南蛮人や日本人たちの姿

*「安土城資料館」展示 {安土城屏風絵陶板壁画}
(長崎へ上陸する南蛮人の荷揚げの様子と、信長に託されて安土城屏風を持ち船出する天正使節)

長崎を出港した~
水平線の彼方を目指し、潮の流れに乗りながら、
風をいっぱいにはらんで帆船は進む。
見渡す限りの青い海、入道雲が立ちのぼる空。
頭上高く舞い上がるカモメの群れ、夜間に鱗をきらめかせる魚影。
さぁ、船は出ました・・・
以後、彼が日本に帰国するまでの8年5カ月の間
これから、一体 どんなドラマを展開していくのでしょうか ?・・・
「下巻」届きましたので、これから 読み始めますので・・・
また次回まで~











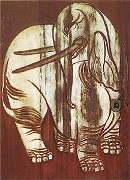















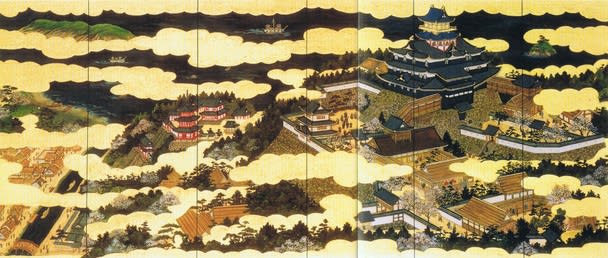











 秀次
秀次 秀頼
秀頼















 復元図による安土城
復元図による安土城






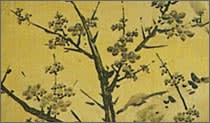





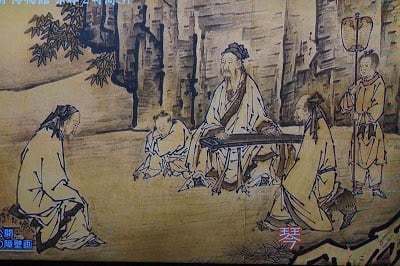










 →
→ 


 の遠縁にあたる少年であった。
の遠縁にあたる少年であった。




 ヴァリニヤーノの願いを
ヴァリニヤーノの願いを に謁見ができた。
に謁見ができた。





























