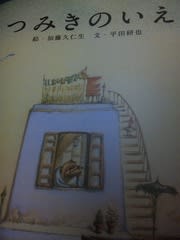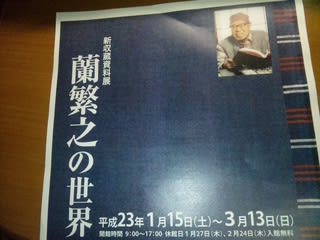スリンカチュ。ロンドンを舞台に活躍する写真家。
これって、「マン盆栽」(家元:パラダイス山元)の世界と基本的には一緒ですね。使っているフィギュアもプライザー社のものだし。ただ、異なるのは、マン盆栽が、いわば「閉じられた空間」であるのに対し、スリンカチュの作品は都市の見慣れた光景と対になっている、開かれた世界だということか。また、スリンカチュは写真家ですから、「写真」というフレームの中で「いかに見 . . . 本文を読む
絵・加藤久仁生、文・平田研也による絵本バージョンの「つみきのいえ」もアニメーションとはまた違った良さがあります。
何より、加藤久仁生の描く絵の、デリケートでふんわりした雰囲気がじっくり楽しめるのが絵本バージョンの最大の魅力かも。細い鉛筆の線と、淡い水彩。こういう絵は、描かれた時のタッチを感じることができるから、見ていて飽きないのです。微妙な色の変化とか重ね塗りの美しさを、ページの隅から隅まで味わ . . . 本文を読む
クールベ、シスレー、ピサロ、モネ、マネ、ルノワール、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンといったそうそうたる印象派の画家の作品を並べただけなら、よくある「印象派展」ですが、今回の企画の目玉は、作品に込められた謎を解き明かすこと、です。ケルンのヴァルラフ・リヒャルツ美術館が科学技術を駆使して印象派の作品を調査した結果をもとに、「なぜ印象派の画家たちは古い伝統から抜け出して新しい絵画を創造することができたのか . . . 本文を読む
とある山中に人知れず存在するフシギ空間「熊の沢アート」。以前紹介した時と比べると、作品が大きく入れ替わっています。作者は今も新しい作品を次々と生み出しているらしい。そして、おそらく、夜中にこっそりと作品の入れ替えを行っているに違いない。
今回の新作品?、まずは「素足のひととき」。素足の少女が、ハーモニカ(昔小学校で使っていた2段のハーモニカ)を気持ちよさげに吹いています。おそらくは、彼女が素 . . . 本文を読む
「加藤久仁生展」を見たあと、もちろん、常設展も見てきました。2008年4月のオープン初日に行って以来、もう4~5回目になるでしょうか。行くたびに新しい発見があります。しかも、今回は初めて解説員のガイドツアーに参加することができました。一緒に回った人たちは、ほとんどが県外から初めて訪れた人たちのようで、作品を見て驚き、解説を聞いて感動して、と、この美術館の全国的な人気の高さをうかがい知ることができま . . . 本文を読む
「つみきのいえ」で2009年米国アカデミー賞短編アニメーション賞を受賞して一躍名前が知られるようになった加藤久仁生。十和田市現代美術館で昨日から「加藤久仁生展」が開催されています。これから、来年にかけて全国4つの美術館を巡回するという。十和田市現代美術館がその皮切り。たまたま初日に見に行ったのですが、オープニングセレモニーでは、加藤さん本人が登場したらしい。間に合わなくてザンネン!
今回は、「つ . . . 本文を読む
いやー。彼の作品のことを、というか、彼の生み出したキャラクターのことを書いていると、いくらでも書けてしまうのだ。というワケで、前回の続きなのだ。
今回はまずは「もーれつア太郎」。
このマンガの舞台は、下町の八百屋。「ア太郎」って奇天烈な名前は、父親がたくさん子供を作ろうと、以降「イ太郎」、「ウ太郎」…と名付けていくつもりだったらしい。ところが、母親が亡くなってしまったため、「ア」で終わってしま . . . 本文を読む
八戸市美術館で開催中の「追悼 赤塚不二夫展」。
え、追悼? 赤塚不二夫が亡くなったのは2008年。もう3年も経ってるのに? 実はこの展覧会、読売新聞社が元締めで、全国各地の美術館を巡回してて、このたびようやく青森までやってきたということですね。3年経とうが何年経とうが、追悼は追悼なのだ!
というわけで、数年前に東京の青梅赤塚不二夫会館を訪れた時以来の赤塚ワールド、楽しんできました。白川東一(K . . . 本文を読む
上野の国立西洋美術館で開催されている「大英博物館古代ギリシャ展」。大英博物館の「ギリシア・ローマ部門」は、10万点以上(!!)の収蔵品を持つのだそうですが、その中から、サブタイトル「THE BODY 究極の身体、完全なる美」のとおり、古代ギリシア人が愛してやまなかった「人間の肉体美」を表現した作品を中心に構成されています。「最大の見所」は、日本初公開の《円盤投げ(ディスコボロス)》。
それにして . . . 本文を読む
先日書いたamazarashiは、音楽と映像のコラボレーションがお見事なのですが、そういう流れでいくと、今、ちょっと作品を見てみたいなあと思っているのが、束芋(たばいも)と、小林賢太郎です。
束芋は、アニメーションを中心に、映像と立体を組み合わせた極めて印象的な作品(そういうのを「インスタレーション」と言うのだそうですが)を世に送り出しているアーティスト。「古き良き日本」的なテーマで、現代社会を . . . 本文を読む
国立新美術館で開催されている「シュルレアリスム展─パリ、ポンピドゥセンター所蔵作品による─」を見る機会がありました。
1924年、パリの若き詩人アンドレ・ブルトンは「シュルレアリスム宣言」なるものを発表。
「いとしい想像力よ、私がおまえのなかでなによりも愛しているのは、おまえが容赦しないということなのだ」
と言い放つ。人間の「想像力」や「無意識」の世界を表現しようとするのがシュルレアリスム。 . . . 本文を読む
なぜだか忘れたけれど、いつだったか「豆本」をつくってみたことがありました。何かの雑誌に作り方が載っていたのを見たからかもしれません。思いのほか難しくて、出来映えは決して満足いくものではなかったのですが、「自分で本を作る」という作業自体が発想の転換だよなあと思ったものでした。本は買ったり借りたりするもので、自分で作るものじゃないですよね、フツー。
弘前市出身の蘭繁之さん(1920-2008)という . . . 本文を読む
「ベラスケスもデューラーもルーベンスも、わが家の宮廷画家でした。」
ってのが、「THE ハプスブルク」展のキャッチコピー。なかなか嫌みったらしいコピーじゃありませんか。でも、実際その通りなのだから、仕方ありませんね。秀逸なキャッチコピーに比べたら、サブタイトルの方は「華麗なる王家と美の巨匠たち」とごくありきたり。それなら、ハプスブルク家のライバル、ブルボン家にもあてはまるわい!
この展覧会の最 . . . 本文を読む
前回行ったときは、「太陽の塔」のある公園が閉園後だったので、門のところから眺めだだけで泣く泣く帰ってきたのですが、今回、しっかり初接近してきました!
近づくたびに高鳴る胸。その大きさ(高さ65m)、迫力、スタイルの完璧さ、フォルムの美しさに、スゴイ!!という言葉しか出てこない。帰り際に、これから接近しようとする人たちの顔を観察してみたら、みんな、まるで憑かれたかのように太陽の塔からまったく目を離 . . . 本文を読む
青森県立美術館の「吉村作治の新発見!エジプト展 ~国立カイロ博物館所蔵品と~」、最終日の今日、ギリギリセーフで行ってきました。
それほど駆け足で見たわけではないのに、入口から出口まで、40分弱で見終わってしまいました。なんだかなあ…という感じでした。
「エジプト展」というだけで、見ておかなくちゃと思ったものの、よくよくタイトル見れば、「吉村作治の」とあるわけで、これはもう、吉村作治氏の「業績」 . . . 本文を読む