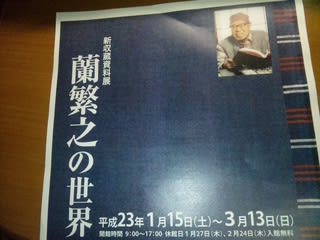
なぜだか忘れたけれど、いつだったか「豆本」をつくってみたことがありました。何かの雑誌に作り方が載っていたのを見たからかもしれません。思いのほか難しくて、出来映えは決して満足いくものではなかったのですが、「自分で本を作る」という作業自体が発想の転換だよなあと思ったものでした。本は買ったり借りたりするもので、自分で作るものじゃないですよね、フツー。
弘前市出身の蘭繁之さん(1920-2008)という人は、豆本や本の装幀に生涯を捧げた人、といっていいでしょう。この人は、本をつくることが楽しくてしょうがなかったらしい。青森県立近代文学館で開催されている「新収蔵資料展 蘭繁之の世界」で、彼の膨大な作品群をまのあたりにして、つくづくそう思いました。
どのコーナーでも、思わず、わーこりゃすごいと声が出てしまうような見事な作品の数々。もちろん、彼の遺した最大の遺産は、「緑の笛豆本」シリーズ。その数全423巻。10cm×8cmくらいの大きさの豆本423巻が、ビニールの袋に入れられてずらりとぶら下がっている展示コーナーでは、しばらく動くことすらできなかったくらいです。彼は、これらの豆本を限定250部作って、「緑の笛」の会員に毎月1度送っていたそうです。記念すべき第1号は昭和40年8月発行。既に刊行されている本を豆本に仕立てたものもあれば、新たに地元・津軽の人々が書き下ろした本もある。版画集、小説、論文、詩集と内容も多岐にわたっています。彼はことのほか、竹久夢二と棟方志功が好きだったようで、このシリーズにも何度か登場しています。最終号は平成16年7月1日発行となっています。実に40年にわたって展開された豆本ワールド。津軽塗りで作らせたという、豆本を収める木箱までありました。これだけでも相当の評価を得ていいはずですね。

でも、豆本もすごいけど、彼の真骨頂は本の装幀かもしれません。そのアイディアにはただただびっくりです。たとえば、彼の趣味だったという蕎麦猪口をアレンジした版画集。蕎麦猪口風の陶器を表紙にはめ込んであります。その名も「蕎麦猪口版画集」。あるいは、デザインガラスを表紙にはめ込んだもの、紫色の浅草海苔を表紙の前面に貼り付けたもの、高木恭三の「まるめろ」は、市販の本を表紙だけ自分風の装幀に変えていました。本に対する「思い」を感じますね。畏敬を込めて、「究極の本フェチ」と呼ばせていただきます。
うろ覚えですが、彼の言葉に「本は読むだけのものではない。人が見たり触ったりすることも本の魅力だ」というのがありました。世界でたった一つしかない本を「自分で作る」ことで、蘭さんはそういう思いを見事に体現しています。そういう生き方ってすごいと思う。
彼は、自分で本を作るほか、「特装本」の収集にも努めていました。その一部、成瀬書房刊行の特装本が何冊か展示されていましたが、『蒼氓』とか『俘虜記』とか『山椒魚』とか、通常の書店に並んでいる本のほかに、こういう世界もあったのかと驚きました。どの本にも「特装200部の内第168番本」とか、シリアルナンバーが振ってあります。それは確かに、世界でたった一つしかない本に違いない。
今回の特別展は、弘前市や北海道立文学館から寄贈された作品や蔵書を中心に開催されているものです。一昨年、蘭さんが亡くなった際に、奥さんが彼の膨大な作品や蔵書の管理について弘前市に相談し、そのツテで県の近代文学館が収蔵することになったのだと、同館の室長が教えてくれました。その室長もおっしゃっていましたが、青森県の「文学」の奥深さを改めて感じます。太宰や寺山だけじゃないのです。まだまだ掘り起こせば蘭さんのような「隠れた才能」がたくさん潜んでいそうですね。近代文学館の常設展示室には、太宰治や寺山修司、石坂洋次郎、葛西善蔵、北畠八穂、高木恭三、三浦哲郎、長部日出雄といったそうそうたる文学者33人について紹介していますが、この中には蘭さんは入っていない。恐ろしや、青森県。
弘前市出身の蘭繁之さん(1920-2008)という人は、豆本や本の装幀に生涯を捧げた人、といっていいでしょう。この人は、本をつくることが楽しくてしょうがなかったらしい。青森県立近代文学館で開催されている「新収蔵資料展 蘭繁之の世界」で、彼の膨大な作品群をまのあたりにして、つくづくそう思いました。
どのコーナーでも、思わず、わーこりゃすごいと声が出てしまうような見事な作品の数々。もちろん、彼の遺した最大の遺産は、「緑の笛豆本」シリーズ。その数全423巻。10cm×8cmくらいの大きさの豆本423巻が、ビニールの袋に入れられてずらりとぶら下がっている展示コーナーでは、しばらく動くことすらできなかったくらいです。彼は、これらの豆本を限定250部作って、「緑の笛」の会員に毎月1度送っていたそうです。記念すべき第1号は昭和40年8月発行。既に刊行されている本を豆本に仕立てたものもあれば、新たに地元・津軽の人々が書き下ろした本もある。版画集、小説、論文、詩集と内容も多岐にわたっています。彼はことのほか、竹久夢二と棟方志功が好きだったようで、このシリーズにも何度か登場しています。最終号は平成16年7月1日発行となっています。実に40年にわたって展開された豆本ワールド。津軽塗りで作らせたという、豆本を収める木箱までありました。これだけでも相当の評価を得ていいはずですね。

でも、豆本もすごいけど、彼の真骨頂は本の装幀かもしれません。そのアイディアにはただただびっくりです。たとえば、彼の趣味だったという蕎麦猪口をアレンジした版画集。蕎麦猪口風の陶器を表紙にはめ込んであります。その名も「蕎麦猪口版画集」。あるいは、デザインガラスを表紙にはめ込んだもの、紫色の浅草海苔を表紙の前面に貼り付けたもの、高木恭三の「まるめろ」は、市販の本を表紙だけ自分風の装幀に変えていました。本に対する「思い」を感じますね。畏敬を込めて、「究極の本フェチ」と呼ばせていただきます。
うろ覚えですが、彼の言葉に「本は読むだけのものではない。人が見たり触ったりすることも本の魅力だ」というのがありました。世界でたった一つしかない本を「自分で作る」ことで、蘭さんはそういう思いを見事に体現しています。そういう生き方ってすごいと思う。
彼は、自分で本を作るほか、「特装本」の収集にも努めていました。その一部、成瀬書房刊行の特装本が何冊か展示されていましたが、『蒼氓』とか『俘虜記』とか『山椒魚』とか、通常の書店に並んでいる本のほかに、こういう世界もあったのかと驚きました。どの本にも「特装200部の内第168番本」とか、シリアルナンバーが振ってあります。それは確かに、世界でたった一つしかない本に違いない。
今回の特別展は、弘前市や北海道立文学館から寄贈された作品や蔵書を中心に開催されているものです。一昨年、蘭さんが亡くなった際に、奥さんが彼の膨大な作品や蔵書の管理について弘前市に相談し、そのツテで県の近代文学館が収蔵することになったのだと、同館の室長が教えてくれました。その室長もおっしゃっていましたが、青森県の「文学」の奥深さを改めて感じます。太宰や寺山だけじゃないのです。まだまだ掘り起こせば蘭さんのような「隠れた才能」がたくさん潜んでいそうですね。近代文学館の常設展示室には、太宰治や寺山修司、石坂洋次郎、葛西善蔵、北畠八穂、高木恭三、三浦哲郎、長部日出雄といったそうそうたる文学者33人について紹介していますが、この中には蘭さんは入っていない。恐ろしや、青森県。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます