
2014年8月31日(日)
第2回自主研修 『さわって、匂いをかいで樹を知ろう!』
天候 曇りときどき晴れ間
参加 22名(内、東京都緑ボラ体験入会2名を含む) リーダー(講師)関さん
コース:清滝駅前~ 稲荷山コース~東屋(昼食)~5号路 ~6号路~清滝駅前(解散)
第2回自主研修『さわって、匂いをかいで樹を知ろう!』として開催されました。
8月中旬発行された会報に、研修の事前紹介がありました。引用すると『樹は(植物は)動物と違い、動くことができません。その分、知恵を働かせ生きていく努力をしています。昆虫に受粉の手伝いをしてもらいその報酬として蜜をプレゼントし、野鳥に種子を遠方へ運んでもらいご褒美に果肉を提供します。昆虫も野鳥も自分のしたいことをしているだけで、まさか自分が受粉や種子散布の手伝いをしているとは思ってもいないでしょう。樹は虫や鳥の特徴・癖を知った上で彼らを上手に利用しているんだ、と考えてみて下さい。こうした視点で樹を観てみると、実にしたたかに生きていることに気づきます。』
先ず、今回の研修の狙いと本日の主要行程が説明されました。
1)高尾山の利用者に自然の素晴らしさを伝えるための基礎的な知識を身につける。
2)自然への興味関心を深め、「もっと知りたい」という気持ちを「巡回に参加したい」気持ちに繋げる。
予備知識として、①高尾山には豊富な樹種があり、そして、登りに選んだ②稲荷山コースは尾根筋のコースであることの説明があり、参加者皆が興味津々。
ストレッチを行い、出発。
これから、『五感(WHYとHOWも考えて)を働かせて、樹木の魅力に触れてみよう!』掛け声のもと、いくつかの樹の生き様を披露しながら、巡回時に高尾山の利用者に高尾の自然の素晴らしさを紹介する時の話題作り・ネタ作りとなるように、研修が進みました。

参加者が22名と多いため、他の利用客の迷惑にならないように、細心の注意を払いながら、広い場所やポイントを選びながらの説明でした。
また、説明が全員に届くように、ポストイットの用紙に話題にする(注目の)樹木の種名を書き、ワンポイントの説明を伝言ゲームのように後ろの人に伝える工夫もありました。そして、広い場所を見つけて、まとめて説明を受けました。



各所で、樹木とその隣に生えている木との関わり(競争と共生)、別種の樹や草との関わり、様々な野鳥、昆虫、哺乳類、キノコとの関わり、更には土壌、気象、地形との関わりについても随所に話が拡がり、とても興味深いものでした。
この他にも、樹は成長に必要な日光と水を求め他の植物との競争に勝つ戦略、競争を避けニッチな場所で我慢して生存する能力、幼虫に葉を食べられないようにする防衛手段、子孫を残していくための戦術等々、多種多様の知恵を教えてもらいました。
【説明のあった主な樹木・植物】
モミジ3種(イロハモミジ、オオモミジ、ヤマモミジ)、アジサイ3種(タマアジサイ、ガクアジサイ、ヤマアジサイ)、カタツムリとアジサイの話、アジサイの装飾花、ハナイカダ、ヒサカキとサカキ、クサギ、コナラとハイイロチャッキリムシ(ドングリ)、ナツハゼ、ナガバノコウヤボウキ、コウヤボウキ、カキ(種の散布あれこれ)、シラキ、アオキ(青木さんと青木君)、シラカシ(根返りを打つ、根回し)、ミズキ(針葉樹と広葉樹のアテの違い、適材適所)、マツ、ケヤキ、トチノキ、ホウノキ、アカメガシワ、クヌギ(萌芽更新、里山、雑木林)、スギ(尾根マツ・中ヒノキ・沢スギ、適地適木)、ヒノキ(人工林、天然林)、ツルグミ、モミ、イチイ、カヤ、ウラジロガシ、アカシデとイヌシデ、ゴンズイ(虫こぶ)、ヤマザクラ、シロダモ(花と実が同時、葉裏のロウ)、アカガシとアラカシ、ヤブムラサキ(ベルベット肌)、ムラサキシキブ、ウワミズザクラ(赤ちゃんの肌)、マルバアオダモ、タラヨウ、セイヨウバクチノキ(後から字が浮かび上がる)・・・・。

丁寧に、わかるまで手ほどきしてもらいましたので、9時半に出発して、稲荷山コースの中間点「東屋」展望台に着いたのが12時頃、腹時計とも合い、昼食をとりました。
ここから、多少ピッチが上がり、5号路のまき道を経て、4号路分岐のトイレ前で休憩、下りは、(尾根沿いの稲荷山コースとは樹種が異なる)6号路を。
【説明のあった主な樹木・植物】
ブナ(種子の豊作・凶作戦略と動物の貯食の関係)、ミズナラ、ヤマグリ(フィボナッチ級数と葉序)、アワブキ、カラスザンショウ、ウリカエデ、ヤマボウシ、クロモジ、マユミ、ニシキギ、ツタウルシ、ヤマハゼ、ヤマウルシ、ハゼノキ、ヌルデ、エンコウカエデ、ヤブツバキ、リョウブとサトウカエデ(シカの好物、円周の樹皮をはがれての大丈夫)、ウリノキ、カツラ、アセビ、ツツジ、ネジメ、コクサギ、ガクウツギ、カマツカ、オニグルミ、チドリノキ、マタタビ、ニガキ、キハダ、シンジュ(ニワウルシ)、ムクゲ(韓国の国花)、・・・・・・。
下山後、振り返りとまとめを行いました。
○樹の同定を難しくするもの
・ライフステージ毎の様子が異なる
・♂♀に加え、個体差がある
・ハイライトの時期が短い
・花や実が高所にある
○見分けるポイント
1)マクロで当たりをつける
環境(気候帯・立地・地形)、樹形、枝ぶり
2)ミクロで確定していく
花、実、枝、葉、樹皮、冬芽、葉痕、トゲ
○今後にむけての宿題
まずは、基本50種を覚えよう!
研修全体を通じて、「樹は成長に必要な日光と水を求め他の植物との競争に勝つ戦略、競争を避けニッチな場所で我慢して生存する能力、幼虫に葉を食べられないようにする防衛手段、子孫を残していくための戦術等々、多種多様の知恵を働かせている。」などなど具体的に、樹木の比較をしながら学習でき、今後の巡回時の利用客への自然解説に活用していただきたい。
リーダー、参加の皆様お疲れ様でした。
(記録:M・K(M・S談)、写真提供:S・I、K・K、M・K)















































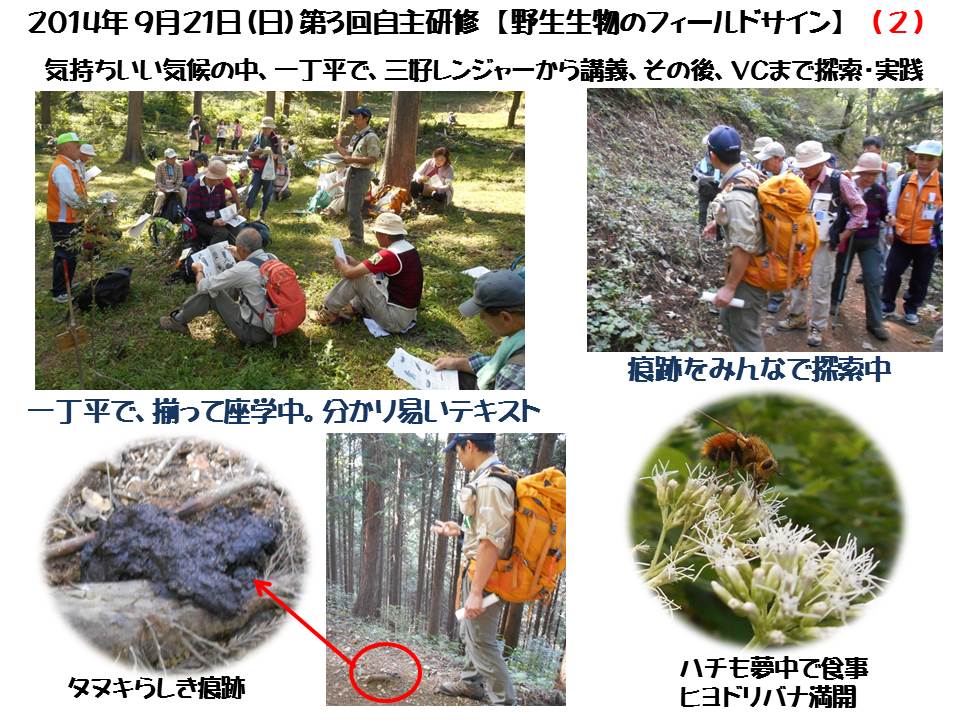


 支障木
支障木  初沢山方面
初沢山方面





































