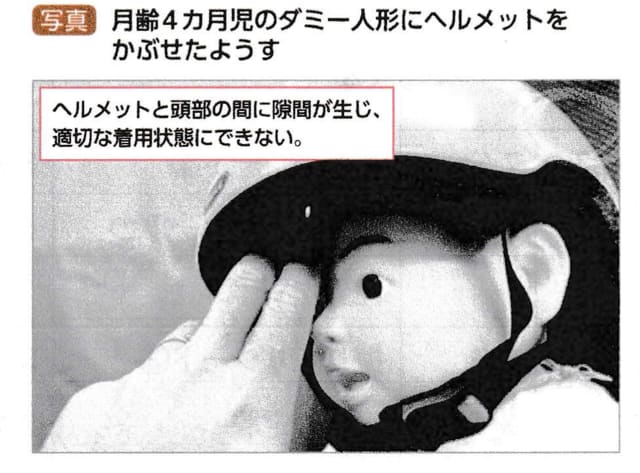独立行政法人国民生活センター発行 国民生活 2023.11
暮らしの法律Q&A 第137回より
カタログギフトの申し込み期限を過ぎてしまったら?
相談者の気持ち
カタログギフトをもらいました、うっかり注文し忘れて、
申込期限を過ぎてしまいました。
事業者に電話をしたところ「期限を1日でも過ぎたら注文を受け付けない」と
言われてしまいました。
贈り主からお金だけ取って、商品を送らないなんておかしくないですか?
回答 小島直樹弁護士
「カタログギフト」とは、贈り主が代金を支払い、受取人がカタログのなっかから商品を選択して
事業者に連絡すると、事業者がその商品を受取人に発送するという一連の行為について
取り決めた契約のことを指すと考えられます。
そうすると、この契約は贈り主と事業者の間で、受取人に商品の選択権を与え、
受取人が選択をすると事業者は受取人に選択された商品を発送する義務を負うという、
第三者のためにする贈与契約ということになります。
では、受取人の選択権はいつまで認められるのでしょうか。
受取人の選択権は、一種の債権ですから、いつまでも行使しないでいると
時効の期間は5年(民法宇166条1項1号)ということになりそうです。
しかし、ほとんどのカタログギフトでは、5年よりもずっと短い期間を
申し込み期限として定め(資金決済法の適用対象外となる6ヶ月以内としていることが多い)
申込期限を過ぎて申し込みをしても、
ご相談のように、「注文を受け付けない」という対応をしています。
それは、事業者が約款(民法548条の2第1項)によって、申込期限を制限しているからです。
このように約款によって権利を制限することが認められているのは、
民法の規定によれば、
①不特定多数の者を相手方として行う取引であって、
②双方にとって合理的なものであること及び
③取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして、相手方の利益を一方的に
害すると認められるものではない場合です(同条1項、2項)
カタログギフトは①に当たることは明らかです。
②については、カタログギフトというものの特性上、
時間が経てばカタログに掲載された商品が提供されなくなったり、
価格が変動したりすることがありますので、期限の制限をすることは
事業者にとっては合理的ですが、受取人にとっても一応は合理的といえるでしょう。
③については、②に述べたような事情を考えると、受取人の利益を一方的苦いするとまではいえないように思えます。
さらに、民法には「あらかじめ約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」は
「約款の個別の条項についても合意したものとみなす」ということも定められています。
ほとんどのカタログギフト業者は約款を定めて、カタログに「約款を契約の内容とする」ことを表示していますし、
期限制限についても明示していますので、
この規定によって、期限制限は有効と考えられます。
利用する際は、約款をよく確認するようにしましょう。
**********************************
小島先生の丁寧な説明により約款を守らなければならないことがわかります。
消費者は、約款をよく確認することが重要ですね!
でも、約款って読んだことがありますか?
法律によって守られているしくみですので、
面倒でもしっかり確認する癖をつけたいものです。
もう少しわかりやすいものにしてもらうことや、
理解するまで説明してもらうことがよいかと思います。
少しでも約款のここが納得できないと思われた方は、
適格消費者団体 NPO法人 消費者支援ネットワークいしかわ
お問い合わせ:TEL.076-254-6733
〒920-0206 石川県金沢市北寺町へ9番地3
にご相談ください👍
*************************************
暮らしの法律Q&A 第137回より
カタログギフトの申し込み期限を過ぎてしまったら?
相談者の気持ち
カタログギフトをもらいました、うっかり注文し忘れて、
申込期限を過ぎてしまいました。
事業者に電話をしたところ「期限を1日でも過ぎたら注文を受け付けない」と
言われてしまいました。
贈り主からお金だけ取って、商品を送らないなんておかしくないですか?
回答 小島直樹弁護士
「カタログギフト」とは、贈り主が代金を支払い、受取人がカタログのなっかから商品を選択して
事業者に連絡すると、事業者がその商品を受取人に発送するという一連の行為について
取り決めた契約のことを指すと考えられます。
そうすると、この契約は贈り主と事業者の間で、受取人に商品の選択権を与え、
受取人が選択をすると事業者は受取人に選択された商品を発送する義務を負うという、
第三者のためにする贈与契約ということになります。
では、受取人の選択権はいつまで認められるのでしょうか。
受取人の選択権は、一種の債権ですから、いつまでも行使しないでいると
時効の期間は5年(民法宇166条1項1号)ということになりそうです。
しかし、ほとんどのカタログギフトでは、5年よりもずっと短い期間を
申し込み期限として定め(資金決済法の適用対象外となる6ヶ月以内としていることが多い)
申込期限を過ぎて申し込みをしても、
ご相談のように、「注文を受け付けない」という対応をしています。
それは、事業者が約款(民法548条の2第1項)によって、申込期限を制限しているからです。
このように約款によって権利を制限することが認められているのは、
民法の規定によれば、
①不特定多数の者を相手方として行う取引であって、
②双方にとって合理的なものであること及び
③取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして、相手方の利益を一方的に
害すると認められるものではない場合です(同条1項、2項)
カタログギフトは①に当たることは明らかです。
②については、カタログギフトというものの特性上、
時間が経てばカタログに掲載された商品が提供されなくなったり、
価格が変動したりすることがありますので、期限の制限をすることは
事業者にとっては合理的ですが、受取人にとっても一応は合理的といえるでしょう。
③については、②に述べたような事情を考えると、受取人の利益を一方的苦いするとまではいえないように思えます。
さらに、民法には「あらかじめ約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」は
「約款の個別の条項についても合意したものとみなす」ということも定められています。
ほとんどのカタログギフト業者は約款を定めて、カタログに「約款を契約の内容とする」ことを表示していますし、
期限制限についても明示していますので、
この規定によって、期限制限は有効と考えられます。
利用する際は、約款をよく確認するようにしましょう。
**********************************
小島先生の丁寧な説明により約款を守らなければならないことがわかります。
消費者は、約款をよく確認することが重要ですね!
でも、約款って読んだことがありますか?
法律によって守られているしくみですので、
面倒でもしっかり確認する癖をつけたいものです。
もう少しわかりやすいものにしてもらうことや、
理解するまで説明してもらうことがよいかと思います。
少しでも約款のここが納得できないと思われた方は、
適格消費者団体 NPO法人 消費者支援ネットワークいしかわ
お問い合わせ:TEL.076-254-6733
〒920-0206 石川県金沢市北寺町へ9番地3
にご相談ください👍
*************************************