アグスティン・バリオスのギター曲がクラシックというジャンルに属するか、ということを考えると、すぐにクラシックで間違いないとは言えないような気がする。
だから人によってはクラシック音楽に分類しない方もいる。
クラシックギターの巨匠と言えば、アンドレス・セゴビアとナルシソ・イエペスとジュリアン・ブリームの3人であるが、この3人の中でバリオスの曲を録音したのはイエペスだけで、しかも「大聖堂」(但し第2、第3楽章のみ)1曲しかない。
しかしバリオスの曲は美しく庶民的で親しみやすい。
「前奏曲ハ短調」、「演奏会用練習曲イ長調」などは名曲だと思う。
これらの曲はシンプルであるが、左手の押さえがとても難しく、録音も少ない。
バリオスの曲のなかで比較的やさしく、親しみやすいのが「クリスマスの歌(Villancico de Navidad)」という曲だ。
この曲を初めて弾いたのが20代の後半の頃だったと記憶しているが、当時バリオスの全集と言えばヘスス・ベニーテスとリチャード・ストーバーにより編纂されたものしかなく、ベニーテス版が全音から出版されていることもあって安価であり、殆どの人がこのベニーテス版を利用していたのではないかと思われる。
私もベニーテス版全4巻を揃え、その中からいくつかの曲を手掛けたが、第2巻に出てくる「クリスマスの歌」は楽に弾けるし、メロディが親しみやすいので何度か繰り返し弾いていた。
30代初めの頃だったが、現代ギター誌の読者投稿覧にこの「クリスマスの歌」の一部のフレーズ、それは開放弦のみで奏され、2度現れる部分(16小節3拍目から24小節目5拍目の間)なのであるが、この部分は実は自然ハーモニックスで演奏されるのではないか、バリオスは元々クリマスに鳴らされる鐘の音をイメージしてこのフレーズを作ったのではないかと問題提起し、実際に譜面が提示されている記事を見たことがあった。
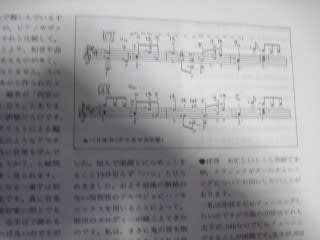
私はこの記事を読んですぐギターを取り出し、添付の譜面どおりにハーモニックスで弾いてみたが、なるほど実際に弾いてみると、開放弦のみの譜面とは異なる、8小節目3拍目から16小節目2拍目までに現れるメロディーどおりとなる。
これはもしかする本当にハーモニックス記号の欠落で、いままで誰も欠落に気付かずにいたかもしれない、と思ったが、このハーモニックスが終り次のフレーズの最初の音(ミ)を弾いた瞬間、何かつながりが変な感じがするな、とも感じた。
つまりハーモニックスのフレーズから次のフレーズへのつながりや流れが何となく違和感を感じさせたのである。
(ベニーテス版にフレットのポジション番号を書き込んで弾いた時の譜面)

その後この「クリスマスの歌」を弾くことから遠ざかったが、今日までの間に、このハーモニックスで弾くバージョンが、徐々に開放弦のみで弾くバージョンにとって代わり、今では開放弦の記譜は間違いでありハーモニックスで奏するのが通常であり、正しいと、とらえられるようになった感がある。
実際、近年出版されているこの曲の譜面はハーモニックス版によるものが殆どだそうだ。
今回あるきっかけでこの曲を久しぶりに聴く機会があり、あらためて開放弦版とハーモニックス版について、Youtubeで最も再生回数の多い演奏を聴き比べてみた。
開放弦版の印象は、この開放弦のフレーズは開放弦であるが故に素っ気ない、味気ない感じが若干しないでもなかったが、このフレーズの前後のつながりに違和感は感じられなかった。

次にハーモニックス版を聴いた印象だが、やはり25年前に実際に弾いて感じた違和感を感じた。
それはハモニックスの終わったあとすぐに続くフレーズへのつながりだったが、何か違うような気がするのだ(17と18小節目、21と22小節目)。


またこのハーモニックスのメロディは、前述のように8小節目3拍目から16小節目2拍目までに現れるメロディなのであるが、開放弦ではなくハーモニックスで弾くと、このメロディが4回も繰り返されることになり、曲全体のバランスからしてもこの部分が4度繰り返されることにも違和感を感じたのである。
このメロディーは8小節目3拍目から始まり、12小節目3拍目から16小節目2拍目までの間で和音の層がより厚くなり、音量も増すが、14小節目4拍目でクライマックスを迎え、そこからから16小節目2拍目まで下降する共に音量も徐々に下がっていく。


つまり、このメロディはこの2回の繰り返しだけで終わるのが自然の流れではないだろうかと思ったのである。
2回目の繰り返しの部分を弾いてみると、16小節目2拍目でこのフレースは完結し、ここから新たに別の展開が始まる。
その展開こそがあの開放弦で奏される部分とこの曲の最高音が続くフレーズ(18,19小節目と22、23小節目)との組み合わせの部分である。


この16から24小節目まで続くフレーズ、それは3番目のフレーズと言っていいと思うのだが、このフレーズの開放弦をハーモニックスで弾いてしまうと、2番目のフレーズ(すなわち8~15小節目)に出てくるメロディが再び再現されるので、何かおかしい感じがする。
自分は、8~15小節目と16~24小節目のフレーズは、違う展開を意図して作られたのではないかと感じたのである。
そうであれば、16~24小節目のフレーズに出てくる開放弦の部分は開放弦のそのままに弾くのが自然であり、本来、そのように意図してこの曲が作られたとも考えられるのである。
この8小節目3拍目から16小節目2拍目までのフレーズは、ニ短調に転調しニ長調に戻った、33~40小節目にも再現されるが、ここでもメロディが2回繰り返される。
その後冒頭のフレーズが再現され、最後は単音のハーモニックスの連続を経てニ長調の静かな和音で終結する。
この曲のバリオスのオリジナルの自筆譜には開放弦の部分にはハーモニックス記号が無かったのであろうが、記載漏れとみるか、元から存在しなかったのか、今ではその事実を確かめるすべは無く、この部分をどう弾くかは奏者の判断に任せられているのが現状だ。
断定的なことは言えないし、人により感じ方は異なるであろうが、私の感じ方としては開放弦の方が自然のように感じる。
【開放弦版の演奏】
Barrios: Villancico de Navidad
【ハモニックス版の演奏】
Christmas song - Villancico de Navidad by A. Barrios, performed by Tatyana Ryzhkova
だから人によってはクラシック音楽に分類しない方もいる。
クラシックギターの巨匠と言えば、アンドレス・セゴビアとナルシソ・イエペスとジュリアン・ブリームの3人であるが、この3人の中でバリオスの曲を録音したのはイエペスだけで、しかも「大聖堂」(但し第2、第3楽章のみ)1曲しかない。
しかしバリオスの曲は美しく庶民的で親しみやすい。
「前奏曲ハ短調」、「演奏会用練習曲イ長調」などは名曲だと思う。
これらの曲はシンプルであるが、左手の押さえがとても難しく、録音も少ない。
バリオスの曲のなかで比較的やさしく、親しみやすいのが「クリスマスの歌(Villancico de Navidad)」という曲だ。
この曲を初めて弾いたのが20代の後半の頃だったと記憶しているが、当時バリオスの全集と言えばヘスス・ベニーテスとリチャード・ストーバーにより編纂されたものしかなく、ベニーテス版が全音から出版されていることもあって安価であり、殆どの人がこのベニーテス版を利用していたのではないかと思われる。
私もベニーテス版全4巻を揃え、その中からいくつかの曲を手掛けたが、第2巻に出てくる「クリスマスの歌」は楽に弾けるし、メロディが親しみやすいので何度か繰り返し弾いていた。
30代初めの頃だったが、現代ギター誌の読者投稿覧にこの「クリスマスの歌」の一部のフレーズ、それは開放弦のみで奏され、2度現れる部分(16小節3拍目から24小節目5拍目の間)なのであるが、この部分は実は自然ハーモニックスで演奏されるのではないか、バリオスは元々クリマスに鳴らされる鐘の音をイメージしてこのフレーズを作ったのではないかと問題提起し、実際に譜面が提示されている記事を見たことがあった。
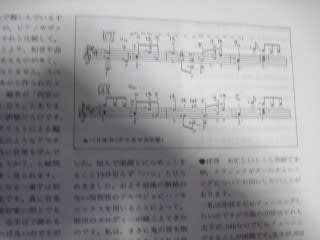
私はこの記事を読んですぐギターを取り出し、添付の譜面どおりにハーモニックスで弾いてみたが、なるほど実際に弾いてみると、開放弦のみの譜面とは異なる、8小節目3拍目から16小節目2拍目までに現れるメロディーどおりとなる。
これはもしかする本当にハーモニックス記号の欠落で、いままで誰も欠落に気付かずにいたかもしれない、と思ったが、このハーモニックスが終り次のフレーズの最初の音(ミ)を弾いた瞬間、何かつながりが変な感じがするな、とも感じた。
つまりハーモニックスのフレーズから次のフレーズへのつながりや流れが何となく違和感を感じさせたのである。
(ベニーテス版にフレットのポジション番号を書き込んで弾いた時の譜面)

その後この「クリスマスの歌」を弾くことから遠ざかったが、今日までの間に、このハーモニックスで弾くバージョンが、徐々に開放弦のみで弾くバージョンにとって代わり、今では開放弦の記譜は間違いでありハーモニックスで奏するのが通常であり、正しいと、とらえられるようになった感がある。
実際、近年出版されているこの曲の譜面はハーモニックス版によるものが殆どだそうだ。
今回あるきっかけでこの曲を久しぶりに聴く機会があり、あらためて開放弦版とハーモニックス版について、Youtubeで最も再生回数の多い演奏を聴き比べてみた。
開放弦版の印象は、この開放弦のフレーズは開放弦であるが故に素っ気ない、味気ない感じが若干しないでもなかったが、このフレーズの前後のつながりに違和感は感じられなかった。

次にハーモニックス版を聴いた印象だが、やはり25年前に実際に弾いて感じた違和感を感じた。
それはハモニックスの終わったあとすぐに続くフレーズへのつながりだったが、何か違うような気がするのだ(17と18小節目、21と22小節目)。


またこのハーモニックスのメロディは、前述のように8小節目3拍目から16小節目2拍目までに現れるメロディなのであるが、開放弦ではなくハーモニックスで弾くと、このメロディが4回も繰り返されることになり、曲全体のバランスからしてもこの部分が4度繰り返されることにも違和感を感じたのである。
このメロディーは8小節目3拍目から始まり、12小節目3拍目から16小節目2拍目までの間で和音の層がより厚くなり、音量も増すが、14小節目4拍目でクライマックスを迎え、そこからから16小節目2拍目まで下降する共に音量も徐々に下がっていく。


つまり、このメロディはこの2回の繰り返しだけで終わるのが自然の流れではないだろうかと思ったのである。
2回目の繰り返しの部分を弾いてみると、16小節目2拍目でこのフレースは完結し、ここから新たに別の展開が始まる。
その展開こそがあの開放弦で奏される部分とこの曲の最高音が続くフレーズ(18,19小節目と22、23小節目)との組み合わせの部分である。


この16から24小節目まで続くフレーズ、それは3番目のフレーズと言っていいと思うのだが、このフレーズの開放弦をハーモニックスで弾いてしまうと、2番目のフレーズ(すなわち8~15小節目)に出てくるメロディが再び再現されるので、何かおかしい感じがする。
自分は、8~15小節目と16~24小節目のフレーズは、違う展開を意図して作られたのではないかと感じたのである。
そうであれば、16~24小節目のフレーズに出てくる開放弦の部分は開放弦のそのままに弾くのが自然であり、本来、そのように意図してこの曲が作られたとも考えられるのである。
この8小節目3拍目から16小節目2拍目までのフレーズは、ニ短調に転調しニ長調に戻った、33~40小節目にも再現されるが、ここでもメロディが2回繰り返される。
その後冒頭のフレーズが再現され、最後は単音のハーモニックスの連続を経てニ長調の静かな和音で終結する。
この曲のバリオスのオリジナルの自筆譜には開放弦の部分にはハーモニックス記号が無かったのであろうが、記載漏れとみるか、元から存在しなかったのか、今ではその事実を確かめるすべは無く、この部分をどう弾くかは奏者の判断に任せられているのが現状だ。
断定的なことは言えないし、人により感じ方は異なるであろうが、私の感じ方としては開放弦の方が自然のように感じる。
【開放弦版の演奏】
Barrios: Villancico de Navidad
【ハモニックス版の演奏】
Christmas song - Villancico de Navidad by A. Barrios, performed by Tatyana Ryzhkova
















クリスマスの歌は、開放弦の方が良いと思いました。
you Tubeも男性のほうが良いのではないでしょうか。
きっと、緑陽さんお推察通り、バリオスは開放弦を指定したのでしょうね。
バリオスは若い時、ジョンの演奏を聴いて「大聖堂」「郷愁のショーロ」「森に夢見る」などをひっしで練習したことがあります。
特に「郷愁のショーロ」は頑張ったのですが、例の1か所が弾けず涙を呑みました。「大聖堂」は、無理な運指もなく、比較的楽に弾けたように思います。
しかし数年前、誰かの演奏を聴いた時、「つまらない」と感じてしまいました。
そんな感覚で「ワルツ第3番」ほか、バリオスを聴いてみると、音楽的にクラシックとは言えないように感じ、弾くのをやめてしまいました。
この感覚は、ヴィラローボスにはない、ライトな感覚を意味しますよね。
やはりセゴビアやブリームが弾かなかったのもうなずけるような気がします。
それに比べて、以前、緑陽さんがブログで書かれていた、ポンセの「ソナタロマンチカ」は、素晴らしい曲ではないでしょうか。
しかし、この曲を最初に聴いたのは、山下さんだったため長い間「つまらない曲」と思っていました。セゴビアを聴いた時に、「なんて美しい曲だ」と思いました。
どんなに素晴らしい曲でも、演奏者によって悪いイメージを持つときがありますよね。(笑い)
そう考えると、ヨークやディアンズは、誰が弾いてもつまらなくしか聴こえませんよね。
ポンセ・テデスコ・タンスマン・トロ―バ・トゥリーナなどはもっともっと評価されて弾かれるべきではないでしょうか。
それにしても、ポンセの「主題と変奏と終曲」は素晴らしい曲ですが難しすぎる!(笑い)
今年1年で仕上がらなかった。
来年も取り組むつもりでいます。
緑陽さんの大好きな季節ですが、風邪などひかぬようご自愛ください。
fado
バリオスの「クリスマスの歌」ですが、私はやはり開放弦の方がより自然で、これがオリジナルではないかと思うのです。その根拠として、
①開放弦の部分をハーモニックスにしてしまうと同じメロディが連続で4度繰り返されることになり、くどく聴こえてしまうこと。
このメロディは2回目でクライマックスを迎え、そこで打ち止めではないかと思うのです。
またこのメロディは短調から長調に戻った直後にも2回繰り返されますから、ハーモニックスだと全部で6回弾くことになりますね。
これは全体のバランスを考えた場合、ちょと多すぎるのではないかと思います。
②ハーモニックスの最後の音(2弦F#、3弦Dの重音)の次にくる実音、高いEへのつながりがどうも違和感を感じてしまうこと(跳躍してしまうためか)。
ここはEではなくやや低いAの方がしっくりきます。
開放弦であれば重音は2弦B、3弦Gなので,高いEへのつながりは特段違和感は感じられません。
③バリオスが肝心のハーモニックス記号の記譜を忘れたまま、脱稿すことがあるだろうか、ということです。バリオスはこの曲を自分のためだけでなく、他の人にも弾いてもらうことを意図していたでしょうから、忘れることはあり得ないとい思います。
バリオスの曲はギター曲であることは間違いありませんが、クラシックというジャンルに属するか、と言われると疑問を感じます。
(昨今の国際コンクールの自由曲で、平然とバリオスを選曲する方もいますが、他楽器から見るとちょっと情けない感じもする)。
それからポンセのソナタ・ロマンティカですが、山下和仁の演奏を聴いて、私もfadoさんと同様、つまらない、セゴビアの演奏と比べると天と地以上の差があると感じましたね。
心が痛くなるほどの速いスピードで弾いていて、全くこの曲を理解していないと感じました。
ポンセの「主題と変奏と終曲」ですが、難しい曲ですね。この曲もセゴビアの名演があります。
私は20代後半の頃に挑戦して途中で断念しました。
fadoさんがいつか紹介下さった、松田晃演さんの著作「天国と地獄」を買って読み始めました。
鈴木一郎さんの著作も買って先に読みましたが、内容は対照的ですね。
松田さんの前作もかなり以前に読みましたが、留学時代の裏話などが紹介されており、興味深かったですね。
北海道はめっきり寒くなったことだと思います。
9月のあの地震の後、父が入院してしまい、先月帰省して見舞いに行きましたが、衰弱した父を見ることはかなり辛いものがありました。
fadoさんもお体を大切になさって下さい。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
記事の転載の件、了解しました。
紹介したギター曲が良い贈り物となれれば幸いです。
以下のようなコメントをつけてアップしました。
〜〜〜〜〜〜〜
敬愛する緑陽さんからの音楽と楽譜の贈り物。
クリスマスをギターの聴き比べで贅沢に過ごしましょう。
お裾分けになれば幸いです。
「バリオス作曲「クリスマスの歌」を聴くhttps://blog.goo.ne.jp/ryokuyoh/e/b255b6ecde3c62c90e8f1954001963e5
記事の掲載、ありがとうございました。