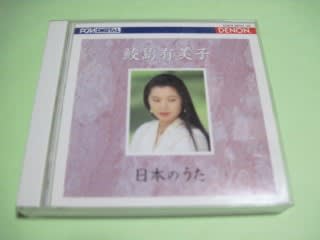木村雅信氏の名前を知ったのは今から20年くらい前だと思う。
ギタルラ社発行のピースの中にギター曲「アステリスクI Op.77」(1976年)というのがあった。
丁度邦人作曲家のギター曲を探し求めていた時だった。
この「アステリスクI Op.77」の楽譜は買わなかったのであるが、恐らく難解な現代音楽だと記憶している。
確かこの曲の楽譜の解説に、「因数分解」という言葉があったからだ。
木村雅信氏のギター曲はこれ以外に、プレリュード第1番~第19番があり、第2番と第16番の録音CDを持っている(北海道のギタリスト、星井清氏の演奏)。
プレリュードの楽譜の一部は現代ギター誌のバックナンバーの添付楽譜にあるはずだ。
今日、木村雅信氏の歌曲でいい曲を見つけた。
「アイヌの子守歌」という曲。
悲しいが、素朴で美しい歌だ。
伊福部昭の歌曲にも「摩周湖」というアイヌの悲しみを歌ったものがある。
アイヌの子守歌
この「アイヌの子守歌」のピアノ伴奏が結構難しく、歌のためだけでなくピアノのための曲であるように感じる。
木村雅信氏は長い間、札幌の大谷大学で教えていたようだ。
意外にもマンドリン・オーケストラ曲を20曲作曲している。
Youtubeで探してみたが、タンゴ・シンフォニカ Op.288(1997年)という曲の演奏しかなかった。
ギタルラ社発行のピースの中にギター曲「アステリスクI Op.77」(1976年)というのがあった。
丁度邦人作曲家のギター曲を探し求めていた時だった。
この「アステリスクI Op.77」の楽譜は買わなかったのであるが、恐らく難解な現代音楽だと記憶している。
確かこの曲の楽譜の解説に、「因数分解」という言葉があったからだ。
木村雅信氏のギター曲はこれ以外に、プレリュード第1番~第19番があり、第2番と第16番の録音CDを持っている(北海道のギタリスト、星井清氏の演奏)。
プレリュードの楽譜の一部は現代ギター誌のバックナンバーの添付楽譜にあるはずだ。
今日、木村雅信氏の歌曲でいい曲を見つけた。
「アイヌの子守歌」という曲。
悲しいが、素朴で美しい歌だ。
伊福部昭の歌曲にも「摩周湖」というアイヌの悲しみを歌ったものがある。
アイヌの子守歌
この「アイヌの子守歌」のピアノ伴奏が結構難しく、歌のためだけでなくピアノのための曲であるように感じる。
木村雅信氏は長い間、札幌の大谷大学で教えていたようだ。
意外にもマンドリン・オーケストラ曲を20曲作曲している。
Youtubeで探してみたが、タンゴ・シンフォニカ Op.288(1997年)という曲の演奏しかなかった。