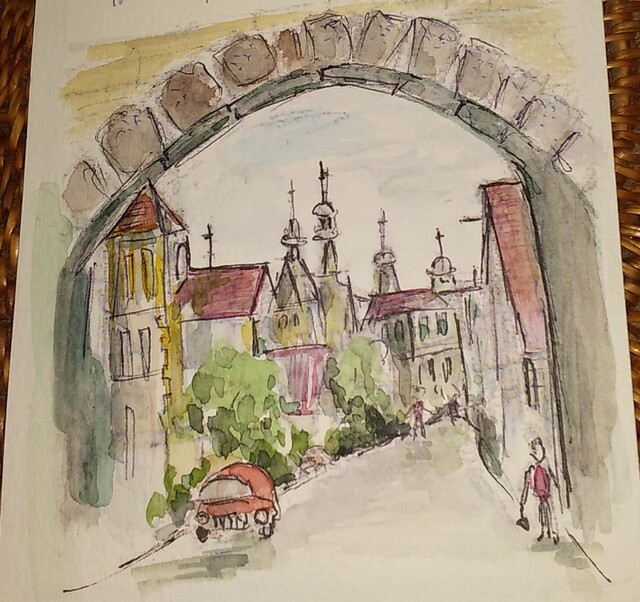「大津順吉」 (大正元年 1912年) 志賀直哉
「大津順吉」の中にも父親との不和の原因が隠されていました。
この物語は、ほぼ事実に近いように思います。
「その頃私は生ぬるいキリスト信徒だったのである。20過ぎたころからは
女に対する要求が強くなって行った。そして私はなんとなく偏屈になった。」
「私の「心」と「体」とがたえず恋する者をさがしながら、
「境遇」と「思想」とにさまたげられている。
その不調和が苦しくてたまらない。」
そしていわば、上流階級をさけて、自分の家の女中「千代」との
結婚を決めますが、、。
このことは、当然、父、家族全体の反対にあうのです。
その後、別の短編の中で、最終的ににはこの「千代」にあきたりなく別れます。
(左)ダンスの会に嫌々出席するが、相手になることは全て拒否する
(右)女中の千代に「約束した人がいるのか?」と問う順吉
この挿絵はちなみに 「和解」 最後の場面
父と子が和解の瞬間お互いに涙する、、。

「日本の文学」全集の中に珍しく挿絵まで描かれていました。
「武蔵野市立吉祥寺図書館」
6/15日、別の目的で訪ねた 我孫子 手賀沼でしたが、偶然にも
「志賀直哉」に巡り合い、改めて小説を読む機会をえました。
遠く昔に読んだ限りで、あらすじは殆んど忘れていました。物語は
私が生まれる前に書かれた物が殆んどで、でも簡潔な文章と言葉使いの
美しさに引き込まれ、短編は読み終わりました。後、長編はこれしかない
と言われる「暗夜行路」を今一度読むつもりです。
この物語は 「時任謙作」は本人に近いが、祖父もその他も完全に架空の
物語。なぜなら、志賀直哉はこの祖父を一番と言うほど尊敬していました。
10日以上も読書の虫になりました。 さあ、大変、小さな庭も草だらけ!!





















 一つ欲しいなあ~と。
一つ欲しいなあ~と。