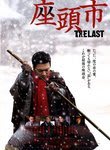梅雨の典型のような日々が続くが、幸い雨が落ちてこないので、実家の母をさいたま新都心のシネコンに誘って一緒に観た。当初は中井貴一の「Raleways」にしようとネットでチケットをとったのだが、香取の「座頭市」の方が観たいというので、カウンターで頼み込んで変更してもらった。無理を聞いてくれたMOVIXさいたまのスタッフの皆様に感謝したいm(_ _)m

【香取慎吾主演映画「座頭市 THE LAST」】
ストーリーは、以下、「映画のことならeiga.com」の「座頭市 THE LAST」の項から引用、加筆。
「勝新太郎、ビートたけしが演じてきた盲目の居合いの達人・座頭市にSMAPの香取慎吾が扮し、市の最期を描く「最後の座頭市」。旅の途中で妻(石原さとみ)を殺され傷心の市は余生を静かに暮らそうと帰郷し、かつて一緒に博打の旅に出た旧友の農民・柳司(反町隆史)の家に居候する。だが、市の故郷は博徒の天道(仲代達矢)一家に支配されており、市は再び戦いの渦中に巻き込まれていく。
監督は「亡国のイージス」、「闇の子供たち」の阪本順治。
他の主な配役は、以下の通り。
工藤夕貴、寺島進、高岡蒼甫、ARATA、ZEEBRA、加藤清史郎、宇梶剛士、柴俊夫、豊原功補、岩城滉一、中村勘三郎、原田芳雄、倍賞千恵子






タネ(石原さとみ)が市の妻になってくれたかと思うとすぐに市の盾になって殺されてしまう。この二人のコンビによる色っぽい場面はなし。確かに二人には似合わないなと納得。しかしながら命を賭けて愛してくれた女がいたことがこの映画に一本の芯を通す。
海の見える半農半漁の故郷をめざすも廃墟となっていて、同じような土地に暮らす元の仲間の柳司をたずねて百姓としてともに生きることに精を出す市。柳司の母ミツ(倍賞千恵子)は市を歓迎しないが息子の五郎(加藤清史郎)はすぐになつく。
昔から漁場を仕切るヤクザを島地(岩城滉一)とその代貸し達治(寺島進)は新興のヤクザの天道(仲代達矢)にショバを奪われる。達治の女房トヨ(工藤夕貴)が色っぽい方の役回りを引き受けてバランスをとっているが、そのトヨを天道一家の代貸し十蔵が横恋慕してものにしてしまう。役人の梶原(宇梶剛士)も脅して支配権を奪取する天道。
島地から借金の証文を奪って柳司たちから金を搾ろうとするあの手この手の暴虐に、普通の杖に持ち替えていた市は、仕込み杖を再び手にし、柳司たちを救おうとする。
梶原の上役の北川(柴俊夫)による見回りをねらって上訴の計画を立てた柳司は、三叉路を使って市を囮に使う。ミツが市に防寒の衣を着せ掛けて「ただ弱いから耐えるのじゃないよ百姓は」という辺りが、雑草のように踏まれても生きる民の力を思わせる。

追うものも追われるものも最終的には同じところに集まっての上訴、梶原の乱心、結局北川も斬られ、役人の権威も何も役に立たない状態になり、大人数の斬り合いの中、柳司は市に赦しを請いながら落命。
圧倒的な「悪」の権化、天道を倒すために満身創痍の市は最後の力を振り絞る。天道を倒すが自らも致命傷を受け、海をめざす市。中途失明の市の心の原風景に海があり、命の源の「海」に還るかのよう。そこにタネの魂が市を招くようなイメージが重ねられる。
地に足をつけた暮らしは全うできなかったが、最後まで悪と闘い、燃え尽きる市の最後にふさわしいと思った。
「座頭市」シリーズの有終の美を飾る作品という宣伝ではあるが、2017年以降はまた自由につくれるということらしい。それでもとりあえず今の状態でのTHE LASTという作品に豪華なキャストが大集結しているのが贅沢。
主演の香取慎吾も大河ドラマの「新撰組!」の近藤勇の頃からけっこう気に入って観ている。「西遊記」の孫悟空のように茶目っ気たっぷりなのもいいし、近藤勇のように真面目な演技もけっこう好み。今回の市も真面目に徹している。アウトローの盲人らしく言葉はより少ないので安心して見ていられるし、さらに影を背負った人間の哀しさも滲ませていて好演。(6/24追記:プログラムを読んだら香取慎吾は殺陣のところでも一切目を開けなかったのだという。殺陣師の方がその覚悟とやりきったことに感動されていた。抜刀した仕込み杖を戻す時のぎこちなさはそのためかとあらためて感心。慎吾ちゃん、やる時はやるんだねとまたまた見直した!!)

場末の賭場に立派な刺青を入れた壷振りがいるなぁと思ったら勘三郎だった!市を知る旅の博徒の役だが、話題作にはしっかりとはずさずにご出演というのがさすがだ!!
村の医者の玄吉(原田芳雄)と市のからみは貴重なチャリ場となっている。笑いをとるのはそこくらいで、あとは実に生真面目な展開なのに、香取も浮かずにきちんと主人公の存在感を見せる。観終わって母と「香取、がんばったよね」という評価で一致。

私はTVのシリーズで勝新太郎の座頭市を何回か観たが、殺陣が派手というのはどうでもいいことなので、好みの時代劇ではなく、特に印象に残っている場面があまりなかった。
さらにビートたけしもそんなに好きではなく、金髪で話題の座頭市もあまり興味なし。
今回のプログラムで「座頭市」が勧善懲悪で市が悪者をバッタバッタ斬っていくところに人気の秘密があったとわかり、後の「必殺シリーズ」につながっていくのかなぁとわかった次第。

そういった過去の人気シリーズの把握にも役に立ち、ある程度の見ごたえもあり、母が楽しかったと言ってくれて親孝行ができたので満足、満足。
うーん、それにしても前日のコクーン歌舞伎「佐倉義民伝」に続き、上訴もの続きというのも、なんとなく今の時代に符合しているのかもしれないとも思えるのだった。
以下、系統的に把握するためにリンクをつけておく。
Wikipediaの「座頭市」の項はこちら
Wikipediaの「座頭市」(2003年の映画)の項はこちら
Wikipediaの「座頭市THE LAST」の項はこちら
写真は今回の作品のチラシ画像。
さっそくの追記!
私は時代劇好きである。小さい頃から北大路欣也のお父ちゃんの市川右太衛門の「旗本退屈男」やら近衛十四郎・品川隆二コンビの月影兵庫もの、杉良太郎・梶芽衣子の「大江戸捜査網」、必殺シリーズ・・・・・・。そして御馴染みの斬られ役・福本清三の姿が見られるのが嬉しい。映画「ラスト・サムライ」でもそして今回の映画でもけっこういい役がついていて嬉しかった。ちゃんと本も読んでます(^^ゞ
「名脇役 福本清三」の応援サイトはこちら