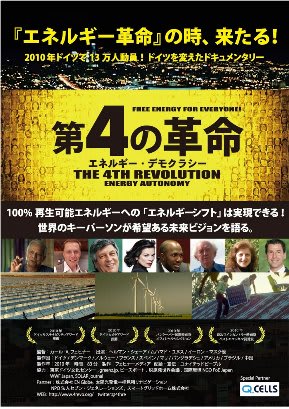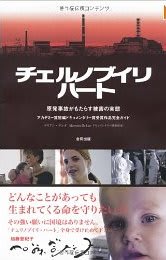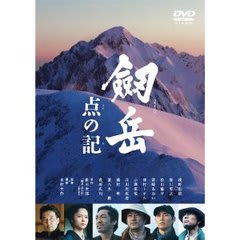玲小姐さんの娘さんのおすすめということで映画のチラシをいただき、ご贔屓の新猿之助も出演(撮影時は亀治郎)ということもあり、有楽町スバル座に観に行った。
【道 白磁の人】
映画.comの「道 白磁の人」から以下、「解説」を引用。
日本統治時代の朝鮮半島で植林事業に勤しみ、民族間で争いあう中でも信念を貫いて生きた実在の青年・浅川巧の半生を描いたドラマ。監督は「光の道」「火火」の高橋伴明。浅川役に吉沢悠、浅川と親交を深めた韓国人青年チョンリムにペ・スビン。1914年、朝鮮総督府の林業試験場で働くことになった23歳の浅川は、京城(現ソウル)に渡り、そこで出合った朝鮮の工芸品・白磁の美しさに強くひかれる。職場では同僚のチョンリムから朝鮮語を習い始め、研究に没頭。チョンリムとも友情を育んでいくが、その一方で、朝鮮の地で横暴に振る舞う日本人の現実を知る。
さらに詳しい解説・ストーリーは、cinematopicsの映画作品紹介「道~白磁の人~」が参考になる。
公式サイトはこちら

監督=高橋伴明
製作総指揮=長坂紘司
原作=江宮隆之「白磁の人」
主な配役は以下の通り。
浅川巧=吉沢悠 李青林(イ・チョンリム)=ペ・スビン
浅川伯教=石垣佑磨 浅川けい=手塚理美
朝田みつえ=黒川智花 朝田政歳=市川猿之助(撮影時亀治郎)
園絵=近野成美 大北咲=酒井若菜
柳宗悦=塩谷瞬 小宮=堀部圭亮
町田=田中要次 野平=大杉漣
チョンス=チョン・ダヌ ジウォン=チョン・スジ

浅川巧は、山梨県北巨摩郡甲村(今の北杜市)に生まれた。1914年、兄伯教が渡った朝鮮に自分も林業試験場技手として渡ることになり、故郷の緑の山野で親友の朝田政歳に別れを告げる場面から始まる。大きな木の下に寝転んで土の匂いをいっぱいに吸い込む巧の顔は下向きなのでよく見えない。話しかける猿之助の政歳の顔の方がまともに映り、さらに「木や土が一番で俺はその次か」と愚痴る台詞はキーワード。贔屓としてはここだけで観に来た甲斐があったとニンマリ(^^ゞ政歳の妹みつえと巧が相思相愛で、兄としては身体が弱い妹を朝鮮には嫁がせたくないが、本人が強く望むので仕方がないという。
そして山梨の山並みがぐるっと回っていくと朝鮮の山並みに続いていく転換!これは映画ならではの手法で素晴らしく、のっけから舌を巻いた。

兄伯教の友人が柳宗悦で、二人の朝鮮民族美術の収集研究を手伝ううちに、高麗の「青磁」に比べて当時は価値を認められていなかった日常使いの「白磁」の魅力に気づく。巧は朝鮮の自然と人間と文化を愛し、朝鮮の人々に敬意を払って対等につきあう。1910年の日韓併合以降、日本が植民地支配をしている状況で、巧のような日本人は少なかった。大河ドラマ「平清盛」で関白藤原忠通役の堀部圭亮が、今作に憲兵の小宮に出ていて、何度も巧を傷めつける。原作では最後に改心するらしいが、映画では最後まで憎々しく、解放後の朝鮮人民に報復を受けているのが象徴的な存在となっている。

バスの中で朝鮮人の老人に席を譲った巧が小宮に見咎められた時がチョンリムとの出会いとなり、老人の感謝の言葉がわからなかった巧はチョンリムに朝鮮語を教えて欲しいと頼む。チョンリムは巧の職場の工員であり、熱心に作業に取り組んでおり、二人は朝鮮のはげ山に木を植えて緑にするという共通の夢に一緒に向かっていく親友となる。
日本の支配に抵抗する運動も起こり、1919年の「三・一独立運動」の場面も入っている。チョンリムと一緒に働いている工員のチョンスは抗日運動の中で射殺されてしまう。その葬列を見て「アイゴー、アイゴー」と大きな声で泣いて嘆く人々に露骨な差別意識をひけらかすのは兄弟の母のけいだ。巧に娘の園絵が生まれて祝いにかけつけたチョンリムにも嫌な顔を見せる。

相思相愛の妻のみつえは兄政歳の心配が的中、朝鮮の厳しい気候で体調を悪化させてしまう。幼い園絵に父を守っての願いを込めた白磁のかけらを託す夕景の中、渡り鳥の群れを追っていくと日本の山梨へと転換、ここも素晴らしい。故郷に帰って闘病するがとうとう亡くなってしまう。山梨の山野を歩くみつえの弔いの葬列。両国の葬列の対比が効いている。

チョンリムの妻ジウォンや息子は抗日運動に身を投じ、チョンリムにも参加を迫る。チョンリムは一線を画し、信頼する巧とともに植林の仕事に励み、白磁等の収集にも協力している。日本人に協力するチョンリムへの同胞の目も厳しい。巧は「日本人と朝鮮人が理解しあえるなんて、見果てぬ夢なのだろうか」と絶望するが、チョンリムは「夢であったとしても、それに向かって行動することに意味があるのではないですか」と答える。二人は苗を育て木を植えていくことを続け、友情が深まっていく。ここで涙腺決壊(T-T)

民芸収集の集大成となる朝鮮民族美術館開館の日、なんとチョンリムの息子が総督府の要人へのテロリストとしてやってくる。その爆薬を取り上げて逃がしたチョンリムは不発だったためにそのまま捕えられて獄中の人になり、面会に行った巧に心を閉ざしてしまう。
柳宗悦は大北咲に「白磁のような人物」として巧との結婚をすすめ、巧は再婚。咲には死産の不幸が襲うが、なついていた園絵が「死なないで」「お父さんを守って」と咲に実母から託された白磁のかけらを託す。子どもを喪った悲しみの中でなさぬ仲の母と娘の気持ちはしっかり結ばれた。

巧は急性肺炎で倒れる。死期を悟った巧は兄に最後に2箇所に連れていって欲しいと願う。刑務所でのチョンリムと面会し、チョンリムの家の庭に埋めたチョウセンゴヨウマツの木を見る。40歳での早世。
その葬儀の日に、これまで巧が親身に接してきた朝鮮の人々が「棺をかつがせてください」と大勢押しかけてくる。朝鮮式の葬儀の中、母のけいは堪えきれず隠れて声を上げて泣く。そこに朝鮮服の女が肩を抱き「泣きたいだけ泣くといい」と朝鮮語で声をかけて慰める。民族を超えて気持ちがつながったと思わせ、ここも泣ける。巧の亡骸はついに朝鮮で埋葬され、その墓は朝鮮の人々に大事にされ続けている。
やがて時が過ぎて日本の敗戦イコール朝鮮の解放の日、それまで自分たちを苦しめた日本人を襲う暴徒が咲や園絵の家にもやってくる。「ここは浅川巧さんの家だ」と一喝したのは解放されたチョンリムだった。かくして母娘は「お父さんは私たちを守ってくれた」と巧に想いを馳せる。

予想以上に感動的で、これまで浅川巧のような人がいたことを知らなかったので、この映画を観て本当によかった。しかしながら、巧はなぜこの時代に民族差別意識にとらわれないでいられたのだろうと少し疑問に思った。そこでネット検索して納得。巧はクリスチャンでもあったのだ。
Wikipediaの「浅川巧」はこちら
浅川伯教・巧兄弟が学んだ「北杜市立高根西小学校」のHPにある浅川兄弟のコーナーは、年表や写真が充実しているので参考になる。ただし、クリスチャンだったことには触れていない。日本の行政は宗教をその人の思想形成の要因としてきちんと言及することに変に遠慮するためだと思われる。
チョンリムは青林であり、あまりにもぴったりすぎる名前なのでもしやと思ったら、史実の人ではなく原作のオリジナルキャラクターだった。それでも浅川巧が理解しあい、ともに生きた朝鮮の人々の象徴であり、二人の友情を縦軸にすることでよりドラマが魅力的になっているのだと思う。

浅川巧役の吉沢悠も大河ドラマで藤原家成の嫡男で後白河帝の側近の成親を演じている。またチャンリム役のペン・スビンが韓流ドラマ「トンイ」に出ているということだったので、この日の夜に最終回のオンエアに間に合って見てみたら主人公トンイの兄役だった。この日韓の二人の若い俳優は、撮影の中で親友になったということで、その気持ちがスクリーンにもあふれていたように思われた。

映画の中の二人が語っていたように、両国の人々が不幸な歴史を踏まえながらも乗り越えて、理解しあい協力しあえるようになりたいと思う。そのためには、日本人があまりにも歴史を知らなすぎるので(これはあえて教えない政策をとっているという問題がある)、両国の不幸な歴史も義務教育の中できちんと教え、前向きな関係を築いていくことが大事だと考えている。そのためにやれるだけのことはしていきたい。

高橋伴明監督は、高橋恵子の夫ということ以外にあまりよく知らなかったが、当初の映画化の動きが頓挫してもう一度立ち上がった時に監督を打診されたとのこと。道元を主人公にした2009年の「禅 ZEN」もよかったし、過去の作品も機会があったら見てみようかと思っている。