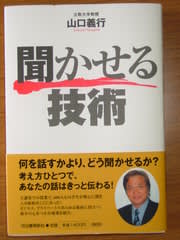1学期の終業式の日は、子どもたちは通信票をもらいます。子どもたちは顔には出しませんが、通信票の成績はどうなのか、胸の内はドキドキハラハラなのです。
ちょうど私が通りかかった教室では、子どもたち一人ひとりに先生が通信票を渡していました。1学期の学習や生活、健康等のことで子どもを褒めながら、励ましながら、また、努力や頑張りをうながしながら、でるだけ明るい顔で温かい言葉を掛けながら手渡していました。通信票をいただいた子どもたちも、にこっと笑ったり、ちょっと戸惑った顔をしたりして自席に戻り、そうして再びゆっくりと通信票を見るのでした。
通信票の目的は、1学期の学習や生活等の様子を受けとる子どもたちや親の気持ちを考えながら、その状況をきちんと伝えなければなりません。それだけに先生は、通信票をつけるときにも、子どもたちに手渡すときにも大変苦心しています。
ちょうど私が通りかかった教室では、子どもたち一人ひとりに先生が通信票を渡していました。1学期の学習や生活、健康等のことで子どもを褒めながら、励ましながら、また、努力や頑張りをうながしながら、でるだけ明るい顔で温かい言葉を掛けながら手渡していました。通信票をいただいた子どもたちも、にこっと笑ったり、ちょっと戸惑った顔をしたりして自席に戻り、そうして再びゆっくりと通信票を見るのでした。
通信票の目的は、1学期の学習や生活等の様子を受けとる子どもたちや親の気持ちを考えながら、その状況をきちんと伝えなければなりません。それだけに先生は、通信票をつけるときにも、子どもたちに手渡すときにも大変苦心しています。