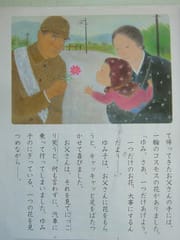子どもは授業の中でも、生活一般の中でも、断片的ではあるがよいものを出してくる場合が多い。
授業中の発言の中に、書写や絵の作品の中に、一見だめだと思われる中に、よく聴き取ると、よく見ると必ずよいところがある。教師はそれを目ざとく見つけ出し、本人や学級全体の子どもたちに教えたり紹介したりすることが大切である。そうすることにより、本人は自信を持ち、学習に意欲的に立ち向かうようになる。また、学級全体の学びの参考にもなる。私は常々子どもを教育するとき、これを基本としている。
ところで加藤秀俊(放送大学学園)教授は、「わたしの知的生産の技術」という本の中で「情報の中から砂金を拾う」というタイトルで次のような文を書いている。
・・・砂金堀りが川底をさらっていると、ほとんどが砂ですが、たまに金を見つけるわけです。つまり、その気にさえなってみれば、きわめて雑然とした情報の中からでも、砂金を見つけ出すことができるということなのです。・・・(後略)
このことは、子どもの教育にもあてはまるものと思われる。教師の資質として、子どもの言動の中から砂金を拾い、つかみ出す力は、絶対必要であると思う。