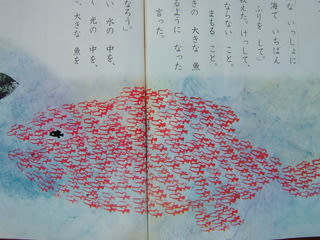一方に「教え込みの教育」があり、その反対に「放任の教育」があるとするれば、今までの教育改革の大方はそのどちらかに大きく揺れてきたようである。
しかし、その繰り返しを長年あきることもなくやってきてもなかなか効果が上がらないのは、その双方に問題があるからである。
その問題もかなり明確に分かっていながら教育の第三の道を見出せないのは、国の教育行政の怠慢であると言えよう。
国は何とかその解決法として「教えて考えさせる教育」とか「習得学習と探求学習」というような教育法を打ち出してきたが、今ひとつ具体性に欠ける。
本当の教育は「教え込みの教育」と「放任の教育」の中間にあるというような単純な問題ではない。第三の教育改革の道を模索しなければならない。「教え込みの教育」と「放任の教育」の線上でなく、枝分かれしていく教育法である。
※下記のブログも検索しご覧ください。
①totoroの小道
②藍色と空色と緑のページ(各教科等の実践事例が掲載されています)