場J 原子力施設等防災専門部会 防災指針検討ワーキンググループとは
原子力施設等防災専門部会 防災指針検討ワーキンググループが設置されました。原子力施設の防災に関する基本的考え方のとりまとめを行うということです。今回の事故を受け、その対応を反省した上で、今後に生かす話し合いがなされる部署と解釈します。重要なワーキンググループであると私は認識しています。
****原子力安全委員会ホームページより****
http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/sisetubo/sisetubo022/siryo6-2.pdf
原子力施設等防災専門部会 防災指針検討ワーキンググループの設置について
平成23年7月14日 原子力施設等防災専門部会
1.目的
原子力安全委員会 原子力施設等防災専門部会(以下「部会」という。)におい て、原子力安全委員会の原子力施設等防災に関する基本的考え方の取りまとめを 行うに当たり、専門的かつ効率的な審議に資するため、部会に「原子力施設等防 災専門部会防災指針検討ワーキンググループ」を設置し、次のような検討を行う。
2.検討事項
(1)「原子力施設等の防災対策について」及び関連の指針類に反映させるべき事項 (2)その他、重要と認められる事項
3.構成員
【専門委員】
池内 嘉宏 日本分析センター理事
梶本 光廣 原子力安全基盤機構原子力システム安全部次長
鈴木 元 国際医療福祉大学教授
野村 保 放射線影響協会常務理事
本間 俊充 日本原子力研究開発機構安全研究センター副センター長
渡辺 憲夫 日本原子力研究開発機構安全研究センター研究主席
【外部協力者】
齊藤 実 原子力安全基盤機構防災対策部審議役
高橋 知之 京都大学原子炉実験所准教授
塚田 祥文 環境科学技術研究所主任研究員
【オブザーバー】
(全国原子力発電所所在市町村協議会)
(原子力発電関係団体協議会)
※原子力施設等防災専門部会の部会長は、議題に応じて、適宜、構成員を追加する ことができる。
場K ワーキンググループ第一回会合傍聴
そのワーキンググループの第一回会合が、7/27開催され、一部傍聴して参りました。
議題
| (1) | 「原子力施設等の防災対策について」の改定に向けた課題について |
| (2) |
その他 |
会合で出された意見のポイント(一部)
*技術的な判断を出すのは当然であるが、ガバナンス面も含め言及する
ガバナンスでいうのであれば、誰がするのか、訓練は誰の責務かまで踏み込む。
*テロもふくめ、検討する。
*わかりやすいもので、動くことが出来るものをつくる。
*施設面からみた対応も書く。
など。
場L「原子力施設等の防災対策について」改訂作業
そのワーキンググループでは、「原子力施設等の防災対策について」という指針が改定されます。
****原子力安全委員会ホームページより*****
http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/sisetubo/sisetubo022/siryo6-1.pdf
「原子力施設等の防災対策について」の改定に向けた検討の進め方について(案)
平成23年7月 原子力安全委員会事務局 管理環境課
1.検討の方向性について
○今般の、東京電力福島第一原子力発電所事故は、我が国において未曾有の原子力 災害となり、現在、国、地方自治体、事業者等の関係機関が一体となって、この 被害を押さえるべく当該事故対策に引き続き全力で対応している。
○今後、事故の全体像を把握し、分析・評価を行い、これらに対応した抜本的な対 策を講じる必要があり、今般の福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原子力安 全委員会原子力施設等防災専門部会において、「原子力施設等の防災対策について」 の改定に向けた検討を行う。
○「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関しては、福島第一原子力発電 所の事故の状況や、「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」 の審議の状況等を踏まえて議論を進めるとともに、国際放射線防護委員会(IC RP)の2007年勧告、国際原子力機関(IAEA)策定の安全要件(GS- R-2)/安全指針(GSG-2)等を踏まえたものとし、また、諸外国におけ る原子力防災体制に係る調査、我が国における実情、実効性等を考慮し、検討を 行う。
2.検討すべき課題について
(1)「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(EPZ)について
○現行の防災指針で定めている「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(E PZ:Emergency Planning Zone)の範囲(原子力発電所では約8~10 km)については、現状、避難区域(警戒区域)は福島第一原子力発電所から全 方向半径20km圏内であり、また、計画的避難区域は同発電所から北西方向 半径50kmまで及んでおり、見直しに向けて検討を進める。
○また、IAEAの安全要件においては、緊急防護措置の整備を行う範囲として、
・重篤な確定的健康影響の発生を回避又は低減するために、施設の状態に基づ いて、放射性物質の放出前又は直後に予防的緊急防護措置が取られることを目標とした整備が行われなければならない予防的措置範囲(PAZ:Precautionary Action Zone)
・国際基準にしたがって敷地外の住民の被ばく線量を低減するために、迅速に緊急防護措置が取られるよう整備が行われなければならない緊急防護措置計画策定範囲(UPZ:Urgent Protective action planning Zone) が示されている。
○これらの措置範囲の概念の導入も含め、「防災対策を重点的に充実すべき地域 の範囲」の目安として各原子力事業所の種類・放射能インベントリ等に応じた 距離を用いること等について検討を進める。
(2)防護対策(屋内退避/避難等)実施の判断基準となる線量について
○現行の防災指針で定めている防護対策実施の判断基準となる線量は、その指標 を予測線量で、外部被ばくによる実効線量10~50mSv を屋内退避、外部 被ばくによる実効線量50mSv 以上を避難の指標として示しているところで ある。
○一方、国際放射線防護委員会(ICRP)、国際原子力機関(IAEA)では、 緊急時被ばく状況、現存被ばく状況においては、参考レベルに基づく防護対策 が計画され、最適化されることが提案されており、今回の事故では、この考え 方に基づき、「計画的避難区域」等が設定された。今後、このような考え方を 防災指針に取り入れること等を検討することが必要である。
(3)防護措置の実用上の判断基準(OIL、EAL)の設定について
○IAEAの基準等において規定されている防護対策を実施するための測定可 能な指標で表された、実用上の介入レベル(OIL:Operational Intervention Level)や緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)の導入も含め、 検討を進める。
○OILに基づき実施される防護対策の内容等について検討する。
(4)その他の検討課題について
○防災基本計画等で定められていた「緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセ ンター)」については高放射線の影響、通信途絶等により機能の低下があり、 移転を余儀なくされた。オフサイトセンターの機能等のあり方についての検討 を進める。
○原子力施設の周辺で実施される環境放射線モニタリングの計画、測定、評価等 にあたっての考え方についての検討を進める。
○長期にわたり放射線防護を考慮することになる現存被ばく状況への移行と現 存被ばく状況における防護対策・参考レベルの設定、原子力緊急事態解除宣言 及び各種防護対策の解除等に関する基本的な考え方、事故後の復旧対策のあり 方、除染・改善措置等についての検討を進める。
○被ばく医療のあり方、除染のためのスクリーニングレベル等についての検討を 進める。
○緊急時対応準備の目標、脅威区分についての検討を進める。
○原子力発電所に近い地域から段階的に避難させる方法についての検討を進め る。
○原子力防災業務関係者等の教育および訓練についての検討を進める。
○防災指針の対象とすべき範囲、適用する期間について検討を進める。
○その他
3.今後の進め方について
○7月下旬以降、原子力施設等防災専門部会に設置した防災指針検討ワーキング グループを随時開催する。なお、「原子力施設等の防災対策について」の改定 に向けて検討すべき課題について、必要に応じて原子力施設等防災専門部会被 ばく医療分科会を開催し、放射線防護専門部会等の他の専門部会・分科会とも 適宜連携を取るとともに、中央防災会議等、他機関による検討を踏まえる。
○優先すべき課題から順次、必要に応じて適宜考え方を示しつつ、年度内を目処 に中間取りまとめを行う。
以上
場M 福島第一・第二原子力発電所に おける原子力災害への対応(概要) スライド
→ http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/sisetubo/sisetubo022/siryo3-1.pdf

















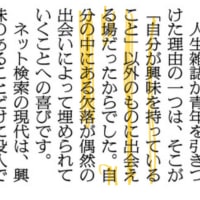










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます